インボイスの市場特例ガイド!対象者から条件・必要書類までわかりやすく解説
更新日:2025.07.28
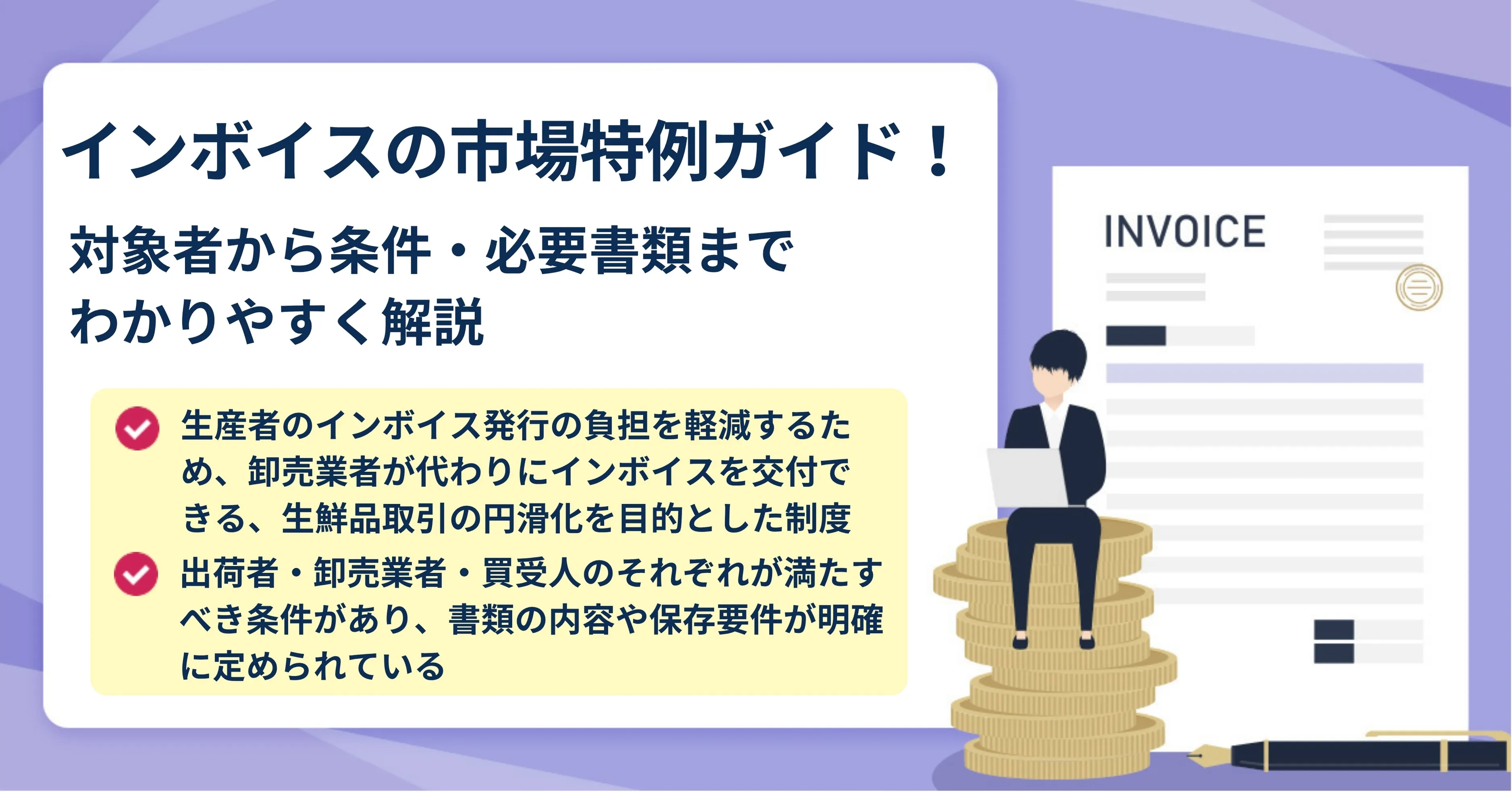
ー 目次 ー
インボイス制度の「卸売市場特例」について、誰がどう対応すればいいのか迷われていませんか?本記事では、この特例のしくみをはじめ、対象となる方の条件や必要な書類、実務の流れまでを丁寧にご紹介します。
生産者・卸売業者・買受人、それぞれの立場にあわせて解説しているため、「自分は何をすればよいのか」が自然と見えてくる内容です。ぜひ、実務にお役立てください。
インボイス制度の市場特例とは?基本を解説
2023年10月1日から始まったインボイス制度で、卸売市場で生鮮食料品などを取引する事業者にとっては、業務の進め方が大きく変わる可能性があります。この章では、インボイス制度の基本をおさらいしつつ、市場特例がどのような制度なのかその仕組みをわかりやすく解説します。
そもそもインボイス制度とは?わかりやすく解説
インボイス制度とは、正式名称を「適格請求書等保存方式」といいます。これは、消費税の仕入税額控除を受けるための新しいルールです。
これまで事業者は、取引先から受け取った請求書を保存していれば、仕入れにかかった消費税分を納める税額から差し引く「仕入税額控除」ができました。しかし、インボイス制度の開始後は、原則として「適格請求書(インボイス)」がなければ、この仕入税額控除が受けられなくなります。
適格請求書とは、以下の項目が記載された請求書や領収書のことです。
- 適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
- 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜きまたは税込み)および適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
- 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
つまり、商品を仕入れる側の事業者(買手)は、商品を販売する側の事業者(売手)からこの適格請求書を発行してもらい、正しく保存することで、消費税の負担を軽減できるのです。この基本ルールが、卸売市場における取引の実態に合わせる形で設けられた「市場特例」を理解する上での大前提となります。
卸売市場特例のしくみ
卸売市場特例は、生産者(農家や漁師など)から委託を受けて農水産物などの販売を行う卸売市場において、インボイスの交付義務を生産者から卸売業者へ移行できる制度です。
なぜこのような特例が必要なのでしょうか。卸売市場では、非常に多くの生産者がJA(農業協同組合)や漁協(漁業協同組合)などを通じて商品を卸売業者に委託販売します。もし原則通り、個々の生産者が買受人(仲卸業者や小売業者など)に対してインボイスを発行するとなると、膨大な事務負担が発生し、取引がスムーズに進まなくなる恐れがあります。この問題を解決するのが市場特例です。
市場特例を適用した場合、取引の流れは以下のようになります。
|
取引の形態 |
インボイス発行者 |
インボイス受領者 |
ポイント |
|
原則的な取引 |
生産者(出荷者) |
買受人 |
生産者が買受人へ直接インボイスを発行する必要がある。 |
|
市場特例を適用した場合 |
卸売業者 |
買受人 |
生産者に代わって、卸売業者が買受人へインボイスを発行する。 |
このように、卸売業者が取引全体を取りまとめることで関係者全員の事務負担を軽減し、円滑な市場取引を維持することを目的とした合理的な制度といえるでしょう。
インボイス制度で市場特例を選ぶかどうか判断基準をチェック!
インボイス制度の「卸売市場特例」は、特定の取引における事務負担を軽減するための制度です。しかし、すべての事業者にとってメリットがあるとは限りません。ここでは、市場特例のメリット・デメリットと、利用を判断するためのポイントを解説します。
市場特例のメリット・デメリット
市場特例を利用することには、関係する事業者それぞれの立場でメリットとデメリットが存在します。以下の表で全体像を把握し、自社にとってどのような影響があるかを確認しましょう。
|
メリット |
デメリット |
|
|
出荷者(生産者) |
|
|
|
卸売業者(JAなど) |
|
|
|
買受人(小売業者など) |
|
|
市場特例を使うべきか迷ったときに見るべきポイント
自社が市場特例を利用すべきか、あるいは取引先が利用している特例にどう対応すべきか。迷った際には、以下のポイントを確認して判断しましょう。
ポイント1:あなたの事業者の立場はどれか
まず、ご自身が「出荷者(生産者)」「卸売業者(JA・漁協など)」「買受人(小売業者・飲食店など)」のどの立場にあるかを確認しましょう。前述のメリット・デメリットで解説した通り、立場によって影響が大きく異なるため、自社の視点で検討することが第一歩です。
ポイント2:主な取引形態は委託販売か
市場特例が適用されるのは、卸売市場や農業協同組合、漁業協同組合などを通じて行われる「委託販売」が基本です。生産者自身が消費者や小売店に直接商品を販売する取引には、この特例は適用されません。自社の取引が特例の対象となる取引形態かどうかを確認することが不可欠です。
ポイント3:事務負担の軽減をどれだけ重視するか
特に、小規模な生産者や個人事業主で、インボイス発行に伴う事務作業やシステム導入の負担を避けたい場合、市場特例は非常に有効な選択肢となります。一方で、卸売業者はインボイス受領の手間が省ける代わりに、買受人への書類作成という新たな事務負担が発生します。この負担のトレードオフを考慮する必要があります。
ポイント4:取引先のインボイス登録状況
卸売業者の場合、取引のある生産者の多くが免税事業者であるならば、市場特例を適用することで事業への影響を最小限に抑えられます。買受人の場合も、仕入先である卸売業者が特例に対応しているか事前に確認しておくことで、仕入税額控除を確実に受けるための準備ができます。取引先との円滑な関係維持も重要な判断材料です。
インボイス制度の市場特例の対象となる事業者と取引!
インボイス制度の「卸売市場特例」は、誰でも利用できるわけではありません。ここでは、市場特例の対象となる事業者と取引の具体的な範囲について、詳しく見ていきましょう。
市場特例の対象になるのはだれ?対象となる事業者
市場特例は、農産物や水産物の生産者(出荷者)と、それらを委託販売する卸売業者との間の取引を円滑にするための制度です。主に以下の事業者が関係します。
|
立場 |
概要とインボイス登録の要否 |
具体例 |
|
出荷者(生産者) |
卸売業者に生鮮食料品等の販売を委託する事業者です。インボイス発行事業者である必要はありません(免税事業者でも可)。 |
農家、漁師、酪農家、個人事業主など |
|
卸売業者等 |
出荷者から委託を受け、卸売市場で生鮮食料品等を販売する事業者です。インボイス発行事業者である必要があります。 |
卸売市場の卸売業者、仲卸業者、農業協同組合(JA)、漁業協同組合(JF)、森林組合など |
|
買受人 |
卸売市場で卸売業者等から商品を購入する事業者です。仕入税額控除を受けるために、卸売業者等が発行する書類を保存します。 |
小売業者(スーパーマーケットなど)、飲食店、食品加工業者など |
どんな取引が市場特例の対象になる?判断ポイントをチェック!
市場特例の対象となるには、取引内容にも条件があります。以下の3つのポイントをすべて満たす取引が対象となります。
ポイント1:卸売市場を介した「委託販売」であること
市場特例が適用されるのは、生産者(出荷者)が卸売業者に商品の販売を「委託」する取引に限られます。生産者から卸売業者が商品を直接「買い取って」販売するケース(買取販売)は、この特例の対象外となるため注意が必要です。あくまで、販売業務を任せる「委託販売」であることが前提となります。
ポイント2:国が定める「卸売市場」で行われる取引であること
取引が行われる場所も限定されています。特例の対象となるのは、卸売市場法に規定される中央卸売市場や地方卸売市場、または国税庁の通達で定められた特定の市場で行われる取引です。産地直売所や個別の相対取引などは対象になりません。
ポイント3:対象品目が「生鮮食料品等」であること
特例の対象となる品目は、生鮮食料品および花き(かき)など、価格変動が激しく、多くの生産者から集荷される商品に限定されています。具体的には以下のような品目が該当します。
- 野菜、果物
- 鮮魚、冷凍魚、塩干魚、貝類、海藻類などの水産物
- 食肉、鶏卵
- 切り花、枝もの、鉢ものなどの花き類
加工食品や酒類などは原則として対象外です。ご自身が取り扱う品目が対象になるか不明な場合は、所轄の税務署や取引のある卸売市場に確認することをおすすめします。
インボイス制度における市場特例を受けるための適用条件
インボイス制度の卸売市場特例を適用するには、出荷者(生産者)、卸売業者、買受人(仲卸業者や小売業者など)のそれぞれが、定められた条件を満たす必要があります。ここでは、それぞれの立場別に満たすべき適用条件を詳しく解説します。
出荷者(生産者)が満たすべき条件
出荷者(農家や漁師などの生産者)が市場特例の対象となるための条件は、以下の通りです。
まず、JA(農業協同組合)や漁協(漁業協同組合)、森林組合などに対して、生産した農林水産物の販売を無条件委託していることが必要です。「無条件委託」とは、価格や出荷先などを定めず、販売を包括的に委託する方式を指します。
重要なポイントは、出荷者自身がインボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)である必要はないという点です。免税事業者であっても、上記の条件を満たせば市場特例の対象となる出荷者になることができます。
卸売業者が満たすべき条件
卸売業者が市場特例を適用するためには、以下の条件をすべて満たす必要があります。
第一に、卸売業者はインボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)として登録している必要があります。その上で、出荷者から販売委託を受けた農林水産物を、卸売市場において販売していることが求められます。
また、卸売業者は、販売した農林水産物について、買受人に対してインボイス(適格請求書)の代わりに、一定の事項が記載された書類(売上伝票や精算書など)を交付する義務があります。この書類が、買受人が仕入税額控除を受けるための証明となります。
買受人が仕入税額控除を受けるための条件
買受人(仲卸業者、小売業者、飲食店など)が、卸売市場での仕入れについて仕入税額控除を受けるためには、次の2点を満たす必要があります。
それは、「卸売業者から交付された、インボイスの代わりとなる書類」と、「仕入税額控除の適用を受けるための帳簿」の両方を適切に保存することです。どちらか一方だけでは仕入税額控除は認められないため、注意が必要です。
保存が必要な書類と帳簿の要件は、以下の表の通りです。
|
保存が必要なもの |
満たすべき主な要件 |
|
卸売業者から交付される書類 (売上伝票など) |
以下の事項が記載されている必要があります。
|
|
帳簿 |
通常の記載事項(課税仕入れの相手方の氏名・名称、取引年月日、取引内容、対価の額)に加えて、その課税仕入れが「卸売市場特例の対象である」旨を明記する必要があります。(例:「市場特例」「特例」など) |
出荷者が免税事業者である場合でも、卸売業者が適格請求書発行事業者であり、必要な書類や帳簿が揃っていれば、買受人は仕入税額控除を受けることが可能です。
【立場別】インボイス制度における市場特例の手続き|いつ・どこに提出する?
「出荷者(生産者)」「卸売業者」「買受人」の3つの立場に分けて、それぞれの手続きや必要書類について具体的に解説します。
出荷者が市場特例を使うには?届出先と必要な手続き
出荷者(農家や漁師などの生産者)が市場特例の適用を受けるために、税務署へ個別の届出や申請を行う必要は特にありません。ただし、以下の2つの対応が必須となります。
- 適格請求書発行事業者の登録
大前提として、インボイス制度に対応するため「適格請求書発行事業者」の登録を済ませておく必要があります。未登録の場合は、所轄の税務署へ登録申請書を提出し、登録番号の通知を受けなければなりません。 - 卸売業者への登録番号の通知
取引のある卸売業者に対して、ご自身の氏名または名称と、適格請求書発行事業者の登録番号を事前に通知します。この通知がないと、卸売業者は特例を適用した書類を作成できず、買受人が仕入税額控除を受けられなくなる可能性があります。通知方法に法的な定めはありませんが、トラブルを避けるためにも書面やメールなど記録の残る形で行うと安心です。
卸売業者が行う市場特例の手続きは?必要書類や届出先
卸売業者も、市場特例を適用するために税務署への特別な届出は不要です。卸売業者の主な役割は、出荷者に代わって、インボイスの要件を満たした書類を買受人へ交付することです。
交付書類の記載事項
卸売業者は、買受人に交付する売上票や仕切書などの書類に、通常のインボイスの記載事項に加えて、ご自身の登録番号を記載する必要があります。これにより、その書類がインボイスとして扱われます。
|
記載事項 |
内容 |
|
書類作成者 |
卸売業者の氏名または名称および登録番号 |
|
取引年月日 |
課税資産の譲渡等を行った年月日 |
|
取引内容 |
販売した商品名(軽減税率の対象品目である旨) |
|
税率ごとの合計額と適用税率 |
税率(8%・10%)ごとに区分して合計した対価の額(税抜または税込)および適用税率 |
|
税率ごとの消費税額等 |
税率ごとに区分した消費税額等 |
|
書類の交付を受ける事業者 |
買受人の氏名または名称 |
|
(参考)出荷者情報 |
出荷者の氏名または名称(※国税庁のQ&Aでは、出荷者の登録番号の記載は不要とされています) |
書類の保存義務
卸売業者は、以下の2種類の書類を、課税期間の末日の翌日から2ヶ月を経過した日から7年間保存する義務があります。
- 買受人へ交付した書類(売上票など)の写し
- 出荷者から交付を受けた、自身の登録番号が記載された書類(売上票や精算書など)の写し
買受人の市場特例の必要書類は?必要な手続き
卸売市場で商品を仕入れる買受人(小売店や飲食店など)も、市場特例を利用するために税務署への特別な届出は不要です。仕入税額控除を受けるためには、卸売業者から交付される書類を適切に保存することが重要になります。
仕入税額控除のために必要なこと
買受人は、卸売業者から交付された「売上票」や「仕切書」などを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることができます。この書類が、インボイス(適格請求書)の代わりとなります。
受け取った書類に、以下の項目が正しく記載されているかを確認しましょう。
- 卸売業者の氏名または名称および登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(品目)
- 税率ごとに区分した合計額および適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
- 自身の氏名または名称
これらの記載がある書類と、取引の事実を記録した帳簿の両方を、定められた期間(原則7年間)保存することで、仕入税額控除が認められます。
まとめ
インボイス制度における「卸売市場特例」は、生産者の方々の事務負担を減らすために設けられた制度です。この特例を活用することで、出荷者がインボイスを発行する代わりに、卸売業者が買受人へ対応できるようになります。ただし、適用にはそれぞれの立場で必要な条件や書類の保存が求められますので、ご自身の役割をしっかり確認したうえで、制度に沿った対応を進めていただければと思います。










