軽油税にインボイスは必要?消費税の扱いや請求書・領収書の正しい処理方法を解説
更新日:2025.12.06
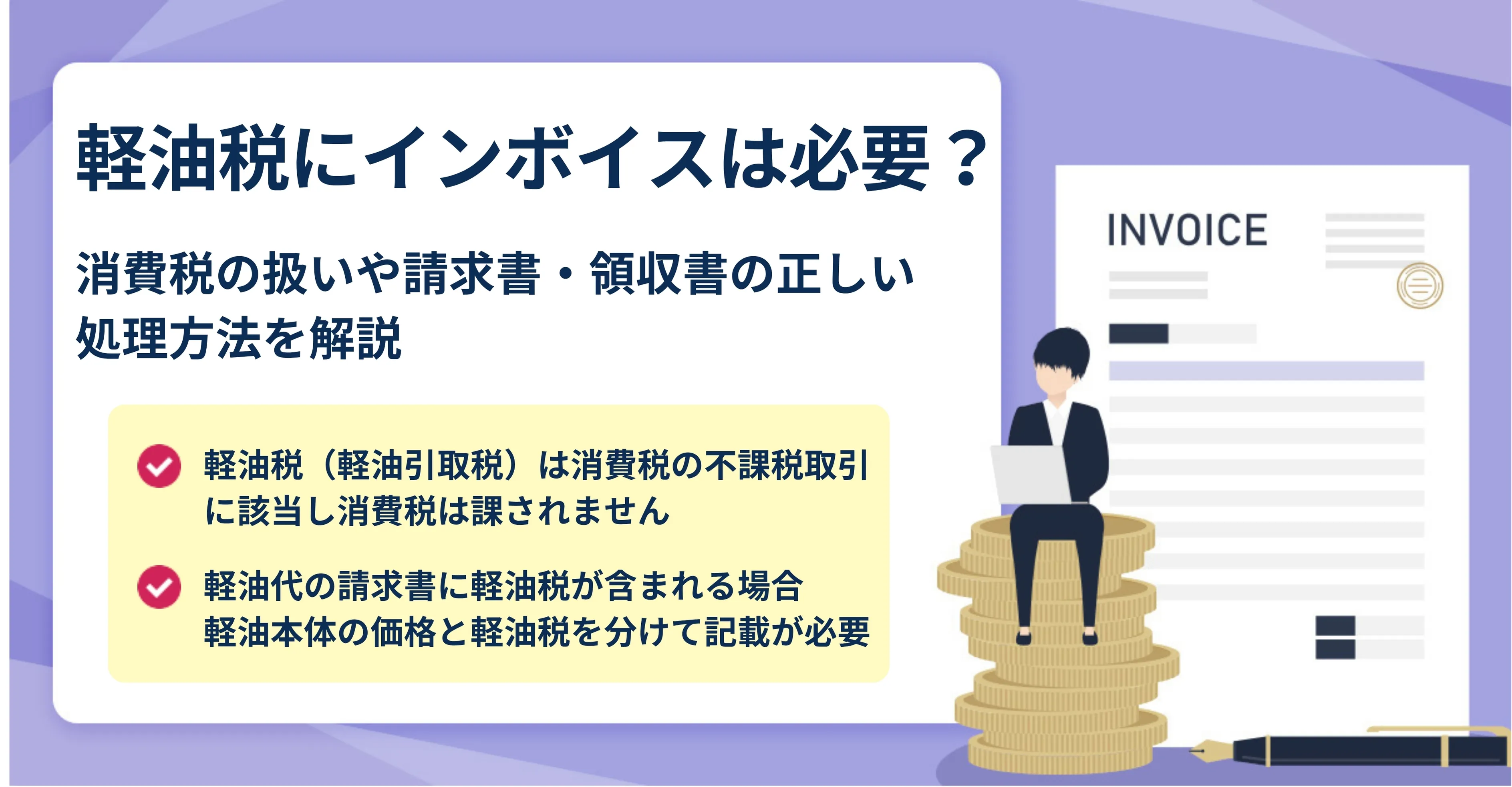
ー 目次 ー
軽油税そのものは消費税の「不課税」に該当するため、インボイス(適格請求書)の交付は不要です。
しかし、軽油の仕入れには消費税が含まれているため、インボイス制度の対象から完全に外れるわけではありません。
たとえば、ガソリンスタンドや燃料業者から軽油を購入する場合、
請求書や領収書には軽油税と消費税の内訳が分かるように記載されている必要があります。
正しく消費税額を仕入税額控除するには、軽油税を除いた課税対象額に対して
インボイスが交付されていること、そして帳簿と適格請求書の保存が必須です。
この記事では、軽油税が消費税において「不課税」となる理由を解説し、軽油代の請求書や領収書でインボイスが必要な場合と不要な場合を具体的に説明します。正しい処理方法を理解し、仕入税額控除の適用や経理業務をスムーズに進めるための知識が得られます。
軽油税とは?インボイス制度の基本もおさらい
この章では、まずインボイス制度と軽油税それぞれの基本的な知識について、わかりやすく解説します。
そもそもインボイス制度とは?わかりやすく解説
インボイス制度とは、正式名称を「適格請求書等保存方式」といい、2023年10月1日から開始された消費税の仕入税額控除に関する新しい制度です。この制度の主な目的は、複数税率(8%と10%)に対応した消費税の仕入税額控除の仕組みをより適正なものにすることです。
インボイス制度導入後の大きな変更点は、買い手側が消費税の仕入税額控除を受けるためには、原則として売り手側から交付された「適格請求書(インボイス)」の保存が必要になったことです。適格請求書には、発行事業者の登録番号や適用税率、税率ごとの消費税額などが正確に記載されている必要があります。
この制度は、課税事業者だけでなく、免税事業者にも影響を与える可能性があります。例えば、免税事業者は適格請求書を発行できないため、取引先である課税事業者が仕入税額控除を受けられなくなるケースが出てくるため、取引の見直しが行われることもあります。
軽油税とは?軽油引取税の概要と目的
軽油税とは、正式には「軽油引取税」と呼ばれる地方税の一つです。この税金は、バスやトラック、一部の乗用車などのディーゼルエンジンを搭載した車両の燃料として使用される軽油の「引取り」に対して課税されます。
軽油引取税は、最終的には軽油を購入する消費者や事業者が負担しますが、納税の事務手続きは、軽油を販売する特約業者や元売業者(ガソリンスタンドなど)が「特別徴収義務者」として行い、各都道府県に納入する仕組みとなっています。つまり、消費者は軽油の代金と一緒に軽油引取税を支払い、販売業者がそれをまとめて納税しているのです。
この税金の主な目的は、道路の建設、改良、維持、修繕といった道路整備に関する費用や、その他交通に関連する施策の財源に充てられることです。私たちの生活や経済活動に不可欠な道路インフラを支える重要な役割を担っています。
軽油引取税の概要を以下にまとめます。
|
項目 |
内容 |
|
正式名称 |
軽油引取税 |
|
課税物件 |
軽油の引取り(特約業者または元売業者からの引取り) |
|
納税義務者 |
軽油の引取りを行う者(実質的には軽油の購入者が負担) |
|
特別徴収義務者 |
軽油の販売を行う特約業者または元売業者(ガソリンスタンド等) |
|
税率 |
1リットルにつき32.1円 (2024年5月現在。本則税率15.0円に、当分の間の税率として17.1円が加算されています) |
|
課税主体 |
都道府県(地方税) |
|
使途目的 |
主に道路の建設・維持管理などの財源 |
軽油の店頭価格には、この軽油引取税が含まれています。そのため、軽油代の請求書や領収書を確認する際には、軽油本体の価格と軽油引取税額を区別して理解しておくことが、インボイス制度との関連を考える上でも重要になります。
軽油税は課税対象?非課税・不課税の正しい区分とは
インボイス制度を理解する上で、軽油にかかる税金、特に軽油税(軽油引取税)が消費税の課税対象となるのか、それともならないのかを正確に把握しておくことは非常に重要です。ここでは、消費税における「非課税」「不課税」といった税区分の基本から、軽油税がどのように扱われるのかを詳しく解説します。
「非課税」と「不課税」はどう違う?税区分の基本を整理
消費税の対象となる取引かどうかを判断する際、「課税」「非課税」「不課税」という3つの区分があります。これらの違いを理解することは、インボイス制度における適切な経理処理の第一歩となります。
「非課税」と「不課税」はどちらも消費税がかからない点では共通していますが、その性質や理由は異なります。「非課税」は本来課税対象となり得るもののうち政策的に課税しないものを指し、「不課税」は初めから消費税の課税要件を満たさない取引を指します。
|
税区分 |
概要 |
具体例 |
|
課税取引 |
国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、貸付け、役務の提供など、消費税が課される取引。 |
商品の販売、運送サービスの提供、事務所の家賃(事業用)など。 |
|
非課税取引 |
消費税の性格から課税対象としてなじまないものや、社会政策的な配慮から消費税を課さないと法律で定められている特定の取引。仕入れにかかった消費税は原則として仕入税額控除ができません。 |
土地の譲渡・貸付け、有価証券の譲渡、預貯金の利子、社会保険医療、介護保険サービス、学校の授業料など。 |
|
不課税取引(課税対象外取引) |
そもそも消費税の課税の対象とならない取引。事業として行われない取引や、対価性がない取引などが該当します。 |
国外取引、給与・賃金、寄付金、祝金、損害賠償金、配当金、保険金、軽油税・ゴルフ場利用税・入湯税などの一部の租税。 |
軽油税の消費税はなぜ「不課税」になるのか?根拠と実務的な意味
軽油税、正式には「軽油引取税」と呼ばれるこの税金は、地方税法に基づき、軽油の引取りに対して課される地方税です。ガソリンスタンドなどで軽油を購入する際、軽油本体の価格とは別に軽油引取税が課されています。
では、この軽油税は消費税の観点からどのように扱われるのでしょうか。結論から申し上げますと、軽油税(軽油引取税)は消費税の「不課税取引」に該当します。つまり、軽油税そのものには消費税は課されません。
その主な根拠は以下の通りです。
- 租税の性格:軽油引取税は、軽油の引取りという特定の行為に対して課される目的税であり、消費税の課税対象となる「資産の譲渡等」の対価には当たらないと解釈されます。国税庁の見解でも、軽油引取税、ゴルフ場利用税、入湯税などは、消費税の課税対象とならない不課税取引として扱われています。
- 二重課税の回避:仮に軽油税に消費税が課されると、税金に対してさらに税金が課されるという二重課税の状態が生じる可能性があります。消費税法では、このような二重課税を避けるための調整が行われています。
実務的な意味としては、以下の点が重要になります。
- 請求書・領収書での区分:軽油を販売する事業者は、請求書や領収書において、軽油本体の価格と軽油税額を明確に区分して記載する必要があります。消費税は軽油本体の価格に対してのみ計算されます。
- 仕入税額控除の対象外:軽油税部分は消費税の不課税取引であるため、買い手側は軽油税部分について消費税の仕入税額控除を行うことはできません。仕入税額控除の対象となるのは、軽油本体価格に係る消費税額のみです。
軽油代の請求書にインボイスが必要なケース・不要なケース
軽油代の請求書や領収書におけるインボイスの必要性は、軽油本体の価格部分と軽油税(軽油引取税)部分で扱いが異なります。ここでは、それぞれのケースについて、消費税の仕入税額控除の観点から詳しく解説します。
インボイスが必要なケース|軽油本体に対する仕入税額控除の要件
軽油の購入代金のうち、軽油本体の価格部分は消費税の課税対象となります。したがって、買い手が仕入税額控除を受けるためには、原則として売り手であるガソリンスタンドなどの適格請求書発行事業者から発行された適格請求書(インボイス)の保存が必要です。
適格請求書には、登録番号、適用税率、税率ごとに区分した消費税額などが記載されている必要があります。買い手は、受け取った適格請求書を法令で定められた期間保存する義務があります。
|
項目 |
詳細 |
|
インボイスが必要な対象 |
軽油本体の価格部分(消費税課税対象) |
|
インボイスの要否 |
原則として必要 |
|
主な理由 |
軽油本体価格に係る消費税の仕入税額控除を受けるため |
|
ポイント |
売り手が適格請求書発行事業者であり、適格請求書の記載要件を満たしていること。買い手はインボイスを適切に保存すること。 |
インボイスが不要なケース|軽油税部分の処理と記帳の注意点
軽油代に含まれる軽油税(軽油引取税)は、消費税の課税対象外です。そのため、軽油税部分については消費税の仕入税額控除という概念が存在せず、インボイスも不要となります。
請求書や領収書においては、軽油本体価格と軽油税額が区分して記載されていることが一般的です。経理処理を行う際には、軽油本体価格(課税仕入れ)と軽油税(租税公課などの費用科目で処理、消費税対象外)を分けて記帳する必要があります。
|
項目 |
詳細 |
|
インボイスが不要な対象 |
軽油税(軽油引取税)部分 |
|
インボイスの要否 |
不要 |
|
主な理由 |
軽油税は消費税の課税対象外(不課税または非課税扱い)であるため |
|
ポイント |
請求書等で軽油本体価格と軽油税額が明確に区分されていること。経理処理上も、軽油税は消費税の仕入税額控除の対象とならないため、区分して処理すること。 |
このように、軽油の取引においては、軽油本体価格と軽油税でインボイス制度上の取り扱いが異なります。仕入税額控除を正しく行うためには、これらの違いを理解し、請求書や領収書の記載内容を確認した上で、適切な経理処理を行うことが重要です。
軽油税が記載された請求書・領収書の正しい書き方とは?
インボイス制度の開始に伴い、軽油取引における請求書や領収書の取り扱いにも変更点が生じています。特に、軽油税が含まれる場合の記載方法や、仕入税額控除の適用可否について正しく理解しておくことが重要です。この章では、軽油税が記載された請求書・領収書の具体的な書き方や、買い手側・売り手側双方の注意点について詳しく解説します。
軽油税はいくら?税率とリットル数からの計算方法
軽油税(正式名称:軽油引取税)は、軽油の引取数量に基づいて課税される地方税です。現在の標準税率は、1キロリットルあたり32,100円、つまり1リットルあたり32.1円と定められています。
したがって、軽油税の金額は以下の計算式で求められます。
軽油税額 = 給油した軽油の数量(リットル) × 32.1円/リットル
例えば、50リットルの軽油を給油した場合、軽油税額は 50L × 32.1円/L = 1,605円 となります。この軽油税額は、請求書や領収書に明記されることになります。
軽油税を含む請求書の正しい書き方
インボイス制度(適格請求書等保存方式)においては、仕入税額控除を受けるために、原則として適格請求書(インボイス)の保存が必要です。軽油代の請求書に軽油税が含まれる場合、軽油本体の価格と軽油税を分けて記載し、消費税の取り扱いを明確にする必要があります。
適格請求書には、以下の事項を記載しなければなりません。
- 適格請求書発行事業者の登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象品目である旨も記載)
- 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜または税込)および適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
- 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
軽油の請求書における記載例は以下の通りです。
|
項目 |
記載例 |
備考 |
|
発行事業者登録番号 |
T1234567890123 |
|
|
宛名 |
株式会社〇〇 様 |
|
|
取引年月日 |
2023年10月26日 |
|
|
品名 |
軽油 |
|
|
数量 |
100 リットル |
|
|
単価(税抜) |
120 円/リットル |
軽油本体の単価 |
|
軽油本体価格(税抜) |
12,000 円 |
100L × 120円 |
|
消費税額(10%) |
1,200 円 |
12,000円 × 10% |
|
軽油税(不課税) |
3,210 円 |
100L × 32.1円 |
|
合計金額 |
16,410 円 |
(軽油本体価格 + 消費税額) + 軽油税 |
上記のように、軽油税は消費税の課税対象外(不課税または非課税)であるため、消費税額の計算には含めません。「軽油税(不課税)」や「軽油税(消費税等対象外)」などと明記することで、税区分を明確にすることが重要です。
軽油税が"記載されていない"請求書はリスクがある?
はい、軽油税が明確に記載されていない請求書は、
消費税の仕入税額控除において否認リスクを伴います。
軽油本体価格と軽油引取税の区分があいまいだと、
不課税部分を含めて誤って控除してしまう可能性があるためです。
特にインボイス制度の導入後は、
課税対象となる軽油本体価格のみが適格請求書に明記され、
不課税である軽油税とは明確に区別されていなければなりません。
請求書の適正性を欠くと、税務調査時に指摘される可能性もあるため、
取引先に軽油税の記載を依頼し、課税区分が明確な帳票を受け取ることが、
実務上のリスクヘッジになります。
軽油税を含む領収書の記載方法
ガソリンスタンドなどで給油した際に受け取るレシート形式の領収書も、インボイス制度に対応した記載が求められます。多くの場合、これらは適格簡易請求書の要件を満たすように発行されます。
適格簡易請求書では、書類の交付を受ける事業者の氏名または名称の記載は不要です。領収書においても、軽油本体価格、それに対する消費税額、そして軽油税額が区別して記載されることが一般的です。軽油税部分には「軽油税」や「(内)軽油税」といった形で金額が示され、消費税の計算からは除外されます。
買い手側が行うインボイスの保存と経理処理のポイント
買い手側は、仕入税額控除の適用を受けるために、交付された適格請求書または適格簡易請求書を保存する必要があります。保存期間は、その課税期間の末日の翌日から2ヶ月を経過した日から7年間と定められています。
経理処理を行う際には、軽油の代金を「車両費」「燃料費」「仕入高」などの費用勘定で処理し、そのうち軽油本体価格にかかる消費税を「仮払消費税等」として計上します。軽油税部分は消費税の課税対象外であるため、仕入税額控除の対象にはなりません。軽油税は「租税公課」として処理するか、燃料費などに含めて費用処理します。
例えば、軽油代金16,410円(内、軽油本体価格12,000円、消費税1,200円、軽油税3,210円)を現金で支払った場合の仕訳例は以下のようになります。
|
借方 |
金額 |
貸方 |
金額 |
|
車両費 (または燃料費) |
12,000円 |
現金 |
16,410円 |
|
仮払消費税等 |
1,200円 |
||
|
租税公課 (または車両費に含める) |
3,210円 |
電子帳簿保存法の要件を満たせば、これらの書類を電子データで保存することも可能です。
売り手側(ガソリンスタンド等)のインボイス発行義務と注意点
適格請求書発行事業者の登録を受けた売り手(ガソリンスタンドなど)は、課税事業者である買い手から求められた場合、インボイス(適格請求書または適格簡易請求書)を交付する義務があります。
発行するインボイスには、前述の通り、軽油本体価格と軽油税を明確に区分し、それぞれの税率や税額を正しく記載する必要があります。特に、軽油税が消費税の課税対象ではないことを明確に示し、誤って消費税額に含めてしまわないよう注意が必要です。
POSシステムやレジシステムを利用している場合は、インボイス制度に対応した設定がされているかを確認し、必要に応じて改修やアップデートを行います。手書きでインボイスを発行する場合も、記載事項に漏れがないよう、国税庁の示す様式などを参考に正確に作成しましょう。
また、交付したインボイスの写しを保存する義務も発生します。保存期間は、交付した日の属する課税期間の末日の翌日から2ヶ月を経過した日から7年間です。
特例措置はある?免税軽油とインボイス制度の関係
免税軽油制度の仕組みを理解する
免税軽油制度とは、特定の事業者が法律で定められた特定の用途に軽油を使用する場合に、軽油引取税が免除される制度です。この制度は、主に農林漁業や特定の製造業、運送業などの事業活動を支援し、産業振興やコスト負担の軽減を図ることを目的としています。
免税軽油の適用を受けるためには、事業者はあらかじめ管轄の都道府県税事務所などに申請し、「免税軽油使用者証」の交付を受ける必要があります。そして、実際に軽油を購入する際には、この免税軽油使用者証を提示するとともに、使用量に応じた「免税券」を販売業者(ガソリンスタンドなど)に提出します。これらの手続きは地方税法に基づいて厳格に運用されています。
免税軽油の対象となる主な事業と用途の例は以下の通りです。
|
対象事業 |
主な用途例 |
|
農業 |
農耕用トラクター、田植機、コンバインなどの動力 |
|
林業 |
高性能林業機械(ハーベスタ、フォワーダ等)、チェーンソー、刈払機などの動力 |
|
漁業(船舶) |
登録漁船の主機関及び補機関の動力 |
|
鉱物採掘業 |
鉱山で使用する掘削機械、運搬車両などの動力 |
|
製造業の一部 |
陶磁器製造業における窯業用機械の動力、セメント製品製造業における汽かん等の熱源 |
|
港湾運送業 |
港湾区域内で使用するフォークリフト、ストラドルキャリアなどの荷役機械の動力 |
|
鉄道・軌道事業 |
ディーゼル機関車、気動車などの鉄道車両・軌道車両の動力 |
上記は一例であり、対象となる事業や用途は地方税法および関連法令で詳細に定められています。
免税軽油取引におけるインボイスの扱いはどうなるか
免税軽油の取引においても、インボイス制度への対応が求められます。重要なのは、免税軽油制度によって免除されるのは「軽油引取税」であり、軽油本体の代金に含まれる「消費税」は免除されないという点です。したがって、免税軽油の購入者が課税事業者であり、軽油本体にかかる消費税について仕入税額控除を受けたい場合には、原則として適格請求書(インボイス)の保存が必要となります。
売り手側(ガソリンスタンド等)の対応
免税軽油を販売するガソリンスタンドなどの事業者(適格請求書発行事業者である場合)は、免税軽油使用者(買い手)から適格請求書(インボイス)の交付を求められた際には、これに応じる義務があります。発行するインボイスには、通常の課税取引と同様に、登録番号、取引年月日、取引内容(「軽油」など)、税率ごとに区分した対価の額および適用税率、税率ごとに区分した消費税額等を正確に記載する必要があります。免税となる軽油引取税額については、インボイスの必須記載事項ではありませんが、買い手の経理処理の便宜のため、請求書や領収書に参考情報として区分して記載することが望ましい対応とされています。
買い手側(免税軽油使用者)の対応
免税軽油を使用する事業者(買い手)が、軽油本体の購入にかかる消費税について仕入税額控除の適用を受けるためには、売り手から交付された適格請求書(インボイス)を適切に保存することが必要です。従来通り、給油時には免税軽油使用者証と免税券を提示しますが、これらはあくまで軽油引取税の免税手続きに関する書類であり、消費税の仕入税額控除のためのインボイスとは役割が異なります。したがって、免税証等を提示したからといってインボイスの受領が不要になるわけではありません。受領したインボイスに基づき、軽油本体の消費税額を帳簿に記載し、適切に経理処理を行うことが求められます。
まとめ
結論として、軽油税は消費税の課税対象外であるため、インボイスは不要ですが、軽油本体の代金については課税取引にあたるため、適格請求書(インボイス)の保存が必要です。請求書や領収書では、軽油本体と軽油税を区分し、消費税の扱いを明確に記載することが重要です。免税軽油などの特例についても注意点がありますので、該当する事業者の方は確認のうえ、実務にご活用ください。










