インボイス対応後の仕訳入力はこう変わる!実例付きでわかりやすく解説
更新日:2025.12.06
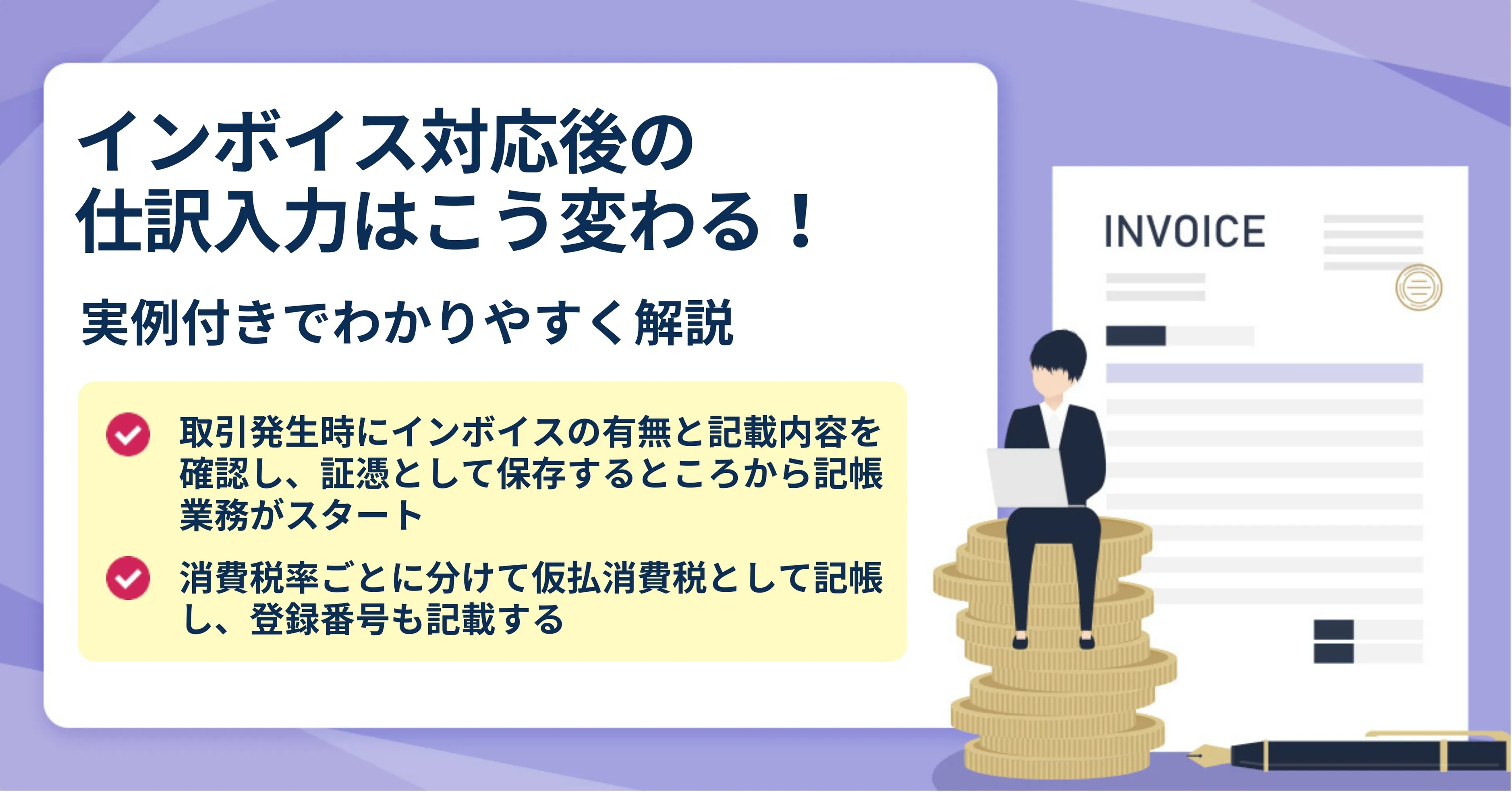
ー 目次 ー
インボイス制度対応後の仕訳入力は、消費税区分や適格請求書保存要件など大きな変化が生じています。本記事では、制度の概要から実際の仕訳例、よくある注意点までをわかりやすく解説。この記事を読めば、インボイス制度に沿った正しい仕訳入力方法が実践できるようになります。
インボイス制度とは?
インボイス制度(適格請求書等保存方式)は、2023年10月1日から導入された日本の消費税制度における新しい仕組みです。簡単に言うと、「仕入税額控除」を正しく行うために、一定の要件を満たした請求書(インボイス)を発行・保存することが必要になる制度です。これにより、取引ごとに消費税の控除要件や記録の方法が大きく変わりました。
インボイス制度の要件
インボイス制度の下では、適格請求書(インボイス)の発行と保存が重要なポイントとなります。ここではインボイスの要件を詳しく整理します。
|
要件項目 |
詳細内容 |
|
発行者 |
適格請求書発行事業者(課税事業者として登録された者)のみ発行可能 |
|
記載事項 |
|
|
保存方法 |
紙または電子データにより、一定期間保存が義務付けられる |
|
税率毎の表示 |
標準税率(10%)・軽減税率(8%)それぞれの合計額および消費税額を明記 |
これらの要件を満たしている請求書や領収書のみが「適格請求書」となり、仕入税額控除の要件として有効になります。
インボイス制度導入の背景
インボイス制度は、従来の区分記載請求書等保存方式に比べて、消費税の適正な納税と仕入税額控除をより明確化する目的で導入されました。社会的背景としては、消費税率引き上げ、複数税率(軽減税率)の導入による納税管理の複雑化、不正な仕入税額控除の防止といった課題がありました。
また、欧州連合(EU)をはじめとする多くの国でもインボイス制度が導入されており、国際的な会計・税務基準への整合性を図る狙いもありました。これにより、日本国内でも透明性の高い消費税の管理が期待されています。
インボイス制度の仕訳入力への影響は?
インボイス制度導入後、仕訳入力の実務にはいくつかの大きな影響があります。主なポイントは以下の通りです。
- 取引先や取引内容ごとに、適格請求書の有無や税率の確認が必要となる
- 消費税区分(課税、非課税、免税、軽減税率など)を従来以上に正確に区分して仕訳する必要がある
- 適格請求書発行事業者の「登録番号」を仕訳明細や証憑として記録・管理する必要がある
- 免税事業者との取引では、仕入税額控除ができなくなるため、勘定科目・補助科目・摘要欄等への記録方法が変わる
- 会計ソフトや経理システム側でもインボイス対応バージョンへの改修または設定が不可欠となる
これらの変化に適切に対応することが、今後の経理業務、ひいては税務申告において重要となります。特に中小企業や個人事業主の場合、新しい記帳方法や証憑管理の徹底が求められるため、制度の仕組みを正しく理解し実務に落とし込むことが必須となっています。
インボイス制度導入後の仕訳入力の基本的な流れ!
インボイス制度(適格請求書等保存方式)が導入されたことで、日々の会計記帳や仕訳入力の手順や注意点が大きく変わりました。ここでは、インボイス対応後における仕訳入力の基本的なフローについて、業務の実務レベルで詳しく解説します。
1. 取引内容の確認と帳票類の取得
まず、取引が発生した際に「適格請求書(インボイス)」かどうかを必ず確認します。インボイスには、発行者の登録番号、取引年月日、取引内容、税率ごとの消費税額など、法定の記載事項が必要です。受け取った請求書や領収書がインボイス要件を満たしているかチェックした上で、証憑として保存します。
2. 消費税区分の判定
インボイス制度後は、仕訳入力ごとに消費税の区分を正確に判定する必要があります。課税仕入、課税売上のほか、非課税や不課税取引、免税事業者との取引であるかどうかを証憑から判断し、適切な消費税区分を決定します。
|
取引内容 |
インボイス要件 |
消費税区分 |
証憑保存義務 |
|
課税仕入(適格請求書あり) |
登録番号等あり |
課税(仕入税額控除可) |
必要 |
|
課税仕入(適格請求書なし) |
登録番号未記載 |
課税(仕入税額控除不可) |
必要 |
|
非課税・不課税取引 |
不要 |
非課税 / 不課税 |
必要 |
|
免税事業者からの仕入 |
登録番号なし |
課税(仕入税額控除不可 or 経過措置) |
必要 |
3. 仕訳入力の初期設定と勘定科目の選定
証憑をもとに、商取引の内容や目的に合った勘定科目(例:仕入、消耗品費、旅費交通費など)を選びます。インボイス制度後は、消費税の税率毎(10%、8%など)が明確に分かるよう入力が必要です。税率混在取引の場合は、「税率ごとの合計金額」や「消費税額」を分割して入力します。
4. 適格請求書番号や消費税額などの情報入力
仕訳入力時には、インボイスの登録番号や消費税額、また税率ごとの内訳を会計システムに入力します。多くの会計ソフトでは、インボイス番号や税率ごとの区分入力欄が設けられていますので、入力漏れがないよう注意が必要です。
|
必要な情報 |
入力内容 |
|
適格請求書発行事業者登録番号 |
「T」から始まる13桁の番号 |
|
消費税率 |
10%・8%など税率ごとに分類 |
|
消費税額 |
税抜金額・税込金額・税額欄に分けて |
|
取引日 |
実際のサービスや物品の提供日 |
|
取引先名(仕入先・顧客名) |
証憑に記載のまま |
5. 仕入税額控除の適用判断
入力後、適正に仕入税額控除が受けられる取引かどうかの判定も重要です。適格請求書発行事業者でない相手先との取引は、仕入税額控除が受けられません(経過措置期間中は一部控除可)。会計システムで自動判定できる場合もありますが、手入力の場合は特に注意しましょう。
6. 仕訳入力後の証憑書類保存とチェック
仕訳入力が完了したら、インボイスおよび関係書類を電子保存もしくは紙で整理・保管します。保存要件には注意し、証憑の管理台帳やチェックリスト等を併用することで、税務調査時の対応もスムーズになります。
|
証憑の保存方法 |
ポイント |
|
電子保存 |
会計ソフトやクラウドストレージで原本データ保存 |
|
紙保存 |
ファイリングルールを設けて管理台帳と紐付け |
|
両方併用 |
電子保存+紙保存で証憑の二重管理が確実 |
7. 定期的な記帳・仕訳内容の見直し
インボイス制度導入により、消費税申告や帳簿の適正化が重視されています。定期的に仕訳内容や証憑ファイルの点検を行い、不備がないかチェックしましょう。特に決算や確定申告前には、税率区分やインボイス番号、記載漏れなどの最終確認が重要です。
消費税区分ごとの仕訳入力方法の違いとは?
インボイス制度の導入により、取引ごとに消費税の区分を正確に把握し、適切に仕訳入力することが今まで以上に重要になっています。区分ごとに会計処理や記帳内容が異なるため、インボイス対応後に求められる消費税区分毎の仕訳入力の違いを詳しく解説します。
課税仕入の場合の仕訳入力
課税仕入とは、適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)から受けた課税対象の取引を指します。消費税額控除を適用するためには、インボイスの保存が必須条件となりました。
仕訳入力の際は「仕入/経費」に対応する科目のほか、「仮払消費税」など消費税の仕訳を明確に行います。
|
取引内容 |
借方科目 |
貸方科目 |
消費税区分 |
インボイス保存要否 |
|
商品仕入(課税取引・8%) |
仕入 100,000円 仮払消費税 8,000円 |
買掛金 108,000円 |
課税(8%) |
要 |
|
備品購入(課税取引・10%) |
備品 200,000円 仮払消費税 20,000円 |
現金 220,000円 |
課税(10%) |
要 |
適格請求書(インボイス)の発行事業者かどうかを必ず確認し、仕訳の備考欄にインボイス番号(登録番号)を記載すると記録管理が容易になります。また、消費税率ごとに区分集計する必要があるため、複数税率取引の場合の入力には特に注意しましょう。
免税事業者からの取引時の仕訳入力
免税事業者はインボイス発行ができません。そのため、免税事業者からの仕入れについてはインボイス保存要件を満たさず、原則として仕入税額控除が出来なくなります。仕訳入力時の消費税区分設定も変わるので慎重な対応が求められます。
|
取引内容 |
借方科目 |
貸方科目 |
消費税区分 |
仕入税額控除 |
|
デザイン料(免税事業者取引) |
広告宣伝費 50,000円 |
未払金 50,000円 |
対象外(消費税区分:対象外や区分なしで処理された仕訳など会計ソフトに応じて選択) |
不可 |
免税事業者取引で仕入税額控除の対象外となった場合、仕訳上は課税仕入とは区別し、「対象外」や「区分なし」等の消費税区分で備考欄に「免税事業者のためインボイスなし」等の説明を残しておくと税務調査でも説明が明確です。
非課税・不課税取引の仕訳入力ポイント
非課税取引や不課税取引も適切に区分する必要があります。会計ソフト上では「非課税」「不課税」など専用の区分を選択する場合が多く、消費税額の集計に含めず誤って計上することのないよう注意しましょう。
|
取引内容 |
借方科目 |
貸方科目 |
消費税区分 |
|
家賃支払 |
地代家賃 120,000円 |
普通預金 120,000円 |
非課税 |
|
給与支払 |
給与手当 300,000円 |
普通預金 300,000円 |
不課税 |
|
寄附金支出 |
寄附金 10,000円 |
普通預金 10,000円 |
不課税 |
非課税取引には土地の譲渡や家賃、利息等が、不課税取引には給与や配当金、社会保険料等が該当します。これらの区分を正しく選択しないと、消費税計算や申告時に誤りが生じるため注意が必要です。
消費税区分別 仕訳整理のポイント
消費税区分ごとの仕訳入力には、以下のポイントを押さえることが求められます。
- 取引相手が適格請求書発行事業者か(インボイス発行の有無)を確認し入力する
- 課税取引は税率(8%、10%等)ごとに区分して入力する
- 免税事業者との取引では消費税区分を「対象外」または「区分なし」で記帳し、控除不可を明確にする
- 非課税・不課税取引はそれぞれ専用の区分で入力し、誤った消費税集計を防ぐ
- 備考欄欄や会計ソフトのメモ機能などを活用し、インボイス番号や免税事業者である旨を記録する
インボイス制度施行後は、会計ソフトの消費税区分機能を適切に利用することで、より正確に仕訳入力を行うことが可能となります。
実際の仕訳入力例と解説!
一般的な仕入取引の実例
インボイス制度導入後は、適格請求書(インボイス)に基づいた仕訳入力が求められます。ここでは、株式会社Aが商品を仕入れた際の実際の仕訳例を紹介します。
|
取引日 |
内容 |
借方科目 |
金額(税抜) |
消費税 |
貸方科目 |
摘要(適格請求書番号) |
|
2024/4/10 |
商品の仕入 |
仕入 |
100,000 |
10,000 |
買掛金 |
T1234567890123 |
この例では、税込110,000円の商品を仕入れた場合です。「適格請求書発行事業者番号」を摘要欄に記載することで、仕入税額控除を正しく行えるようにします。消費税額を別区分で記入することもインボイス制度における重要なポイントです。
経費精算時の仕訳入力例
交通費や消耗品などの経費を社員が立替払いする場合も、インボイスへの対応が必要です。以下は交通費精算の実例です。
|
取引日 |
内容 |
借方科目 |
金額 |
消費税区分 |
貸方科目 |
摘要(請求書番号・詳細) |
|
2024/4/15 |
新幹線代 |
旅費交通費 |
16,500 |
課税10% |
未払金 |
T9876543210987(適格請求書あり) |
インボイス対応対象の交通機関(例:JR東日本など)から適格請求書を受領し、摘要欄に「T」から始まる登録番号を記録します。経費精算の際も、消費税額区分や適格請求書の保存が必須です。
仕入返品や値引き取引の仕訳入力例
返品・値引きの場合もインボイス番号の確認・記載が重要です。以下は前述の仕入の返品が発生した場合の仕訳例です。
|
取引日 |
内容 |
借方科目 |
金額(税抜) |
消費税 |
貸方科目 |
摘要(適格請求書番号) |
|
2024/4/20 |
商品の返品 |
買掛金 |
10,000 |
1,000 |
仕入 |
T1234567890123(返品分) |
返品分の仕訳では、消費税も連動して逆仕訳を記帳します。摘要欄には該当インボイス番号とともに「返品分」と明記すると、確認作業がスムーズです。同様に値引き時もインボイス番号を必ず記録しましょう。
課税、免税、非課税取引の違いの実例
インボイス制度では取引の相手先や内容によって、仕訳入力時の消費税区分の扱いが異なります。例をまとめると下記の通りです。
|
区分 |
借方科目 |
金額 |
消費税 |
貸方科目 |
インボイス記載 |
|
課税取引 |
仕入 |
220,000 |
20,000 |
買掛金 |
あり(T番号) |
|
免税事業者からの仕入 |
仕入 |
55,000 |
0 |
買掛金 |
なし |
|
非課税(例:家賃) |
地代家賃 |
100,000 |
0 |
普通預金 |
不要 |
課税取引は必ずインボイス番号を記入します。免税事業者との取引はインボイスの交付・番号記載が不可となるため、仕入税額控除対象外です。非課税取引(家賃・給与等)は従来通りの処理ですが、混同しないよう「消費税区分」の明示を意識しましょう。
現金取引・現金出納帳への入力実例
小規模事業者など現金出納帳で管理している場合も、インボイス番号が必要です。例えば、消耗品代金を現金購入した場合は以下の通り入力します。
|
日付 |
内容 |
入金 |
出金 |
科目 |
消費税区分 |
摘要 |
|
2024/4/27 |
消耗品購入 |
5,500 |
消耗品費 |
課税10% |
T2233445566778 |
現金管理帳簿でも摘要欄などでインボイス番号の記載を徹底しましょう。帳簿と請求書・領収書の双方で番号の紐付け保存が要点です。
知っておきたい仕訳入力に関する注意点とよくある質問
領収書や請求書の保存要件の変更とは?
インボイス制度の導入により、仕訳入力を正確に行うためには、取引に関する領収書や請求書の保存要件に注意が必要です。インボイス(適格請求書)を保存しなければ消費税の仕入税額控除ができなくなるため、以下の項目が記載されている適格請求書を必ず保存しましょう。
|
項目名 |
保存要件 |
|
発行者の氏名または名称及び登録番号 |
インボイス発行事業者の名称・登録番号が必要 |
|
取引年月日 |
実際の取引が行われた日付 |
|
取引内容 |
品目・数量・金額(税抜・税込) |
|
税率ごとに区分した消費税額等 |
消費税率ごとの区分記載が必須 |
|
受領者の氏名または名称 |
取引先の名称または氏名 |
電子帳簿保存法への対応も進んでおり、電子データで受領した場合は原則電子保存が必要です。紙で保存する場合も、インボイスの記載要件を満たしているかを必ず確認し、不備や記載漏れがないかチェックすることが重要です。
仕訳入力時の税率・適格請求書番号の記録方法
インボイス制度対応後は、消費税率の異なる取引が増加し、それぞれの取引ごとに税率区分を明確にして仕訳入力する必要があります。また、適格請求書発行事業者の登録番号の記録も求められます。
仕訳帳や会計ソフトへの入力ポイント
素早く正確な仕訳を行うためには、下記の点に注意しましょう。
|
記録内容 |
具体的な方法 |
注意点 |
|
税率区分 |
8%・10%・非課税・不課税・対象外などを区別し入力 |
消費税率ごとの金額を分けて集計 |
|
適格請求書番号 |
摘要欄や備考欄に「T+13桁の番号」を記載 |
仕入税額控除の要件となるため、入力漏れに注意 |
|
区分記載請求書 |
従来タイプとインボイスを分けて管理 |
インボイス対応前後の請求書を混同しない |
市販の会計ソフトは、インボイス項目の入力欄や税率自動判定機能が搭載されています。ソフトのバージョンや設定も適切に行いましょう。手書きの場合は、摘要欄への丁寧な記載を忘れないことが大切です。
小規模事業者・個人事業主の仕訳入力の留意点
インボイス制度により、小規模事業者や個人事業主にも新たな負担が生じていますが、効率的に対応するためには以下のような点に気をつけましょう。
- 現金取引・少額取引におけるインボイスの有無と対応方法を確認
- 免税事業者との取引では、仕入税額控除が原則できないため、税区分を明確化
- 取引先からインボイスがもらえない場合の記録(摘要欄に「インボイス無」等を記載)
- 簡易課税制度利用の事業者も税率区分・インボイス保存の必要性を把握
また、小規模事業者向けの簡易な会計ソフトでは、インボイス項目追加や税率選択の機能が追加されている場合も多いので、システムのアップデート状況を必ず確認しましょう。取引規模が小さくても、インボイス保存と税率の正確な区分管理は必須となります。
よくある質問(FAQ)
|
質問 |
回答 |
|
インボイスがない場合、どのように仕訳入力すればいいですか? |
保存した請求書・領収書がインボイスの要件を満たしていなければ、仕入税額控除は受けられません。摘要に「インボイス無」と記載し、税区分を「非対応」とします。 |
|
インボイス番号の未記載を後から補記できますか? |
可能です。補記が必要な場合は、請求書・領収書に番号を追記し、仕訳帳上の摘要欄にも記載してください。ただし、必ず適格請求書発行事業者から公式の通知を受けてください。 |
|
値引きや返品時の仕訳入力で特に注意すべき点は? |
値引き・返品の場合も、元の取引と同じ税率区分でマイナス仕訳を入力し、必要ならば関連するインボイス番号を明記しましょう。返金伝票や訂正請求書の保存も忘れずに。 |
|
電子インボイスやスキャナ保存は必須ですか? |
電子取引で受領した場合は電子保存が原則ですが、一定の要件下で紙保存も可能です。電子帳簿保存法の要件(真実性・可視性の確保)を満たしているか確認する必要があります。 |
|
仕訳入力ミスを見つけたときの修正方法は? |
原則として訂正仕訳または修正伝票で適切に対応し、摘要には「訂正」や「修正」の理由を明記します。不明点は必ず税理士等の専門家に相談してください。 |
このように、インボイス制度対応後の仕訳入力では、書類の保存・入力区分の明確化・番号の記録といった新たな留意点が発生します。最新の会計ソフトや関連法令の動向も随時チェックしましょう。
まとめ
インボイス制度導入により、仕訳入力は消費税区分の正確な判断や適格請求書番号の管理が重要となりました。仕入先や取引内容、領収書の保存要件も見直しが必要です。会計ソフトでの記載欄活用や、国税庁のガイドラインを遵守することで、正確な経理処理が求められます。










