【必読】インボイス制度は所得税に影響あり?節税対策と確定申告のコツ
更新日:2026.01.29
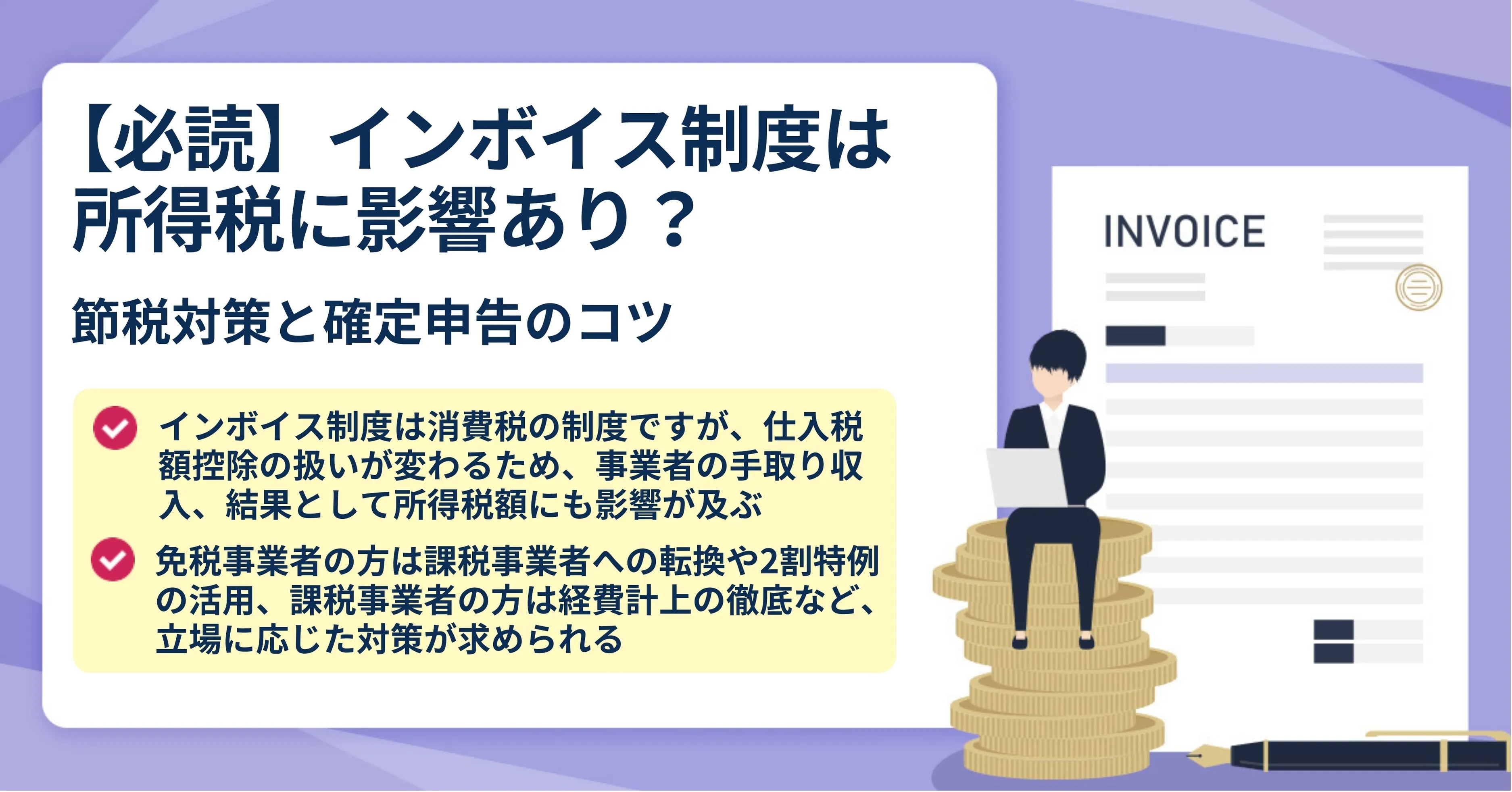
ー 目次 ー
インボイス制度が始まり、「自分の所得税にも影響があるのかな?」と気になっている方も多いのではないでしょうか。実は、制度を正しく理解し、適切な対策を講じることで、所得税の負担増を抑えることが可能です。この記事では、インボイス制度の基本から、立場別の影響、節税策、確定申告のコツまでやさしく解説します。あなたの所得税に関する疑問を解消し、最適な対応策を見つけましょう。
インボイス制度の基本
2023年10月1日から開始されたインボイス制度(適格請求書等保存方式)は、消費税の仕入税額控除の仕組みに関わる重要な変更点です。この制度が所得税にどのような影響を及ぼすのか、まずは基本的な内容を理解しましょう。
インボイス制度とは?導入の背景と目的をわかりやすく解説
インボイス制度とは、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の適正化を主な目的として導入された制度です。具体的には、売手が買手に対して、適用税率や消費税額などを正確に伝えるための「適格請求書(インボイス)」を交付し、双方がこれを保存することを求めるものです。
導入の背景には、消費税率が複数(標準税率10%、軽減税率8%)存在することにより、仕入税額控除の計算が複雑化し、不正や誤りが生じやすい状況があったことが挙げられます。インボイス制度は、取引の透明性を高め、正確な納税を促すことを目指しています。
|
項目 |
内容 |
|
正式名称 |
適格請求書等保存方式 |
|
開始時期 |
2023年10月1日 |
|
主な対象 |
消費税の課税事業者、およびその取引先となる事業者 |
|
適格請求書(インボイス)とは |
売手が買手に対して発行する、登録番号、適用税率、税率ごとの消費税額などの記載が義務付けられた請求書や領収書のことです。 |
インボイス制度が所得税に影響を与える仕組み
インボイス制度は、直接的には消費税に関する制度ですが、事業者の所得計算、ひいては所得税額にも間接的に影響を及ぼす可能性があります。特に、これまで消費税の納税義務が免除されていた免税事業者が、取引先の意向などにより適格請求書発行事業者(課税事業者)を選択する場合、大きな変化が生じます。
課税事業者になると、新たに消費税の納税義務が発生します。これにより、売上にかかる消費税額から仕入れにかかる消費税額を差し引いた差額を納付する必要が出てきます。この消費税の納税額は、事業の利益を圧迫する要因となり得ます。事業の利益、つまり所得金額が変動すれば、それに基づいて計算される所得税額も変わってくるのです。
また、課税事業者にとっては、仕入税額控除を受けるために、取引先から交付された適格請求書を適切に保存・管理することがより一層重要になります。もし適格請求書の保存がなければ、原則として仕入税額控除が受けられず、消費税の負担が増加します。これも結果的に所得を圧迫し、所得税に影響を与える可能性があります。
インボイスで納税額はどう変わる?消費税と所得税の違い
インボイス制度の登録を迷う際、最も重要なのは「手元に残るお金(利益)がどう変わるか」です。
結論から言うと、免税事業者がインボイス登録をすると、消費税の納税義務が新たに発生するため、トータルの納税額は増えます。ただし、所得税への影響は限定的です。
この2つの税金の性質を整理しましょう。
- 消費税(増える):
お客様から預かった税金を、国に納めるものです。これまでは免税事業者として「預かった消費税」をそのまま自分の利益(益税)にできましたが、インボイス登録後はこれを納税する必要があります。 - 所得税(少し減る可能性あり):
あなたの1年間の「儲け(利益)」に対してかかる税金です。インボイス制度とは直接関係ありませんが、支払った消費税を経費(租税公課)として計上できるため、その分だけ利益が圧縮され、結果的に所得税がわずかに減るケースがあります。
立場別|インボイス制度による所得税への影響シミュレーション
インボイス制度の導入は、消費税の仕組みに関する変更が主ですが、事業者の売上や経費、ひいては所得に影響を与える可能性があり、結果として所得税額にも変動が生じることがあります。ここでは、事業者の立場別に、インボイス制度が所得税にどのような影響を及ぼし得るのか、具体的なシミュレーションを交えて解説します。
免税事業者の所得税はどう変わる?インボイス未登録の場合
インボイス制度開始後も免税事業者のままでいることを選択し、適格請求書(インボイス)を発行しない場合、所得税に直接的な影響はありません。しかし、間接的な影響として、取引先の意向によっては売上が減少し、結果的に所得が減り、所得税額も減少する可能性が考えられます。
例えば、取引先が課税事業者であり、仕入税額控除のためにインボイスの受領を必要としている場合、インボイスを発行できない免税事業者との取引を見直したり、消費税相当額の値引きを要求したりするケースが想定されます。これにより、以下のような影響が考えられます。
|
影響パターン |
売上への影響 |
所得への影響 |
所得税への影響(概算) |
|
取引の減少・停止 |
減少 |
減少 |
減少 |
|
値引き交渉による単価下落 |
減少 |
減少 |
減少 |
上記のように、売上や利益が減少すれば、課税所得も減少し、結果として納付すべき所得税額も少なくなる可能性があります。ただし、これは事業の継続性や収益性の観点からは望ましい状況とは言えません。
課税事業者になった場合の所得税への影響
免税事業者がインボイス発行事業者として登録し、課税事業者になった場合、消費税の納税義務が発生します。この納税する消費税額は、所得税の計算上、経費(租税公課)として計上することができます。そのため、経費が増加し、所得が圧縮される結果、所得税額が軽減される効果が期待できます。
具体例で見てみましょう(数値はあくまで簡易的なシミュレーションです)。
|
項目 |
免税事業者のままの場合(仮定) |
課税事業者になった場合(仮定・本則課税) |
|
売上高(税抜) |
500万円 |
500万円 |
|
経費(消費税除く) |
200万円 |
200万円 |
|
納税消費税額(経費計上分) |
0円 |
30万円(※1) |
|
所得金額 |
300万円 |
270万円(500-200-30) |
|
所得税額(概算・税率10%と仮定) |
30万円 |
27万円 |
※1:売上にかかる消費税50万円 - 仕入にかかる消費税20万円 = 30万円と仮定。
この例では、課税事業者になることで消費税の納税負担(30万円)が生じますが、その分所得が減少し、所得税が3万円軽減されています。ただし、消費税の負担増と所得税の軽減額を総合的に比較検討する必要があります。また、インボイス発行事業者となることで取引が維持・拡大し、売上自体が増加すれば、所得が増え、結果的に所得税額が増加する可能性もあります。
副業をしている会社員の所得税 インボイスの影響範囲
会社員として給与所得を得ながら、個人事業主やフリーランスとして副業を行っている場合、給与所得に関しては、インボイス制度による直接的な影響はありません。
副業の取引先からインボイスの発行を求められた場合、対応によって副業収入が変動し、結果として全体の所得税額に影響が出ます。
- 免税事業者のままでいる場合:副業の取引先がインボイスを必要とする場合、取引が縮小したり、報酬が減額されたりする可能性があります。これにより副業の所得が減少し、給与所得と合算した総所得金額が減るため、所得税額も減少する可能性があります。
- 課税事業者になる場合:副業収入について消費税の申告・納税が必要になります。納税する消費税額は副業の経費として計上できるため、副業の所得が圧縮され、全体の所得税額が軽減される可能性があります。ただし、消費税の納税負担が発生します。
例えば、副業の年間所得が20万円減った場合、その減少額に所得税率を乗じた分だけ所得税が減少することになります(他の所得控除額等が変わらないと仮定)。逆に、課税事業者になることで取引が拡大し副業所得が増えれば、全体の所得税額も増加します。副業の状況と取引先の意向を踏まえ、慎重な判断が求められます。
インボイス制度に対応する所得税の節税対策ガイド
インボイス制度の導入は、消費税の納税額に影響を与えるだけでなく、結果として所得税の負担にも関わってきます。ここでは、事業者の立場別に、インボイス制度に対応しつつ所得税の節税を図るための具体的な対策を解説します。
免税事業者が検討すべき所得税節税の選択肢
インボイス制度開始後も免税事業者を継続する場合、取引先から消費税分の値下げを要求されたり、最悪の場合、取引を打ち切られたりするリスクがあります。このような状況を踏まえ、所得税への影響を最小限に抑えるための選択肢を検討しましょう。
あえて課税事業者になるメリットと適格請求書発行
免税事業者がインボイス制度に対応するために、あえて課税事業者を選択し、適格請求書発行事業者として登録する道があります。これにより、取引先は仕入税額控除を継続できるため、取引の継続や新規開拓が期待できます。消費税の納税義務は発生しますが、この納税額は所得税計算上の必要経費として計上できるため、課税所得を圧縮する効果があります。適格請求書を発行できることで、事業者としての信頼性向上にもつながるでしょう。
2割特例を利用した所得税負担の軽減
インボイス制度への対応を機に免税事業者から課税事業者になった場合、「2割特例」という負担軽減措置を選択できます。これは、売上にかかる消費税額の2割を納付すればよいという制度で、仕入れにかかる消費税額を計算する必要がありません。この特例を利用することで消費税の納税額を大幅に抑えることができ、結果として手元に残る資金が増え、間接的に所得税の負担感を軽減する効果が期待できます。ただし、この特例は期間限定の措置である点に注意が必要です。
課税事業者が実践できる所得税節税の具体策
既に課税事業者である方や、新たに課税事業者になった方が実践できる所得税の節税策について解説します。消費税の申告・納税方法の選択や、日々の経理処理が重要になります。
簡易課税制度の選択で所得税計算を有利に
課税事業者は、消費税の計算方法として「原則課税(一般課税)」の他に「簡易課税制度」を選択できます。簡易課税制度は、売上にかかる消費税額に業種ごとに定められた「みなし仕入率」を掛けて仕入税額控除額を計算する方法です。実際の仕入れや経費が少ない業種の場合、原則課税よりも納税額を抑えられる可能性があります。消費税の納税額が減れば、その分、所得税の課税対象となる所得が増える可能性はありますが、資金繰りの改善や事務負担の軽減につながり、結果として事業運営全体に良い影響を与えることが期待できます。
簡易課税制度のみなし仕入率は、事業の種類によって以下のように区分されています。
|
事業区分 |
みなし仕入率 |
該当する事業(例) |
|
第一種事業 |
90% |
卸売業 |
|
第二種事業 |
80% |
小売業、農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業) |
|
第三種事業 |
70% |
農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業を除く)、鉱業、建設業、製造業など |
|
第四種事業 |
60% |
飲食店業など(第一種、第二種、第三種事業以外のもの) |
|
第五種事業 |
50% |
運輸通信業、金融・保険業、サービス業(飲食店業に該当するものを除く) |
|
第六種事業 |
40% |
不動産業 |
簡易課税制度を選択するには、原則として適用を受けたい課税期間の開始の日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を税務署に提出する必要があります。
経費計上の徹底とインボイス保存による節税
所得税の節税の基本は、事業にかかった費用を漏れなく経費として計上することです。インボイス制度開始後は、仕入税額控除を受けるために、原則として適格請求書(インボイス)の保存が必要となります。受け取ったインボイスを適切に保存し、帳簿に正確に記録することで、消費税の仕入税額控除を確実に受けられます。これにより消費税の納税負担が軽減され、結果として所得税の課税対象となる所得を圧縮することにつながります。日々の取引で発生する経費の領収書や請求書を確実に管理し、計上漏れがないようにしましょう。
副業収入がある場合の所得税節税ポイント インボイス対応
会社員として給与所得を得ながら副業を行っている方も、インボイス制度の影響を受ける可能性があります。特に、副業の取引先が課税事業者である場合、インボイスの発行を求められるケースが考えられます。副業収入が事業所得または雑所得のどちらに該当するか、また、その規模や取引先の状況によって対応は異なります。
免税事業者のままでいるか、課税事業者になるかを検討する際には、取引先との関係性や、副業収入の金額、将来的な事業拡大の意向などを総合的に考慮する必要があります。課税事業者になる場合は、2割特例や簡易課税制度の活用も視野に入れましょう。また、青色申告を選択している場合は、青色申告特別控除(最大65万円または55万円)の適用を受けることで、所得税額を大きく抑えることができます。インボイス制度への対応と合わせて、既存の所得税節税策も最大限に活用することが重要です。
インボイス制度導入後の確定申告!所得税計算と手続きのコツ
インボイス制度の導入は、消費税だけでなく、所得税の確定申告にも影響を及ぼします。特に、これまで免税事業者だった方が課税事業者になった場合や、新たにインボイスの保存・管理が必要になる点で、申告手続きや所得税額の計算に注意が必要です。この章では、インボイス制度導入後の確定申告における変更点、所得税計算のポイント、そしてスムーズな手続きのための準備について解説します。
確定申告の変更点 インボイス制度と所得税申告
インボイス制度開始に伴い、所得税の確定申告においてもいくつかの変更点や注意すべき点があります。主なポイントを理解し、適切な申告を行いましょう。
まず、課税事業者になった方は、消費税の申告が新たに必要になります。消費税の申告内容(納税額または還付額)は、所得税の計算における経費(租税公課)や事業収入に影響を与えるため、正確な消費税申告が所得税申告の前提となります。
所得税の確定申告書自体に、インボイス制度専用の大きな様式変更は現時点(2023年10月以降の制度開始時点)ではありませんが、以下の点に留意が必要です。
帳簿付けと書類保存の徹底
適格請求書(インボイス)の保存は、仕入税額控除を受けるための必須条件です。これは消費税の計算に直接関わりますが、経費の証拠書類としての重要性も増します。日々の取引において、受け取ったインボイスと発行したインボイスの控えを適切に整理・保存しましょう。電子帳簿保存法の要件も確認し、対応が必要です。
2割特例を適用する場合の申告
免税事業者からインボイス発行事業者になった方向けの負担軽減措置である「2割特例」を適用する場合、消費税の申告書にその旨を記載する必要があります。所得税の申告においては、この特例によって計算された消費税納税額を租税公課として経費計上します。
|
項目 |
インボイス制度導入による主な変更・注意点 |
|
消費税申告 |
課税事業者になった場合、新たに消費税の申告・納税が必要。 |
|
帳簿・書類保存 |
適格請求書(インボイス)の保存が仕入税額控除の要件。経費の証拠書類としても重要。 |
|
2割特例 |
適用する場合、消費税申告書に記載。所得税申告では納税額を経費計上。 |
所得税の計算方法 仕入税額控除とインボイス
インボイス制度は主に消費税の仕組みですが、所得税の計算にも間接的に影響します。特に「仕入税額控除」の扱いや、消費税の納税額が経費として計上できる点がポイントです。
「仕入税額控除」は、消費税の納税額を計算する際に、売上にかかる消費税額から仕入れにかかった消費税額を差し引くことを指します。この仕入税額控除を適切に行うためには、適格請求書(インボイス)の保存が不可欠です。
所得税の計算において、この仕入税額控除が直接影響するわけではありません。しかし、消費税の納税額は、所得税法上「租税公課」として必要経費に算入できます(税込経理方式の場合)。つまり、支払う消費税額が増えれば経費が増え、所得金額が減少するため、結果として所得税額が軽減される可能性があります。逆に、還付される消費税額は事業収入に加算されます。
課税事業者の場合
課税事業者は、原則として消費税の申告・納税が必要です。確定申告で納付した消費税額は、その年の事業所得を計算する上で「租税公課」として経費計上できます。適格請求書をきちんと保存し、正確な仕入税額控除を行うことが、適正な消費税納税額の算出、ひいては所得税計算における経費計上の正確性につながります。
免税事業者の場合
免税事業者は消費税の納税義務がありませんので、仕入税額控除という概念もありません。取引先からインボイスを受け取ったとしても、消費税の申告は不要です。仕入れにかかった費用は、消費税額を含んだ総額を経費として計上します(税込経理方式)。
ただし、免税事業者がインボイス発行事業者(課税事業者)に支払った代金に含まれる消費税相当額について、取引先が仕入税額控除を受けられない可能性があるため、取引価格への影響などを考慮する必要が出てくる場合があります。
確定申告をスムーズに行うための準備と注意点
インボイス制度導入後の確定申告を円滑に進めるためには、事前の準備と申告時の注意点を押さえておくことが重要です。特に初めて消費税の申告を行う方や、経理処理が複雑になる方は早めの対策を心がけましょう。
事前の準備
- インボイスの整理・保存ルールの確立: 受け取ったインボイス、発行したインボイスの控えを日付順や取引先別に整理し、いつでも確認できるようにしておきましょう。紙だけでなく、電子データで授受した場合は電子帳簿保存法の要件に従った保存が必要です。
- 会計ソフトの確認・アップデート: 使用している会計ソフトがインボイス制度に対応しているか確認し、必要であればアップデートや設定変更を行います。インボイス制度対応の会計ソフトは、消費税の区分計算やインボイス情報の管理を効率化してくれます。
- 必要な情報の収集と整理: 売上や経費に関する書類(インボイス、領収書、契約書など)、各種控除証明書(生命保険料控除証明書、医療費の領収書など)を早めに収集し、整理しておきましょう。
申告時の注意点
- 申告期限の確認と遵守: 所得税の確定申告期限(通常は翌年3月15日)と、消費税の確定申告期限(個人事業主の場合は翌年3月31日)をしっかり確認し、期限内に申告・納税を済ませましょう。
- 記載ミス・計算ミス防止: 申告書の作成は慎重に行い、記載漏れや計算ミスがないか複数回確認しましょう。特に消費税の計算は複雑な場合があるため注意が必要です。
- e-Taxの活用: 国税庁のe-Tax(電子申告・納税システム)を利用すると、自宅から申告でき、一部の添付書類が省略できるなどのメリットがあります。マイナンバーカードと対応するICカードリーダライタまたはスマートフォンが必要です。
- 専門家への相談: 自身での申告が難しい場合や、判断に迷う点がある場合は、税理士などの専門家に早めに相談することを検討しましょう。特にインボイス制度開始直後は不明な点も多いため、専門家のアドバイスが役立ちます。
これらの準備と注意点を踏まえ、計画的に確定申告を進めることが、インボイス制度下での適切な税務処理につながります。
Q&A|インボイスと所得税に関するよくある質問
インボイス制度によって所得税の還付は変わりますか?
インボイス制度は、主に消費税の仕入税額控除に関する制度であり、所得税の還付計算の仕組み自体を直接変更するものではありません。
しかし、インボイス制度への対応状況によって消費税の納税額が変動する場合があります。例えば、これまで免税事業者だった方が課税事業者になった場合や、受け取った適格請求書(インボイス)に基づいて仕入税額控除の金額が変わる場合などです。この納付すべき消費税額(または還付される消費税額)は、所得税の計算上、経費(租税公課)または事業収入の一部として扱われることがあります。
そのため、消費税の納税額や還付額の変動が事業所得に影響を与え、結果として課税所得が変わり、間接的に所得税額や所得税の還付額に影響を及ぼす可能性はあります。具体的には、消費税の納税負担が増えれば経費が増加し所得が圧縮され、所得税が減少する(または還付が増える)ケースが考えられます。
少額特例は所得税の計算に関係しますか?
インボイス制度における「少額特例」とは、一定の条件を満たす事業者(基準期間における課税売上高が1億円以下の事業者など)が、税込1万円未満の課税仕入れについて、適格請求書(インボイス)の保存がなくとも帳簿への一定事項の記載のみで仕入税額控除を受けられるという、消費税法上の特例措置です。
この特例は消費税の計算に関するものであり、所得税の計算において経費を計上するための証拠書類の保存義務を直接的に変更するものではありません。所得税の計算上、経費として認められるためには、原則として領収書や請求書といった一般的な証拠書類の保存が必要です。
ただし、少額特例の適用によって消費税の仕入税額控除の事務処理が簡略化されたり、控除できる消費税額が変動したりすることで、結果として納付する消費税額が変わることはあり得ます。その変動した消費税納税額は、所得税計算上の経費(租税公課)に影響するため、間接的に所得税額に影響を与える可能性があります。
まとめ
インボイス制度は消費税の制度ですが、仕入税額控除の扱いが変わるため、事業者の手取り収入、結果として所得税額にも影響が及びます。免税事業者の方は課税事業者への転換や2割特例の活用、課税事業者の方は経費計上の徹底など、立場に応じた対策が求められます。本記事で解説した節税策や確定申告のポイントを参考に、ご自身の状況に最適な対応を検討し、変化に備えましょう。










