インボイスで不利になる?フリーランスが今すぐ始めるべき対策3選
更新日:2026.01.29
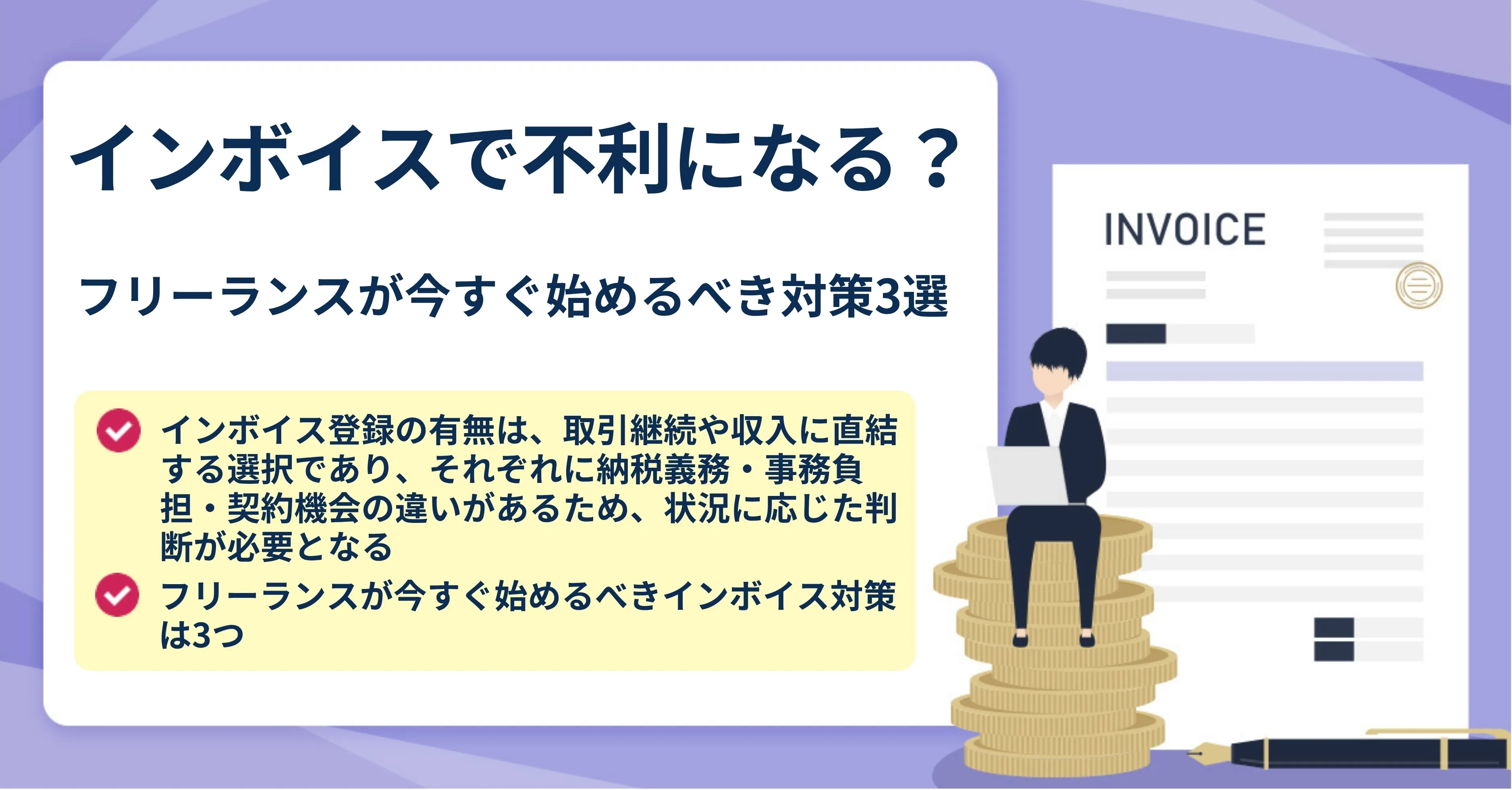
ー 目次 ー
インボイス制度の導入で「収入が減るのでは?」「取引を打ち切られないか?」と不安を抱えるフリーランスは多いでしょう。結論として、今すぐ始めるべき対策は「取引先への事前相談」「収入減への備え」「契約・請求書の見直し」の3つです。
本記事では、インボイス登録の要否を判断する基準から、不利な立場を避けるための交渉術まで、実務的なポイントをわかりやすく解説いたします。ご自身にとって最適な選択ができるよう、ぜひ最後までご覧ください。
インボイス制度でフリーランスが不利になると言われる理由
2023年10月1日から開始されたインボイス制度(適格請求書等保存方式)は、多くのフリーランスにとって大きな影響を与えています。ここでは、その理由を理解するために不可欠な制度の基本を解説します。
そもそもインボイス制度とは?基本の仕組み
インボイス制度とは、消費税の仕入税額控除を受けるための新しい方式です。仕入税額控除とは、事業者が商品を販売した際に受け取った消費税から、仕入れや経費で支払った消費税を差し引いて、国に納める税額を計算する仕組みのことです。
この制度が始まって以降、買い手側(発注者)が仕入税額控除を受けるためには、売り手側(フリーランス)から「インボイス(適格請求書)」を発行してもらい、それを保存する必要があります。インボイスには、従来の請求書にはなかった「登録番号」などの記載が義務付けられています。
もしフリーランスがインボイスを発行できない場合、取引先はそのフリーランスに支払った報酬に含まれる消費税分を控除できなくなり、結果として取引先の納税額が増えてしまうのです。これが、フリーランスが取引の継続や新規契約において不利な立場に置かれる可能性がある最大の理由です。
課税事業者と免税事業者の違いとは
インボイスを発行できるのは「課税事業者」のみです。フリーランスがインボイス制度を理解するには、この「課税事業者」と、これまで多くのフリーランスが該当していた「免税事業者」の違いを正確に把握することが重要です。
両者の主な違いは、基準期間(個人事業主の場合は前々年)の課税売上高と、それに伴う消費税の納税義務の有無です。以下の表で違いを確認しましょう。
|
項目 |
課税事業者 |
免税事業者 |
|
課税売上高(基準期間) |
1,000万円超 |
1,000万円以下 |
|
消費税の納税義務 |
あり |
原則、免除 |
|
インボイスの発行 |
可能(適格請求書発行事業者の登録が必要) |
不可 |
これまで多くのフリーランスは、課税売上高が1,000万円以下であるため「免税事業者」として、受け取った報酬にかかる消費税の納税を免除されていました。しかし、免税事業者のままではインボイスを発行できないため、取引先から値下げを要求されたり、最悪の場合は契約を打ち切られたりするリスクが生じています。このため、免税事業者では不利になる可能性があるため、登録の是非を検討する必要があります。
インボイス登録する?しない?対策の前にフリーランスが考える2つの選択肢
インボイス制度への対応で、フリーランスはまず大きな選択を迫られます。それは「適格請求書発行事業者として登録し課税事業者になる」か、「登録せずに免税事業者のままでいる」かです。この章ではそれぞれのメリット・デメリットをご紹介します。
インボイス登録(課税事業者になる)メリットとデメリット
インボイス登録を行うと、消費税の納税義務が発生する「課税事業者」になります。企業(課税事業者)との取引が多いフリーランスにとっては、取引の継続や新規開拓の観点から有力な選択肢となります。主なメリットとデメリットは以下の通りです。
|
具体的な内容 |
|
|
メリット |
|
|
デメリット |
|
インボイス登録しない(免税事業者のまま)メリットとデメリット
インボイス登録をせず、これまで通り「免税事業者」でいることも選択肢の一つです。取引先が一般消費者や免税事業者である場合や、事務負担を増やしたくない場合に検討されます。メリットとデメリットをしっかり比較しましょう。
|
具体的な内容 |
|
|
メリット |
|
|
デメリット |
|
まずは取引先の状況を確認することが重要
どちらの選択肢が最適かは、フリーランス一人ひとりの状況によって異なります。判断に迷ったら、まずはご自身の主な取引先がどのような事業者であるかを確認しましょう。
取引先が課税事業者(一般的な企業など)中心であれば、インボイス登録をしないと今後の取引に影響が出る可能性が高いと言えます。一方で、取引先が一般消費者(BtoC)や免税事業者ばかりであれば、インボイス登録を急ぐ必要性は低いかもしれません。ご自身の状況がわからない場合は、まず主要な取引先にインボイス登録の予定があるか、また、もし自分が免税事業者のままでいた場合に取引条件(価格や契約継続)に変更があるかなどを、事前に相談してみることが判断の第一歩となります。
フリーランスが今すぐ始めるべきインボイス対策3選
インボイス制度への対応について、登録する・しないの方針を決めたら、次はいよいよ具体的な行動に移す段階です。ここでは、フリーランスが不利益を被らないために、今すぐ始めるべき3つの対策を具体的に解説します。
対策① 取引先に事前相談し、継続取引や単価への影響を確認する
インボイス制度への対応で最も重要なのが、主要な取引先とのコミュニケーションです。ご自身の判断だけで方針を決め、事後報告すると思わぬトラブルに発展しかねません。まずは取引先がインボイス制度に対してどのような方針を持っているかを確認し、今後の取引についてすり合わせを行いましょう。
免税事業者のまま取引を続けるための交渉
免税事業者のままでいることを選択した場合、取引先はあなたの発行する請求書では仕入税額控除ができません。このデメリットを取引先がどう捉えるかが、今後の取引継続の鍵となります。
交渉の際は、まず取引先のインボイス対応方針(原則として適格請求書発行事業者とのみ取引するのか、など)を確認しましょう。その上で、免税事業者との取引を継続してもらうために、以下のようなアプローチが考えられます。
- 専門性や独自性をアピールする:あなたにしか提供できないスキルや価値があることを伝え、「仕入税額控除ができないデメリット」を上回るメリットがあることを理解してもらう。
- 価格について協議する:取引先から消費税相当額の値下げを求められる可能性があります。ただし、一方的な値下げ要求は独占禁止法や下請法に抵触する恐れがあるため、あくまで双方合意の上での価格調整を目指しましょう。
- 取引先の影響を確認する:取引先が簡易課税制度を選択している場合や、顧客が一般消費者(BtoC)である場合は、仕入税額控除の有無が影響しないケースもあります。取引先への影響が軽微であることを伝え、理解を求めるのも一つの方法です。
課税事業者になる場合の価格交渉のポイント
課税事業者になることを決めた場合、新たに消費税の納税義務が生じます。この負担分を価格に適切に転嫁できるかどうかが、手取り収入を維持するための重要なポイントです。
理想的なのは、現在の報酬を「税抜価格」とし、そこに消費税10%を上乗せして請求することです。しかし、取引先の予算によっては交渉が難航することも考えられます。価格交渉を有利に進めるために、以下の点を押さえておきましょう。
- 交渉のタイミング:契約更新や新規案件のタイミングが、価格交渉を切り出しやすい機会です。
- 根拠を明確にする:インボイス制度への対応に伴い、課税事業者として消費税を納める義務が生じたことを明確に伝え、価格改定の必要性を丁寧に説明します。
- 書面で合意を残す:口頭での約束だけでなく、改定後の価格(税抜価格と消費税額)を明記した覚書や契約書を交わし、後のトラブルを防ぎましょう。
もし満額の価格転嫁が難しい場合でも、一部だけでも上乗せできないか、あるいは他の条件で調整できないかなど、粘り強く交渉することが大切です。
対策② 登録してもしなくても、「実質手取りが減る」可能性に備えた対策を
インボイス制度は、課税事業者になる・ならないにかかわらず、フリーランスの実質的な手取り収入が減少する可能性があります。「手取り減」のインパクトを最小限に抑えるため、収入の柱を太くし、支出を最適化する対策を並行して進めましょう。
- 経費の見直し:事業で使っているツールやサービス、通信費など、固定費を中心に無駄がないかを見直し、コスト削減を図ります。
- スキルアップと付加価値向上:専門性を高めたり、新たなスキルを習得したりすることで、自身の市場価値を高め、単価アップ交渉やより条件の良い案件の獲得につなげます。
- 新規取引先の開拓:特定の取引先への依存度を下げ、収入源を多様化させましょう。特に、事業者ではない一般消費者(BtoC)向けのサービスや、簡易課税制度を利用している事業者との取引は、インボイスの影響を受けにくいため、積極的に開拓する価値があります。
対策③ 報酬の税込/税抜表示ルールを確認!今後の契約書・請求書を整理する
インボイス制度の導入を機に、これまで曖昧にしていた契約内容や請求書の記載ルールを明確にすることが、将来のトラブル防止につながります。特に報酬額の「税込」「税抜」の扱いは重要です。
例えば、これまで「報酬11万円」で契約していた場合、これが「税込11万円(本体価格10万円+消費税1万円)」なのか、「税抜11万円(本体価格11万円)」なのかで、課税事業者になった際の手取り額は大きく変わります。契約書を見直し、報酬が税抜・税込のどちらの金額であるかを取引先と再確認し、必要であれば覚書などを交わして書面に残しておきましょう。
また、課税事業者になる場合は、適格請求書(インボイス)の要件を満たす請求書フォーマットを準備する必要があります。従来の請求書との主な違いは以下の通りです。
|
項目 |
従来の請求書(区分記載請求書等) |
適格請求書(インボイス) |
|
登録番号 |
不要 |
必要 |
|
適用税率 |
記載が望ましい |
必要(税率ごとに区分) |
|
税率ごとの消費税額 |
記載が望ましい |
必要(税率ごとに区分) |
会計ソフトや請求書作成サービスは、多くがインボイス制度に対応したフォーマットを提供しています。ご自身の事業に合ったツールを導入し、スムーズに移行できるよう準備を進めましょう。
Q&A|インボイス制度とフリーランスの対策に関するよくある質問
インボイス制度に関して、フリーランスの方から特に多く寄せられる質問とその回答をまとめました。ご自身の状況と照らし合わせながら、対策を考える上での参考にしてください。
フリーランスが使えるインボイスの軽減措置はある?
はい、インボイス制度の開始に伴い、フリーランスを含む小規模事業者の負担を軽減するための特例措置が設けられています。主なものは次の2つです。
|
軽減措置の名称 |
内容 |
対象期間 |
|
2割特例 |
免税事業者からインボイス発行事業者(課税事業者)になった場合、売上にかかる消費税額の2割を納税額とすることができる制度です。事前の届出は不要で、確定申告書に付記するだけで適用できます。 |
2023年10月1日~2026年9月30日を含む課税期間 |
|
少額特例 |
税込1万円未満の経費(課税仕入れ)については、インボイスの保存がなくても、帳簿への記載のみで仕入税額控除が認められます。 |
2023年10月1日~2029年9月30日 |
特に「2割特例」は、消費税の計算が非常にシンプルになり、納税額も抑えられるため、多くのフリーランスにとってメリットの大きい制度です。ご自身の事業内容と照らし合わせて、どの制度を利用するのが最も有利か検討しましょう。
インボイス登録したら確定申告はどう変わる?
インボイス登録をして課税事業者になると、確定申告の際に大きな変更点があります。
これまでの免税事業者の場合は「所得税」の確定申告のみでしたが、課税事業者になると、それに加えて「消費税」の確定申告と納税が必要になります。つまり、年に一度の確定申告で、所得税と消費税の2つの税金を申告・納税することになります。
消費税の計算方法には、売上にかかる消費税から経費にかかる消費税を差し引いて計算する「一般課税(本則課税)」と、売上税額に業種ごとに定められた「みなし仕入率」を掛けて納税額を計算する「簡易課税制度」があります。前述の「2割特例」も選択肢の一つです。どの計算方法を選択するかは、事前に届出が必要な場合もあるため注意が必要です。
副業フリーランスのインボイス対策はどうすればいい?
会社員などをしながら副業でフリーランス活動をしている方も、基本的な対策は専業フリーランスと同じです。まずは、副業の取引先がインボイスを必要としているかを確認することが第一歩となります。
副業の売上規模が比較的小さい場合、取引先に相談することで、免税事業者のままでも取引を継続してもらえる可能性があります。インボイスを発行できない分、報酬の値下げを交渉される可能性もありますが、課税事業者になる手間や納税負担と比較して判断しましょう。
なお、インボイス登録(個人事業主として課税事業者になること)をしても、その情報が自動的に本業の会社に通知されることはありません。ただし、副業収入が増えて住民税の額が大きく変わると、会社の経理担当者に副業の存在が推測される可能性はあります。これはインボイス制度とは直接関係ありませんが、念頭に置いておくとよいでしょう。
一度インボイス登録したら取りやめることはできる?
はい、一度インボイス発行事業者として登録した後でも、登録を取りやめて免税事業者に戻ることは可能です。
登録を取りやめたい場合は、管轄の税務署に「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を提出します。この届出書を提出すると、原則として提出した日の属する課税期間の「翌」課税期間の初日から、登録の効力が失われます。課税期間の途中で登録を取りやめることは原則できないため、タイミングには注意が必要です。
ただし、一度登録を取りやめると、再度必要になった場合にすぐ登録できないケースや、消費税の納税義務が一定期間継続する「2年縛り」などのルールも存在します。状況が変わり登録の取りやめを検討する際は、税務署や税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
まとめ
インボイス制度は、フリーランスの収入や取引に影響を及ぼすため、事前の対策が不可欠です。取引先が仕入税額控除を受けられなくなることで、契約の見直しや値下げ交渉につながる可能性があるからです。まずは取引先の意向を確認し、課税事業者になるか否かを慎重に判断しましょう。その上で、価格交渉や収入減への備え、請求書の様式変更といった対策を進めることが求められます。将来の不利益を避けるためにも、できるだけ早めに準備を始めておきましょう。










