インボイス制度を利用した場合の費用の計算方法!免税事業者への影響も解説
更新日:2026.01.29
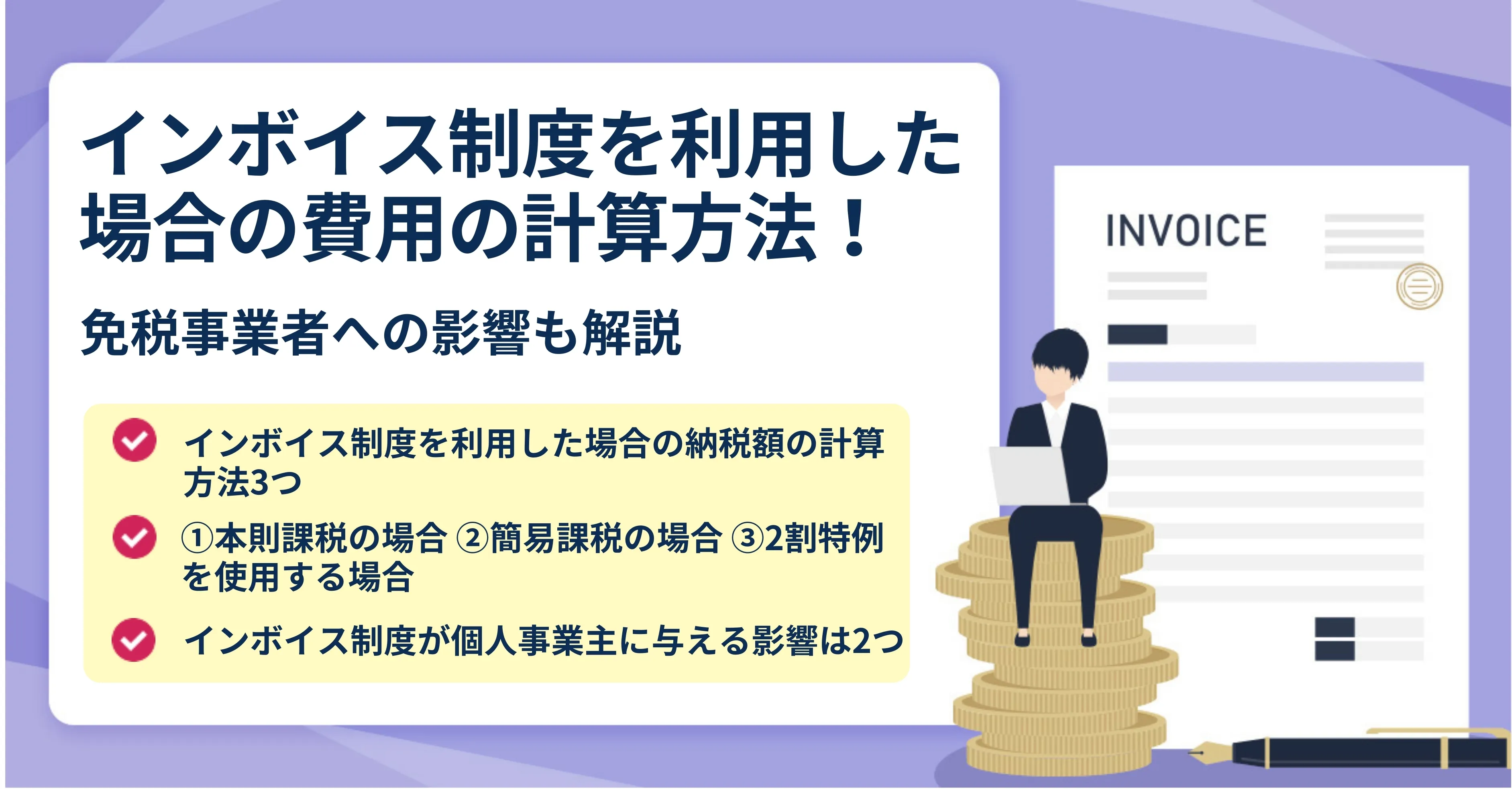
ー 目次 ー
インボイス制度の開始で、取引先との関係性や事務負担の増加など、事業者に大きな影響が生じています。とくに、基準期間の課税売上高が1,000万円以下の免税事業者は、今後の事業の運営についての検討も必要となるでしょう。
事業者がインボイス制度に適切に対応できていないと、取引先との関係悪化や事業収益の低下など、事業の継続に関わる重大なトラブルに発展する可能性があります。また、制度対応の遅れは取引機会の損失にもつながりかねません。
本記事では、インボイス制度を利用した場合の費用の計算方法について、免税事業者への影響もあわせて解説します。
インボイス制度は、消費税の計算をより正確におこなうための制度
インボイス制度とは、2023年10月から開始された、消費税の計算をより正確におこなうための制度です。
取引で売り手はインボイス(適格請求書)の発行、買い手は発行されたインボイスの保存をする必要があり、要件を満たせば仕入税額控除が受けられます。この仕入税額控除は売上の消費税から仕入に使った消費税を差し引けるもので、税負担を軽減できる可能性があります。
ただ、制度を利用するためには、税務署や登録センターにインボイス発行事業者への登録が必要です。また、発行したインボイスには以下の項目を記載しなければなりません。
- 発行者の氏名または名称および登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象品目の場合はその旨も)
- 税率ごとに区分した合計金額および適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額
- 受領者の氏名または名称
(※)太字の項目は、インボイス制度で追加された項目
インボイス制度を利用した場合の納税額の計算方法3つ
インボイス制度では、消費税の納税額を正確に計算しなければなりません。適切な計算方法を選択しないと、必要以上の税負担の発生や、税務調査で指摘を受けるなどのリスクがあります。
ここでは、インボイス制度を利用した場合の納税額の3つの計算方法について、それぞれ解説します。
①本則課税の場合
本則課税は実際の取引にもとづいて計算する方法です。本則課税の具体的な計算方法は以下のとおりです。
- 納税額 = 売上にかかる消費税 - 仕入にかかる消費税
本則課税の場合は売上と仕入れを正確に記録して、インボイス(適格請求書)を保存する必要があります。また、帳簿へも詳細を記載しなければなりません。
本則課税を選択すると、設備投資や輸出取引をおこなう場合にメリットがあります。たとえば、高額な設備投資で支払った消費税が売上にかかった消費税を上回る場合、その差額が還付されます。
②簡易課税の場合
簡易課税は、納税事務の負担を軽減するために設けられた制度です。個人事業主は前々年、法人は前々事業年度の課税売上高が5,000万円以下の事業者が簡易課税を利用できます。
簡易課税の場合の納税額は、以下のようにして求めます。
- 納税額=売上にかかる消費税額 -(売上にかかる消費税額 × みなし仕入率)
なお、みなし仕入率は業種ごとに異なり、それぞれのみなし仕入率は以下のとおりです。
- 第1種事業(卸売業):90%
- 第2種事業(小売業):80%
- 第3種事業(製造業など):70%
- 第4種事業(サービス業など):60%
- 第5種事業(不動産業など):50%
- 第6種事業(金融・保険業など):40%
③2割特例を使用する場合
2割特例は、免税事業者からインボイス(適格請求書)発行事業者になった事業者の負担を軽減するための特例制度です。2割特例では、売上にかかる消費税の20%を納税額とする極めてシンプルな計算方法を採用しています。
2割特例を使用した場合の納税額の計算方法は、以下のとおりです。
- 納税額 = 売上にかかる消費税 × 20%
2割特例は、2023年10月1日〜2026年9月30日の期間に限り適用でき、本則課税や簡易課税と比べて税負担が大幅に軽くなるのがメリットです。
インボイス制度が個人事業主に与える2つの影響とは?
インボイス制度は個人事業主に重大な影響を与える可能性があります。とくに、免税事業者のままでいると取引機会の損失や収益の減少につながるかもしれません。
これらの影響を回避するためには、事前に対策を講じることが大切です。
ここでは、インボイス制度が個人事業主に与える2つの影響について、それぞれ解説します。
①取引が減少する可能性がある
インボイス(適格請求書)発行事業者以外と取引した場合、仕入税額控除が適用されないことを理由に取引条件の見直しを求められるかもしれません。
このため、取引維持のためにはインボイス制度への登録を検討しましょう。ただし、もしインボイス制度への登録ができない事情があれば、取引が維持できるように商品・サービスの本質の向上や、価格の調整などで対応する必要があります。
②インボイスの発行を求められる可能性がある
取引先からインボイス(適格請求書)の発行を求められた場合、事業の状況に応じた対応が必要です。
まずは、取引規模や取引先との関係性を考慮して、インボイス発行事業者への登録を検討する必要があります。そのうえで、インボイス発行事業者への登録を選択した場合は、事務負担の増加に備えて記帳・管理体制を整備しましょう。
なお、発行事業者への登録後は以下の対応が必要です。
- 適格請求書の記載事項を満たしたテンプレートの作成
- 請求書発行システムの導入検討
- 消費税の確定申告の実施
- 発行したインボイスの写しの保存
インボイス発行事業者に登録する2つの方法
インボイス(適格請求書)発行事業者への登録は、事業者がインボイスを発行するために必要不可欠な手続きです。登録をおこなわないと取引先にインボイスを発行できないため、重要な取引機会を失うリスクがあります。
手続きには一定の時間を要するため、期限に余裕を持って対応しましょう。
ここでは、インボイス発行事業者に登録する2つの方法について、それぞれ解説します。
①郵送での申請方法
郵送での申請は「適格請求書発行事業者の登録申請書」を使用します。申請書は税務署で直接受け取る、あるいは国税庁のホームページからダウンロードすると入手可能です。
申請書には基本情報や事業内容を正確に記入して、必要な添付書類とともに管轄の税務署へ提出します。提出後は審査を経て、登録番号が記載された登録通知書が送付されます。
登録通知書は再発行できないため、大切に保管しましょう。
②e-Taxでの申請方法
e-Taxでの申請は、マイナンバーカードと電子証明書を使用したオンライン手続きです。e-Taxでの申請に必要なものは、以下のとおりです。
- マイナンバーまたは電子証明書
- ICカードリーダーまたはスマートフォン
- e-Tax利用者識別番号
- e-Taxソフト
事前にICカードリーダーの準備やe-Tax利用者識別番号の取得が必要ですが、一度環境を整えれば、その後の手続きはスムーズにおこなえます。e-Taxでの申請には、申請データの作成から送信までをオンラインで完結でき、申請後の処理状況もシステム上で確認できるメリットがあります。
まとめ|取引先との関係を考慮してインボイス制度を利用するか判断しよう
本記事では、インボイス制度を利用した場合の費用計算について、免税事業者への影響もあわせて解説しました。
インボイス制度は、事業者の取引環境に大きな影響を与えます。制度への対応方法を判断する際は、取引先との関係性や事業規模、事務負担の増加などを総合的に検討しましょう。
納税額の計算方法には、本則課税、簡易課税、2割特例があり、事業規模や設備投資の予定、取引先との関係などを考慮して計算方法を選択する必要があります。
とくに、設備投資を予定している場合は本則課税、小規模で取引が安定している場合は簡易課税、免税事業者から新たに登録する場合は2割特例など、自社の状況に合わせて検討しましょう。
また、不明な点がある場合は、税理士などの専門家に相談がおすすめです。










