【サンプルあり】見積書にインボイス制度の登録番号は不要!書き方や対応を解説
更新日:2026.01.13
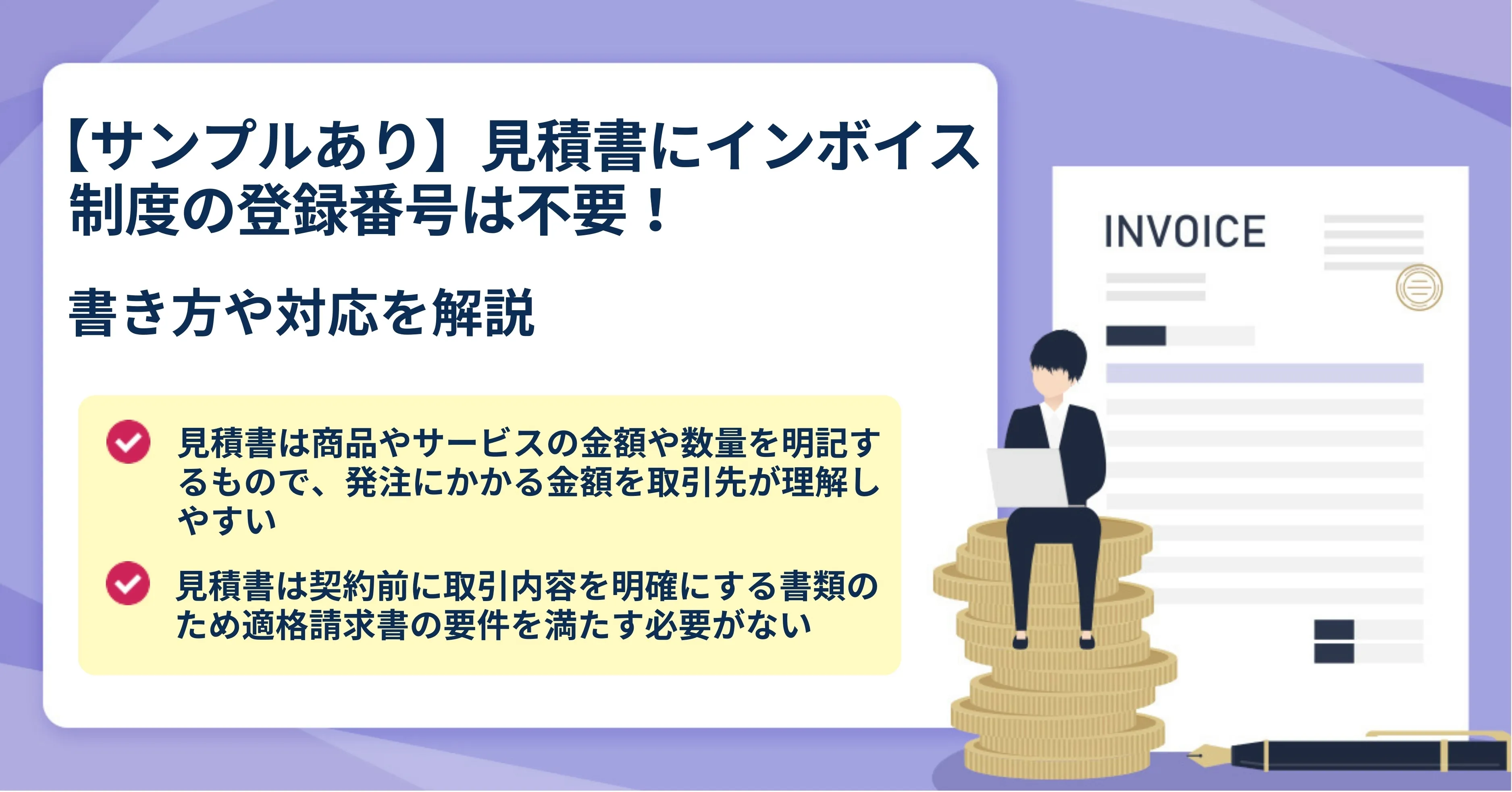
ー 目次 ー
【サンプルあり】見積書にインボイス制度の登録番号は不要!書き方や対応を解説
インボイス制度では適格請求書発行事業者として申請すると、事業者ごとに登録番号が発行されます。適格請求書では登録番号をはじめとした記載事項が追加されており、インボイス施行後はフォーマットの変更が必要になる書類も多くあります。
このような書類のなかで、商品やサービスの金額や数量を明記する「見積書」への影響が気になる方も少なくありません。見積書の発行がある事業者は、インボイスでの対応方法を理解しておくことで、作成時に悩まずに済むでしょう。
本記事では、インボイス制度での見積書の対応方法や書き方を解説します。サンプルもあわせて紹介するため、自社のテンプレートを作る際にお役立てください。
インボイス制度の前に!見積書を発行する理由
見積書とは商品やサービスの金額や数量を明記することで、契約前に注文時の総額を発注者が把握しやすくなる書類です。見積書の用途を理解しておくことでインボイス制度での対応が明確になります。
ここからは、見積書が作成される理由を解説します。
①発注を検討してもらうため
見積書の発行は法律上で義務付けられていないものの、発注者側からの申請で発行する企業が多くあります。
発注者側は複数の企業から見積書を発行することで、どの企業を利用するのかを比較しやすくなる点がメリットです。
②契約後の認識の齟齬を防ぐため
見積書に提供する商品やサービスの数量、金額を記載することで、契約後に内容の認識で齟齬が起きにくくなります。口頭で契約してしまうと、万が一納品時に「金額や商品が違う」といわれた場合、トラブルに発展しかねません。
見積書を作成しておけば、発注者・受注者のどちらも確認が可能な書類で契約内容が明らかになり、ミスやトラブルが防げます。
【結論】見積書にインボイスの登録番号は必要ではない
法律上は、見積書にインボイスの登録番号を記載する必要はありません。見積書は契約前に取引内容を明確にする書類であり、適格請求書の要件を満たす必要がないためです。
このことから、すでに自社に見積書のテンプレートがある場合は、無理に変更する必要はありません。
ただし、発注者側が適格請求書発行事業者であれば、見積書にインボイスの登録番号を記載しておくこともおすすめです。仕入税額控除を利用できることが伝わり、失注が避けられる可能性があります。
インボイス制度での見積書の対応とは?
インボイス制度後の見積書の扱いを理解しておかないと、不要な事務作業によって経理担当者の負担を増やしてしまう可能性があります。インボイス制度によって変わる業務フローは多いため、混乱しないためにも書類ごとの対応を理解しておきましょう。
ここでは、インボイス制度での見積書の対応方法を解説します。
①インボイス施行後も見積書のフォーマットを変える必要はない
見積書は契約前に発行する書類のため、発行時には金銭のやりとりがありません。このことから、インボイス施行後も見積書のフォーマットの変更は不要です。
ただ、もしインボイス制度に定められたフォーマットにあわせての対応を検討していれば、登録番号の記載がおすすめです。登録番号を記載しておくことで、企業が取引するのかを判断しやすくなり、受注につながる可能性があります。
②見積書を適格請求書とする必要はない
インボイス制度では、要件を満たした適格請求書の発行を取引先から求められる可能性があります。適格請求書を発行する場合は、請求書や納品書、領収書などの書類で要件を満たせば問題ないため、見積書で対応する必要はありません。
インボイス施行後に、フォーマットを変える書類を減らしたいときは、見積書は現状のものを使用しましょう。
見積書の書き方
見積書の書き方を理解していないと、必要な項目を記載せずに発行して、取引先からの信用を失ってしまう可能性があります。作成するときに項目で悩まないよう、事前に書き方を理解しておくと安心です。
ここでは、見積書の書き方や必要な項目を解説します。
- 宛名
- 発行者の名称
- 発行日
- 見積もりの内容
- 小計・合計金額・消費税
①宛名
見積書の宛名には、発注者になる取引先の正式名称を記載しましょう。
記載時は、「〇〇株式会社 御中」とするか、担当者名がわかる場合は「〇〇株式会社 〇〇部 〇〇様」と書きます。
取引先の名称に誤りがあると、契約後もミスがあるのではと不安に思われる可能性があるため、送付前にダブルチェックをおこなっておきましょう。
②発行者の名称
見積書の発行者欄には、自社の正式名称・住所・電話番号・担当者名を記載しましょう。
発行者を明記しておくことで、取引先が複数の企業に見積もりをとった場合でも、ソートをかけて調べられ、管理に手間がかかりません。
なお、見積書にインボイス登録番号を記載する際は、発行者欄に記載場所を作ることで取引先が見たときにわかりやすくなります。
③発行日
見積書の発行日は、作成した日を記載しましょう。
なお、見積もり金額の有効期限は一般的に2週間〜6か月ですが、企業によって異なる場合もあるでしょう。発行日の近くに有効期限も記載しておくことで、取引先が有効期限を過ぎてから発注する可能性を減らせます。
④見積もりの内容
見積書の内容は、品目名・単価・個数・商品ごとの合計金額などを記載しましょう。
商品名やサービス名は、発注者と受注者の間に齟齬がないよう、正式名称や型番を明記しておくと安心です。
さらに、商品ごとの合計金額を記載しておくことで内訳が理解しやすくなり、発注者が予算と比較するときに役立ちます。
⑤小計・合計金額・消費税
見積書の金額欄は、税抜の小計・総合計金額・消費税を記載しましょう。
軽減税率の対象品目があり、商品ごとにかかる税率が異なる場合は、税率ごとの合計金額と消費税額を記載しておくことで、取引先が税額の管理をするときに計算しやすくなります。
さらに、総合計金額を明記しておけば、取引先が最終的に支払う金額が明確になり、わかりやすい見積書を作成できます。
【テンプレート】見積書のサンプル
見積書の作成方法がわからないときは、サンプルを参考にして自社にあったテンプレートを作成しましょう。
|
見積書 発行日:〇年〇月〇日 株式会社〇〇 御中 お見積もり金額 ¥2,180-
自社の企業名 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
まとめ|インボイス施行後の見積書は登録番号を記載しておくと安心
本記事では、インボイス制度における見積書の対応方法や書き方を解説しました。
見積書は契約前に取引内容を明確にする書類のため、インボイス施行後でもフォーマットの変更は必要ありません。しかし、登録番号を記載しておくことで受注につながる可能性があります。
見積書の書き方に悩んだときは、本記事のサンプルを参考に自社のフォーマットを作成しましょう。










