デザイナー向けインボイス制度完全ガイド!登録から請求書発行まで徹底解説
更新日:2026.01.29
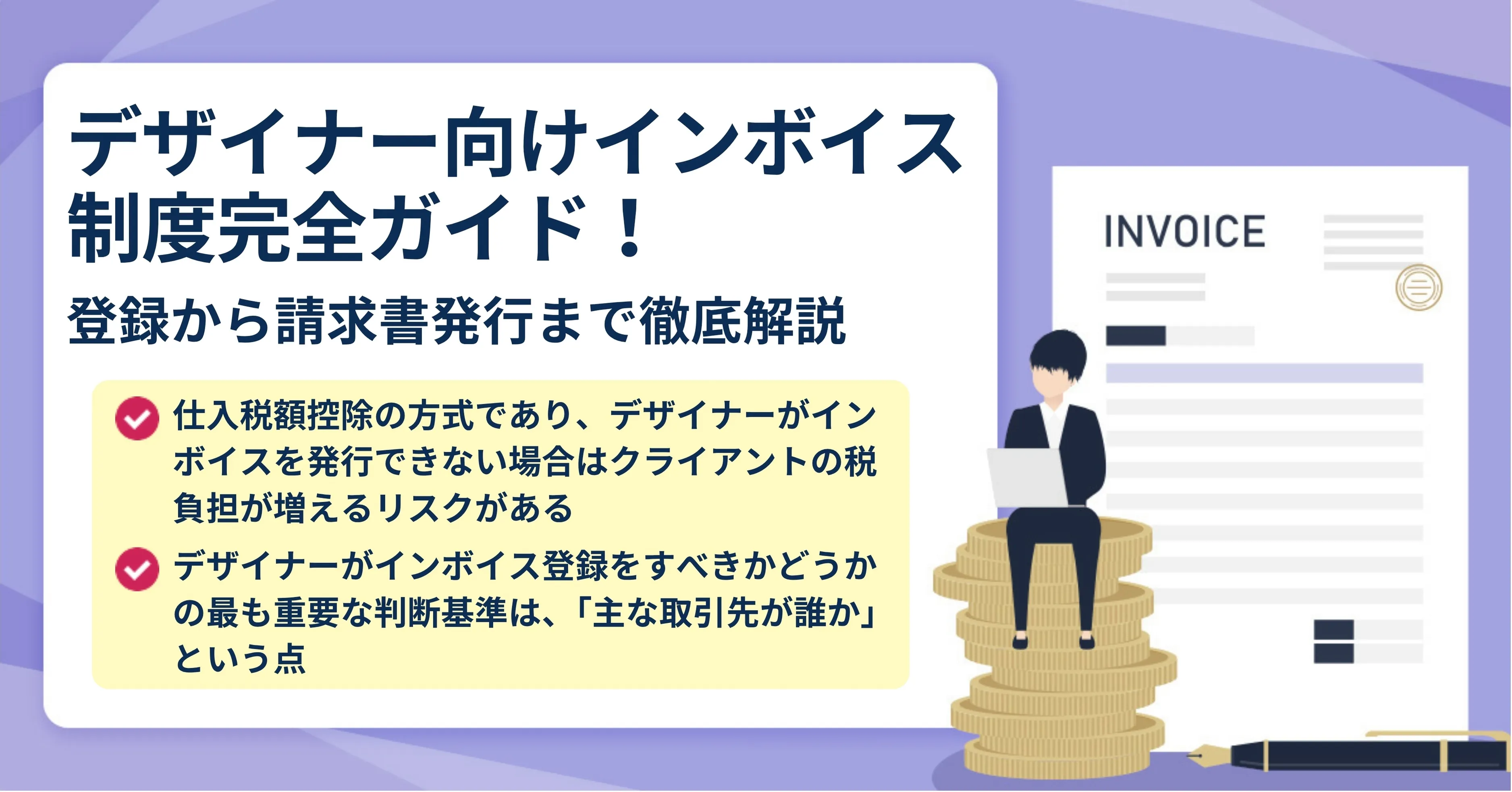
ー 目次 ー
インボイス制度の導入で「登録すべき?」「請求書はどう変わる?」と悩むデザイナーの方も多いのではないでしょうか。本記事では、取引先との関係性を踏まえた登録の判断ポイントから、申請方法、新しい請求書の書き方、クライアントへの伝え方までを丁寧にご紹介します。ご自身の働き方やクライアント層に合った対応が見えてくる内容になっていますので、ぜひ参考になさってください。
インボイス制度とは?デザイナーに関係あるポイントだけ解説
2023年10月1日から、インボイス制度(適格請求書等保存方式)が開始されました。この制度は、フリーランスや個人事業主として活動する多くのデザイナーの取引や収入に直接影響を与える可能性があります。ここでは、複雑な制度の中からデザイナーに関係するポイントに絞って、インボイス制度の基本をわかりやすく解説します。
そもそもインボイス制度とは?基本をわかりやすく解説
インボイス制度とは、正式名称を「適格請求書等保存方式」といい、複数税率(8%と10%)に対応した新しい消費税の仕入税額控除の方式です。簡単に言うと、「売り手と買い手の間で、消費税額を正確に把握するための新しいルール」です。
デザイナーにとっての最大のポイントは、取引先(クライアント)の納税額に関わる点です。クライアントが自社の消費税を納める際、デザイナーのような外注先に支払った消費税分を差し引くことができます。これを「仕入税額控除」と呼びます。インボイス制度開始後は、この仕入税額控除を受けるために、デザイナー側が発行する「インボイス(適格請求書)」が必要不可欠になりました。つまり、デザイナーがインボイスを発行できないと、クライアントは消費税の負担が増えてしまう可能性があるのです。
課税事業者・免税事業者の違いとは
インボイス制度を理解する上で、「課税事業者」と「免税事業者」の違いを知ることが重要です。事業者は、基準期間(通常は前々年)の課税売上高が1,000万円を超えるかどうかで、どちらかに分類されます。多くのフリーランスデザイナーは、売上1,000万円以下の免税事業者に該当するケースが多いでしょう。
インボイスを発行できるのは、税務署に申請し登録を受けた「適格請求書発行事業者」のみです。そして、この登録ができるのは原則として「課税事業者」だけです。しかし課税事業者には消費税の納税義務があります。免税事業者には納税義務がありません。
このような基本を踏まえて次章で課税事業者になるかどうかの判断基準を解説します。
デザイナーはインボイス登録すべき?判断基準を徹底解説
インボイス登録は任意ですが、取引先や自身の事業形態によって最適な選択は異なります。ここでは、登録するべきかどうかの判断基準を、メリット・デメリットを比較しながら詳しく解説します。
免税事業者のままでいるメリットとデメリット
免税事業者のままでいることには、いくつかのメリットがあります。まず大きいのは、消費税の納税義務がないという点です。取引先から受け取った消費税相当分をそのまま収入にできるため、「益税」として実質的な利益になります。また、クライアントが個人や他の免税事業者であれば、インボイス未対応でも取引への影響は少ないと考えられます。事務面でも、確定申告の作業がこれまでと変わらず、手間が増えないのは安心材料です。
一方でデメリットは、取引先が課税事業者の場合には注意が必要ということです。インボイスが発行できないことを理由に、取引を断られたり、消費税相当分の値引きを求められたりする可能性があります。とくに法人クライアントとの取引が中心の場合は、この点が大きなデメリットになることもあるでしょう。
課税事業者になるメリットとデメリット
次に、インボイス登録をして課税事業者になる場合のメリットとデメリットを解説します。
インボイス発行を目的として課税事業者になることのメリットは、たとえば仕入れや経費で支払った消費税を差し引ける「仕入税額控除」が受けられるため、実質的な納税額を抑えることができます。また、適格請求書発行事業者として登録することで、課税事業者のクライアントとも継続的な取引がしやすくなり、ビジネス拡大のチャンスが広がります。登録していること自体が信用につながるケースもあるでしょう。
ただし、課税事業者になることで新たに消費税の納税義務が発生し、手取りが減る可能性がある点には注意が必要です。また、クライアントの多くが個人や免税事業者である場合は、登録による実質的なメリットが少ないケースもあります。さらに、請求書の記載要件や消費税の計算、確定申告など、事務負担がこれまでより増えることも避けられません。
まずはココを確認!取引先次第で変わるデザイナーのインボイス登録判断
デザイナーがインボイス登録をすべきかどうかの最も重要な判断基準は、「主な取引先が誰か」という点です。ご自身の状況を以下のケースに当てはめて考えてみましょう。
ケース1:主な取引先が課税事業者(企業など)の場合
クライアントの多くが法人や課税事業者の個人事業主である場合、インボイス登録をしないとクライアントは仕入税額控除を受けられず、税負担が増えてしまいます。その結果、取引が打ち切られたり、消費税分の値下げを要求されたりするリスクが高まります。今後も企業との取引を継続・拡大していきたいのであれば、課税事業者になることを強くおすすめします。
ケース2:主な取引先が免税事業者や一般消費者(BtoC)の場合
個人のクライアントからのイラスト制作依頼や、免税事業者である小規模店舗のロゴデザインなどが売上の中心である場合、取引先は仕入税額控除を必要としません。そのため、インボイス登録をしなくても取引に影響が出る可能性は低いでしょう。このケースでは、納税や事務作業の負担がない免税事業者のままでいるメリットが大きいと言えます。
ケース3:課税事業者と免税・一般消費者の両方と取引がある場合
取引先が混在している場合は、売上構成比で判断しましょう。売上の大部分を課税事業者が占めているのであれば、登録を検討するのが賢明です。一方で、免税事業者や一般消費者との取引がメインであれば、無理に登録する必要はないかもしれません。ただし、インボイス制度には負担軽減措置として「2割特例」などもあります。課税事業者になった場合の納税額をシミュレーションし、事業全体への影響を考慮して総合的に判断することが大切です。
インボイス制度の登録申請方法と流れをデザイナー向けに解説!
インボイス制度への登録を決めたデザイナーの方が、スムーズに手続きを進められるよう、具体的な申請方法と流れを解説します。特にフリーランスや個人事業主のデザイナーが一人でも対応できるよう、準備するものから見ていきましょう。
登録申請の前にデザイナーが準備する必要書類
インボイスの登録申請は、e-Tax(電子申請)を利用すると迅速に進められます。ここではe-Taxでの申請を前提に、事前に準備しておくと良いものをリストアップします。
個人事業主のデザイナーが準備するものは、主に以下の通りです。
- マイナンバーカード
e-Taxで電子署名を行う際に必要です。お持ちでない場合は、市区町村の窓口で申請・取得しておきましょう。 - 利用者識別番号
e-Taxを利用するために必要な16桁の番号です。過去に確定申告などでe-Taxを利用したことがあれば取得済みのはずです。もしなければ、国税庁のウェブサイトからオンラインで発行手続きが可能です。 - 事業内容がわかるもの
申請書に事業内容を記載する欄があります。デザイナーとしての具体的な業務内容(例:グラフィックデザイン、Webデザイン、イラスト制作など)を簡潔に説明できるよう、あらかじめ考えておくとスムーズです。
法人の場合は、上記に加えて法人番号が必要となります。
インボイス登録の流れと申請方法!
インボイスの登録申請には、主に「e-Tax(電子申請)」と「郵送」の2つの方法があります。それぞれの特徴を解説します。
最も推奨される方法が、国税庁の「e-Taxソフト(SP版)」などを使ったスマートフォンやパソコンからの電子申請です。登録通知までの期間が短く(約1.5ヶ月)、自宅や事務所から24時間申請が可能です。
一方で郵送で申請する場合、パソコン操作が苦手な方でも申請することができます。e-Taxにくらべ登録通知までの期間が長め(約2ヶ月)で、書類の印刷や郵送の手間がかかりますが、ご自身の状況と照らし合わせて、適切な方法を選びましょう。
e-Taxによる申請の流れ
- 国税庁のウェブサイトにある「e-Taxソフト(SP版)」または「e-Taxソフト(WEB版)」にアクセスし、利用者識別番号とパスワードでログインします。
- 申請・届出メニューから「適格請求書発行事業者の登録申請書」を選択します。
- 画面の案内に従い、氏名、住所、事業者区分などの必要事項を入力します。免税事業者の場合は、登録希望日などを入力する項目もあります。
- 入力内容を確認後、マイナンバーカードを使って電子署名を行い、データを送信します。
- 送信後、受付完了のメッセージが表示されれば申請は完了です。後日、税務署から登録通知書が届きます。
郵送による申請の流れ
郵送で申請する場合は、まず申請書を入手する必要があります。
- 国税庁のウェブサイトから「適格請求書発行事業者の登録申請書」のPDFファイルをダウンロードし、印刷します。
- 申請書に必要事項をボールペンで記入します。記入例も国税庁のサイトで確認できますので、参考にしながら正確に記載しましょう。
- 記入した申請書を、ご自身の納税地を管轄する「インボイス登録センター」へ郵送します。送付先は国税庁のウェブサイトで確認できますので、管轄の税務署ではない点にご注意ください。
申請が受理され、審査が完了すると、登録番号が記載された「登録通知書」が送付されます。この登録番号は請求書に記載する重要な番号となるため、大切に保管しましょう。また、登録情報は「国税庁インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイト」でも確認できるようになります。
デザイナー向けインボイス(適格請求書)の書き方ガイド
インボイス制度が始まると、これまで使用していた請求書にいくつかの項目を追加する必要があります。ここでは、デザイナーが発行する「適格請求書(インボイス)」の具体的な書き方を、必須項目と記載例を交えて詳しく解説します。
インボイス制度対応の請求書に必須の記載項目
適格請求書として認められるためには、従来の請求書の記載項目に加えて、新たに3つの項目を記載する必要があります。以下の表で、従来の請求書との違いを確認しましょう。
|
記載項目 |
記載内容 |
【重要】インボイスでの変更・追加点 |
|
発行事業者の氏名・名称 |
請求書を発行するデザイナーの氏名や屋号を記載します。 |
変更なし |
|
登録番号 |
税務署から通知された「T」から始まる13桁の番号を記載します。 |
【追加必須】 |
|
取引年月日 |
デザイン業務の提供日など、取引を行った年月日を記載します。 |
変更なし |
|
取引内容 |
「デザイン制作費」「ディレクション費」など、具体的な業務内容を記載します。 |
※軽減税率(8%)の対象品目がある場合は、その旨がわかるように記載が必要です。(例:「※」印など) |
|
税率ごとに区分した合計額と適用税率 |
税率(10%対象、8%対象)ごとに合計した取引金額(税抜または税込)と、適用税率(「10%」など)を記載します。 |
【追加必須】 |
|
税率ごとに区分した消費税額 |
税率(10%対象、8%対象)ごとに区分した消費税額を記載します。 |
【追加必須】 |
|
書類の交付を受ける事業者の氏名・名称 |
取引先(クライアント)の会社名や氏名を正確に記載します。 |
変更なし |
特に重要なのが「登録番号」「適用税率」「税率ごとの消費税額」の3点です。これらの記載がないと適格請求書として認められず、取引先が仕入税額控除を受けられなくなる可能性があるため、必ず記載するようにしましょう。
消費税は何%?デザイナーが気を付けたい項目や請求書の記載例
デザイナーが提供するデザイン制作やディレクションなどのサービスには、軽減税率は適用されず、標準税率10%の消費税がかかります。食品の販売などとは異なり、軽減税率(8%)が適用されるケースは基本的にありません。そのため、請求書には消費税率10%として計算・記載します。
以下に、デザイナー業務の請求書記載例を示します。
【記載例】Webサイトデザイン制作費の請求書
|
内容 |
単価 |
数量 |
金額(税抜) |
|
WebサイトTOPページデザイン制作費 |
200,000円 |
1 |
200,000円 |
|
下層ページデザイン制作費 |
50,000円 |
4 |
200,000円 |
|
10%対象 小計 |
400,000円 |
|
消費税 (10%) |
40,000円 |
|
合計金額 |
440,000円 |
この例のように、税率ごとに取引金額の合計と消費税額を明確に分けて記載することがポイントです。また、デザイナーの報酬は源泉徴収の対象となる場合があります。源泉徴収が必要な場合は、請求書の備考欄などに源泉徴収税額を明記すると、取引先にとって親切です。源泉徴収税額は、原則として消費税込みの報酬額に対して計算します。
Q&A|デザイナーとインボイス制度に関するよくある質問
インボイス制度に関して、多くのデザイナーが抱えるであろう実務的な疑問にお答えします。
インボイス登録を機に請求金額は見直すべき?
インボイス登録(適格請求書発行事業者の登録)を機に請求金額を見直すかどうかは、ご自身の事業方針やクライアントとの関係性によって慎重に判断する必要があります。主に、免税事業者から課税事業者になる場合に検討することになります。
課税事業者になると、これまで免除されていた消費税の納税義務が発生します。この新たに発生する税負担分を、現在の請求金額に上乗せ(価格転嫁)するか、あるいはご自身で負担するかを決めなければなりません。
判断のポイントは以下の通りです。
- 価格に転嫁する場合:クライアントの理解を得られるかが重要です。インボイス制度への対応という客観的な理由を伝えつつ、自身のスキルや提供価値を改めてアピールし、納得してもらうための交渉が必要になる場合があります。
- 自身で負担する場合:請求金額は据え置きとなるため、クライアントとの取引は継続しやすいでしょう。しかし、消費税分の利益が減少するため、事業全体の収支計画を見直す必要があります。
独占禁止法や下請法では、取引上の優越的な地位を利用して一方的に価格を据え置くことは問題となる可能性があります。まずはクライアントに相談し、双方にとって納得のいく着地点を探ることが大切です。安易に値上げや値下げを判断するのではなく、取引先との関係性や自身の事業への影響を総合的に考慮しましょう。
クライアントへの説明はどうすればいい?伝え方の例文
インボイス制度への対応についてクライアントへ説明する際は、丁寧かつ分かりやすいコミュニケーションを心がけることが、良好な関係を維持する鍵となります。ご自身の状況に合わせて、以下の例文を参考に伝えてみてください。
課税事業者になり、請求金額に消費税分を上乗せする場合
インボイス登録に伴い、消費税分の負担増を価格に転嫁したい場合の例文です。一方的な通知ではなく、相談・お願いという形で伝えるのがポイントです。
課税事業者になったが、請求金額は据え置く場合
インボイス登録はしたものの、クライアントの負担を考慮して価格を据え置く(実質的に自身の利益から消費税を負担する)場合の例文です。クライアントにとってはメリットしかないため、登録番号を通知するシンプルな連絡で問題ありません。
免税事業者を継続する場合
インボイス登録をせず、免税事業者のままでいることを選択した場合の例文です。クライアントが仕入税額控除を受けられなくなる可能性があるため、その旨を正直に伝え、取引を継続してもらえるか意向を確認することが重要です。
まとめ
ここまで、インボイス制度の概要から、登録すべきかどうかの判断基準、登録方法や請求書の書き方までを解説してきました。とくに大切なのは、メインの取引先が課税事業者かどうかを確認し、その意向を踏まえてご自身の対応を考えることです。制度への対応次第で今後の取引や信頼関係にも影響しますので、本記事の内容を参考に、納得のいくかたちで準備を進めていただければと思います。










