【わかりやすく解説】インボイス制度は建設業の一人親方にどう影響?やるべき対策と注意点まとめ
更新日:2026.01.20
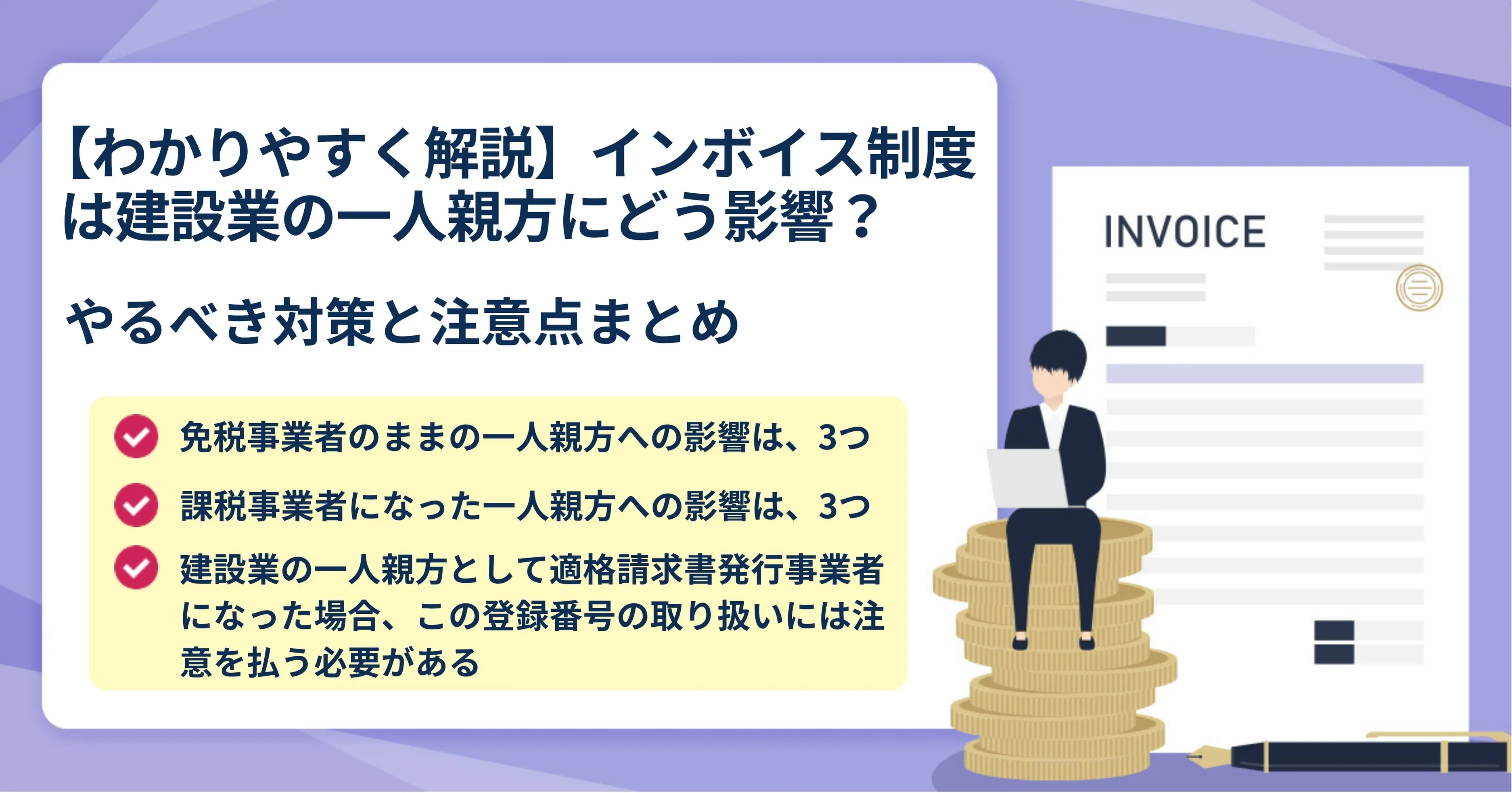
ー 目次 ー
2023年10月から始まったインボイス制度。建設業の一人親方にとって、「仕事が減ってしまうのでは...」「手取りが減るの?」と不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
本記事では、インボイス制度の基本的な仕組みから、取るべき具体的な対策、さらには注意点までをやさしく、わかりやすく解説いたします。ご自身の状況に合わせた最適な選択ができるよう、ぜひ最後までお読みください。
インボイス制度とは?建設業の一人親方が押さえるべき基本
インボイス制度(適格請求書等保存方式)は、建設業で働く一人親方の皆さんにとっても、事業の進め方や税金の取り扱いに大きな影響を与える可能性のある新しい制度です。まずは、この制度の基本的な仕組みをしっかりと理解しましょう。
インボイス制度の概要をわかりやすく解説!
インボイス制度とは、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式です。具体的には、売手が買手に対して、適用税率や消費税額などを正確に記載した「適格請求書(インボイス)」を交付し、買手はそのインボイスを保存することで、消費税の仕入税額控除を受けることができるようになります。
これまでの区分記載請求書等保存方式では、免税事業者からの仕入れについても一定の条件のもと仕入税額控除が可能でしたが、インボイス制度開始後は、原則として適格請求書発行事業者から交付されたインボイスがなければ仕入税額控除が受けられなくなります(経過措置あり)。この変更点が、特に一人親方のような免税事業者の方々に影響を与えるポイントとなります。
建設業の一人親方とインボイス制度の深い関係性
建設業界では、元請業者から下請業者へ、さらにその先の専門工事業者や一人親方へと仕事が発注される、重層的な下請構造が一般的です。多くの一人親方は、年間の課税売上高が1,000万円以下の免税事業者として活動しています。
インボイス制度導入後、元請業者や上位の下請業者(これらは多くが課税事業者です)が仕入税額控除を受けるためには、支払い先である下請業者や一人親方から適格請求書(インボイス)を受け取る必要があります。しかし、免税事業者のままではインボイスを発行できません。そのため、元請業者からインボイスの発行を求められた場合、免税事業者の一人親方は取引の継続や新規案件の受注において、不利な立場に置かれる可能性が出てくるのです。これが、建設業の一人親方とインボイス制度が深く関係していると言われる理由です。
適格請求書発行事業者とは?免税事業者との違い
適格請求書発行事業者とは、税務署に申請し登録を受けることで、適格請求書(インボイス)を交付できる事業者のことを指します。この登録を受けることができるのは、原則として消費税の課税事業者です。
一方、免税事業者とは、基準期間(通常は前々事業年度)の課税売上高が1,000万円以下の事業者など、消費税の納税義務が免除されている事業者を指します。両者の主な違いを以下の表にまとめました。
|
項目 |
適格請求書発行事業者(主に課税事業者) |
免税事業者 |
|
適格請求書(インボイス)の発行 |
可能 |
不可 |
|
消費税の納税義務 |
あり |
原則なし |
|
税務署への登録申請 |
必要 |
不要(免税事業者のままでいる場合) |
|
請求書への登録番号記載 |
必要(「T」+13桁の番号) |
不可 |
|
仕入税額控除の適用(買手側) |
この事業者からの仕入れは原則可能 |
この事業者からの仕入れは原則不可(経過措置あり) |
建設業の一人親方にとって、自身が適格請求書発行事業者になるべきか、それとも免税事業者のままでいるべきかを選択することは、今後の事業運営において非常に重要な判断となります。
インボイス制度が建設業の一人親方に与える影響とは?
ここでは、インボイス制度(適格請求書等保存方式)が具体的にどのような影響が考えられるのか、立場別に解説します。
免税事業者のままの一人親方への影響
インボイス制度開始後も免税事業者のままでいることを選択した一人親方には、主に取引関係において以下のような影響が考えられます。
最も大きな影響は、あなたの主な取引先である元請け企業(課税事業者)が、あなたへの支払いについて仕入税額控除を受けられなくなる点です。元請け企業は、仕入税額控除ができないとその分、消費税の納税負担が増えることになります。その結果、元請け企業から以下のような対応をされる可能性があります。
- 適格請求書発行事業者との取引を優先するため、仕事の依頼が減少する、あるいは新規の取引が見送られる。
- 消費税相当額の値引きを交渉される。
- 取引自体は継続するものの、徐々に取引量が減らされる。
ただし、一人親方自身が持つ技術力や専門性が非常に高く、代替が難しい場合には、免税事業者のままでも取引条件に大きな変更がないケースも考えられます。重要なのは、取引先との関係性や自身の市場における競争力を客観的に把握し、交渉に備えることです。
課税事業者になった一人親方への影響
インボイス制度に対応するため、適格請求書発行事業者(課税事業者)になることを選択した一人親方には、以下のような影響が考えられます。
最大のメリットは、適格請求書を発行できるようになるため、取引先の元請け企業が仕入税額控除を問題なく受けられることです。これにより、取引の継続や新規案件の獲得において、免税事業者のままの場合と比較して有利になる可能性が高まります。
一方で、次のような変化も伴います。
- 消費税の申告および納税の義務が発生します。これまで免税事業者であった場合、新たに消費税の計算方法を理解し、定期的な申告と納税手続きが必要になります。これにより、手取り収入が減少する可能性があります。
- 適格請求書の記載要件を満たした請求書の発行、その控えの保存が必要となり、経理事務の負担が増加する可能性があります。
- 適格請求書発行事業者としての登録申請を行い、登録番号を取得する必要があります。
事務負担の増加に対しては、会計ソフトの導入や税理士などの専門家への相談を検討する必要が出てくるでしょう。また、消費税の納税負担を考慮した価格設定の見直しも課題となります。
建設業の一人親方にとってのメリット・デメリットを整理
インボイス制度への対応は、建設業の一人親方にとってメリットとデメリットの両側面があります。自身の事業規模、取引先の状況、将来の事業計画などを総合的に考慮し、慎重に判断することが求められます。ここでは、免税事業者のままでいる場合と課税事業者(適格請求書発行事業者)になる場合の主なメリット・デメリットを整理して比較します。
免税事業者のままでいる場合のメリット・デメリット
|
区分 |
内容 |
|
メリット |
|
|
デメリット |
|
課税事業者(適格請求書発行事業者)になる場合のメリット・デメリット
|
区分 |
内容 |
|
メリット |
|
|
デメリット |
|
どちらの選択が最適かは、一人親方ご自身の置かれた状況や将来の展望によって大きく異なります。メリットとデメリットをしっかりと比較検討し、必要であれば税理士などの専門家にも相談しながら、ご自身にとって最善の道を選択することが重要です。
建設業の一人親方がインボイス制度でやるべき具体的な対策!
インボイス制度への対応は、建設業で働く一人親方の皆さんにとって、今後の事業運営に大きく関わる重要な課題です。しかし、具体的に何をすれば良いのか、不安に感じる方も多いのではないでしょうか。この章では、一人親方がインボイス制度に対して取るべき具体的な対策を、ステップごとにわかりやすく解説します。
まず確認!取引先(元請け)のインボイス対応方針
インボイス制度への対策を考える上で、まず最初に行うべきことは、主要な取引先である元請け企業がインボイス制度に対してどのような方針を持っているかを確認することです。元請け企業の方針によって、一人親方として取るべき対応が大きく変わってくるため、非常に重要なステップとなります。
確認すべき主なポイントは以下の通りです。
- 適格請求書発行事業者への登録を求めているか。
- もし免税事業者のままでいる場合、取引条件(契約金額、消費税分の支払いなど)に変更はあるか。
- インボイス制度対応に関して、いつまでにどのような対応を求めているか。
これらの情報は、直接元請けの担当者にヒアリングする、または契約書や通知書面などで確認しましょう。曖昧な点を残さず、明確にしておくことが肝心です。この確認結果を踏まえ、自身が免税事業者のままでいるか、課税事業者(適格請求書発行事業者)になるかを判断する材料とします。
免税事業者のままでいる場合の対策と交渉術
取引先との確認の結果やご自身の事業規模などを考慮し、免税事業者のままでいることを選択する一人親方もいらっしゃるでしょう。その場合に考えられる影響と、取り組むべき対策、そして価格交渉が必要になった際のポイントについて解説します。
免税事業者のままでいる場合、元請け企業は仕入税額控除を受けられなくなるため、取引価格の引き下げや、最悪の場合、取引の縮小・停止を求められる可能性があります。しかし、インボイス制度開始後3年間は、免税事業者からの仕入れについても80%の仕入税額控除が可能な経過措置があります(その後3年間は50%)。この点を元請けに説明し、理解を求めることが重要です。
具体的な対策と交渉術としては、以下のような点が挙げられます。
- 自身の強みをアピールする: 高い技術力、専門性、納期遵守など、価格以外の付加価値を提示し、取引継続の必要性を訴えます。
- 価格交渉に応じる場合のライン設定: 消費税相当額の全額ではなく、一部の値引きで交渉するなど、事前に落としどころを考えておきましょう。
- 経過措置の活用を提案する: 上述の経過措置について説明し、元請けの負担が一定期間軽減されることを伝えます。
- 新たな取引先の開拓: 状況によっては、インボイス発行を求めない事業者や消費者向けの仕事を探すことも視野に入れますが、建設業の特性上、容易ではないことも理解しておきましょう。
交渉の際は、感情的にならず、冷静に、そして建設的な対話を心がけることが大切です。自身の状況と相手の立場を理解し、双方にとって受け入れ可能な着地点を見つける努力が求められます。
課税事業者になる場合の対策と準備
インボイス制度に対応するため、課税事業者となり、適格請求書発行事業者として登録する道を選ぶ一人親方も多いでしょう。この場合、いくつかの準備と手続きが必要になります。計画的に進めることで、制度開始後もスムーズに事業を継続できます。
課税事業者になる場合にやるべき主な対策と準備は以下の通りです。
|
準備項目 |
内容 |
備考 |
|
適格請求書発行事業者の登録申請 |
管轄の税務署に対し、「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出します。これにより登録番号が発行されます。 |
e-Taxを利用したオンライン申請も可能です。申請から登録通知まで一定期間を要するため、早めの手続きを心がけましょう。 |
|
会計ソフト・請求書発行システムの準備 |
インボイス(適格請求書)の保存や発行に対応した会計ソフトや請求書発行システムを導入するか、既存のシステムをアップデートする必要があります。 |
クラウド型の会計ソフトは、制度改正への対応も早く、導入しやすい場合があります。 |
|
請求書の様式変更 |
発行する請求書に、登録番号、適用税率、税率ごとの消費税額などを記載する必要があります。適格請求書の記載要件を満たすフォーマットに変更しましょう。 |
国税庁のウェブサイトなどで記載例が公開されていますので、参考にしてください。 |
|
消費税の申告・納税準備 |
課税事業者になると、消費税の申告と納税義務が生じます。経理処理の方法を理解し、納税資金の準備も必要です。 |
初めて消費税申告を行う場合は、税理士に相談することも有効な手段です。 |
|
取引先への通知 |
適格請求書発行事業者の登録が完了したら、登録番号やインボイスの発行開始時期などを元請けなどの取引先に通知します。 |
事前に連絡しておくことで、取引先もスムーズに対応できます。 |
これらの準備を計画的に進め、インボイス制度への円滑な移行を目指しましょう。
建設業の一人親方も使える!インボイス制度に有効な補助金
インボイス制度への対応には、会計ソフトの導入や税理士への相談など、新たな費用が発生する場合があります。建設業の一人親方が活用できる可能性のある、負担軽減のための支援策(特例措置や制度)について解説します。これらを活用することで、制度移行に伴う経済的な負担を少しでも和らげることができます。
2割特例の対象と建設業での活用
「2割特例」とは、インボイス制度の開始を機に免税事業者から課税事業者になった事業者を対象とした負担軽減措置です。具体的には、売上にかかる消費税額の2割を納付すればよいという特例で、事務負担も大幅に軽減されます。
対象となるのは、インボイス発行事業者の登録を受けた方のうち、基準期間(前々年・前々事業年度)の課税売上高が1,000万円以下の事業者などです。多くの建設業の一人親方がこの条件に該当する可能性があります。
建設業の一人親方がこの2割特例を活用するメリットは、消費税の納税額を抑えられる点と、仕入れに関する消費税額を細かく計算・記帳する必要がなくなり、経理事務の負担が軽減される点です。この特例は、令和5年10月1日から令和8年9月30日の属する課税期間まで適用されます。事前の届出は不要で、消費税の申告書に2割特例の適用を受ける旨を付記することで適用を受けられます。
簡易課税制度の選択と一人親方の判断
「簡易課税制度」とは、中小事業者の納税事務負担を軽減するために設けられている制度で、売上にかかる消費税額に、事業の種類ごとに定められた「みなし仕入率」を掛けて仕入税額控除額を計算します。実際の仕入れや経費にかかった消費税額を計算する必要がないため、経理処理が簡素化されます。
建設業の場合、一般的に「第五種事業」に該当し、みなし仕入率は70%です。ただし、提供するサービスの内容によっては他の事業区分に該当する場合もあるため、自身の事業実態を確認する必要があります。
一人親方が簡易課税制度を選択するかどうかの判断基準としては、以下のような点が考えられます。
- 実際の課税仕入れが少なく、みなし仕入率で計算した方が有利になる場合。
- 経理事務の負担をできるだけ軽減したい場合。
簡易課税制度を選択するためには、原則として適用を受けたい課税期間の開始の日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を税務署に提出する必要があります。また、一度選択すると原則として2年間は継続適用となり、2割特例との有利不利も考慮して慎重に判断することが重要です。どちらの制度が有利になるかは、売上や経費の状況によって異なるため、税理士などの専門家に相談することも検討しましょう。
インボイス制度で建設業の一人親方が知っておくべき注意点とは?
適格請求書発行事業者の登録番号の取り扱い
インボイス制度において、適格請求書発行事業者の登録番号は極めて重要な情報となります。建設業の一人親方として適格請求書発行事業者になった場合、この登録番号の取り扱いには細心の注意を払う必要があります。
登録番号は、所轄の税務署に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、審査を経て通知される「T」から始まる13桁の識別番号です。この番号は、発行する請求書や領収書といったインボイス(適格請求書)に正確に記載することが義務付けられています。記載漏れや誤りがあると、取引先(元請けなど)が仕入税額控除を正しく受けられなくなる可能性があるため、発行時には十分な確認が求められます。
ご自身の登録番号の管理はもちろんのこと、取引先から受け取るインボイスに記載された登録番号が正しいものかを確認することも大切です。国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」を利用すれば、登録番号が有効であるか、また事業者の情報を確認できます。これにより、不正な請求書や誤った情報に基づく取引を防ぐ一助となります。
登録番号は厳重に管理し、紛失や第三者による不正利用がないように注意しましょう。また、登録情報(氏名、屋号、本店所在地など)に変更が生じた場合や、事業を廃止して登録を取り消す場合には、速やかに税務署へ所定の届出書を提出する必要があります。
インボイス制度開始後の経過措置と一人親方の対応
インボイス制度の開始に伴い、免税事業者からの仕入れについて、制度移行による急激な影響を緩和するための経過措置が設けられています。建設業の一人親方、特に免税事業者のままでいることを選択した場合や、免税事業者と取引がある場合に、この経過措置の内容を正確に理解しておくことが不可欠です。
経過措置とは、免税事業者からの課税仕入れであっても、制度開始から一定期間は、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額として控除できるというものです。この措置により、発注者側(元請け企業など)は、免税事業者である一人親方への発注を継続しやすくなる側面があります。経過措置の期間と控除可能な割合は以下の通りです。
|
期間 |
仕入税額控除として認められる割合 |
|
2023年10月1日~2026年9月30日 |
課税仕入れに係る支払対価の額の80% |
|
2026年10月1日~2029年9月30日 |
課税仕入れに係る支払対価の額の50% |
一人親方自身が免税事業者の場合、取引先である元請け企業はこの経過措置を利用して仕入税額控除を行います。この点を理解した上で、取引先との価格交渉や契約条件の協議に臨むことが重要です。なお、経過措置の適用を受けるためには、買い手側は帳簿への一定事項の記載と、区分記載請求書等と同様の事項が記載された請求書等の保存が必要です。
建設業の一人親方が注意すべき契約と請求
インボイス制度の導入は、建設業の一人親方の契約関係や日々の請求業務にも直接的な影響を及ぼします。制度開始後の無用なトラブルを避け、円滑な事業運営を継続するためには、事前に注意すべきポイントを把握し、適切に対応することが求められます。
契約書の見直しと確認
現在締結している、あるいは今後新たに締結する業務委託契約書などにおいて、消費税の取り扱いやインボイス(適格請求書)の発行に関する条項を改めて確認することが非常に重要です。特に、ご自身が免税事業者のままでいる場合、または取引先が免税事業者である場合には、消費税相当額の負担や請求金額の取り扱いについて、元請けなどの取引先と明確に合意しておく必要があります。曖昧な状態のまま取引を進めると、後々支払いに関するトラブルに発展する可能性があるため、必要に応じて契約内容の変更や覚書の締結も検討しましょう。
請求書の様式変更と記載事項
適格請求書発行事業者となった建設業の一人親方は、発行する請求書の様式をインボイスの要件を満たすものに変更しなければなりません。インボイスとして認められるためには、従来の請求書記載事項に加えて、主に以下の項目を正確に記載する必要があります。
- 適格請求書発行事業者の登録番号
- 適用税率(標準税率10%、軽減税率8%の別)
- 税率ごとに区分した消費税額等
これらの記載漏れや誤りがないよう、使用している請求書発行システムや会計ソフトの設定確認・アップデートを行うか、手書きの場合は記載内容を十分に確認する体制を整えることが不可欠です。国税庁のウェブサイトなどでインボイスの記載例が公開されていますので、参考にするとよいでしょう。
消費税の端数処理ルール
インボイスに記載する消費税額等の端数処理は、一つの適格請求書につき、税率ごとにそれぞれ1回ずつ行うというルールが定められています。例えば、請求書内に複数の取引品目がある場合でも、各品目ごとに消費税額を計算して端数処理を行うのではなく、税率ごとに合計した対価の額に対して消費税額を計算し、その結果に対して端数処理を行います。このルールを誤ると、請求金額に差異が生じ、取引先に迷惑をかける可能性がありますので注意が必要です。端数処理の方法(切り上げ、切り捨て、四捨五入など)については、法令で特段の定めはないため、取引先との間で事前に取り決めておくと、よりスムーズな取引につながります。
下請法との関連性と不当な取り扱いへの注意
インボイス制度への対応を理由として、元請け企業が下請けである一人親方に対し、一方的に不利益な取引条件を強いることは、優越的地位の濫用として下請法や独占禁止法に違反する可能性があります。例えば、適格請求書発行事業者への登録を強要したり、登録しないことを理由に取引価格を不当に引き下げたり、あるいは消費税相当額の一部または全部を支払わないといった行為は問題となる場合があります。このような状況に直面した場合は、一人で抱え込まず、公正取引委員会や中小企業庁が開設している相談窓口、または建設業団体などに相談することも検討しましょう。
Q&A|インボイス制度と建設業の一人親方に関するよくある質問
「抜け道」って本当にあるの?免税のままでもやっていける方法は?
インボイス制度において、法制度の趣旨から外れるような、いわゆる「抜け道」というものは存在しません。しかし、建設業の一人親方が免税事業者のままで事業を継続するための現実的な方法や考え方はあります。
まず最も重要なのは、取引先である元請け企業とのコミュニケーションです。元請け企業が、免税事業者であるあなたとの取引を継続するために、消費税の仕入税額控除が一部できなくなる影響をどの程度許容できるかを確認しましょう。あなたの技術力や信頼関係が、取引継続の鍵となることもあります。
その上で、価格交渉を行うことも一つの手段です。インボイスを発行できないことによる元請けの負担増について、一部を価格に転嫁できないか、あるいは他の条件で見直せないかなどを相談してみましょう。ただし、交渉は相手の状況も考慮し、慎重に進める必要があります。
また、ご自身の提供するサービスの付加価値を高め、代替の難しい存在になることも、免税事業者のまま取引を続ける上で有効です。安易な情報に流されず、税理士などの専門家にも相談し、ご自身の状況に合った最善の方法を検討することが大切です。
一人親方は必ずインボイス発行事業者になるべき?
建設業の一人親方の方が、必ずインボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)に登録しなければならないわけではありません。免税事業者のままでいるか、課税事業者となりインボイス発行事業者になるかは、個々の事業状況や取引先の意向などを総合的に考慮して判断すべきです。
判断する際の主なポイントは以下の通りです。
- 主要な取引先(元請け)の意向:元請けが課税事業者であり、仕入税額控除のためにインボイスを必要としている場合、対応しないと取引の継続が難しくなる可能性があります。
- 自身の売上規模と今後の展望:課税売上高が1,000万円を超えると、いずれにしても消費税の課税事業者となります。将来的に事業拡大を目指すのであれば、早期の登録も選択肢の一つです。
- インボイス発行事業者になるメリット・デメリット:メリットとしては、課税事業者である元請けとの取引継続や新規開拓がしやすくなる点が挙げられます。デメリットは、消費税の申告・納税義務が発生し、経理事務の負担が増えることです。
ご自身の状況を正確に把握し、取引先ともよく話し合った上で、最適な選択をしてください。判断に迷う場合は、税理士や地域の商工会議所、建設業団体などに相談することをおすすめします。
インボイス制度で一人親方の廃業リスクは上がる?
インボイス制度の導入により、元請業者が仕入税額控除を適用するために「適格請求書(インボイス)」の発行を求めるようになりました。そのため、インボイスを発行できない一人親方は取引から外される可能性が高まり、実質的に仕事を失うリスクが上がったと言われています。
特に建設業界では、下請け構造が強く、インボイス未対応者を敬遠する動きが加速しています。免税事業者のままでいると「税込報酬を値引きされる」または「取引そのものが終了する」といった事例も報告されており、廃業を選ばざるを得ない一人親方が増加傾向にあるのが実情です。
売上1,000万円以下の一人親方はインボイス登録すべき?
売上1,000万円以下であれば免税事業者のままでいることは可能ですが、取引先(元請)との関係性によってはインボイス登録が実質的に必須となるケースがあります。登録しなければ「発注しづらい」「報酬減額」といった圧力がかかる可能性が高いからです。
一方で、消費税の納税義務が発生するため、年間の利益や経費の状況、業界の慣習をよく確認してから判断する必要があります。例えば、材料費や機材費などで経費が多くかかる場合は、課税事業者となっても大きな納税負担にはならない可能性もあります。
総じて、一人親方でインボイス登録をすべきかどうかは、「仕事の継続性」「元請からの要請」「納税シミュレーション」の3点を踏まえたうえで、慎重に判断することが重要です。
日当制の仕事にもインボイスって関係あるの?
はい、日当制で仕事を受けている建設業の一人親方の方も、インボイス制度と無関係ではありません。その日当が消費税の課税対象となる「役務の提供」の対価である場合、インボイス制度の影響を受けます。
具体的には、日当を支払う側の元請け企業が課税事業者である場合、その日当にかかる消費税額について仕入税額控除を受けるためには、原則としてインボイス(適格請求書)の保存が必要となります。あなたが免税事業者でインボイスを発行できない場合、元請け企業はその分の仕入税額控除ができなくなります。
このため、元請け企業からインボイスの発行を求められたり、それができない場合には取引条件の見直し(例えば、消費税相当額の値引きなど)を打診されたりする可能性があります。日当制であっても、契約内容や報酬の性質(給与所得に該当しないかなど)を確認し、インボイス制度への対応を検討する必要があります。
まとめ
インボイス制度は、建設業に従事されている一人親方の皆さまにとって、今後の働き方や取引関係に少なからず影響を与える制度です。「登録するべきか迷っている」「免税のまま続けられるのか不安」といったお悩みに対して、まずはご自身の取引先の意向や将来の事業計画を見据え
制度を正しく理解し、準備を進めていきましょう。必要に応じて、税理士や専門家の力も借りながら、ご自身にとって最良の選択をしていただければと思います。










