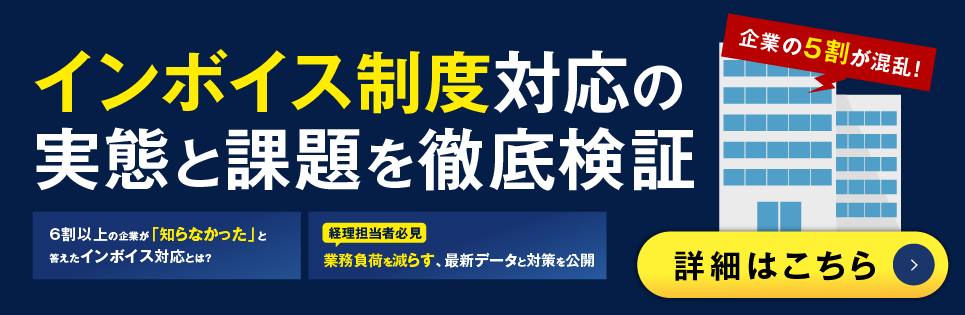インボイス制度は海外では当たり前!日本との違いや主要国の導入状況
更新日:2025.12.24
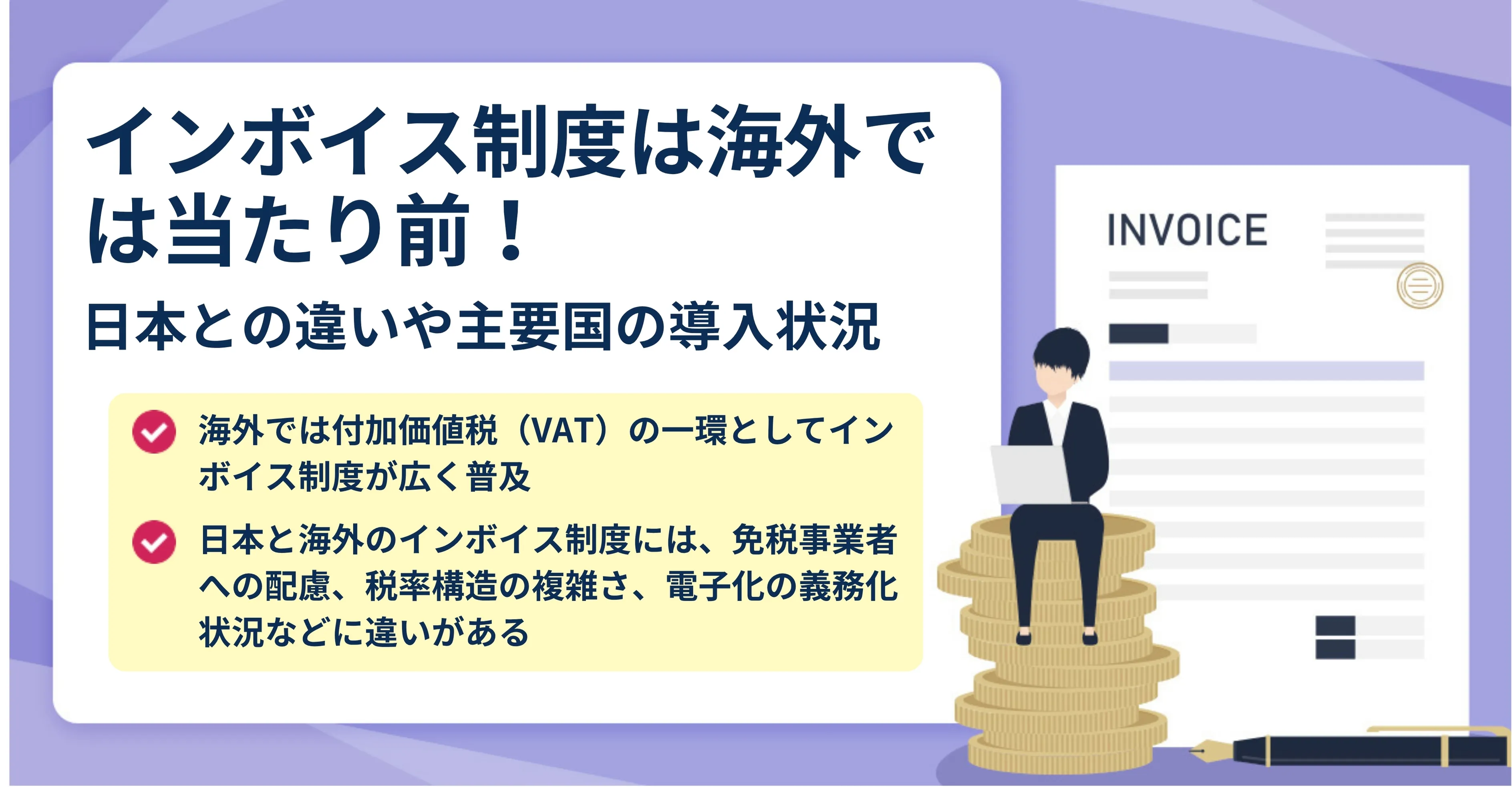
ー 目次 ー
日本のインボイス制度に戸惑いを感じている方もいらっしゃるかと思います。実はこの仕組み、海外では「公平な課税を実現するための当たり前のルール」として広く浸透しているんです。本記事では、欧州やアメリカ、アジア各国など主要国の導入状況をもとに、日本のインボイス制度と何が違うのかを丁寧に解説します。グローバルな視点から日本の制度を客観的に理解するためのヒントになれば幸いです。
インボイス制度とは?仕組みと目的をおさらい
2023年10月1日から日本で開始されたインボイス制度(適格請求書等保存方式)。「海外では当たり前」と言われることもありますが、まずは日本における制度の基本的な仕組みと、導入された目的について正確に理解しておきましょう。
そもそもインボイス制度とは?しくみを簡単に解説
インボイス制度とは、ひとことで言えば「消費税の納税額を正しく計算するための新しいルール」です。この制度の中心となるのが「適格請求書(インボイス)」と呼ばれる、特定の記載要件を満たした請求書や領収書です。
事業者が商品やサービスを購入した際に支払った消費税分を、自社が納める消費税額から差し引くことを「仕入税額控除」と呼びます。インボイス制度導入後は、この仕入税額控除を受けるために、取引相手(売り手)から発行された「適格請求書」の保存が必要不可欠となりました。
つまり、買い手側は適格請求書がなければ、仕入税額控除が適用できず、結果として納税負担が増えることになります。
日本がインボイス制度を取り入れる目的と背景とは?
日本でインボイス制度が導入された背景には、大きく分けて2つの目的があります。
まず一つ目は、「複数税率に対応し、消費税額を正確に把握すること」です。
2019年10月に消費税率が10%に引き上げられた際、食料品など一部の品目には軽減税率8%が適用されるようになり、「複数税率」が導入されました。この複数税率により、ひとつの取引の中に10%と8%の税率が混在するケースが出てきて、消費税の計算がより複雑になったのです。
インボイス制度では、請求書に適用した税率や、それぞれの税率ごとの消費税額を明記することが義務づけられているため、どの取引にどの税率が適用されたのかが一目でわかるようになります。 これによって、税額の計算ミスや不正を防ぎ、正確な納税につなげることが狙いです。
二つ目の目的は、「益税の問題をなくし、課税の公平性を確保すること」です。
これまで年間売上が1,000万円以下の事業者(免税事業者)は、顧客から消費税を預かっても、それを国に納める義務がありませんでした。このように納税が免除されることで生じる利益を「益税」と呼びますが、それが課税事業者との間で不公平だと問題視されていたのです。
インボイス制度のもとでは、免税事業者は「適格請求書(インボイス)」を発行できません。
そのため、取引相手の課税事業者が仕入税額控除を受けられず、免税事業者との取引に不利が生じる可能性があります。こうした状況から、免税事業者が取引を維持するために課税事業者へ転換する流れが促され、結果的に益税の問題を解消していくことが期待されています。
インボイス制度は海外では当たり前!普及した理由と主要国の導入状況
インボイス制度は実は海外に目を向けると、多くの国で以前から導入されており、ごく当たり前の制度として定着しています。海外ではなぜインボイス制度が普及したのか、その理由と主要国の導入状況を詳しく見ていきましょう。
海外のインボイス制度の正体は付加価値税(VAT)
海外で「インボイス制度」と呼ばれるものの多くは、日本の消費税にあたる「付加価値税(VAT:Value Added Tax)」を正確に運用するための仕組みを指します。付加価値税とは、商品やサービスが提供される各取引段階で生じる「付加価値」に対して課される税金です。
この付加価値税の仕組みにおいて、事業者が仕入れの際に支払った税金分を、売上時に預かった税金から差し引く「仕入税額控除」を受けるために、インボイス(適格請求書)が不可欠な証明書類となります。つまり、海外におけるインボイス制度は、付加価値税と一体不可分の関係にあり、税制度の根幹をなすものとして普及してきたのです。
欧州諸国におけるインボイス制度の導入状況
付加価値税(VAT)は、1954年にフランスで世界で初めて導入された後、欧州各国に広がりました。現在、EU(欧州連合)では、加盟国に対して付加価値税の導入を義務付けており、それに伴いインボイス制度も広く採用されています。まさにヨーロッパでは「当たり前」の制度と言えるでしょう。
以下に、欧州主要国の導入状況をまとめました。
|
国名 |
導入年 |
税の名称 |
標準税率(2024年時点) |
|
フランス |
1954年 |
TVA |
20% |
|
ドイツ |
1968年 |
USt. |
19% |
|
イギリス |
1973年 |
VAT |
20% |
|
イタリア |
1973年 |
IVA |
22% |
|
スウェーデン |
1969年 |
Moms |
25% |
※イギリスはEUを離脱しましたが、付加価値税(VAT)制度は維持しています。
アメリカ・アジア主要国のインボイス対応状況
ヨーロッパ以外の国々でも、インボイス制度の導入は進んでいます。ただし、国や地域によって制度は異なります。特にアメリカは、他の主要国とは大きく異なる税制度を採用しています。
アメリカの状況
アメリカには、連邦レベルでの消費税や付加価値税が存在しません。代わりに、州や市などの地方政府が「売上税(Retail Sales Tax)」を課しています。この売上税は、商品が最終消費者に販売される段階でのみ課税される仕組みです。そのため、取引の各段階で税額を計算し控除する「仕入税額控除」の概念がなく、日本や欧州のようなインボイス制度は導入されていません。
アジア・オセアニア主要国の状況
一方で、韓国や中国、オーストラリアなどアジア・オセアニアの多くの国では、付加価値税やそれに類似する「物品・サービス税(GST:Goods and Services Tax)」が導入されており、インボイス制度が運用されています。
|
国名 |
導入年 |
税の名称 |
標準税率(2024年時点) |
|
韓国 |
1977年 |
付加価値税 |
10% |
|
中国 |
1994年 |
増値税 |
13% |
|
シンガポール |
1994年 |
GST |
9% |
|
オーストラリア |
2000年 |
GST |
10% |
|
台湾 |
1986年 |
営業税 |
5% |
このように、アメリカのような例外はあるものの、世界の多くの先進国や主要国では、付加価値税(VAT)や物品・サービス税(GST)と共にインボイス制度が導入されており、国際標準となりつつあることがわかります。
日本のインボイス制度となにが違う?海外制度との違いを3つ解説!
日本のインボイス制度と海外の制度には、具体的にどのような違いがあるのでしょうか。ここでは、主な3つの違いを解説します。
免税事業者の扱いと小規模事業者への配慮
日本のインボイス制度を理解する上で重要なのが「免税事業者」の存在です。海外の制度と比較しながら、その扱いの違いを見ていきましょう。
日本では、課税売上高が1,000万円以下の事業者は、消費税の納税義務が免除される「免税事業者」となります。インボイス制度開始後も免税事業者のままでいることは可能ですが、その場合、取引先が仕入税額控除を受けられないというデメリットが生じます。このため、多くの免税事業者が課税事業者になるかどうかの選択を迫られています。
一方、海外の多くの国にも免税点制度は存在しますが、その基準額や運用は異なります。例えば、EU諸国では加盟国ごとに免税点が設定されており、基準も様々です。VAT制度が長年定着しているため、事業開始時から課税事業者として登録することが一般的であり、日本のように制度導入の過渡期特有の課題は少ないといえます。
また、日本特有の配慮として、小規模事業者の負担を軽減するための激変緩和措置(2割特例や少額特例など)が設けられている点も大きな違いです。
標準税率と軽減税率の運用
消費税の税率構造も、日本と海外では大きく異なります。特に、税率の種類や対象品目の違いは顕著です。
日本の消費税率は、標準税率10%と軽減税率8%の2種類です。軽減税率の対象は「酒類・外食を除く飲食料品」と「定期購読の新聞」に限定されており、比較的シンプルです。
対して、海外、特にEU諸国では標準税率が20%前後と日本より高く設定されている国がほとんどです。さらに、軽減税率が複数存在したり、ゼロ税率(税率0%だが仕入税額控除は可能)や非課税(仕入税額控除が不可)があったりと、税率構造がより複雑になっています。
以下の表で、主要国の税率構造の違いを確認してみましょう。
|
国・地域 |
標準税率 |
軽減税率・その他 |
|
日本 |
10% |
8% |
|
イギリス |
20% |
5%(家庭用燃料など)、0%(食料品、書籍など) |
|
フランス |
20% |
10%(レストラン、交通機関など)、5.5%(食料品、書籍など)、2.1%(医薬品など) |
|
ドイツ |
19% |
7%(食料品、書籍など) |
このように、海外では生活必需品などに対して、より低い税率やゼロ税率を適用するケースが多く見られます。
電子インボイス義務化の世界的な潮流
インボイスの電子化に関する考え方も、日本と海外では違いがあります。世界的には、電子インボイスの義務化が大きなトレンドとなっています。
現在の日本では、電子インボイスの発行は義務化されておらず、紙の適格請求書も引き続き有効です。国際的な標準規格である「Peppol(ペポル)」に準拠した日本仕様「JP PINT」の普及が進められていますが、利用は任意です。
これに対し、海外では脱税防止や業務効率化を目的として、電子インボイスを義務化する国が増えています。特にイタリアでは2019年から国内のBtoB取引で電子インボイスが全面的に義務化されました。他にもフランス、ポーランド、スペインといった欧州諸国や、韓国、中南米の国々でも義務化の動きが加速しています。
これらの国では、政府が指定するプラットフォームを介してインボイスを送受信する「クリアランスモデル」が採用されることが多く、税務当局が取引情報をリアルタイムで把握できる仕組みが構築されています。この点は、あくまで当事者間でのやり取りが基本となる日本の制度との大きな違いです。
共通点は仕入税額控除の仕組み!
ここまで日本と海外の違いを解説してきましたが、制度の根幹にある仕組みは共通しています。それは「仕入税額控除」です。
仕入税額控除とは、事業者が売上にかかる消費税(VAT)から、仕入れや経費にかかった消費税(VAT)を差し引いて納税する仕組みのことです。この仕組みによって、生産や流通の各段階で二重、三重に税金が課されることを防いでいます。
そして、この仕入税額控除を正確に行うために、適用税率や税額が明記された「インボイス(適格請求書)」が必要不可欠となるのです。この基本原則は、日本でも海外でも変わりません。
海外の「当たり前」から日本のインボイス制度を考える
海外では付加価値税(VAT)の一環としてインボイス制度が広く普及していますが、その仕組みや背景は国によって様々です。ここでは、海外の事例を参考に、日本のインボイス制度が抱える課題と、国際取引における実務上の注意点を解説します。
海外事例から学ぶ日本のインボイス制度の課題
海外の制度と比較すると、日本のインボイス制度には、特に事業者への影響やデジタル化の面でいくつかの課題が見えてきます。
一つ目の課題は、免税事業者への影響の大きさです。多くの国では、小規模事業者に対して登録を免除する制度がありますが、日本のインボイス制度は、免税事業者が取引から排除されるリスクを懸念する声が多く上がっています。経過措置は設けられているものの、フリーランスや個人事業主が多い日本の経済構造において、制度移行に伴う負担の大きさは大きな課題です。
二つ目に、複数税率による事務負担の増大が挙げられます。日本の消費税は標準税率10%と軽減税率8%の複数税率が採用されており、正確な税率計算とインボイスへの記載が求められます。これにより、特に軽減税率対象品目を扱う事業者の経理業務は複雑化し、事務負担が増大しています。
三つ目の課題は、デジタル化への移行の遅れです。世界的には、業務効率化やデータ活用の観点から電子インボイスの義務化が進んでいます。日本でも国際標準規格である「Peppol(ペポル)」をベースとしたデジタルインボイスの普及が進められていますが、現状では紙のインボイスも認められており、完全なデジタル化への移行は道半ばです。この遅れは、将来的に国際的な取引における競争力に影響を与える可能性があります。
海外との取引でインボイスを発行する際の注意点
海外企業と取引を行う場合、日本のインボイス制度と相手国の税制度の両方を理解しておく必要があります。特に輸出取引と輸入取引では、消費税の扱いが大きく異なりますので注意しましょう。
商品を輸出する場合、日本の消費税は免除される「輸出免税」が適用されます。そのため、国内取引のように消費税額を記載した適格請求書(インボイス)を発行する義務はありません。ただし、取引の証明として、従来の請求書(Commercial Invoiceなど)は引き続き必要です。
一方で、海外から商品を輸入する場合、仕入税額控除を受けるためには、海外の事業者が発行した請求書ではなく、税関長から交付される「輸入許可通知書」などが必要です。海外の事業者は日本の適格請求書発行事業者ではないため、この点を混同しないように注意しましょう。
|
取引の種類 |
日本の消費税の扱い |
仕入税額控除に必要な主な書類 |
|
輸出取引(自社が輸出) |
輸出免税(消費税はかからない) |
適格請求書の発行義務なし (取引の事実を証明する輸出申告書や請求書は必要) |
|
輸入取引(自社が輸入) |
輸入時に消費税が課税される |
税関長が発行する輸入許可通知書など (海外事業者の請求書では控除不可) |
まとめ
インボイス制度は、海外では付加価値税(VAT)として多くの国で導入されている当たり前の仕組みです。日本の制度とは免税事業者の扱いや電子化の進捗に違いが見られますが、正確な消費税額を把握するための「仕入税額控除」が目的である点は世界共通です。欧州諸国のように電子インボイスが義務化されている事例もあり、世界の流れにも目を向けていくことが求められるでしょう。