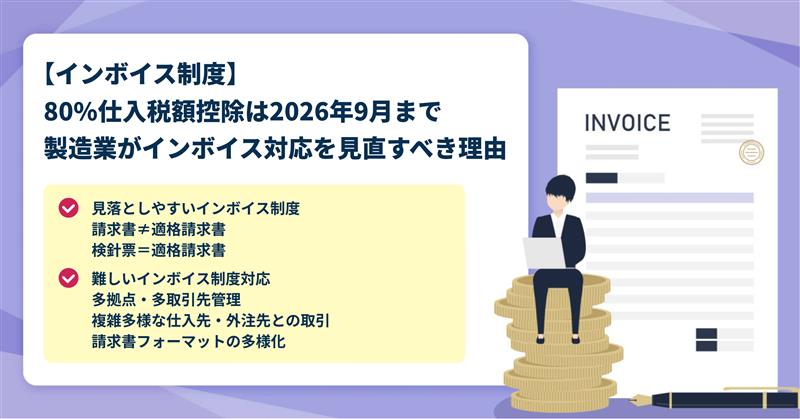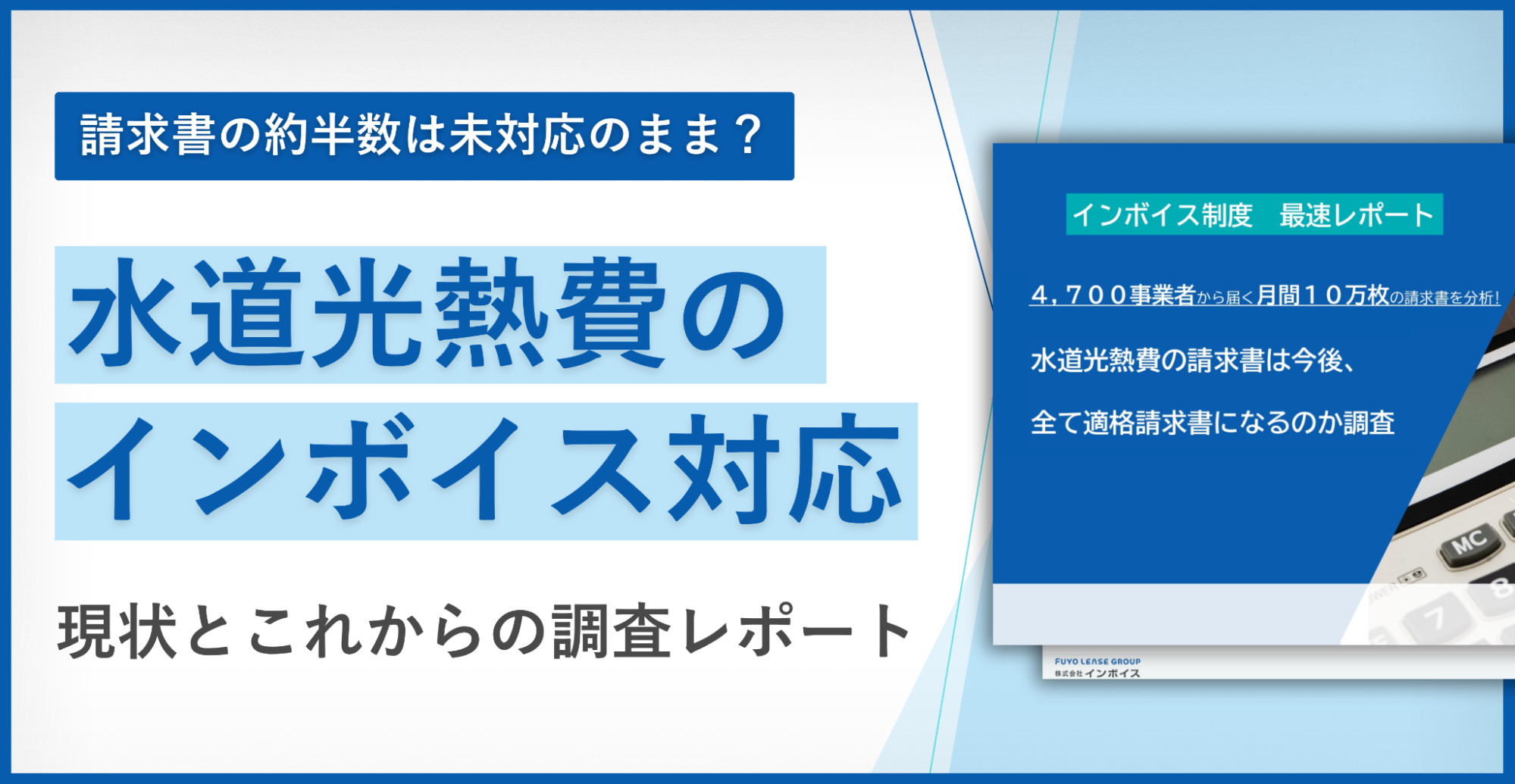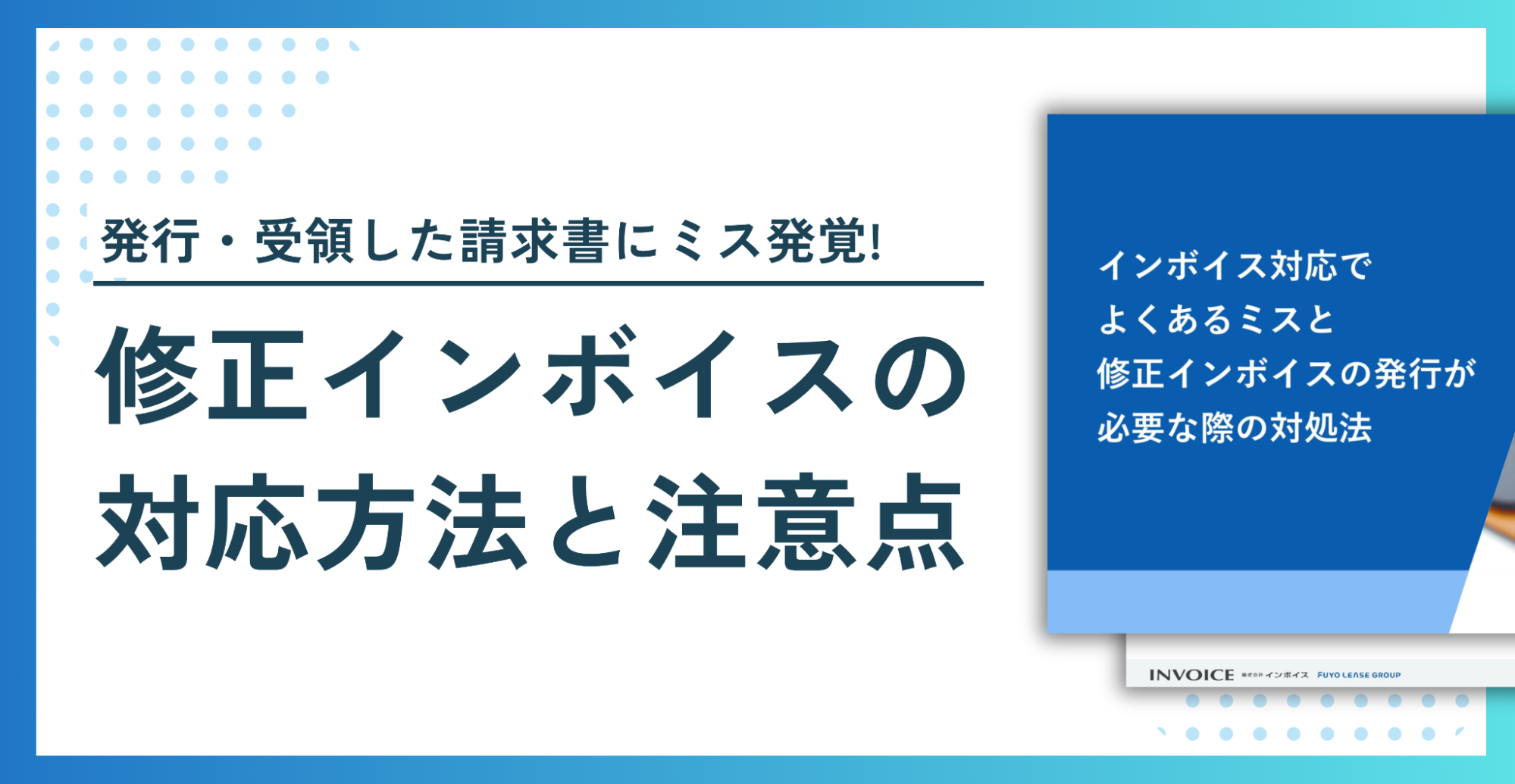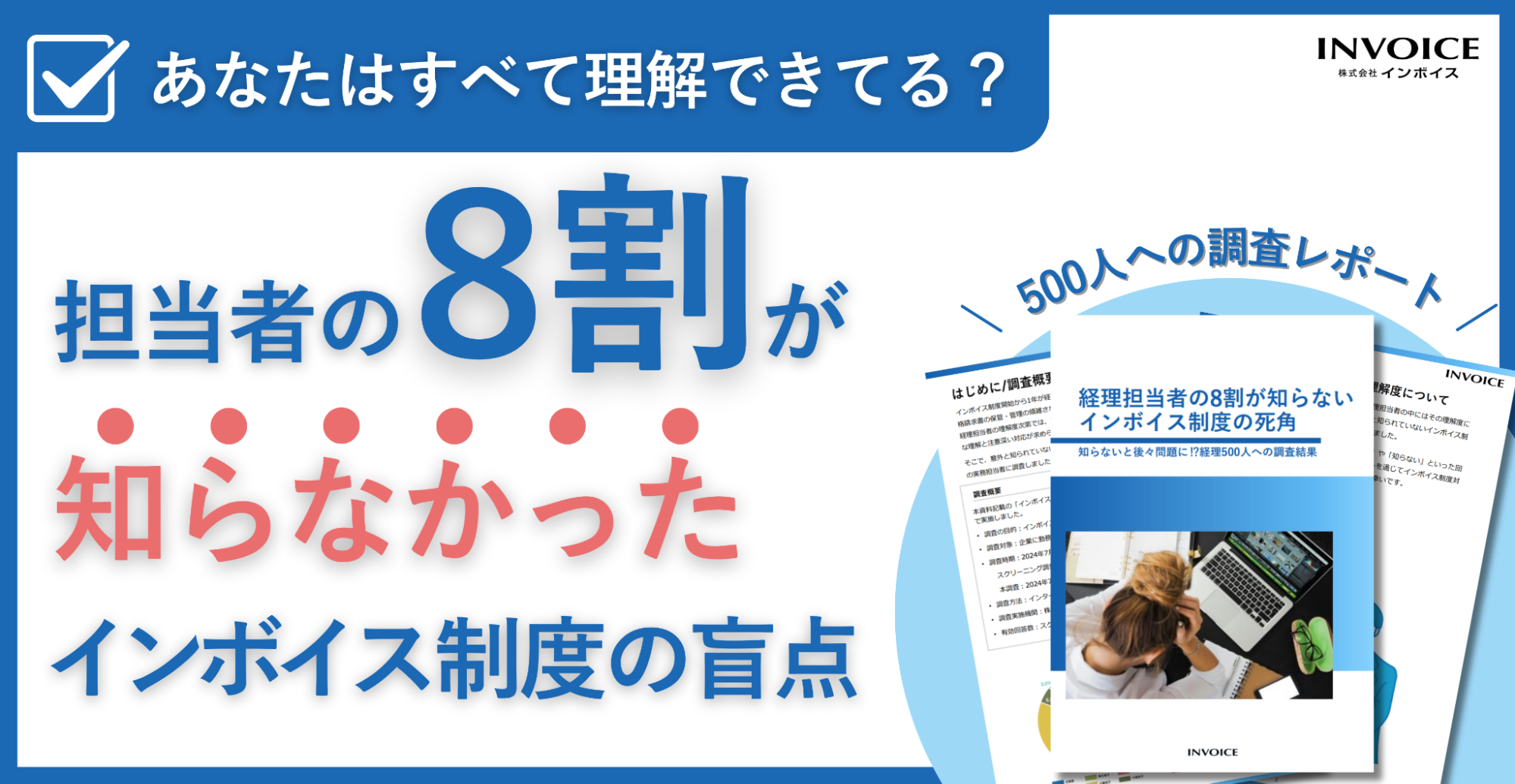キャッシュバックにインボイスは原則不要!消費税の記載方法と例外ケースも解説
更新日:2025.07.28
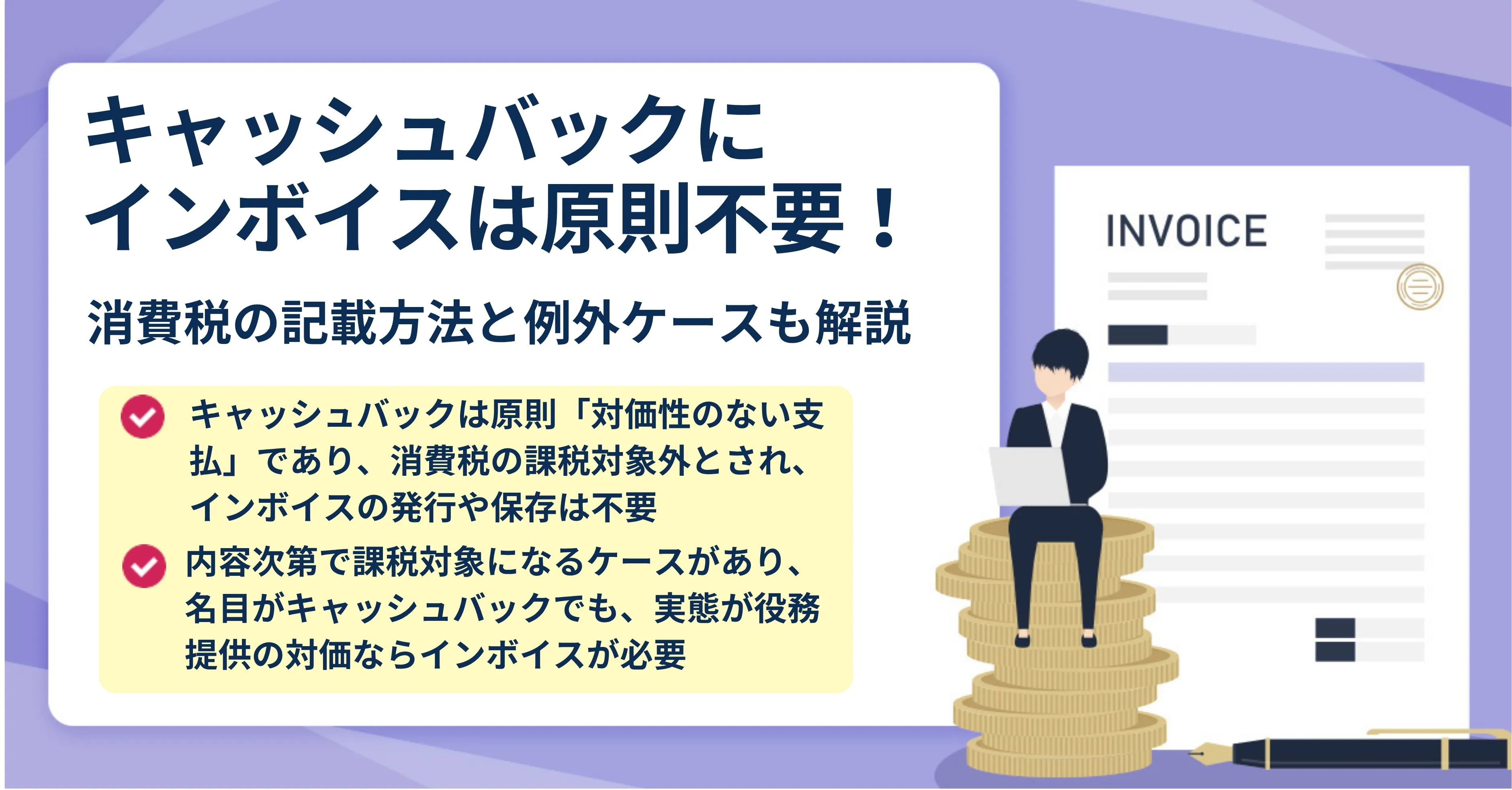
ー 目次 ー
インボイス制度により、「キャッシュバックにもインボイスが必要なのだろうか?」と疑問を感じている方も多いのではないでしょうか。本記事では、そうしたお悩みにお応えすべく、制度上の原則や例外、そして実務での具体的な対応方法を丁寧に解説いたします。
キャッシュバックとインボイス制度の基本!
2023年10月1日から開始されたインボイス制度がキャッシュバックの会計処理にも影響があるのか、気になっている方も多いのではないでしょうか。まずは、キャッシュバックとインボイス制度の基本的な仕組みから確認していきましょう。
そもそもインボイス制度とは?
インボイス制度とは、正式名称を「適格請求書等保存方式」といいます。これは、消費税の仕入税額控除を受けるための新しいルールです。制度開始後は、原則として「適格請求書(インボイス)」と呼ばれる、定められた要件を満たす請求書や領収書などを売り手から受け取り、保存しなければ仕入税額控除が適用できなくなりました。
適格請求書(インボイス)を発行できるのは、税務署に申請し、登録を受けた「適格請求書発行事業者」のみです。インボイスには、従来の請求書に加えて、以下の項目を記載する必要があります。
|
項目 |
記載内容 |
|
適格請求書発行事業者の登録番号 |
「T」+13桁の法人番号または13桁の番号 |
|
適用税率 |
取引に適用される消費税率(10%または8%) |
|
税率ごとに区分した消費税額等 |
税率ごとに合計した消費税額 |
これまでの区分記載請求書の内容に、上記3つの項目が追加されたものがインボイスであると理解しておきましょう。
消費税の仕組みと仕入税額控除の関係
インボイス制度を理解する上で欠かせないのが、「仕入税額控除」の仕組みです。消費税は、商品やサービスの提供といった取引に対して課される税金ですが、生産や流通の各段階で二重、三重に税が課されることを防ぐ仕組みがあります。それが仕入税額控除です。
事業者は、顧客から預かった消費税(売上税額)から、自社が仕入れや経費の支払いで払った消費税(仕入税額)を差し引いた金額を国に納付します。この「差し引く行為」が仕入税額控除です。
インボイス制度導入後は、この仕入税額控除を適用するために、取引相手から発行された適格請求書(インボイス)の保存が原則として必須となりました。つまり、買い手側にとってインボイスは、自社が納める消費税額を正しく計算し、節税するために不可欠な書類なのです。
【結論】キャッシュバックにインボイスは原則不要!国税庁の見解とは
インボイス制度が始まり、キャッシュバックの扱いに悩む方が増えています。結論から言うと、一般的なキャッシュバックにはインボイス(適格請求書)の発行も保存も原則として不要です。ここでは、その理由と具体的な対応について詳しく解説します。
キャッシュバックは「対価性なし」で非課税になるのが原則
消費税は、商品やサービスの提供といった「対価性のある取引」に対して課税されます。ここでいう「対価性のある取引」とは、何らかの財やサービスの提供に対して、直接的な報酬や代金が支払われる関係を指します。たとえば、商品の販売に対して代金を受け取る場合や、広告掲載の依頼に対して報酬を得る場合などが該当します。
しかし、多くのキャッシュバックは、商品購入後に事業者が買主に対して一方的に金銭を支払うものであり、買主から新たな役務の提供(例:業務やサービスの提供など)を受けるものではありません。つまり、金銭の支払いに見合う「提供された役務」が存在しないため、対価性がないとされます。
そのため、キャッシュバックは対価性がないと判断され、消費税の課税対象外(不課税取引)となり、インボイスの発行も不要です。
支払側(売手)には返還インボイスの発行義務がある
キャッシュバックを受け取る側はインボイス発行が不要ですが、支払う側(売手)には注意が必要です。売手にとってキャッシュバックは「売上に係る対価の返還等」に該当するため、原則として買手に対して「返還インボイス(適格返還請求書)」を交付する義務が生じます。
返還インボイスとは、値引きや返品、奨励金の支払いなど、売上にかかる金額を返還したことを証明する書類です。これにより、売手は自身の売上からキャッシュバック分を差し引き、納税する消費税額を正しく計算できます。
ただし、キャッシュバックの金額が税込1万円未満である場合は、返還インボイスの交付義務が免除されます。
受取側(買手)はインボイスの保存がなくても仕入税額控除が可能
キャッシュバックを受け取った側(買手)は、売手から返還インボイスを交付されたとしても、それを保存する義務はありません。帳簿に必要事項を記載しておくだけで、仕入税額控除の適用を受けることが可能です。
つまり、買手は返還インボイスがなくても、当初の仕入れにかかった消費税額から、キャッシュバックによって返還された消費税額を差し引く処理を行えます。
注意!インボイスが必要になるキャッシュバックの例外ケース
キャッシュバックは原則としてインボイスが不要ですが、すべてのケースで非課税扱いになるわけではありません。名目だけで判断せず、その内容を正しく理解することが重要です。
販売奨励金など役務提供の対価とみなされる場合
キャッシュバックという名目であっても、その支払いが「役務提供の対価」であると判断される場合は、消費税の課税対象となります。この場合、キャッシュバックを受け取る側は、提供した役務に対してインボイスを発行する義務が生じます。
例えば、メーカーが販売代理店に対し、特定の販売目標を達成した場合に支払う「販売奨励金」や、目立つ場所に商品を陳列してもらうための「協力金」などがこれに該当します。これらは、販売代理店が行った「販売促進」や「陳列」という役務に対する対価とみなされるためです。
名目は「キャッシュバック」でも内容しだいでインボイスが必要に
インボイス制度においては、取引の名称ではなく、その実態に基づいて課税関係を判断します。したがって、「キャッシュバックキャンペーン」と銘打っていても、受け取る側が何らかの義務(例:SNSでの商品紹介、アンケートへの詳細な回答、友人紹介など)を負う場合は注意が必要です。その義務の履行が支払い条件となっている場合、その支払いは役務提供の対価として課税売上げに該当し、インボイスの発行が必要になる可能性があります。
インボイスが必要か迷った際の判断ポイント
自社のキャッシュバックがインボイス不要の「売上値引き」に該当するのか、それともインボイスが必要な「役務提供の対価」に該当するのか、判断に迷うこともあるでしょう。その際は、以下のポイントを参考に取引の実態を確認してください。
|
判断基準 |
インボイス不要のケース(売上値引など) |
インボイスが必要なケース(役務提供の対価) |
|
受け取り側の義務 |
受け取り側に特別な義務や行為が課されていない。購入や契約といった事実のみに基づき支払われる。 |
受け取り側が支払いを受けるために、何らかの役務提供(販売促進、広告宣伝など)を行う義務を負っている。 |
|
具体例 |
|
|
|
消費税の扱い |
売上値引として処理され、課税対象外(不課税)。支払側は返還インボイスを発行する。 |
役務提供の対価として処理され、課税対象。受取側がインボイスを発行する。 |
このように、キャッシュバックの対価性の有無がインボイスの要否を判断する上での最大のポイントとなります。契約書や覚書の内容を確認し、支払いと役務提供の間に明確な対価関係があるかどうかを慎重に見極める必要があります。
立場別|キャッシュバックのインボイス対応と記載方法
キャッシュバックが発生した際のインボイス制度における対応は、キャッシュバックを「支払う側(売手)」と「受け取る側(買手)」で異なります。ここではそれぞれの立場で必要な対応と、具体的な帳簿への記載方法を解説します。
キャッシュバックを支払う側の対応
キャッシュバックを支払う側(売手)は、そのキャッシュバックが「売上値引」に該当する場合、原則として買手に対して「適格返還請求書(返還インボイス)」を交付する義務があります。これは、売上にかかる対価の返還等にあたるためです。
返還インボイスには、以下の項目を記載する必要があります。
|
記載項目 |
記載内容の例 |
|
発行事業者の氏名または名称および登録番号 |
株式会社〇〇 T1234567890123 |
|
対価の返還等を行う年月日 |
2023年12月1日 |
|
対価の返還等の基となった取引を行った年月日 |
2023年11月15日(※任意記載。記載がない場合は、どの取引に対するものか分かるようにしておく必要があります) |
|
対価の返還等の内容 |
キャッシュバックとして |
|
税率ごとに区分して合計した対価の返還等の金額(税抜または税込) |
10%対象 -10,000円(税抜) |
|
対価の返還等に係る消費税額等または適用税率 |
消費税額等 -1,000円 または 適用税率10% |
帳簿上は「売上値引」や「売上割戻」などの勘定科目で処理します。例えば、11,000円(うち消費税1,000円)をキャッシュバックした場合の仕訳は以下のようになります。
(借方)売上値引 11,000円 / (貸方)現金預金 11,000円
なお、前章で解説した例外ケース、つまりキャッシュバックが販売奨励金など役務提供の対価とみなされる場合は、支払う側にとっては「仕入れ」の扱いになります。この場合、返還インボイスを発行するのではなく、キャッシュバックを受け取る側(役務提供者)から交付されたインボイスを保存する必要があります。
キャッシュバックを受け取る側の対応
キャッシュバックを受け取る側(買手)は、そのキャッシュバックが「仕入値引」に該当する場合、支払側(売手)から交付される返還インボイスを保存する義務はありません。
ただし、仕入税額控除の適用を受けるためには、帳簿に一定の事項を記載して保存する必要があります。具体的には、仕入値引を受けた事実を帳簿に記録することで、仕入税額を正しく調整します。
|
項目 |
帳簿への記載内容 |
|
相手方の氏名または名称 |
株式会社〇〇 |
|
年月日 |
キャッシュバックを受け取った年月日 |
|
内容 |
商品Aのキャッシュバックとして |
|
金額 |
11,000円 |
帳簿上は「仕入値引」や「仕入割戻」などの勘定科目で処理します。例えば、11,000円のキャッシュバックを受け取った場合の仕訳は以下のようになります。
(借方)現金預金 11,000円 / (貸方)仕入値引 11,000円
一方で、キャッシュバックが役務提供の対価とみなされる場合は、受け取る側にとっては「売上」となります。そのため、自身が課税事業者であれば、キャッシュバックを支払う側に対してインボイス(適格請求書)を交付する義務が生じます。この場合、勘定科目は「雑収入」などで処理するのが一般的です。
Q&A|インボイスとキャッシュバックに関するよくある質問
ここでは、インボイス制度とキャッシュバックに関して、事業者の方から寄せられることの多い質問とその回答をまとめました。
キャッシュバックは簡易課税で何業種の区分に該当する?
簡易課税制度を適用している事業者がキャッシュバック(売上値引き等)を受け取った場合、そのキャッシュバックは、元となった課税仕入れの事業区分と同じ区分で処理します。
キャッシュバックは消費税法上「仕入れに係る対価の返還等」に該当します。そのため、どの事業のために行った仕入れに対するキャッシュバックなのかによって、適用される事業区分が変わります。
例えば、小売業(第二種事業)で販売する商品の仕入れに対してキャッシュバックを受けた場合は、第二種事業に係る仕入れのマイナスとして扱います。同様に、製造業(第三種事業)で使用する原材料の仕入れに対するキャッシュバックであれば、第三種事業として処理することになります。
インボイス制度開始前に契約したキャッシュバックは対象になる?
はい、対象になります。
インボイス制度では、取引の契約日ではなく、実際に取引が行われた日(資産の譲渡等が行われた日)が基準となります。キャッシュバックの場合、キャッシュバックの金額が確定し、通知された時点が基準になると考えられます。
したがって、契約を締結したのがインボイス制度開始前(2023年9月30日以前)であっても、キャッシュバックの事実が発生したのが制度開始後(2023年10月1日以降)であれば、インボイス制度のルールが適用されます。この場合、キャッシュバックを支払う側(売手)は、原則として返還インボイスの発行義務を負うことになります。
個人事業主が受け取ったキャッシュバックは課税対象?申告は必要?
個人事業主が受け取ったキャッシュバックは、事業に関連するかどうかで「所得税」と「消費税」の扱いが異なります。事業に関連するキャッシュバックは、確定申告が必要です。
具体的な税金の扱いを以下の表にまとめました。
|
税金の種類 |
事業に関連するキャッシュバックの扱い |
|
所得税 |
事業所得の計算上、経費や仕入高から差し引きます。例えば、仕入れた商品代金の一部がキャッシュバックされた場合、その金額を「仕入割引」として仕入高から控除します。これにより課税所得が減るため、確定申告に正しく反映させる必要があります。 |
|
消費税 |
課税事業者の場合、「仕入れに係る対価の返還等」として扱います。帳簿に記載し、仕入税額控除額からそのキャッシュバックに係る消費税額を差し引いて申告します。 一方、免税事業者の場合は消費税の申告義務がないため、特に対応は不要です。 |
なお、事業とは無関係な個人としてのキャッシュバック(例:個人のクレジットカード利用によるポイント還元など)は、多くの場合、一時所得に該当しますが、年間50万円の特別控除額の範囲内であれば基本的に課税されません。
まとめ
インボイス制度において、キャッシュバックは原則インボイス不要です。これは、国税庁により対価性のない不課税取引とされているためです。ただし、キャッシュバックを支払う売手側には、売上値引きとして返還インボイスの発行義務が生じます。一方で、販売奨励金など実質的に役務提供の対価とみなされる場合は課税対象となり、インボイスが必要になるため注意が必要です。名目だけでなく取引の実態で判断し、適切なインボイス対応を行っていただければと思います。