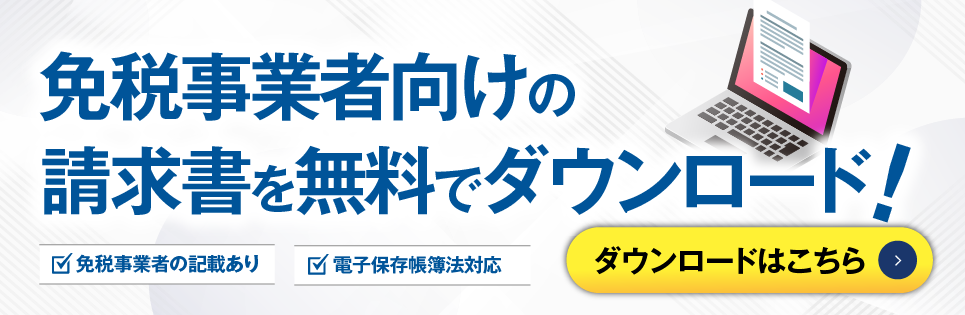インボイス制度に未登録の業者との取引はどうなる?注意点や登録番号の確認方法を解説
更新日:2025.12.06
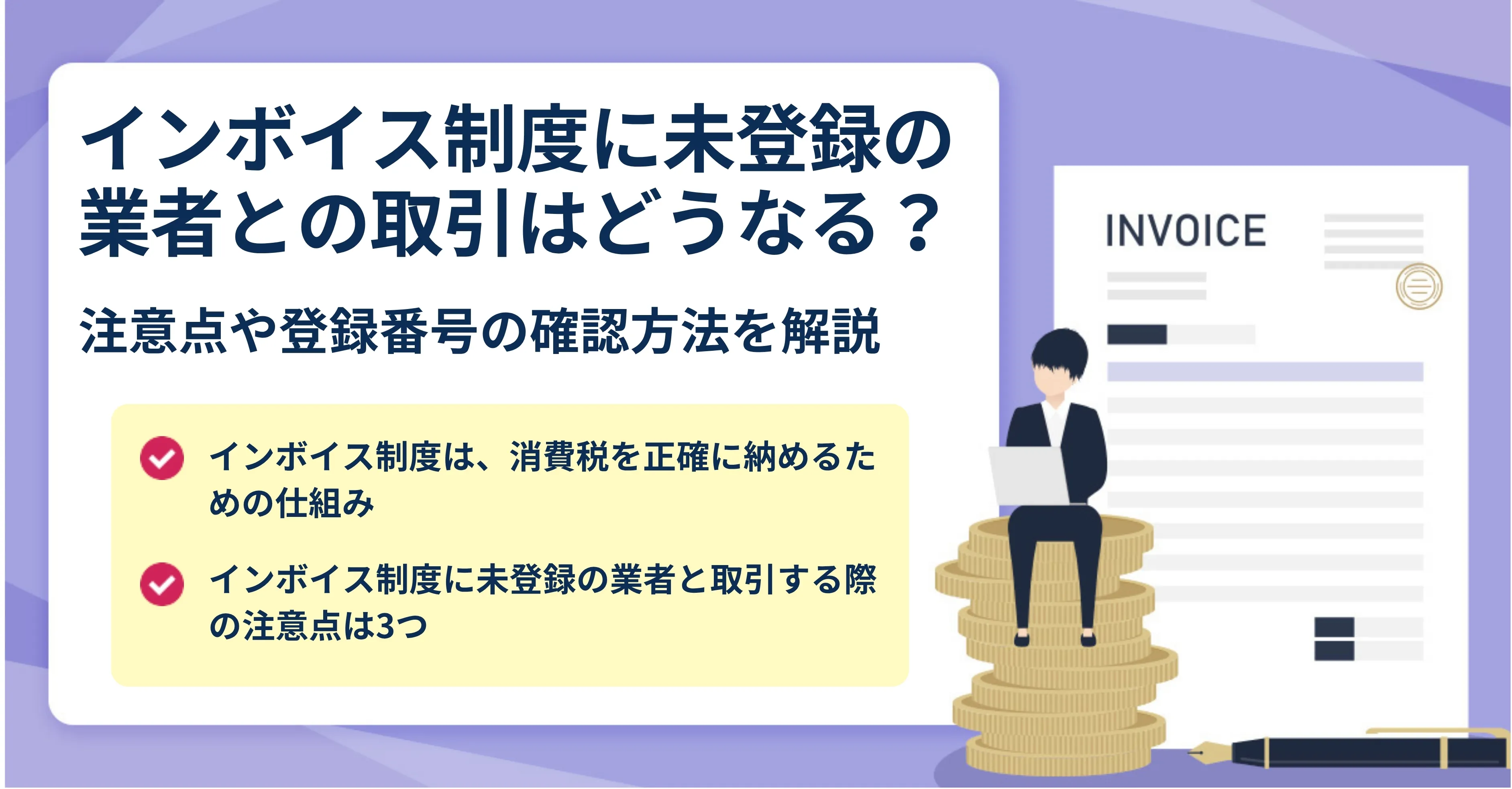
ー 目次 ー
2023年10月1日にインボイス制度が開始され、事業者を取り巻く環境が大きく変化しました。個人事業主であるか法人であるかを問わず、多くの事業者がインボイス制度の影響を受けています。
たとえば、免税事業者との取引をおこなう課税事業者は、仕入税額控除を適用できなくなる可能性があります。取引における消費税の負担が増加する場合があるため、今後の取引にどのような影響があるのかを理解することが重要です。
本記事では、インボイス制度に未登録の業者との取引について、注意点やインボイス登録番号の確認方法を解説します。
【おさらい】インボイス制度とは?取引に影響する2つのポイント
インボイス制度は、複数税率に対応して消費税の仕入税額控除の金額を正しく計算するための制度です。この制度では課税事業者が仕入税額控除を適用する要件として、適格請求書発行事業者から受領したインボイス(適格請求書)の保存が求められます。
インボイス制度は課税事業者・免税事業者ともに影響を与えるため、取引に関係するポイントをおさえておきましょう。
ここでは、インボイス制度における取引に影響する2つのポイントを解説します。
- 登録しないと、インボイスが発行できない
- 課税取引をしているすべての事業者が対象
①登録しないと、インボイスが発行できない
インボイス(適格請求書)とは、買手に対して正しい適用税率や消費税額などを伝えるためのものです。たとえば、請求書や納品書、領収書、レシートなどがインボイスに該当します。
インボイスを発行する際は、以下の項目を記載しなければなりません。
- 適格請求書発行事業者の氏名または名称
- 登録番号
- 取引年月日
- 取引内容
- 適用税率
- 消費税額
- 交付を受ける事業者の氏名または名称
また、インボイスを発行できる対象者は、適格請求書発行事業者として登録を受けた事業者のみです。そのため、未登録の事業者はインボイスの発行・交付がおこなえません。
②課税取引をしているすべての事業者が対象
インボイス制度は複数税率に対応し、消費税を正確に納めるための仕組みです。
課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円を超える課税事業者は、インボイス制度への登録対象となります。一方、基準期間の課税売上高が1,000万円以下の事業者は免税事業者であり、消費税を納める義務がありません。
ただし、免税事業者であっても、取引の状況によってはインボイス制度の登録を受けて課税事業者となるケースもあります。
インボイス制度に未登録の業者と取引する際の3つの注意点
インボイス制度に未登録の業者と取引する場合、消費税の負担が増加する可能性があります。また、取引条件の見直しを強要すると、法律違反に該当するケースがあるため注意が必要です。
インボイス制度に未登録の業者との取引で誤った対応をしないために、注意点を理解しておきましょう。
ここでは、インボイス制度に未登録の業者と取引する際の3つの注意点を解説します。
- 仕入税額控除を適用できない
- 経過措置の適用が限られている
- 取引条件の見直しで法律違反となる可能性がある
①仕入税額控除を適用できない
インボイス制度が開始される前は、免税事業者との取引でも仕入税額控除を適用できていました。
しかし、制度の開始以降は仕入税額控除を適用するために、インボイス(適格請求書)の交付を受けなければなりません。そのため、インボイス制度に未登録の業者との取引では仕入税額控除を適用できず、消費税の負担が増加する可能性があります。
取引内容によっては大きな負担となるため、未登録の業者との取引には慎重な検討が必要です。
②経過措置の適用が限られている
インボイス制度では、免税事業者からの仕入に対して経過措置が設けられています。経過措置を適用できる期間は以下のとおりです。
- 2023年10月1日~2026年9月30日:仕入税額相当額の80%
- 2026年10月1日~2029年9月30日:仕入税額相当額の50%
免税事業者からの課税仕入において、仕入税額とみなして控除できる額の割合は期間の経過とともに減少します。そして、2029年10月1日以降は経過措置が廃止されるため、免税事業者からの仕入れに対して控除を適用できません。
参考:国税庁「5 経過措置」
③取引条件の見直しで法律違反となる可能性がある
課税事業者が免税事業者と取引をおこなう際、消費税の負担を低減するために取引条件を見直すケースがあります。
しかし、交渉の方法や提示する条件を誤ると、独占禁止法や下請法に違反する可能性があるため注意しなければなりません。
たとえば、免税事業者であることを理由に消費税相当額の一部または全部を支払わない行為は下請法違反です。また、取引価格の引き下げや取引の打ち切りを一方的に通告すると、独占禁止法で罰せられる可能性があります。
取引条件を見直す際はしっかりと話し合い、双方の合意のもとでおこなうことが重要です。
参考:中小企業庁「インボイス制度後の免税事業者との取引に係る下請法等の考え方」
取引先がインボイス制度に登録しているか確認する方法とは?
取引先との今後を検討するにあたって、まずは取引先がインボイス制度に登録しているかを確認することが必要です。
取引先が法人の場合は、適格請求書発行事業者公表サイトで登録の有無を簡単に確認できます。ただし、取引先が個人事業主の場合は登録番号がわからないと検索できないため、ほかの方法で確認しなければなりません。
ここでは、取引先がインボイス制度に登録しているかを確認する方法を解説します。
- 個人事業主の場合は取引先に直接問い合わせて確認する
- 法人の場合は適格請求書発行事業者公表サイトで確認する
- インボイス制度の登録業者一覧から探す
①個人事業主の場合は取引先に直接問い合わせて確認する
適格請求書発行事業者に登録すると、事業者には所轄税務署から登録番号が通知されます。そのため、取引先に直接問い合わせることで、登録の有無や登録番号の確認が可能です。
この方法であれば、登録番号である13桁の数字が公表されていない個人事業主であってもインボイス制度への登録の有無を確認できます。
また、登録番号を問い合わせる際は、内容を書面に残すと間違いがなく安心です。eメールや郵便、Googleフォームを使ったアンケートを利用しましょう。
②法人の場合は適格請求書発行事業者公表サイトで確認する
国税庁では「適格請求書発行事業者公表サイト」にて、適格請求書発行事業者の情報を公開しています。
法人の場合は法人番号である13桁の数字を入力して検索することで、インボイス制度への登録の有無を確認可能です。
取引先の法人番号がわからない場合は、国税庁の法人番号公表サイトで調べておきましょう。
③インボイス制度の登録業者一覧から探す
国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトでは、登録業者一覧をダウンロードできます。ファイル上で事業者名を検索することで、インボイス制度への登録を確認可能です。
業者一覧のファイルは、CSV・XML・JSONの3形式に対応しています。また、全件データダウンロード以外には、日次の更新情報を日別にダウンロードすることも可能です。
この方法であれば、法人・個人事業主ともにインボイス制度への登録を確認できます。
インボイス制度に未登録の業者との取引における2つの対応策
課税事業者がインボイス制度に未登録の業者と取引を継続する場合、仕入税額控除を適用できず、消費税の負担が増加します。取引で損をしないためには、今後の対応を考えなければなりません。
どのような対応策があるのかを把握したうえで、取引先と話し合うことが重要です。
ここでは、インボイス制度に未登録の業者との取引における2つの対応策を解説します。
- 登録してもらうよう取引先と交渉する
- 取引先の合意を得たうえで取引価格を値下げする
①登録してもらうよう取引先と交渉する
インボイス制度には、課税売上高が1,000万円以下の免税事業者であっても、課税転換することで登録できます。取引先に対するインボイス制度への登録要請は法的に問題がないため、今後の取引を踏まえて交渉することも1つの方法です。
ただし、「インボイス制度に登録しなければ、取引を打ち切る」というように課税事業者への転換を強要する行為は、独占禁止法違反に該当します。
インボイス制度への登録要請をおこなう際は、取引先が納得できる条件を提示して交渉しましょう。
②取引先の合意を得たうえで取引価格を値下げする
仕入税額控除を適用できないことを踏まえて、取引先に値引き交渉をおこなう場合は、双方が納得したうえで取引価格を設定することが重要です。
公正取引委員会のインボイス制度に対する見解では、「双方が納得した状態での値下げは問題がない」としています。
インボイス制度では経過措置として、2029年9月30日までは免税事業者からの仕入に対して一定割合の仕入税額控除を適用できます。この点も考慮して、取引先が納得できる取引価格を提示しましょう。
まとめ|インボイス制度の登録状況を確認して、免税事業者との取引を慎重に進めよう
本記事では、インボイス制度に未登録の業者との取引について、注意点やインボイス登録番号の確認方法を解説しました。
2023年10月1日にインボイス制度が開始されたことで、課税事業者が仕入税額控除を適用するためには、インボイスの交付が必要です。そのため、インボイス制度に未登録の業者と取引をおこなう場合、課税事業者は消費税の負担が増加する可能性があります。
インボイス制度における消費税の負担を低減するためには、取引先が適格請求書発行事業者として登録しているかを確認することが重要です。
登録の有無は適格請求書発行事業者公表サイトで確認できるため、取引先の登録状況を把握して慎重に今後の対応を検討しましょう。