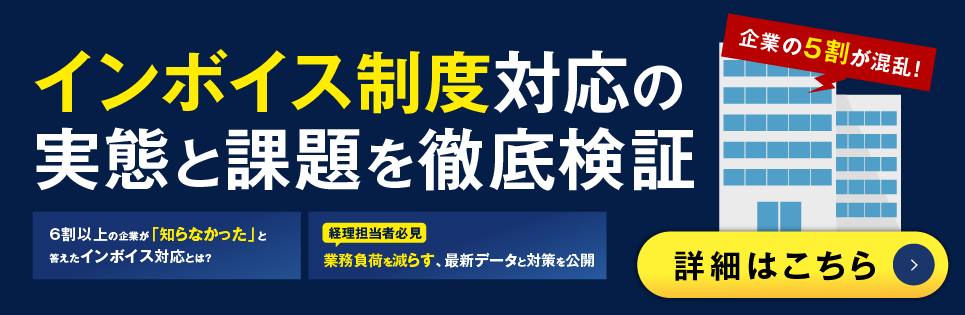なぜインボイス制度で廃業が相次ぐのか?原因や事業継続のための対策とは
更新日:2026.01.29
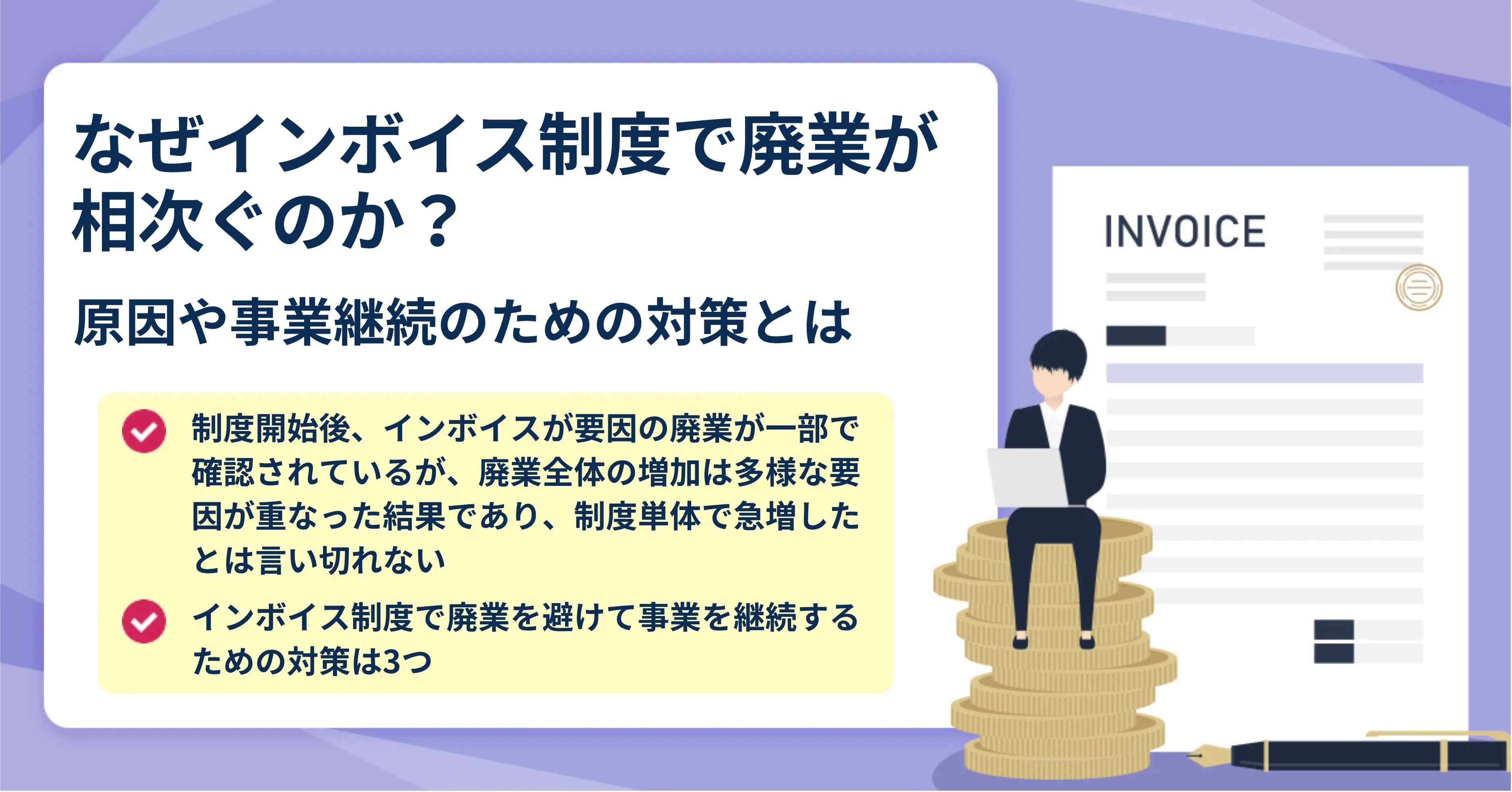
ー 目次 ー
インボイス制度の開始で廃業を検討する事業者が増えています。その主な理由は、免税事業者のままだと取引を打ち切られるリスク、課税事業者になると手取り減や事務負担増に直面するためです。本記事では、データで廃業の現状を明らかにすると共に、事業を続けるための具体的な対策を解説。課税事業者になるべきかの判断基準や、負担を減らす特例・補助金まで解説し、あなたの不安を解消します。
インボイス制度で廃業は実際に増えてる?データで見る現状と廃業率
2023年10月1日にインボイス制度(適格請求書等保存方式)が開始されて以降、「インボイスが原因で廃業する事業者が増えるのではないか」という懸念の声が多く聞かれました。では、実際に廃業は増加しているのでしょうか。ここでは、公表されているデータを基に、インボイス制度と廃業の関連性について客観的に見ていきます。
個人事業主やフリーランスの廃業動向
東京商工リサーチの調査によると、2023年1月から11月の間に「インボイス制度」を要因として休廃業・解散に至った企業は73件あり、その多くが個人事業主を含む「サービス業他」に集中していました。制度への対応が難しい、あるいは対応するメリットが薄いと判断し、廃業を選んだ事業者が一定数存在することがデータから読み取れます。
ただし、廃業率の上昇をインボイス制度のみに帰するのは適切ではありません。近年の廃業は、物価高、人手不足、後継者不在など、複数の要因が複雑に絡み合った結果といえます。インボイス制度は、こうした既存の課題に加わり、廃業を決断する後押しになったケースがあると考えるのが現実に近いでしょう。
特に影響が大きいのは、これまで消費税の納税義務がなかった免税事業者が多い個人事業主やフリーランスです。国税庁によると、2024年4月末時点での適格請求書発行事業者の登録件数は約486万件に達しており、法人よりも個人事業主の登録が多いことから、多くの免税事業者が課税事業者への転換を選んだことがうかがえます。
一方で、登録を見送ったり、事業の見直しを図ったりする動きも見られます。前出の調査でも、休廃業・解散した企業の約7割が資本金1,000万円未満の小規模事業者であり、制度変更の影響が個人事業主やフリーランスに色濃く及んでいることが推測されます。
特に廃業の影響が大きい業種とは
インボイス制度の影響は、すべての業種に等しく及ぶわけではありません。特に、事業者間の取引(BtoB)が中心で、かつ個人事業主や小規模な事業者が多く存在する業種で、廃業への影響が顕著になる傾向があります。
具体的にどのような業種で影響が大きいのか、その理由とともに以下の表にまとめました。
|
特に影響が大きいとされる業種 |
影響を受けやすい理由の例 |
|
建設業 |
元請け企業から仕事を受ける一人親方など、免税事業者の個人事業主が多く、取引継続のためにインボイス発行を求められるケースが多いため。 |
|
情報通信業 |
企業と取引するフリーランスのエンジニア、Webデザイナー、ライターなどが多く、発注元からインボイス対応を求められ、価格交渉で不利になる可能性があるため。 |
|
運輸業 |
個人事業主として活動する軽貨物ドライバーなどが多く、荷主である企業からインボイスの発行を要求されることが一般的であるため。 |
|
飲食料品小売業 |
軽減税率(8%)と標準税率(10%)の商品が混在し、インボイス制度に対応するための経理処理やレジシステムの変更が大きな負担となるため。 |
これらの業種に共通するのは、取引先(買い手)が課税事業者であり、仕入税額控除のためにインボイスを必要とする点です。そのため、売り手である免税事業者は「課税事業者になってインボイスを発行する」か、「取引の打ち切りや値下げ交渉に応じる」かという厳しい選択を迫られやすい構造になっています。
インボイス制度はやばい?廃業の引き金になる理由を解説
インボイス制度は、多くの個人事業主やフリーランスにとって事業の継続を左右する大きな変化です。なぜこの制度が「やばい」と言われ、廃業を考える事業者が現れているのでしょうか。ここでは、インボイス制度が廃業の引き金となりうる3つの主な理由を詳しく解説します。
免税事業者のままだと取引を打ち切られるリスク
インボイス制度で廃業が懸念される最大の理由は、免税事業者のままでいると、取引先から契約を打ち切られたり、新規の取引を敬遠されたりするリスクがあることです。
その背景には「仕入税額控除」という仕組みがあります。買い手側(発注者)の課税事業者は、商品やサービスの仕入れ時に支払った消費税を、自社が納める消費税額から差し引くことができます。これを仕入税額控除と呼びます。
しかし、インボイス制度開始後は、原則として「適格請求書(インボイス)」がなければ、この仕入税額控除が適用できなくなりました。インボイスを発行できるのは、税務署に申請して登録を受けた「適格請求書発行事業者」のみです。そして、この登録ができるのは課税事業者に限られます。
つまり、あなたが免税事業者のままでいるとインボイスを発行できないため、あなたの取引先は消費税分の仕入税額控除ができず、その分多くの税金を納めることになります。取引先にとっては実質的なコスト増となるため、同じ価格であればインボイスを発行できる課税事業者との取引を優先するのは、経営判断として自然な流れです。これが、取引の打ち切りや値下げ交渉につながる大きな要因となっています。
課税事業者になると手取り収入が減る
取引を維持するために免税事業者から課税事業者になる選択をした場合、今度は収入面での問題に直面します。これまで納税が免除されていた消費税を、国に納める義務が生じるためです。
例えば、年間売上高が550万円(税抜500万円、消費税50万円)の個人事業主の場合を考えてみましょう。
- 免税事業者の場合:受け取った消費税50万円は「益税」として、そのまま自身の収入となっていました。年収は550万円です。
- 課税事業者になった場合:受け取った消費税50万円(または経費などを考慮して計算した額)を納税する必要があります。仮に50万円を全額納税すると、手元に残る収入は500万円となり、年収が大幅に減少してしまいます。
このように、売上金額が変わらなくても、納税義務が生じることで手取りが減り、事業の継続が難しくなるケースもあります。特に、利益率が低い業種や、価格転嫁が難しい立場の事業者にとっては深刻な問題です。
経理の事務負担が大幅に増加する
インボイス制度への対応は、金銭的な負担だけでなく、経理を中心とした事務作業の負担を大幅に増加させます。特に、これまで確定申告を自分で行ってきた個人事業主にとっては、大きな壁となり得ます。
課税事業者になると、主に以下のような新たな事務作業が発生します。
|
項目 |
免税事業者の場合 |
課税事業者(インボイス発行事業者)の場合 |
|
請求書の発行 |
自由な形式で発行可能 |
登録番号や税率ごとの消費税額などを記載した「適格請求書」の形式で発行する義務がある |
|
帳簿の記帳 |
売上や経費を記録 |
売上や経費を税率(10%、8%)ごとに区分して記帳する必要がある |
|
消費税の申告 |
不要 |
年に一度、消費税の確定申告と納税を行う義務が発生する |
|
請求書の保存 |
受け取った請求書を保存 |
発行したインボイスの写しを保存する義務がある |
これらの複雑な作業に対応するためには、会計ソフトの導入や税理士への依頼が必要になるケースも少なくありません。その結果、新たなコストが発生するだけでなく、本業に充てるべき貴重な時間が奪われてしまいます。こうした事務負担の増大とそれに伴うコスト増が、事業継続への意欲を削ぎ、廃業という選択肢を現実的なものにしてしまうのです。
まだ間に合う!インボイス制度で廃業を避けて事業を継続するための対策
インボイス制度の開始により、廃業を検討する事業者がいるのは事実です。しかし、適切な対策を講じることで、事業を継続することは十分に可能です。ここでは、廃業を回避し、事業を続けるための具体的な方法を3つのステップで解説します。
自身の状況に合わせて最適な選択をする
インボイス制度への対応は、全事業者が一律に「課税事業者になる」という選択をすべきものではありません。ご自身の事業内容や取引先の状況を客観的に分析し、最適な道筋を見つけることが重要です。まずは以下のチェックリストで、ご自身の状況を整理してみましょう。
課税事業者になるべきか判断するチェックリスト
以下の項目に「はい」が多いほど、課税事業者になるメリットが大きいと考えられます。ご自身の状況と照らし合わせて、慎重に判断しましょう。
|
チェック項目 |
判断のポイント |
|
主要な取引先が課税事業者ですか? |
取引先が仕入税額控除を行うために、あなたからのインボイスを必要としている可能性が高いです。 |
|
取引先からインボイス発行を求められていますか? |
すでに発行を求められている場合、免税事業者のままだと取引縮小や停止のリスクがあります。 |
|
売上の大半が企業向け(BtoB)取引ですか? |
BtoB取引が中心の場合、多くの取引先がインボイスを必要とします。一般消費者向け(BtoC)が中心なら影響は限定的です。 |
|
価格交渉に応じてもらえる関係性ですか? |
課税事業者になる際の消費税負担分を、価格に転嫁できる可能性があります。 |
|
今後、課税事業者との新規取引を拡大したいですか? |
インボイスを発行できることは、新規のBtoB取引において有利に働くことがあります。 |
|
経理の事務負担増に対応できますか? |
会計ソフトの導入や税理士への依頼など、事務負担をカバーできる体制を整えられるか検討しましょう。 |
取引先への意向確認と価格交渉の進め方
チェックリストで状況を整理したら、次に行うべきは取引先とのコミュニケーションです。一方的に判断するのではなく、まずは取引先の意向を確認しましょう。
- 意向の確認
まずは、インボイス登録が必要かどうかを丁寧に確認します。「インボイス制度への対応についてご相談なのですが、弊社からの請求書に関して、貴社ではインボイス(適格請求書)の発行は必要でしょうか」といった形で、メールや書面で問い合わせるのが丁寧です。 - 価格交渉
意向が確認できたら、状況に応じて価格交渉を行います。
- 課税事業者になる場合:「インボイス発行事業者として登録するにあたり、消費税分を価格に反映させていただきたく、ご相談させていただけますでしょうか」など、負担増について相談します。
- 免税事業者を続ける場合:取引先から消費税相当額の値引きを求められる可能性があります。その場合は、どこまで応じられるか、あるいは他の付加価値で補えないかを検討します。
交渉は、制度開始後の混乱を避けるためにも、できるだけ早めに行うことが成功の鍵です。
負担を軽減できる特例や制度を活用する
インボイス制度への移行に伴う急激な負担を和らげるため、いくつかの特例(経過措置)が設けられています。これらを活用することで、納税額や事務作業の負担を大幅に軽減できます。
|
制度名 |
対象者 |
内容 |
適用期間 |
|
2割特例 |
免税事業者からインボイス発行事業者になった事業者 |
売上にかかる消費税額の2割を納税額とすることができる。事前の届出は不要で、申告書に付記するだけで適用可能。 |
2023年10月1日~2026年9月30日を含む課税期間 |
|
少額特例 |
基準期間の課税売上高が1億円以下の事業者など |
税込1万円未満の課税仕入れについて、インボイスの保存がなくても帳簿への記載のみで仕入税額控除が可能。 |
2023年10月1日~2029年9月30日 |
|
仕入税額控除の経過措置 |
免税事業者などから仕入れを行う課税事業者(買い手側) |
免税事業者からの仕入れでも、一定割合の仕入税額控除が可能。 ・~2026年9月30日:80%控除可能 ・2026年10月1日~2029年9月30日:50%控除可能 |
2023年10月1日~2029年9月30日 |
特に「2割特例」は、多くの小規模事業者にとってメリットの大きい制度です。納税額を簡易的に計算でき、事務負担も大きく減らせるため、課税事業者になるハードルを下げてくれます。
使える補助金や支援策をフル活用する
インボイス対応のために会計ソフトを導入したり、税理士に相談したりする費用は、補助金を活用して負担を軽減できる場合があります。積極的に活用を検討しましょう。
IT導入補助金
インボイス対応の会計ソフトや受発注システム、PC、タブレットなどの導入費用の一部を補助してくれる制度です。特に「デジタル化基盤導入枠」では、補助率が最大4分の3と比較的手厚い支援が受けられます。クラウド利用料も最大2年分が対象になるなど、継続的なコストもサポートしてくれます。
小規模事業者持続化補助金
販路開拓や業務効率化の取り組みを支援する補助金です。この補助金には「インボイス特例」が設けられており、免税事業者からインボイス発行事業者に転換する事業者は、補助上限額が50万円上乗せされます。税理士への相談費用も補助対象経費に含まれるため、制度対応に関する専門家への相談にも活用できます。
これらの補助金の申請には商工会議所や商工会のサポートが必要な場合もあります。まずは最寄りの相談窓口に問い合わせてみることをおすすめします。
Q&A|インボイス制度と廃業に関するよくある質問
インボイス制度に関して、特に廃業を検討するほど悩んでいる事業者の方から寄せられる質問にお答えします。
赤字でもインボイス登録していれば、消費税は還付されるんですか?
事業全体の所得が赤字であることと、消費税が還付されることは直接的には関係ありません。消費税の還付は、支払った消費税額(仕入税額)が、受け取った消費税額(売上税額)を上回った場合に受けられます。
例えば、輸出業者のように売上が免税となる事業や、多額の設備投資を行って仕入れに伴う消費税支払いが大きくなった年度などは、消費税の還付を受けられる可能性があります。インボイス登録(課税事業者になること)が還付を受けるための前提条件となりますが、「赤字だから還付される」わけではない点に注意が必要です。
ご自身の事業で還付が見込めるか不明な場合は、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
インボイスは一度登録したら取り消せない?
いいえ、インボイス登録(適格請求書発行事業者の登録)は取り消すことが可能です。
登録を取り消したい場合は、「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を所轄の税務署に提出します。この届出書を提出すると、原則として提出した日の属する課税期間の翌課税期間の初日から登録の効力が失われ、免税事業者に戻ることができます。
なお、制度開始当初に懸念されていた「2年縛り(登録後2年間は免税事業者に戻れないというルール)」は、令和5年度税制改正によって撤廃されました。これにより、事業者の判断でより柔軟に課税事業者と免税事業者を選択できるようになっています。ただし、登録を取り消すと取引先が仕入税額控除を受けられなくなるため、事前に取引先へ相談することが不可欠です。
廃業届を出す前に検討すべきことはある?
インボイス制度を理由に廃業を考える場合でも、最終決断を下す前に検討すべきことがいくつかあります。後悔しないためにも、以下の点を確認してみましょう。
|
検討項目 |
具体的な内容 |
|
取引先との交渉 |
消費税分の価格転嫁や、取引条件の見直しについて交渉したか。取引先も状況を理解し、交渉に応じてくれる可能性があります。 |
|
負担軽減措置の活用 |
課税事業者になった場合の負担を大幅に軽減できる「2割特例」や「少額特例」などの経過措置の対象ではないか。これらの特例を使えば、数年間は事務負担や納税負担を抑えられます。 |
|
補助金・支援策の確認 |
会計ソフト導入に使える「IT導入補助金」や、販路開拓に活用できる「小規模事業者持続化補助金」など、国や自治体の支援策を確認したか。 |
|
専門家への相談 |
税理士や商工会議所、よろず支援拠点など、無料で相談できる公的機関に相談したか。客観的なアドバイスが状況を打開するきっかけになることがあります。 |
これらの選択肢をすべて検討してもなお事業継続が困難な場合に、廃業という決断をすることになります。まずは利用できる制度や支援を最大限に活用する道を模索しましょう。
まとめ
インボイス制度で廃業が懸念される主な理由は、免税事業者が「取引打ち切りのリスク」「消費税納税による収入減」「経理負担の増加」という三重の課題に直面するためです。しかし、すぐに廃業を決断する必要はありません。2割特例などの負担軽減措置やIT導入補助金といった支援策も用意されています。自身の状況を見極め、利用できる制度を最大限活用し、取引先と交渉することで事業継続の道は開けます。本記事が、皆様の前向きな一歩につながれば幸いです。