請求書に消費税はどう書く?インボイス制度の記載ルールや計算方法!
更新日:2026.01.13
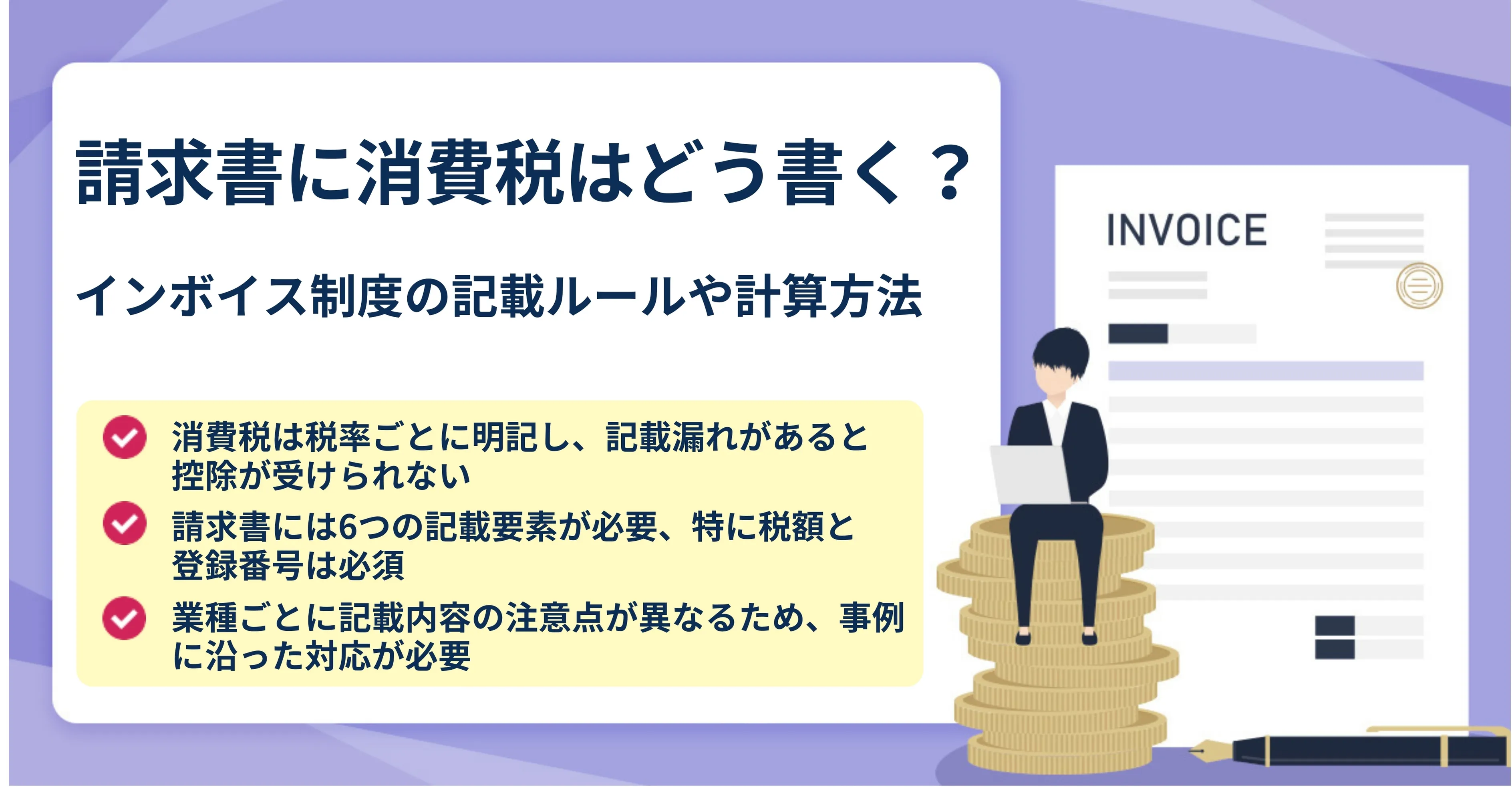
ー 目次 ー
インボイス制度に対応した請求書のルールや消費税の正しい書き方が分からず不安な方へ。本記事では、適格請求書の記載要件や消費税計算のポイント、業種別の記載例までを徹底解説。消費税の明記が適切でないと仕入税額控除が認められない可能性もあるため、正確な記載が必須です。この記事を読むことで、インボイス請求書における消費税の扱い方と記載ルールを確実に理解することができます。
インボイス制度とは?
インボイス制度の概要と導入の目的
インボイス制度とは、正式には「適格請求書等保存方式」といい、2023年10月1日から日本で導入された新しい消費税の仕入税額控除の方式です。これまでの帳簿・請求書保存方式に代わり、一定の要件を満たした「適格請求書(インボイス)」を保存しなければ、事業者が仕入税額控除を受けることができなくなります。
インボイス制度導入の目的は、消費税の適正な課税・徴収を実現することにあります。特に、軽減税率の導入によって取引価格に異なる税率(10%と8%)が混在し、税額控除の透明性が低下していたため、これを明確化・可視化するために導入されました。
これにより、課税事業者同士での取引において、請求書に記載された消費税額の正確性が厳格に求められるようになり、帳簿や請求書の形式にも大きな変更が加わりました。
インボイス請求書に消費税は記載する?
インボイス制度に基づく適格請求書には、消費税に関する明確な記載が義務付けられています。具体的には、取引ごとに適用税率を示したうえで、「税率ごとに区分した消費税額」の記載が必要です。これにより仕入税額控除の計算根拠が明確となります。
例えば、軽減税率の対象商品が含まれている場合には、その旨を示した上で、8%と10%の税率ごとの区分が記載されていなければなりません。また、消費税の金額は税抜価格ごとに計算するため、請求書の明細欄には各取引ごとに税込あるいは税抜の金額を記載し、それに対する消費税を算出・記載します。
以下の表は、請求書に記載が必要な税率区分別の記載例を示したものです。
|
取引内容 |
税抜金額 |
適用税率 |
消費税額 |
|
文房具(標準税率) |
¥10,000 |
10% |
¥1,000 |
|
食品(軽減税率) |
¥5,000 |
8% |
¥400 |
このように、インボイス請求書には消費税額を単に合算するのではなく、税率ごとに分けて記載することが強く求められるため、従来の請求書の形式から変更が必要になるケースも多くあります。
なお、免税事業者はインボイスを発行することができず、必要な要件を満たした「適格請求書発行事業者」に登録されている事業者のみが発行可能です。そのため、仕入先がインボイス発行事業者であるかどうかを確認することも、経理担当者にとっては重要な業務のひとつとなります。
インボイス制度に対応した請求書の要件!
適格請求書とは何か
インボイス制度において、仕入税額控除を適用するためには、「適格請求書(いわゆるインボイス)」の保存が必要です。これは、一定の記載事項が揃った請求書や納品書、領収書などを指します。2023年10月1日から導入されたこの制度では、適格請求書発行事業者のみがインボイスを交付できるため、請求書の記載内容の正確性と網羅性が非常に重要となります。
適格請求書とは、消費税法に基づき、事業者間取引における税額控除の根拠となる「必要事項を記載した請求書」のことです。登録された発行者のみが発行できる制度であり、「登録番号」や「消費税率ごとの合計額」などが明記されていることが求められます。
請求書に記載すべき6つの要素
インボイス(適格請求書)には、次に挙げる6つの項目を必ず記載する必要があります。これらはすべて揃っていることで初めて、仕入税額控除の対象となる請求書として扱われます。
|
項目 |
内容 |
|
1. 登録番号 |
適格請求書発行事業者として登録された事業者は、国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトで交付された「T」から始まる13桁の登録番号を請求書に記載する必要があります。例:T1234567890123 |
|
2. 取引年月日 |
商品やサービスの受け渡しが行われた日付を記載します。請求書の発行日ではなく、取引が実施された実施日を記載することが求められます。 |
|
3. 取引内容(軽減税率対象である旨の記載を含む) |
提供した商品・サービスの名称や数量、内容を具体的に記載し、軽減税率8%が適用される品目の場合は「※軽減税率対象」と明記する必要があります。 |
|
4. 税率ごとに区分した消費税額等 |
商品ごとに適用される税率ごと(10%・8%)の「税抜金額」と「消費税額」を明示し、それぞれを合計して記載します。税込合計金額だけではインボイスの要件を満たしません。 |
|
5. 書類の交付者の氏名または名称 |
請求書を発行する事業者の正式名称または代表者名を記載します。屋号を使用している場合でも、登録された名称を記載する必要があります。 |
|
6. 書類の受領者への記載事項(必要な場合) |
取引相手が法人や事業者である場合には、相手の名称を記載することが求められます。個人顧客に対して軽減税率対象商品のみ販売する場合などには省略可能ですが、基本的には記載が望ましい事項です。 |
登録番号
インボイス制度では「T」から始まる13桁の登録番号が求められます。これは国税庁が事前に登録・付与した適格請求書発行事業者の識別番号です。この番号が記載されていない請求書はインボイスとして認められません。取引先が正しく仕入税額控除を行うためには、正確な番号の記載が不可欠です。
取引年月日
請求書には取引が発生した「年月日」を明確に記載します。複数日にわたる取引の場合は、最終取引日または取引期間(例:2024年4月1日~4月30日)を記載することで対応可能です。請求書発行日との混同に注意が必要です。
取引内容(軽減税率対象である旨の記載を含む)
商品名やサービス内容を具体的に記載し、それぞれの価格も明示します。対象品目に軽減税率(8%)が適用される場合には、商品名の横または別欄に「※軽減税率対象」と明記することで要件を満たせます。曖昧な記載(例:「商品一式」など)は無効と判断される恐れがあります。
税率ごとに区分した消費税額
消費税率ごとに、以下の2点を明記することが求められます。
- 税抜対象金額の合計(10%適用分・8%適用分)
- それぞれの税金(消費税)額
区分記載がない請求書については、税務上、仕入税額控除の認定がされない可能性がありますので注意が必要です。
書類の交付者の氏名または名称
インボイス発行者の正式な社名、個人であれば氏名(法人登記名や屋号を含む)を記載します。これにより発行した事業者の真偽を担保するとともに、税務当局網による追跡を可能とする役割を果たします。
書類の受領者への記載事項(必要な場合)
取引相手(受領者)の名称は、法的には必須ではありませんが、税務監査の際の信頼性や実務上のトラブル回避のためにも記載が望まれます。特に継続的な取引がある法人間では、記載することが一般的です。場合によっては住所や部署を併記することも有効です。
これらの記載要件を満たすことで、請求書がインボイス制度に準拠したものとなり、取引先の仕入税額控除を可能にします。不備がある請求書を交付した場合、取引先が税務上の不利益を被る可能性もあり、信頼関係に影響するため注意が必要です。
消費税の書き方と計算方法を解説!
消費税率ごとの記載方法
インボイス制度において請求書へ記載する消費税は、標準税率(10%)と軽減税率(8%)の取引を区別して記載する必要があります。税率ごとに取引金額とその税額を分けて明記することが義務付けられており、単に税込金額だけを記すことは適格請求書の要件を満たしません。
標準税率(10%)の場合
標準税率の対象となる取引(例:一般的な物品販売やサービス提供)では、以下の内容を請求書に記載します。
|
項目 |
記載例 |
|
品目 |
コンサルティング業務 |
|
取引金額(税抜) |
100,000円 |
|
消費税額(10%) |
10,000円 |
|
税込金額 |
110,000円 |
このように、税率ごとの税抜金額と消費税額を明確に区分して記すことが必要です。また、請求書に「税率10%」という記載を明示することで、後の仕入税額控除に支障がないようにします。
軽減税率(8%)の場合
軽減税率の対象となる取引(例:新聞の定期購読や飲食料品の販売)では、対象商品である旨を明記し、以下のように記載します。
|
項目 |
記載例 |
|
品目 |
ミネラルウォーター(※軽減税率対象) |
|
取引金額(税抜) |
5,000円 |
|
消費税額(8%) |
400円 |
|
税込金額 |
5,400円 |
軽減税率であることを明確に示すために、「※軽減税率対象」や「税率8%(軽減税率)」などの文言を併記することが重要です。
端数処理と計算単位のポイント
消費税の計算では、1円未満の端数が生じることがあります。インボイス制度では、端数処理の方法を統一する義務はありませんが、処理方法を請求書作成時に一定基準に従って対応することが推奨されます。
四捨五入・切り捨て・切り上げの基準
一般的に用いられる端数処理には「四捨五入」「切り捨て」「切り上げ」の3つがあります。事業者は、自社の会計処理方針に基づき、端数処理方法を統一して運用する必要があります。
|
処理方法 |
説明 |
例(8.64円) |
|
四捨五入 |
端数が0.5以上で切り上げ、それ未満で切り捨て |
→ 9円 |
|
切り捨て |
端数をすべて切り捨てる |
→ 8円 |
|
切り上げ |
端数があれば無条件に切り上げ |
→ 9円 |
税額計算の信頼性と一貫性確保のため、金融機関・税務署・取引先を含めて一貫した基準で処理を行うことが求められます。
一括計算と区分計算の違い
消費税額の計算には「一括計算方式」と「区分計算方式」があります。インボイス制度では、いずれも認められていますが、税率が複数混在する取引では区分計算が必要となります。
|
計算方法 |
特徴 |
使用例 |
|
一括計算方式 |
合計金額からまとめて消費税を計算 |
単一税率(10%)の商品販売 |
|
区分計算方式 |
商品ごと、税率ごとに消費税を個別に計算 |
軽減税率(8%)と標準税率(10%)が混在する販売 |
例えば、軽減税率対象の食品を5,000円(8%)、標準税率対象の文具を10,000円(10%)販売した場合、合計金額に対して一括で税率をかけるのは適切ではなく、必ず税率ごとの計算が必要です。
インボイス制度対応の請求書では、区分計算を行い、「標準税率対象商品」と「軽減税率対象商品」それぞれの税抜金額と消費税額を明記しなければなりません。
これにより、買手が正しく仕入税額控除の処理を行えるようになるため、必ず遵守すべき重要なポイントです。
業種別で見るインボイス請求書の書き方!
フリーランス・個人事業主
フリーランスや個人事業主の場合、取引件数が比較的少なく、請求書の項目数もシンプルなケースが多いのが特徴です。ただし、税率の違いなどに留意し、必要な記載事項を押さえる必要があります。
以下は、Webデザイナーなどのフリーランスによる請求書の記載例です。適格請求書発行事業者として求められる要件をすべて満たす形式である必要があります。
フリーランスがよく見落としがちなポイントは「登録番号の記載」と「税率ごとに区分した消費税額の記載」です。軽減税率が発生する業務は少ないものの、標準税率の適用であっても正確な区分記載が不可欠です。
中小企業(サービス業)
中小企業の中でも、コンサルティングやITサービス業などの対面・オンラインサービスは、多数の請求先がある場合があります。請求の明確性と一貫したフォーマットが求められます。
以下は、ITサポート業務などを請け負う中小企業の請求書記載例です。
中小企業では、月額契約やスポット業務の切り分けにより、請求書を複数種類作成する必要がある場合もあります。項目を明確に区分することで、仕入税額控除にもスムーズに対応可能です。
小売業・飲食業など軽減税率対象事業者
小売業や飲食業などでは、標準税率(10%)と軽減税率(8%)の混在が避けられません。そのため、税率区分ごとの明確な記載が求められます。誤記載があると、仕入先や顧客が仕入税額控除を受けられない可能性があり、信用問題にもつながります。
たとえば、お弁当と飲料の販売を行う飲食業の場合の記載例は以下の通りです。
軽減税率の対象商品には「軽減税率対象」である旨の記載が必要です。商品ごとに税率を明示する、税率区分の小計を明記するなど、請求書を受け取る側が容易に内容を読み取れる工夫が求められます。
なお、飲食店で「店内飲食」と「テイクアウト」を両方提供する場合、それぞれ異なる税率となるため、取引内容ごとに税率を区分して記載する必要があります。
経理処理上の実務対応と注意点とは?
仕入税額控除に必要な記載内容
インボイス制度(適格請求書等保存方式)において仕入税額控除を適用するためには、「適格請求書(インボイス)」の保存が条件になります。次のような情報が請求書に正確に記載されている必要があります。
|
記載項目 |
内容 |
チェックポイント |
|
適格請求書発行事業者の登録番号 |
「T+13桁の数字」が記載されているか |
国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトで番号を確認可能 |
|
取引年月日 |
請求書の発行日だけでなく、実際の取引日が明記されているか |
月単位でまとめた請求書では、対象期間の記載が必要 |
|
取引内容 |
商品・サービスの名称、数量、単価など明確に記載 |
軽減税率の対象である場合「※」や「軽減対象」等の明示表記必要 |
|
税率ごとに区分した消費税額 |
標準税率(10%)と軽減税率(8%)を分けて記載 |
必ず税率ごとの課税標準額と対応した税額を明記 |
|
書類の交付者の氏名または名称 |
法人・個人名および必要に応じて所在地等も記載 |
屋号がある場合も正式な名称を使用 |
これらの記載が不足している場合、仕入税額控除の対象にならず、税務調査などで否認される可能性があるため、経理部門は受領書類のチェック体制を強化する必要があります。
記帳作業で気をつけたいポイント
インボイス制度下における記帳業務では、これまで以上に帳簿の正確性と記載情報の一貫性が求められます。以下に具体的な注意点を挙げます。
- 取引先が適格請求書発行事業者かを都度確認
- 帳簿の税率別集計処理(10%・8%・非課税・免税)を分けて管理
- 仕入インボイスに適格請求書としての記載があるかを必ず目視で確認
- キャンセル・返品処理の際は「修正インボイス」や「返還インボイス」の対応を徹底
- 税込・税抜の処理を統一し、計算結果との整合性を確認
経理ソフトに自動取込機能がある場合でも、原始証憑である請求書のチェックは省略できません。特に月次・四半期ごとの消費税集計時には、合計金額と税率別の課税売上・仕入の整合性が正しいか突合する必要があります。
電子インボイス対応の検討
改正電子帳簿保存法の施行やペーパーレス化の流れを受け、電子インボイスへの移行が急速に進んでいます。特に経理・会計業務の効率化を図るうえで、電子インボイスの導入検討は重要な経営課題のひとつです。
2023年10月から提供が始まった「Peppol(ペポル)インフラ」に対応した日本標準の電子インボイス規格「JP PINT」は、多くの会計ソフトが対応を進めています。電子インボイスを使用するメリットには以下があります。
- 請求書のやり取りがリアルタイムで完結、郵送コストの削減
- 記載ミスや転記ミスの削減による業務効率の向上
- 保存要件を満たす形での電子帳簿への連携が容易
- タイムスタンプなどの電子証拠により信頼性が高い
ただし、電子インボイスを導入するには、システム投資や社内運用フローの変更が必要です。特に中小企業では、無料もしくは低コストで利用できる「無料インボイス発行ツール」やクラウド会計サービスを活用することが現実的な選択肢といえるでしょう。
また、電子インボイス対応を進める際には、セキュリティ面の強化、社内教育の実施、得意先・仕入先との連携体制も含めて総合的な計画が求められます。
【Q&A】インボイス制度に関するよくある質問
免税事業者への請求書はどうなるの?
インボイス制度においては、課税事業者(適格請求書発行事業者)でないとインボイス(適格請求書)を発行することができません。免税事業者が発行する請求書は、インボイスと認められず、仕入税額控除の対象外となります。
つまり、取引先が仕入税額控除を受けるためには、課税事業者との取引を選択する必要が出てくるため、免税事業者は取引先から不利な扱いを受ける可能性があります。この影響から、免税事業者が課税事業者に登録(インボイス発行事業者としての登録)するケースが増えています。
また、2023年10月の制度開始以降、6年間は「経過措置」が設けられており、一定割合の仕入税額控除が可能です。具体的には、制度開始から3年間(2023年〜2026年)は80%、その後3年間(2026年〜2029年)は50%が控除できるようになっています。
間違った請求書を発行した場合の対応方法は?
インボイス制度下で、請求書に誤りがあった場合、その訂正方法にはいくつかのパターンがあります。
|
発生した誤りの種類 |
対応方法 |
|
金額の誤り(消費税額、税率を含む) |
訂正分のインボイス(追加入力もしくは修正分)を発行し、内容の整合性を確認する |
|
登録番号の記載漏れ |
登録番号を含む正しいインボイスを再発行 |
|
記載項目の抜け(税率や軽減税率の適用旨など) |
不足項目を補った訂正インボイスを発行し、双方で差し替え処理を行う |
なお、訂正・再発行を行う場合は、元の取引日・インボイス番号といった原始データとの対応関係を明記し、訂正後の内容とともに取引先に連絡して承認を得ることが必要です。
経理処理上も影響が出るため、社内で誤り発見の仕組みや承認フローを構築することが求められます。
海外取引におけるインボイス対応はどうする?
インボイス制度は日本国内での取引に適用されるもので、国外取引(たとえば輸出や海外仕入れ)においては原則として「インボイス」の発行は不要です。ただし、取引が日本の消費税課税対象となるかどうかの判定は重要です。
たとえば、日本からの輸出取引は「輸出免税」に該当し、消費税が課されないためインボイスは必要ありません。一方、逆に海外から輸入した際には「輸入消費税」が課されることがありますが、これは通関時に税関を通じて課税されるものであり、インボイス制度とは異なる処理となります。
なお、海外の取引先がインボイス制度の理解を持たない場合も多いため、日本企業側で説明責任を担う必要があります。特に輸出入取引の invoicing(請求書作成)においては、英語表記に加えて日本国内の税務要件を別紙で補足したり、税理士との相談により適切な処理を行う必要があります。
また、三国間取引など海外を経由した複雑な商流の場合には、税務リスク回避のために顧問税理士や公認会計士の助言を受けることが推奨されます。
まとめ
インボイス制度に対応した請求書には、適格請求書としての要件を満たす6つの記載事項が必要です。取引内容に応じた消費税の表示や計算方法、業種ごとの対応も重要です。仕入税額控除の適用には正確な記載が必須となるため、制度理解と実務対応が求められます。適切な対応により、経理上のリスク軽減と円滑な税務処理が可能になります。










