【最新】インボイス対応の会計ソフトに使える補助金を徹底解説!
更新日:2025.07.28
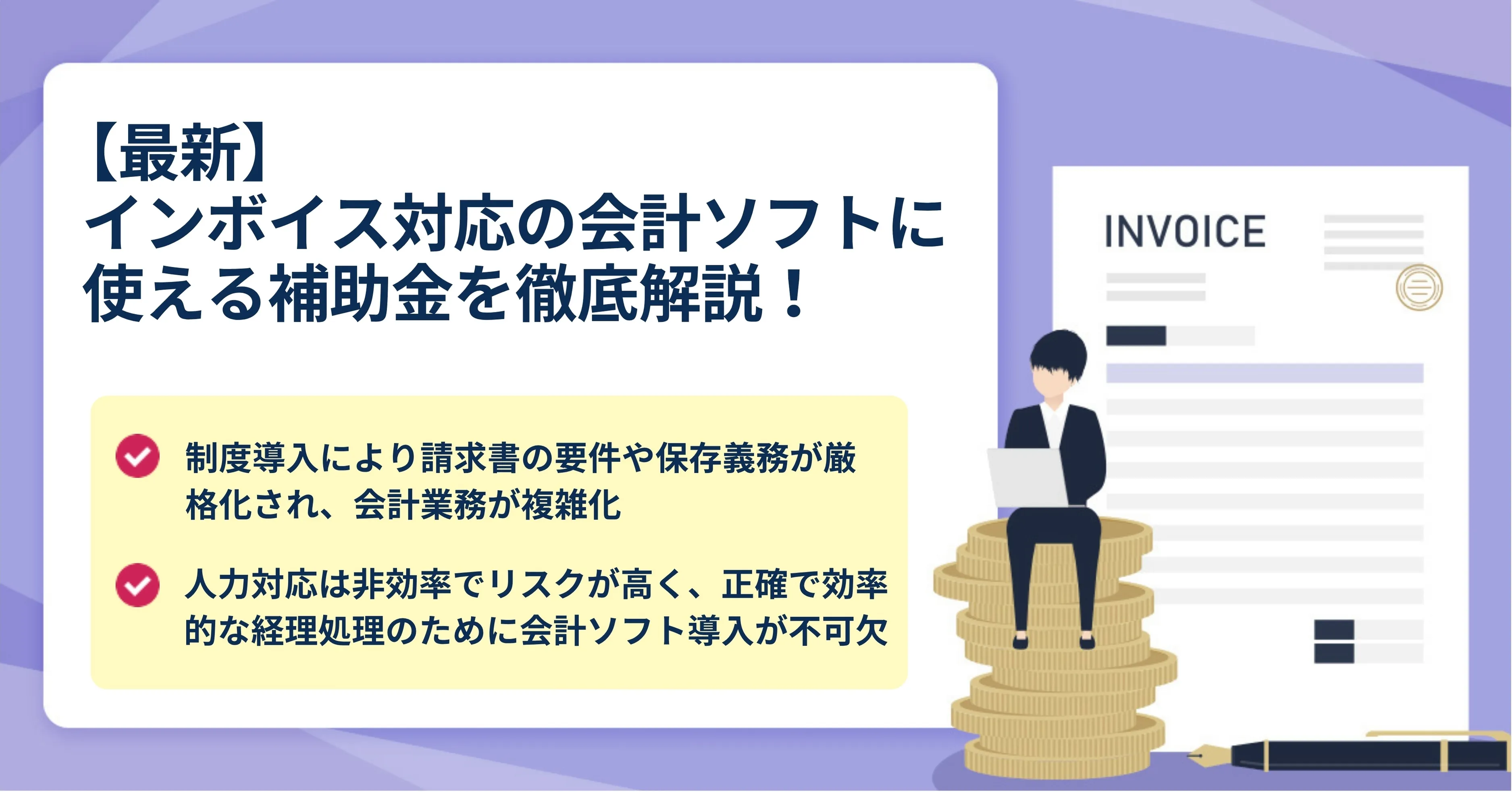
ー 目次 ー
インボイス制度への対応で会計ソフトの導入を検討しているけれど、費用面が気がかり...という方も多いのではないでしょうか。実は、国の「IT導入補助金」などを活用すれば、会計ソフトの導入コストを大幅に抑えることが可能です。本記事では、インボイス制度に対応するために使える補助金の種類や対象者、申請の流れなどを丁寧に解説します。
個人事業主の方にも役立つ情報を盛り込んでおりますので、ぜひ最後までご覧ください。
インボイス制度対応には会計ソフトの導入が必須!
2023年10月1日から開始されたインボイス制度は、多くの個人事業主や中小企業にとって、経理業務の進め方を大きく変える転換点となりました。本章では、まずインボイス制度が会計業務にどのような影響を与えるのか、そして会計ソフトを導入することで得られる具体的なメリットについて詳しく解説します。
インボイス制度の概要と会計業務への影響
インボイス制度とは、正式名称を「適格請求書等保存方式」と言い、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式です。事業者が仕入税額控除を受けるためには、原則として「適格請求書(インボイス)」の保存が必要となります。この変更は、請求書を発行する「売り手」と、受け取る「買い手」の双方の経理業務に大きな影響を与えます。
|
立場 |
インボイス制度による主な業務内容の変更点 |
|
売り手側(請求書を発行) |
|
|
買い手側(請求書を受領) |
|
このように、インボイス制度の導入により、請求書のフォーマット変更だけでなく、日々の記帳や税額計算、書類の保存方法まで、会計業務全体が複雑化します。これらの作業を手作業や従来のExcel管理で行うことは、膨大な手間がかかるだけでなく、記載ミスや計算間違いのリスクを著しく高めてしまいます。
会計ソフトでインボイス対応するメリット
インボイス制度によって複雑化した会計業務は、対応する会計ソフトを導入することで大幅に効率化できます。手作業による負担やミスを減らし、事業者が本来の業務に集中するための時間を生み出すことにも繋がります。主なメリットは以下の通りです。
- 適格請求書(インボイス)の簡単な作成と発行
会計ソフトを使えば、あらかじめ設定した事業者情報が自動で入力され、制度の要件を満たした請求書を簡単に作成できます。消費税額の計算も自動で行われるため、計算ミスを防ぎ、安心して取引先に請求書を発行できます。 - 受け取った請求書の効率的な管理と仕訳の自動化
多くの会計ソフトには、スマートフォンで撮影したりスキャンしたりした請求書をAI-OCR機能で読み取り、インボイスかどうかを自動で判定する機能が搭載されています。これにより、仕訳作業が自動化され、手入力の手間とミスが激減します。適格請求書とそれ以外の請求書を自動で振り分けてくれるため、仕入税額控除の計算もスムーズです。 - 正確な消費税計算と申告サポート
インボイス制度では、仕入税額控除の計算が複雑になりますが、会計ソフトは日々の取引データから自動で消費税額を集計してくれます。免税事業者からの仕入れに関する経過措置など、複雑なルールにも対応しているため、法令に準拠した正確な消費税申告書の作成を強力にサポートします。 - 電子帳簿保存法への同時対応
インボイス制度と並行して対応が求められる「電子帳簿保存法」にも、多くの会計ソフトが対応しています。請求書などの電子取引データを法令の要件を満たした形で保存できるため、法改正にまとめて対応することができ、ペーパーレス化の推進にも繋がります。
インボイス対応の会計ソフト導入に使える補助金一覧
インボイス制度への対応で会計ソフトの導入や買い替えを検討している事業者様が活用できる、代表的な補助金を2つご紹介します。
最もおすすめなのはIT導入補助金
インボイス対応の会計ソフトを導入する場合、最も活用しやすいのが「IT導入補助金」です。中小企業や個人事業主を対象に、会計ソフトなどのITツール導入費用の一部を補助してくれる制度で、「インボイス枠」という専用類型も用意されています。インボイス制度にぴったり合った補助金なので、ほかの補助金よりも通りやすいというメリットがあります。
対象者や補助金額の詳細は、次の章で詳しくご紹介します。
IT導入補助金の対象者や条件とは?
IT導入補助金(インボイス枠)を利用するための主な対象者や条件は以下の通りです。申請を検討する際は、必ず最新の公募要領をご確認ください。
|
対象者 |
日本国内で事業を営む中小企業・小規模事業者等(個人事業主・フリーランスを含む) |
|
主な要件 |
|
|
補助対象経費 |
ソフトウェア購入費、クラウド利用料(最大2年分)、導入関連費用など |
|
補助率・補助額 |
|
小規模事業者持続化補助金も活用できる可能性がある
「小規模事業者持続化補助金」は、小規模事業者が販路開拓や業務効率化に取り組む経費の一部を補助する制度です。IT導入補助金とは異なり、ITツール導入に特化した補助金ではありませんが、事業計画の中で必要と認められれば、会計ソフトの導入費用も補助対象経費に含めることができます。例えば、ホームページ制作やチラシ作成といった販路開拓の取り組みとあわせて、経理業務の効率化のために会計ソフトを導入したい、といった場合に活用しやすいでしょう。
小規模事業者持続化補助金の対象者・条件
小規模事業者持続化補助金には、インボイス発行事業者に転換する事業者向けに補助上限額が上乗せされる「インボイス特例」が設けられています。
|
対象者 |
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く)は常時使用する従業員5人以下など、業種ごとに定められた要件を満たす小規模事業者(個人事業主・フリーランスを含む) |
|
主な要件 |
|
|
補助対象経費 |
機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、開発費、資料購入費、雑役務費など(会計ソフトは「機械装置等費」として計上可能) |
|
補助率・補助額 |
|
IT導入補助金で会計ソフトを導入する場合の流れと申請方法
インボイス対応の会計ソフト導入で最も活用しやすいIT導入補助金。ここでは、補助金を受け取るまでの具体的な流れと、申請手続きをスムーズに進めるためのポイントを解説します。
導入までのステップ|会計ソフト選定から補助金申請までの流れ
IT導入補助金の申請は、IT導入支援事業者と二人三脚で進めるのが基本です。会計ソフトの選定から補助金の入金まで、全体の流れを6つのステップに分けてご紹介します。
|
ステップ |
内容 |
ポイント |
|
STEP 1 |
IT導入支援事業者とITツールの選定 |
まずは補助金の対象となる会計ソフト(ITツール)と、その導入をサポートしてくれるIT導入支援事業者を選びます。多くの会計ソフトメーカー自身が支援事業者として登録されています。 |
|
STEP 2 |
交付申請の準備・提出 |
IT導入支援事業者と共同で事業計画を作成し、申請マイページから交付申請を行います。この際、事前に「gBizIDプライム」アカウントの取得が必須です。 |
|
STEP 3 |
交付決定 |
事務局による審査が行われ、採択されると「交付決定通知」が届きます。この通知を受け取るまでは、会計ソフトの契約や支払いは絶対に行わないでください。 |
|
STEP 4 |
ITツールの契約・支払い |
交付決定後、IT導入支援事業者との間で会計ソフトの契約手続きを進め、費用を支払います。この支払いが補助金の対象となります。 |
|
STEP 5 |
事業実績報告 |
会計ソフトを導入し、支払いが完了したことを証明する書類(契約書・請求書・支払証憑など)を揃え、IT導入支援事業者の確認を経て事務局に提出します。 |
|
STEP 6 |
補助金の交付 |
事業実績報告の内容が確定されると、補助金額が決定し、申請者の銀行口座に補助金が振り込まれます。 |
申請手続きのポイント|必要書類・GビズID登録・注意点も解説
申請を滞りなく進めるためには、事前の準備が重要です。特に必要書類とGビズIDの取得は早めに着手しましょう。ここでは申請における重要なポイントを3つに絞って解説します。
GビズIDプライムアカウントの取得
IT導入補助金の電子申請には、「GビズIDプライム」アカウントが不可欠です。無料で取得できますが、申請からアカウント発行まで2〜3週間程度かかる場合があります。補助金の公募開始に合わせて、余裕をもって準備を進めておくことを強くおすすめします。
事前に準備すべき必要書類
申請には、法人と個人事業主でそれぞれ以下の書類が必要となります。いずれも発行から3ヶ月以内のものが有効です。
- 法人の場合
- 履歴事項全部証明書
- 法人税の納税証明書(「その1」または「その2」)
- 個人事業主の場合
- 本人確認書類(運転免許証、住民票など)
- 所得税の納税証明書(「その1」または「その2」)
- 所得税確定申告書B
申請における注意点
補助金申請で失敗しないために、以下の点に注意してください。
- 交付決定前の契約・支払いは厳禁
補助金の交付が決定する前に会計ソフトの契約や支払いを行うと、補助対象外となります。必ず交付決定通知を受け取ってから手続きを進めてください。 - 申請枠の確認
インボイス対応の会計ソフトは、主に「インボイス枠(インボイス対応類型)」での申請となります。この枠は、会計・受発注・決済機能を持つソフトウェアが対象で、補助率が優遇されています。IT導入支援事業者と相談し、最適な枠で申請しましょう。 - 公募スケジュール
IT導入補助金には公募期間と締切日が設定されています。公式サイトで最新のスケジュールを常に確認し、締切に間に合うように計画的に準備を進めることが大切です。
Q&A|インボイスの会計ソフトの補助金に関するよくある質問
インボイス制度対応の会計ソフト導入や、それに伴う補助金の活用について、多くの事業者様から寄せられる質問をまとめました。申請前に疑問点を解消しておきましょう。
個人事業主やフリーランスも補助金の対象ですか?
はい、個人事業主やフリーランスの方も補助金の対象となります。
本記事で紹介している「IT導入補助金」や「小規模事業者持続化補助金」は、いずれも中小企業・小規模事業者を支援するための制度です。資本金や常時使用する従業員数などの条件を満たせば、法人形態を問わず申請が可能です。インボイス制度への対応は個人事業主やフリーランスにとっても重要な課題ですので、ぜひ補助金の活用を検討してください。
すでに使っている会計ソフトでも補助金申請できる?
補助金は原則として「新規導入」が対象ですが、IT導入補助金の「インボイス枠(インボイス対応類型)」であれば、既存ソフトの利用料も対象になる場合があります。
具体的には、インボイス制度に対応するために、現在利用中の会計ソフトの機能を拡張する費用や、クラウドサービスの利用期間を延長する費用(最大2年分)などが補助対象に含まれます。ただし、単なる保守費用や、機能追加を伴わない更新費用は対象外となるため注意が必要です。詳しくはIT導入支援事業者に確認しましょう。
補助金は最大いくらまで受け取れる?50万円の枠って何に使えるの?
会計ソフトの導入で最も活用しやすいIT導入補助金「インボイス枠(インボイス対応類型)」を例に解説します。この枠は、導入するITツールの機能数によって補助率や上限額が変わります。
ご質問の「50万円の枠」とは、会計・受発注・決済のいずれかの機能を持つソフトウェアを導入する場合の上限額を指します。多くのインボイス対応会計ソフトがこの枠に該当します。
|
対象経費 |
補助率 |
補助上限額 |
|
会計・受発注・決済ソフト(いずれか1機能以上) |
4/5以内 |
50万円以下 |
|
会計・受発注・決済ソフト(上記のうち2機能以上) |
3/4以内 |
50万円超~350万円以下 |
|
PC・タブレットなどハードウェア購入費 |
1/2以内 |
10万円 |
|
レジ・券売機などハードウェア購入費 |
1/2以内 |
20万円 |
このように、会計ソフトの購入費やクラウド利用料に加え、必要であればパソコンやタブレットの購入費用も合わせて補助対象にできます。自社の課題解決に必要なITツールを組み合わせて申請することが可能です。
商工会議所に加入していないと補助金は受けられない?
申請する補助金の種類によって、商工会議所との関わり方が異なります。
IT導入補助金の場合
商工会議所への加入は必須ではありません。IT導入補助金は、国から採択された「IT導入支援事業者」とパートナーシップを組んで申請手続きを進めます。会計ソフトの選定から申請サポートまで、IT導入支援事業者が伴走してくれる仕組みです。
小規模事業者持続化補助金の場合
商工会議所への加入は必須ではありませんが、申請にあたって地域の商工会議所または商工会から「事業支援計画書」の作成支援を受け、交付してもらう必要があります。そのため、非会員であっても商工会議所・商工会への相談が必須となります。
まとめ
インボイス制度への対応には、正確な請求書の発行や消費税の計算が欠かせません。
会計ソフトを導入することで、これらの業務を効率化しながら、電子帳簿保存法への対応も一度に進められます。導入費用がネックに感じる方も、IT導入補助金を活用すれば、費用負担を大きく軽減できます。補助金の申請は事前準備が重要ですので、自社が対象になるかを早めに確認し、信頼できるIT導入支援事業者と一緒に準備を進めていきましょう。










