農家にもインボイス制度は関係する?関連の特例や注意するポイントも解説
更新日:2026.01.29
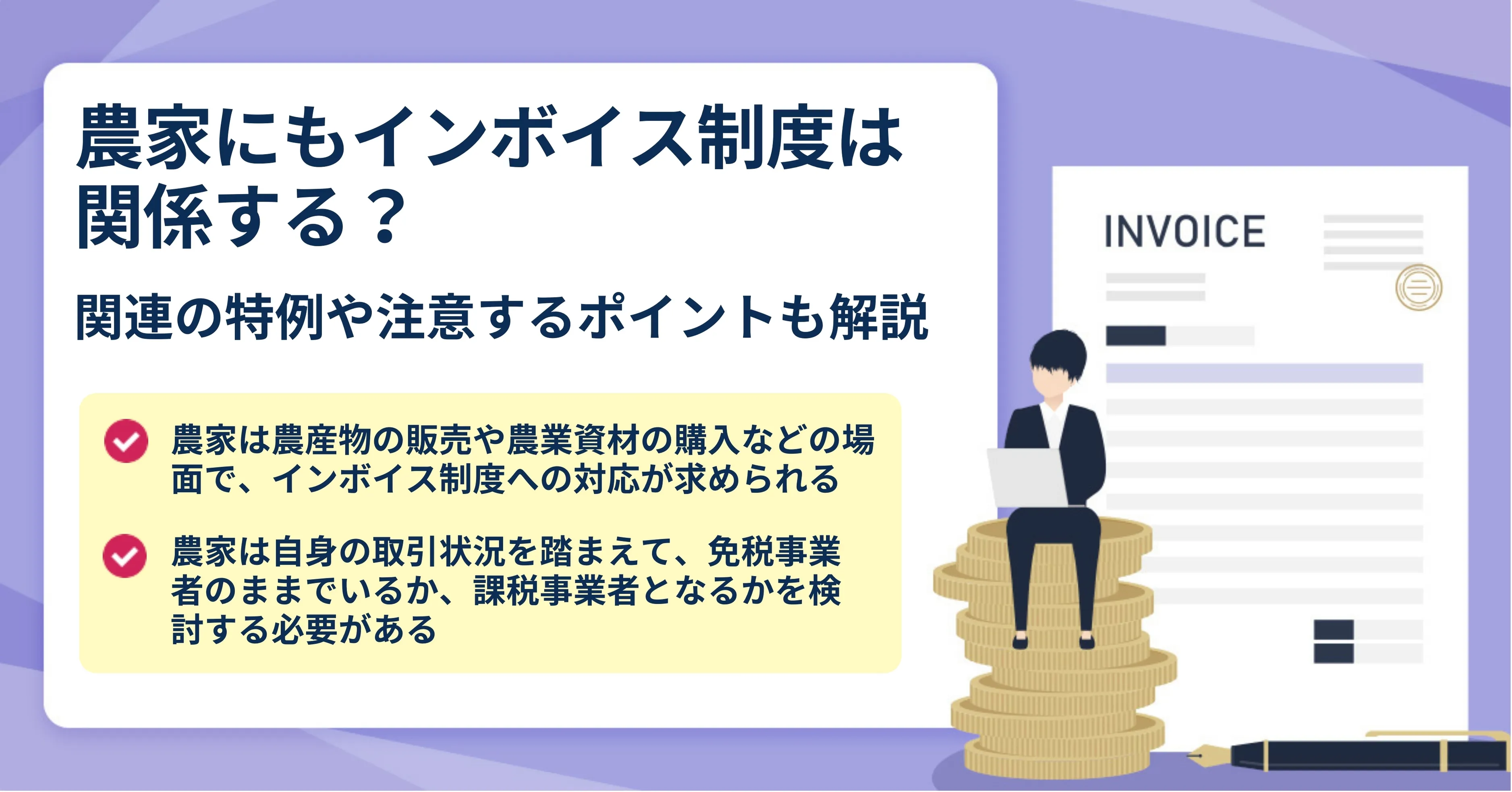
ー 目次 ー
2023年10月からはじまったインボイス制度は、幅広い業種の事業者に影響を与えており、農家にとっても避けて通れない課題となっています。とくに、農家は生産において複数の税率にまたがった取引がおこなわれる特性から、ほかの業種とは異なった課題も抱えています。
一方で、農家に対しては「農協特例」も実施されているため、インボイス(適格請求書)を買い手に交付する必要がありません。
このようにインボイス制度は農家にも影響するルールであり、細かなルールを把握しておかなければ税務上のトラブルになるおそれがあります。そのため、正しい知識を理解するようにしましょう。
本記事では、農家とインボイス制度の関係について、基本的なルールや特例、注意するポイントを交えて解説します。
インボイス制度とは、消費税に関する新しい制度
インボイス制度は、取引の透明性を確保して、消費税の計算をより正確におこなうための制度です。このインボイス制度ではインボイス(適格請求書)の発行・保存をすることで、売上にかかった消費税額から仕入れに支払った消費税額を差し引ける「仕入税額控除」が適用されます。
インボイスを発行するには「インボイス発行事業者」としての登録が必要で、インボイスの発行には以下の記載事項を満たしておく必要があります。
- 発行者の氏名または名称および登録番号
- 税率ごとに区分した合計金額および適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額
農家を含めて、さまざまな事業者がこの制度への対応を迫られており、それぞれの事業形態にあわせた適切な対応が求められています。
農家がインボイス制度の影響を受けるおもな2つのシーンとは?
インボイス制度は農家を営む事業者においても影響を与えています。ただ、その影響は事業の売上や取引先の状況などによって異なるため、一概には判断ができません。
まずはどのような事業者に対して、どのような影響があるのかを理解しておきましょう。
ここでは、農家がインボイス制度の影響を受ける2つのおもなシーンについて、それぞれ解説します。
①売り手として農産物を販売する場合
買い手がインボイス(適格請求書)発行事業者で農家が免税事業者の場合は、農家はインボイスを発行できないため、買い手は仕入税額控除を適用できません。その結果、買い手の税負担が増加し、取引の内容や条件の見直しにつながるリスクがあります。
一方で、農家がインボイス発行事業者になってインボイスを発行できるようになれば、買い手は仕入税額控除を適用できるため、既存の取引関係を維持しやすくなるでしょう。また、インボイス発行事業者であることが新規取引開拓の条件となるケースもあるため、ビジネスチャンスが広がる可能性もあります。
②買い手として種苗や肥料、農業機器を仕入れる場合
農家が免税事業者の場合は、売り手がインボイス(適格請求書)発行事業者・免税事業者に関わらず、農家自身は仕入税額控除を適用されないため、インボイス制度の影響はほとんどありません。
一方で、農家・売り手の双方がインボイス発行事業者であれば、インボイスを受け取ることで仕入税額控除が適用されて、税負担の軽減が図れます。
ただし、売り手が免税事業者の場合は、インボイスが発行されないため、その取引分の仕入税額控除が適用されません。これにより、消費税の納税額が増加する可能性があるため、取引先の選定でインボイスを発行できる事業者を優先する可能性があるでしょう。
農家が利用できるインボイス制度に関連した3つの特例
インボイス制度の導入で生じる可能性のある農業分野での実務上の困難や負担を軽減するために、農家向けの特例制度が設けられました。農家がこれらの特例制度を適切に活用することで、対応負担を軽減しながら、取引先との関係を維持できます。
ただし、それぞれの特例には要件が定められているため、活用を検討する場合には基本的な内容だけでなく、要件や注意点を把握しておきましょう。
ここでは、農家が利用できるインボイス制度に関連した3つの特例について、それぞれ解説します。
①農協特例
農協特例は、インボイス制度における農家のインボイス(適格請求書)の発行義務が免除される特例です。農家が無条件委託方式・共同計算方式で農協に販売を委託している場合に適用されます。
農協特例が適用されると、農家の代わりに農協がインボイスを買い手に交付します。したがって、農家が免税事業者であっても、買い手には仕入税額控除が適用されるため、取引関係を維持しやすいです。
また、農家はインボイス発行事業者に登録する必要がなく、課税事業者にならなくても従来通りの取引を継続できます。消費税の申告・納税や記帳などの事務作業が増えることなく事業を継続できる点も大きなメリットです。
②卸売市場特例
卸売市場特例は、農家の代わりに卸売市場が買い手に対してインボイス(適格請求書)を発行する特例です。
卸売市場特例により、農家のインボイス発行義務が免除されて、卸売市場が発行する書類で買い手には仕入税額控除が適用されます。免税事業者である農家も通常どおりに取引を続けられる点が大きなメリットです。とくに、小規模な農家はインボイス制度での負担がなく取引を継続できるため、事業継続をサポートする効果があります。
卸売市場特例は、国や地方自治体から認定を受けた、卸売市場を通じた取引で適用されます。
③媒介者交付特例
売り手と販売を仲介する事業者の両方がインボイス(適格請求書)発行事業者に登録していることを条件に、委託販売事業者が売り手に代わってインボイスを交付できる制度です。
媒介者交付特例が適用されると、農家自身が個々の取引ごとに買い手にインボイスを発行する手間が省けます。農産物直売所やオンラインマーケットなどの販売を仲介する事業者が農家に代わってインボイスを発行するため、事務負担の大幅な軽減が可能です。
ただし、免税事業者の農家はこの特例を利用できないため、特例を活用したい場合は課税事業者への登録が必要です。
農家がインボイス制度で注意するポイント4つ
インボイス制度は農家の売上げ構成や利益水準に実質的な変化をもたらします。農家は取引先との関係性や販売形態を詳細に分析して、利用可能な特例制度を確認したうえで、免税事業者の立場を維持するか課税事業者へ移行するかを判断する必要があります。
インボイス制度への対応に関して不明点があれば、税理士や公認会計士などの専門家に相談するのがおすすめです。
ここでは、農家がインボイス制度で注意するポイント4つについて、それぞれ解説します。
①免税事業者のままでいるかインボイス発行事業者になるか
おもな取引先がインボイス(適格請求書)発行事業者か、免税事業者かを確認しましょう。取引先が課税事業者の場合は、農家が免税事業者のままだと取引に影響を与えるおそれがあります。
課税売上が1,000万円を超える場合は、消費税の申告・納付義務が発生するため、免税事業者のままでいることができません。将来的に売上拡大を見込む場合は、インボイス制度への登録を検討するべきでしょう。
②特例が利用できるか
各特例制度を利用できるかどうかは、取引形態ごとに異なります。特例ごとの取引条件は、以下のとおりです。
|
特例 |
適用条件 |
|
農協特例 |
無条件委託方式・共同計算方式で農協に販売を委託しているか |
|
卸売市場特例 |
国や地方自治体から認定を受けた卸売市場での取引か |
|
媒介者交付特例 |
自身と販売を仲介する事業者の両方がインボイス(適格請求書)発行事業者か |
自分の取引形態が特例の適用条件を満たしているかを確認して、利用できる特例があれば積極的に活用しましょう。
③複数税率へどのように対応するか
農業では軽減税率と標準税率の両方が関係する取引がおこなわれるため、区分管理が求められます。販売する農産物や仕入れをおこなう資材・機械などの適用税率を正確に把握して、区分して管理する必要があります。
とくに、以下のような区分は間違いやすいポイントであるため注意が必要です。
|
軽減税率の対象 |
食用の農産物 |
|
標準税率の対象 |
種苗や肥料、農業機器など |
④事務負担の増加へどのように対応するか
インボイス(適格請求書)事業者になった場合は、インボイスを正確に発行できる体制を整える必要があります。また、インボイス発行事業者は消費税の申告・納付義務が発生するため、帳簿の整備や税理士への相談など準備が必要です。
このようにさまざまな場面で事務負担が増加する可能性が高いため、事前にどのように対応するかは検討しておきましょう。
まとめ|事業形態に合わせてインボイス制度への適切な対応をしよう
本記事では、農家とインボイス制度の関係について、基本的なルールや特例、注意するポイントを交えて解説しました。
農家は農産物の販売や農業資材の購入などの場面で、インボイス制度への対応が求められます。インボイス制度で直面する事務負担は、農家には大きな課題ですが、これに対応するためには自身の取引形態にあった特例の選択と活用が重要です。
農家は農産物の販売先や取引方法、主要顧客や将来的な事業拡大計画にもとづいて、課税事業者になるかどうかを決定する必要があります。取引先からの要請や市場動向を見極めながら、長期的な経営視点での判断が求められます。










