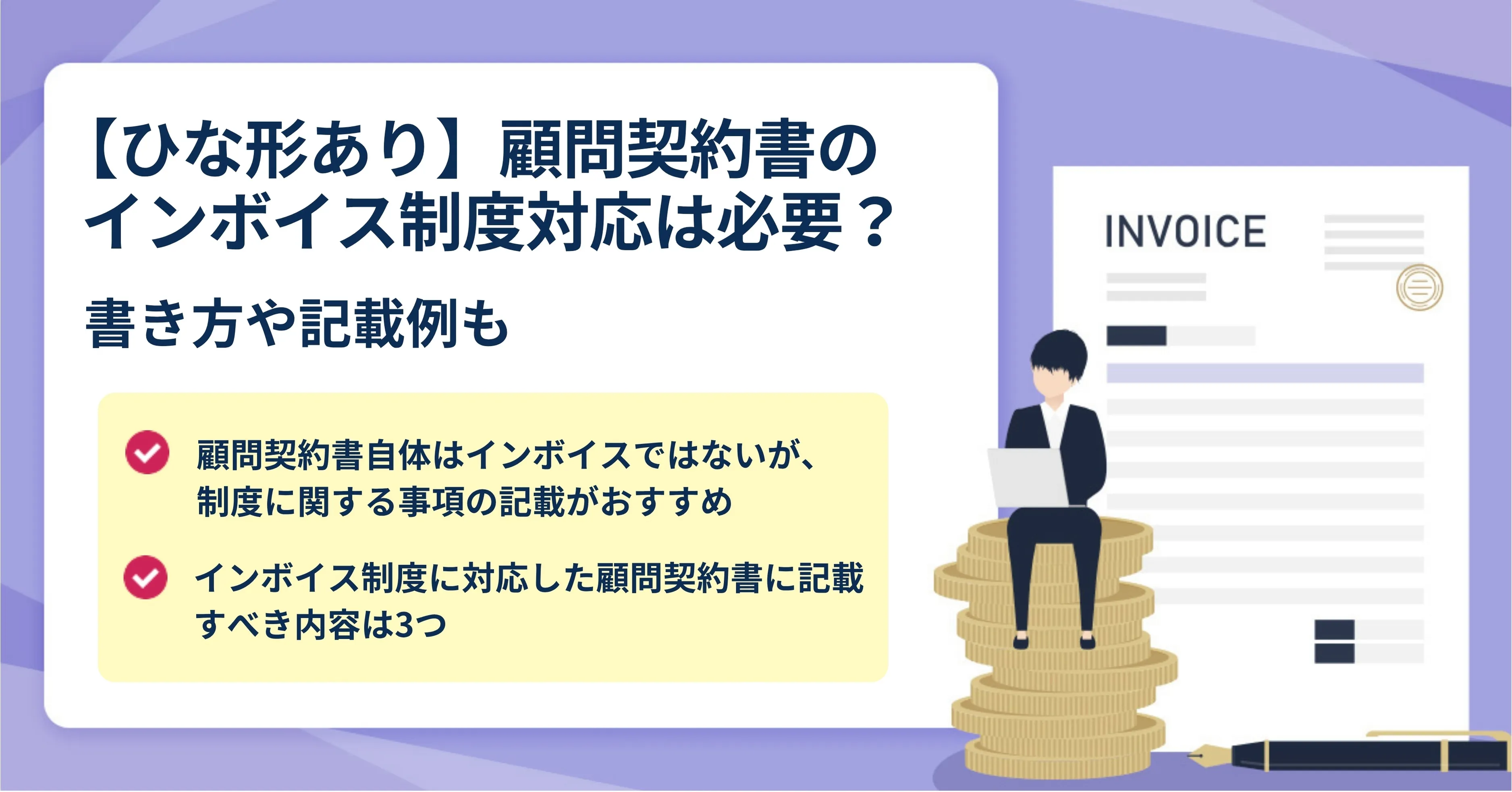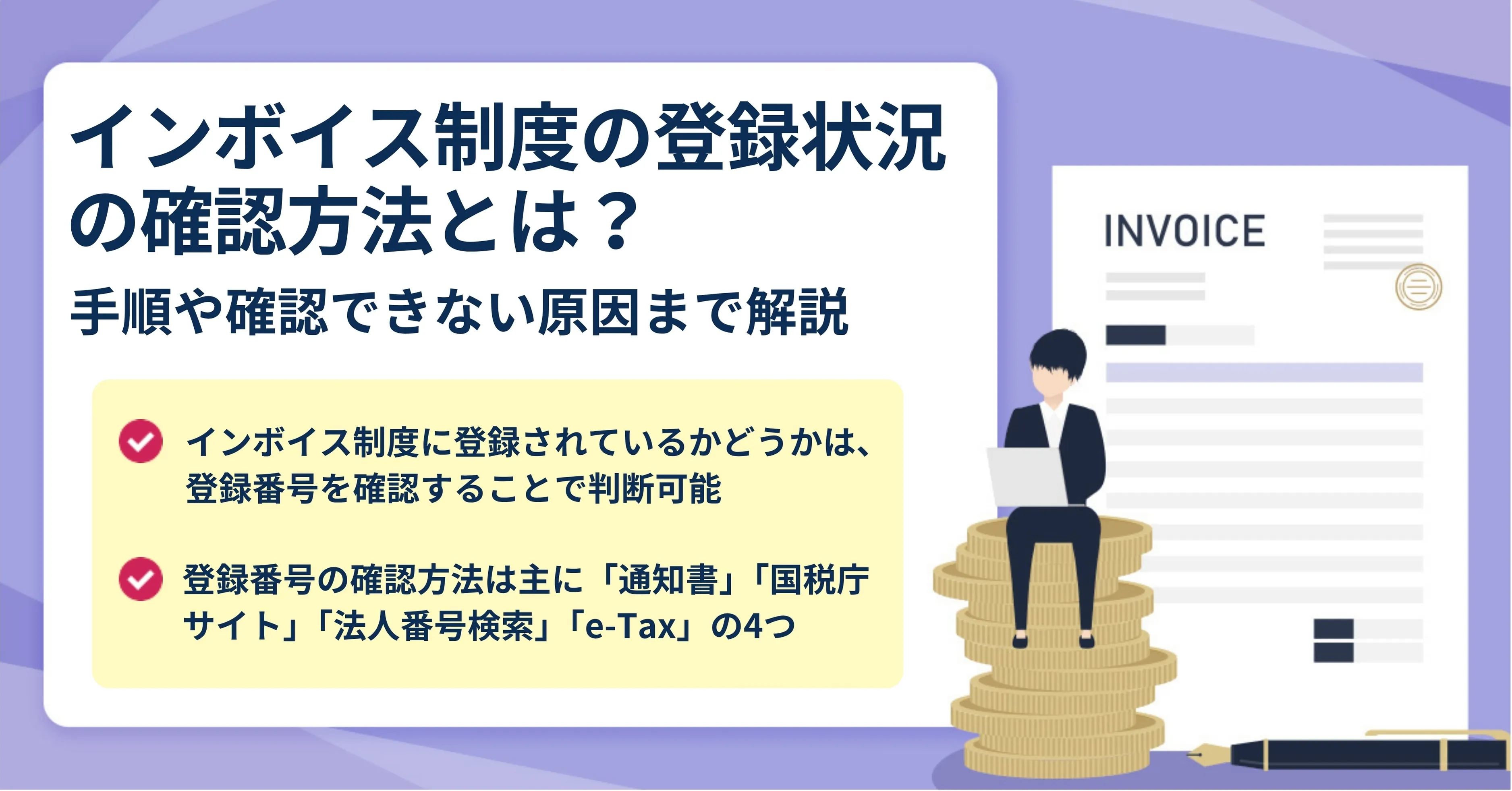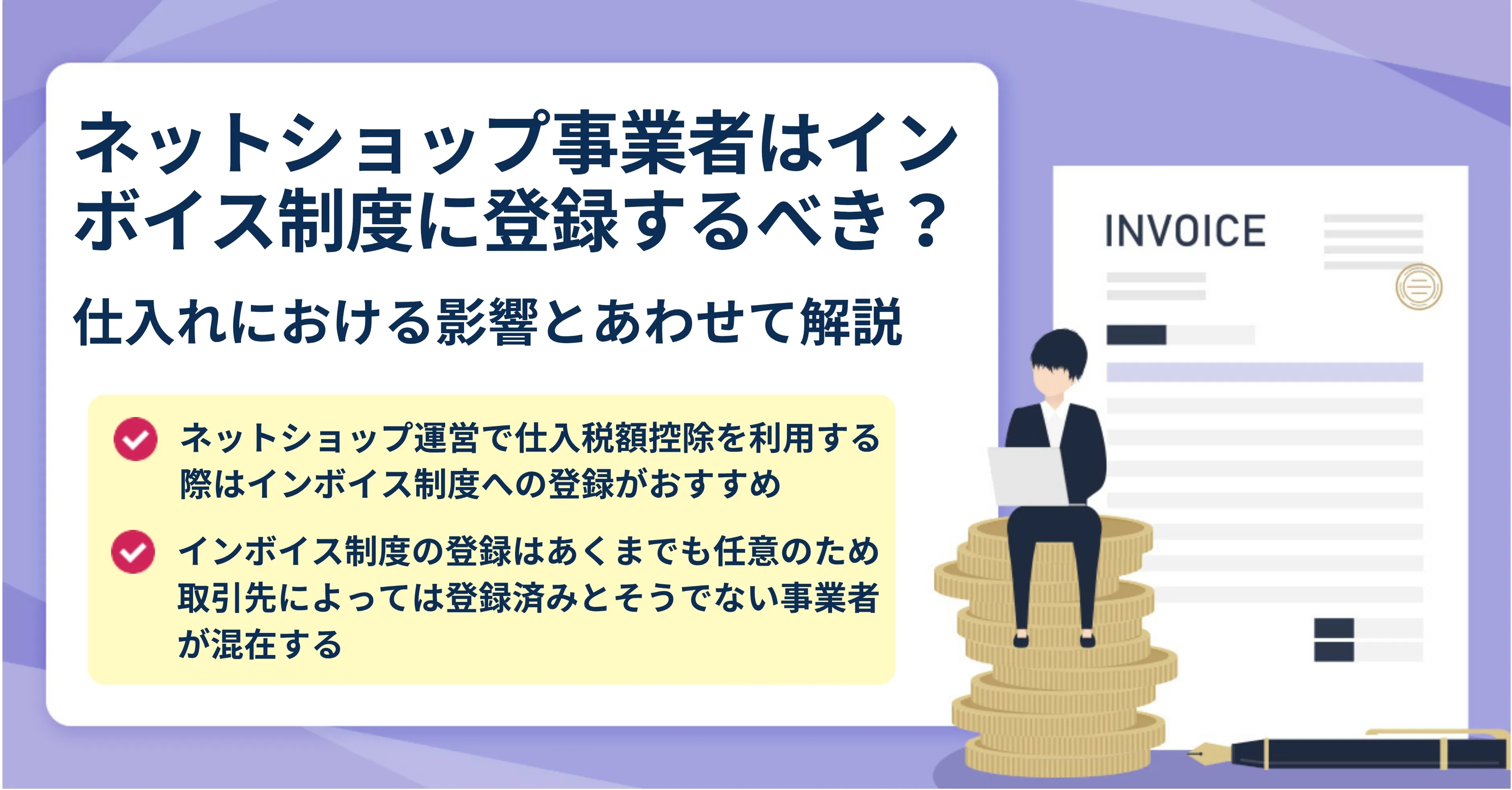電子帳簿保存法がめんどくさい方へ。今すぐできる最もシンプルな解決法
更新日:2025.07.28
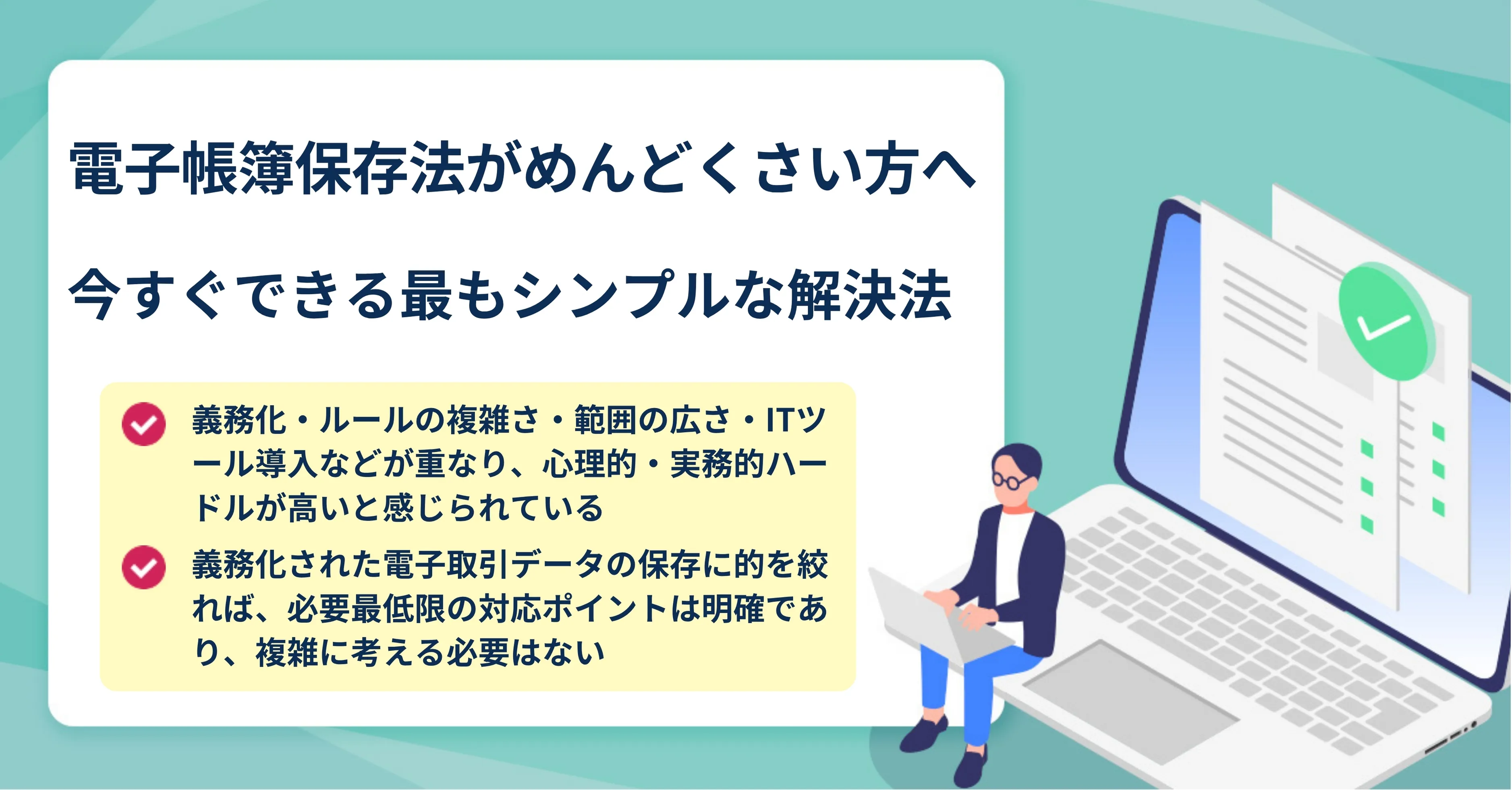
ー 目次 ー
「電子帳簿保存法って、正直めんどくさい......」そう感じていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。この記事では、まず何から始めればよいのか、そして対応しないとどんなリスクがあるのかを、できるだけわかりやすく整理しました。難しいシステム導入なしでも実践できる、シンプルな解決法をお伝えします。
なぜ電子帳簿保存法は「めんどくさい」と感じるのか?
そもそも電子帳簿保存法とは?簡単に解説
電子帳簿保存法(でんしちょうぼほぞんほう)とは、法人税や所得税など、国税に関する帳簿や書類を、紙ではなく電子データ(ファイル)で保存することを認めた法律です。この法律は、ペーパーレス化によるコスト削減や業務効率化を目的としていますが、特に2022年1月の改正で「電子取引」に関するデータの電子保存が義務化されたことで、すべての事業者が対応を迫られることになりました。
対象となる書類の範囲が広すぎる
電子帳簿保存法が「めんどくさい」と感じる理由の一つに、対象となる書類の範囲が非常に広いことが挙げられます。事業に関わるほとんどのデータが対象となると考えてよいでしょう
特に、すべての事業者が対応必須の「電子取引データ保存」は、メール添付の請求書からネット通販の領収書まで、日常業務で発生する多くのデータが対象です。これらのデータを一つひとつルールに沿って保存する必要があるため、管理が煩雑になり「めんどくさい」と感じてしまうのです。
ITツールやシステム導入に手間とコストがかかる
電子帳簿保存法の要件を満たすためには、多くの場合、新たなITツールやシステムの導入が必要になります。これが、手間とコストの両面で大きな負担となり、「めんどくさい」と感じる原因になっています。
例えば、請求書や領収書をデータで保存・管理するためのシステムは初期費用や月額利用料がかかるだけでなく、自社に合ったシステムを選定し、業務フローを見直し、従業員に使い方を教育するといった導入プロセスにも多くの時間と労力を要します。
まずはここだけ!最低限おさえるべき電子帳簿保存法のルール
電子帳簿保存法、どんなデータを残せばいいの?
まず保存対象となるのは、電子データでやり取りした取引情報、いわゆる「電子取引データ」です。紙で受け取った請求書や領収書は、これまで通り紙のまま保存しても問題ありません(スキャナ保存は任意)。
具体的には、以下のようなデータが対象となります。これらをデータで受け取ったり送ったりした場合は、そのデータをそのまま保存する必要があります。
|
取引情報の種類 |
具体的なデータ例 |
|
請求書・領収書・見積書など |
PDFファイルで受け取った請求書、メール本文に記載された領収情報 |
|
ECサイトでの購入 |
Webサイトのマイページからダウンロードした領収書データ、購入履歴のスクリーンショット |
|
クラウドサービス利用料 |
クレジットカードの利用明細データ |
|
その他 |
EDI取引のデータ、FAX機能を持つ複合機で送受信した取引情報データ |
ポイントは「紙で出力して保存」が認められなくなった点です。データで受け取ったものは、必ずデータのまま保存しましょう。
絶対に守るべき3つの保存要件!
電子取引データを保存する際には、国税庁が定めたルールを守る必要があります。難しく聞こえますが、要点は「改ざんされていないことの証明」と「いつでも見られる状態にしておくこと」です。具体的には、以下の3つの要件を満たす必要があります。
まず求められるのが「真実性の確保」です。これは、保存されているデータが本物で、あとから改ざんされたものでないことを証明するための要件です。具体的には、タイムスタンプを付けたり、訂正や削除の履歴が残るシステムを使ったりする方法があります。また、あらかじめ「事務処理規程」を作成し、それに沿って運用することでも対応できます。
次に求められるのが、いざ税務調査などで必要になったときにすぐ確認できる状態にしておくこと、つまり「可視性の確保(見読可能性)」です。パソコンやディスプレイ、プリンタを整備し、保存したデータをすぐに見られる環境を用意しておく必要があります。あわせて、保存場所や操作方法が分かるように、操作説明書なども用意しておくと安心です。
そしてもうひとつ重要なのが、「可視性の確保(検索機能)」です。保存した取引データを後からすぐに見つけられるように、検索性を担保する必要があります。具体的には、「取引年月日」「取引金額」「取引先」の3つの項目で検索できる状態にしておくことが求められています。シンプルな方法としては、ファイル名の中にこれらの情報を入れて保存しておくのが現実的で取り組みやすいでしょう。
難しそうに見えても、ポイントを絞って取り組めば、実はそれほどハードルが高いものではありません。
対応パターンはこの2つだけ!「タイムスタンプ」or「事務処理規程」
保存要件の中でも特に「真実性の確保」をどうクリアするかが、対応の分かれ道です。しかし、選択肢は主に2つしかありません。自社に合った方法を選びましょう。
パターン1:タイムスタンプが付与されるシステムを利用する
一つは、タイムスタンプ機能を持つ会計ソフトや経費精算システム、証憑保存サービスなどを導入する方法です。請求書などのデータを取り込むと、自動でタイムスタンプが付与され、改ざんが困難な状態になります。システム利用料などのコストはかかりますが、手作業の手間を大幅に削減できるのがメリットです。
パターン2:「事務処理規程」を作成して運用する
もう一つは、データの訂正や削除に関するルールを定めた「事務処理規程」を作成し、それに沿って運用する方法です。この規程は、国税庁がウェブサイトで公開しているひな形(テンプレート)を参考にすれば、専門家でなくても作成できます。特別なシステム導入が不要なため、コストをかけずに対応できる最も手軽な方法として、多くの個人事業主や中小企業で採用されています。「めんどくさい」と感じる方にとって、まず検討すべき選択肢と言えるでしょう。
めんどくさいからと放置は危険!電子帳簿保存法を無視するリスク
会社としての信用を失う
電子帳簿保存法への対応は、今や企業のコンプライアンス(法令遵守)体制を示す指標の一つと見なされています。対応を怠っていると、「法律を守らない、管理がずさんな会社」という印象を取引先や金融機関に与えかねません。
その結果、新規取引の開始が難しくなったり、融資審査で不利な評価を受けたりする可能性があります。事業を円滑に進める上で、社会的な信用の維持は不可欠です。法令を軽視する姿勢は、目に見えない形でビジネスチャンスを遠ざけてしまう危険性をはらんでいます。
青色申告の承認が取り消される可能性
電子帳簿保存法の要件を満たさずにデータを保存している場合、税務調査で「帳簿書類の保存義務を果たしていない」と判断され、青色申告の承認が取り消されるリスクがあります。青色申告の承認が取り消されると、以下のような税制上の優遇措置が受けられなくなります。
|
青色申告の主な優遇措置 |
承認が取り消された場合の影響 |
|
青色申告特別控除 |
最大65万円の所得控除が適用できなくなります。 |
|
欠損金の繰越控除 |
事業で生じた赤字(欠損金)を翌年以降の黒字と相殺できなくなります。 |
|
少額減価償却資産の特例 |
30万円未満の資産を一括で経費計上することができなくなります。 |
|
家族への給与の経費計上 |
青色事業専従者給与として、家族に支払った給与を全額経費にすることができなくなります。 |
これらの優遇措置が受けられなくなると、納税額が大幅に増加する可能性があります。日々の業務の効率化や節税のために青色申告を選択している事業者にとって、承認の取り消しは経営に大きな打撃を与えます。
追徴課税や推計課税が課されることも
青色申告の承認が取り消されると、白色申告として扱われることになります。さらに、保存されているデータが不十分だと、税務調査の際に経費の証明ができず、その経費が否認されてしまうことがあります。
また、売上に関する資料が不足している場合は、税務署が売上を推計して課税する「推計課税」が行われる可能性もあります。その結果、本来納めるべきだった税額との差額に加え、ペナルティとして次のような附帯税が課されます。
- 過少申告加算税:申告した税額が本来より少なかった場合に課される税金。
- 無申告加算税:期限内に申告しなかった場合に課される税金。
- 重加算税:事実を隠蔽したり、仮装したりするなど、悪質と判断された場合に課される最も重いペナルティ。
- 延滞税:定められた期限までに税金を納付しなかった場合に、利息として課される税金。
「めんどくさい」という理由で対応を怠った結果、本来払う必要のなかった多額の税金を支払うことになるのは、最も避けたい事態と言えるでしょう。
【結論】電子帳簿保存法のめんどくさいを解決する最もシンプルな方法
ファイル名の命名ルールを決めて保存する
まず取り組むべき最も簡単で基本的な対策が、受け取った請求書や領収書などの電子データ(PDFなど)のファイル名を統一することです。これは、電子帳簿保存法で定められている「検索機能の確保」という要件を満たすための重要なステップです。具体的には、「取引年月日」「取引金額」「取引先」の3つの情報がファイル名からわかるようにルールを決めましょう。
例えば、以下のようなルールでファイル名を変更して、専用のフォルダに保存するだけで要件を満たせます。
|
ファイル名の要素 |
記載例 |
ポイント |
|
取引年月日 |
20240401 |
8桁の西暦で入力します。(例: 2024年4月1日) |
|
取引金額 |
11000 |
税込金額を数字のみで入力します。(例: 11,000円) |
|
取引先名 |
株式会社サンプル |
正式名称または分かりやすい名称で入力します。 |
このルールに沿ったファイル名は「20240401_11000_株式会社サンプル.pdf」のようになります。このルールを社内やチームで統一し、一貫した運用を心がけることが大切です。特別なシステムを導入しなくても、この一手間だけで検索要件はクリアできます。
無料または低コストの証憑保存ツールを使う
手作業でのファイル名変更やフォルダ管理すら「めんどくさい」と感じる方には、証憑保存に特化したツールの利用がおすすめです。高価なシステムを導入しなくても、現在では無料または非常に低コストで利用できるクラウドサービスが数多く存在します。
これらのツールは、電子帳簿保存法の要件を満たすように設計されているため、ファイル名のルールなどを意識しなくても、請求書データをアップロードするだけで自動的に検索要件を満たしてくれます。お使いの会計ソフトに証憑保存機能が付属している場合も多いので、まずは確認してみましょう。
|
ツールの種類 |
主な特徴 |
|
会計ソフト付帯型 |
経理業務と一体で管理できる。追加コストが不要な場合も多い。 |
|
電子帳簿保存特化型 |
シンプルな機能で使いやすい。無料で始められるサービスも豊富。 |
これらのツールを導入することで、手作業によるミスを防ぎ、管理の手間を大幅に削減できます。特に取引件数が多い事業者にとっては、費用対効果の高い選択肢と言えるでしょう。
「事務処理規程」を活用してタイムスタンプを省略する
電子帳簿保存法対応でハードルが高いと感じられがちなのが、「タイムスタンプ」の付与です。これは「事務処理規程」を社内に備え付けることで、タイムスタンプの付与を省略できます。
事務処理規程とは、電子データの訂正や削除に関するルールを定めた社内マニュアルのことです。難しく聞こえますが、国税庁が公式サイトで法人用・個人事業主用のひな形(サンプル)を無料で提供しているため、専門知識がなくても簡単に作成できます。
この方法が、コストをかけずに対応したい事業者にとって最も現実的でシンプルな解決策です。やることは、国税庁のサイトからひな形をダウンロードし、自社の名称などを追記して、いつでも確認できる場所に保管しておくだけ。この規程に沿ってデータを保存・管理していることを示せれば、高価なタイムスタンプは不要になります。
Q&A|めんどくさい電子帳簿保存法に関するよくある質問
電子帳簿保存法の対応は税理士に丸投げできる?
結論から言うと、残念ながら「完全な丸投げ」はできません。税理士はあくまで税務の専門家であり、日々の取引で発生する電子データの保存作業そのものを代行するわけではないからです。
例えば、メールで受け取った請求書PDFを所定のフォルダに保存したり、ファイル名をルール通りに変更したりといった日常的な作業は、事業者自身が行う必要があります。税理士は、そのための最適なルール作りやシステムの選定、運用方法のアドバイスといったサポート役を担います。どこまでを自社で行い、どこから専門家のアドバイスを求めるか、事前に相談して役割分担を明確にしておくことが重要です。
電子帳簿保存法はデメリットしかない?
「めんどくさい」「コストがかかる」といった短期的なデメリットが目立ちがちですが、長期的に見れば多くのメリットがあります。対応を「面倒な義務」と捉えるか、「業務改善のチャンス」と捉えるかで、得られる成果は大きく変わってきます。
|
メリット |
具体的な内容 |
|
コスト削減 |
紙代、インク代、印刷代、書類の郵送費、保管用のキャビネットや倉庫代といった物理的なコストを削減できます。 |
|
業務効率化 |
書類を探す時間が大幅に短縮されます。また、テレワークや複数拠点での経理業務がスムーズになり、働き方の多様化に対応しやすくなります。 |
|
DXの推進 |
経理業務のデジタル化は、会社全体のデジタルトランスフォーメーション(DX)を推進する第一歩となります。 |
|
セキュリティ強化 |
紙の書類と比べて、紛失、盗難、火災や水害による消失リスクを大幅に低減できます。アクセス権限の設定により、情報漏洩のリスクも管理しやすくなります。 |
個人事業主やフリーランスも対応は必須ですか
はい、事業規模や法人・個人を問わず、所得税や法人税の申告を行うすべての事業者が対象です。したがって、個人事業主やフリーランスの方も原則として対応が必須となります。
オンラインストアで事業用の備品を購入した際の領収書データや、取引先からメールで送られてきた請求書のPDFファイルなどが「電子取引データ」に該当し、法律で定められた要件に従って保存する義務があります。ただし、小規模な事業者向けに要件が緩和される猶予措置も設けられていますので、まずは自らが受け取っている電子データを整理することから始めましょう。
電子帳簿保存法は誰が決めたの?
電子帳簿保存法は、国税庁が管轄する日本の法律です。最初に制定されたのは1998年で、当初は紙での保存が原則だった帳簿書類を、特例として電子データで保存することを「認める」ための法律でした。
その後、社会全体のデジタル化の流れを受けて何度も改正が重ねられ、特に2022年1月の改正で「電子取引」で授受したデータは電子データのまま保存することが「義務化」されました。この改正により、ほぼすべての事業者が対応を迫られることになったのです。法律の目的は、納税者の利便性向上や社会全体のペーパーレス化による生産性向上にあるとされています。
まとめ
電子帳簿保存法への対応は、たしかに最初は面倒に感じられるかもしれません。ですが、最低限のポイントさえ押さえておけば、思ったよりシンプルに対応できます。この記事で解説したように、まずは「ファイル名の命名ルールを決める」といった、今すぐ無料でできる対策から始めましょう。
法令遵守と業務効率化の両立を、ぜひ無理のない形で進めてみてください。