みなし仕入れ率はインボイス制度でどうなる?簡易課税・2割特例との比較ポイント
更新日:2025.12.07
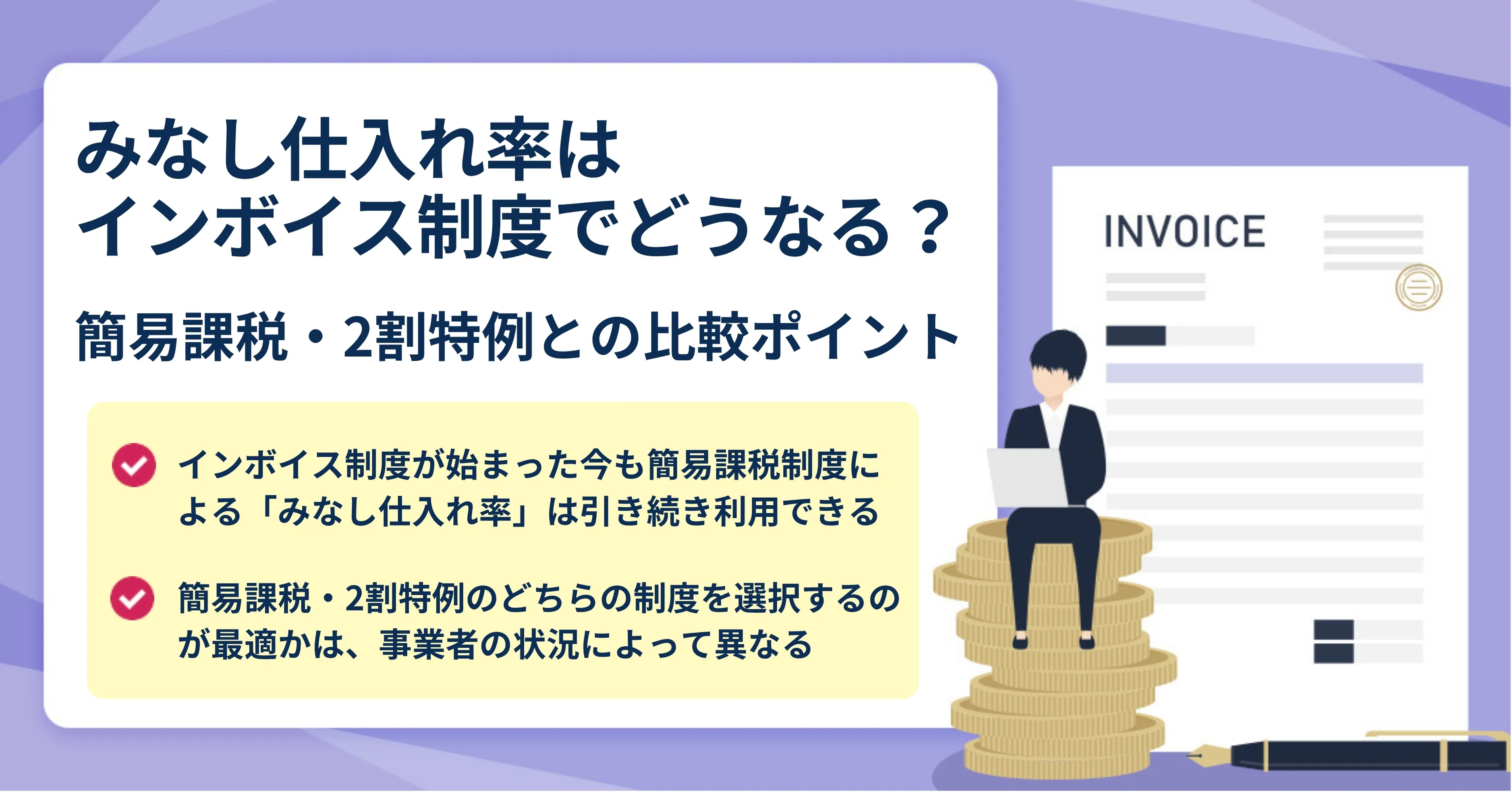
ー 目次 ー
インボイス制度の導入により、消費税の計算方法や事務処理に大きな変化が生じました。中でも、仕入税額控除の方法として注目されているのが、従来から使われている「簡易課税制度」と、新たに登場した「2割特例」です。本記事では、「みなし仕入れ率」の基本から制度間の違いまで、初めての方にもわかりやすく比較しながらご紹介いたします。自社の状況に合った制度選びの参考にしていただければ幸いです。
「みなし仕入れ率」とは?インボイスの基本も簡単におさらい
2023年10月1日から始まったインボイス制度は、多くの個人事業主や法人にとって、消費税の納税事務に大きな影響を与える変更です。この章では、まずインボイス制度の基本的な仕組みと、簡易課税制度における「みなし仕入れ率」とは何かをわかりやすく解説します。
インボイス制度の基礎知識
インボイス制度とは、正式には「適格請求書等保存方式」といい、消費税の仕入税額控除に関する新しいルールです。制度の目的は、複数税率(標準税率10%、軽減税率8%)に対応した消費税額を正確に把握し、適正な課税を確保することにあります。主なポイントは以下の通りです。
- 適格請求書(インボイス):売手が買手に対して発行する、登録番号、適用税率、税率ごとの消費税額などが記載された請求書や領収書のことです。
- 仕入税額控除の適用:買手側は、原則としてこの適格請求書の保存がなければ、支払った消費税額を売上にかかる消費税額から控除する「仕入税額控除」の適用を受けることができません。
- 適格請求書発行事業者:インボイスを発行できるのは、税務署に申請して登録を受けた「適格請求書発行事業者」に限られます。課税事業者であれば登録を受けることができます。
この制度の導入により、特に課税事業者は、仕入税額控除を受けるために取引先からインボイスを入手し、適切に保存する必要が生じました。また、売手側も、取引先の求めに応じてインボイスを発行するための準備が求められます。
みなし仕入れ率とは?わかりやすく解説
「みなし仕入れ率」とは、消費税の納税額を計算する際に「簡易課税制度」を選択している事業者が用いる、業種ごとに国が定めた概算の仕入れ割合のことです。実際の仕入れや経費にかかった消費税額を個別に計算する代わりに、売上にかかる消費税額にこの「みなし仕入れ率」を乗じることで、仕入税額控除の金額を算出します。
簡易課税制度は、基準期間(個人事業主の場合は前々年、法人の場合は前々事業年度)の課税売上高が5,000万円以下の事業者が、事前に税務署に届け出ることによって選択できる制度です。この制度を利用することで、消費税計算にかかる事務負担を軽減できるメリットがあります。
みなし仕入れ率の計算方法
簡易課税制度における消費税の納税額は、以下の計算式で求められます。
納付する消費税額 = 売上にかかる消費税額 - (売上にかかる消費税額 × みなし仕入れ率)
みなし仕入れ率は、事業の種類によって6つの区分に分けられており、それぞれの率は以下の通りです。
|
事業区分 |
該当する事業(例) |
みなし仕入れ率 |
|
第1種事業 |
卸売業 |
90% |
|
第2種事業 |
小売業、農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業) |
80% |
|
第3種事業 |
農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業を除く)、鉱業、建設業、製造業、電気業、ガス業、熱供給業、水道業 |
70% |
|
第4種事業 |
飲食店業など(第1種、第2種、第3種、第5種、第6種事業以外の事業) |
60% |
|
第5種事業 |
運輸通信業、金融業、保険業、サービス業(飲食店業を除く) |
50% |
|
第6種事業 |
不動産業 |
40% |
例えば、サービス業(第5種事業)を営んでおり、年間の課税売上高が1,100万円(うち消費税額100万円)の場合、みなし仕入れ率は50%です。この場合、仕入控除税額は100万円 × 50% = 50万円となり、納付する消費税額は100万円 - 50万円 = 50万円と計算されます。事業者は、自身の事業がどの区分に該当するかを正しく判断する必要があります。
インボイス制度でみなし仕入れ率や簡易課税はどう変わる?
これまで「みなし仕入れ率」を用いて消費税額を計算してきた事業者の方にとっては、制度変更に伴う影響や、簡易課税制度の今後の扱いについて気になるところでしょう。この章では、インボイス制度導入後のみなし仕入れ率や簡易課税制度の変更点、注意点を解説します。
インボイス制度開始後も簡易課税は使える?制度の継続と注意点
結論から申し上げますと、インボイス制度開始後も簡易課税制度は引き続き利用可能です。基本的な適用要件に変更はありません。
インボイス制度下における簡易課税制度のポイントは以下の通りです。
|
項目 |
内容 |
|
制度の継続 |
インボイス制度開始後も、簡易課税制度は存続します。 |
|
適用要件 |
基準期間の課税売上高が5,000万円以下であること、事前に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出することなど、従来の要件から変更はありません。 |
|
メリット |
売上にかかる消費税額から、みなし仕入れ率を用いて仕入税額控除額を計算するため、受け取った請求書がインボイス(適格請求書)であるか否かを問わず、またインボイスの保存も原則不要です。経理事務の負担が軽減されます。 |
|
注意点 |
|
簡易課税制度を選択している事業者は、引き続きそのメリットを享受できますが、ご自身の事業内容や取引状況を考慮し、一般課税と比較検討することが重要です。
みなし仕入れ率の控除計算にインボイスは必要?
簡易課税制度の最大のメリットの一つは、仕入税額控除の計算にインボイス(適格請求書)の保存が原則として不要である点です。これはインボイス制度開始後も変わりません。
具体的には、以下のようになります。
- 仕入れや経費の支払先がインボイス発行事業者でなくても、みなし仕入れ率に基づいた控除が可能です。
- 受け取った請求書や領収書がインボイスの記載要件を満たしていなくても問題ありません。
- 仕入税額控除のために、受け取ったインボイスを区分して管理・保存する必要はありません。(ただし、帳簿への取引内容の記載と、取引の事実を証明する請求書等自体の保存は必要です。)
ただし、注意点として、簡易課税制度を選択している事業者であっても、売上先(買い手)からインボイスの交付を求められるケースがあります。その場合、ご自身が適格請求書発行事業者として登録を受け、インボイスを交付する必要があります。適格請求書発行事業者になるかどうかは、取引先の状況やご自身の事業戦略などを踏まえて判断しましょう。
つまり、簡易課税制度を利用する場合、仕入税額控除の計算においてはインボイスの有無を気にする必要はありませんが、売上に関してはインボイス発行の対応が必要になる場合がある、という点を理解しておくことが大切です。
2割特例とは?みなし仕入れ率との違い
インボイス制度の導入に伴い、小規模事業者の負担軽減策として「2割特例」が設けられました。売上にかかる消費税額の2割を納税額とする制度で、「みなし仕入れ率」を使う簡易課税とは計算方法が異なります。この章では、2割特例の概要と簡易課税との違いを解説します。
2割特例とは?対象者と適用期間
2割特例は、正式名称を「インボイス発行事業者の登録を受けた者の経過措置」といい、インボイス制度への円滑な移行を目的とした、期間限定の特例措置です。納税額の計算が簡素化され、事務負担も軽減される点が特徴です。
対象者
2割特例の適用対象となるのは、インボイス発行事業者の登録を受けたことにより、新たに課税事業者となった事業者(または登録を受けて課税事業者となる事業者)で、かつ基準期間(個人事業主の場合は前々年、法人の場合は前々事業年度)における課税売上高が1,000万円以下の事業者です。
具体的には、以下の条件を満たす事業者が対象となります。
- 免税事業者であったが、インボイス発行事業者の登録申請を行い、課税事業者となった。
- 基準期間の課税売上高が1,000万円以下である。(特定期間の課税売上高による判定も同様)
ただし、以下のいずれかに該当する場合は、2割特例の対象外となりますので注意が必要です。
- 課税期間を1ヶ月または3ヶ月に短縮する特例(消費税課税期間特例選択・変更届出書を提出している場合)の適用を受けている期間。
- インボイス発行事業者の登録とは関係なく、課税事業者選択届出書を提出して課税事業者となっている期間(インボイス制度開始前から継続して課税事業者である場合など)。
- 基準期間の課税売上高が1,000万円を超えるなど、元々免税事業者ではない場合。
- 相続、合併、分割等があった場合の納税義務免除の特例により、インボイス発行事業者の登録に関わらず納税義務が免除されない事業者。
適用期間
2割特例を適用できる期間は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間です。個人事業主の場合、令和5年10月1日から令和5年12月31日までの申告、および令和6年、令和7年、令和8年の各年分の確定申告が対象となります。
2割特例の具体的な計算方法とメリット
2割特例の最大のメリットは、消費税の納税額計算が非常にシンプルになることです。これにより、経理事務の負担が大幅に軽減されます。
具体的な計算方法
2割特例を適用した場合の消費税の納付税額は、以下の計算式で算出します。
納付税額 = 売上にかかる消費税額 × 20%
これは、言い換えると「売上税額から、その売上税額の80%を仕入税額控除として差し引いた金額」を納税するという意味になります。例えば、課税売上高が800万円(消費税率10%)の場合、売上にかかる消費税額は80万円です。この場合、納付税額は80万円 × 20% = 16万円となります。実際に支払った経費や仕入れにかかる消費税額を個別に計算したり、それらのインボイス(適格請求書)を収集・保存したりする必要はありません(売上に関する帳簿や請求書等の保存は必要です)。
メリット
2割特例には、以下のような主なメリットがあります。
- 納税額の計算が極めて簡単:課税売上高に対する消費税額さえ分かれば、簡単に納税額を算出できます。
- 大幅な事務負担の軽減:仕入れや経費に関するインボイス(適格請求書)の収集・保存や、仕入税額控除のための詳細な計算が不要になります。日々の経理処理や確定申告時の作業負担が大きく減ります。
- 事前の届出が不要:簡易課税制度を利用する場合は事前に「消費税簡易課税制度選択届出書」の提出が必要ですが、2割特例は確定申告書に適用を受ける旨を付記するだけで適用可能です。
- 業種によっては簡易課税より有利になる可能性:簡易課税制度では、事業の種類によって「みなし仕入れ率」が定められており、この率が80%未満の業種(例:サービス業や不動産業など)では、2割特例の方が納税額が少なくなるケースがあります。
簡易課税制度の「みなし仕入れ率」は、事業の種類によって第1種事業(卸売業)の90%から第6種事業(不動産業)の40%まで6段階に分かれています。これに対し、2割特例は業種を問わず一律の計算方法であるため、特にみなし仕入れ率が低い業種の事業者にとっては、大きな節税効果が期待できる場合があります。どちらの制度が自社にとって有利かは、事業内容や売上規模などを考慮して慎重な比較検討が必要です。
簡易課税と2割特例はどっちを選ぶべき?判断のポイント
免税事業者から課税事業者になった方向けに、「2割特例」という新たな負担軽減策が導入されました。ここでは、両制度を比較し、ご自身の状況に合わせた最適な選択をするための判断ポイントを解説します。
制度の違いを比較|対象者・計算方法・適用期間
簡易課税制度と2割特例は、消費税の納税額を計算する上で、仕入税額控除の特例という点では共通していますが、対象者や計算方法、適用できる期間などに違いがあります。まずは、それぞれの制度の主な特徴を比較してみましょう。
|
項目 |
簡易課税制度 |
2割特例 |
|
対象者 |
基準期間(前々年または前々事業年度)の課税売上高が5,000万円以下の事業者 |
インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者になった事業者 |
|
計算方法(仕入控除税額) |
課税売上高に係る消費税額 × みなし仕入れ率(業種により異なる) |
課税売上高に係る消費税額 × 80% (みなし仕入れ率80%相当) |
|
適用期間 |
選択後は原則2年間継続(基準期間の課税売上高が5,000万円を超えるなど、適用要件を満たさなくなるまで) |
2023年10月1日から2026年9月30日までの日の属する各課税期間 |
|
事前の届出 |
原則として、適用を受けたい課税期間の初日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」の提出が必要 |
事前の届出は不要(確定申告書に適用する旨を付記して申告) |
|
インボイスの保存 |
原則として不要(ただし、売上にかかるインボイスの保存は必要) |
不要 |
簡易課税制度を利用するには、事前に税務署への届出が必要です。一方、2割特例は事前の届出が不要で、確定申告時に選択できる手軽さがあります。また、2割特例は期間限定の措置である点も大きな違いです。
簡易課税・2割特例どっちが得?業種・売上・インボイス対応の有無で選ぶ基準
どちらの制度を選択するのが有利かは、事業者の状況によって異なります。以下のポイントを参考に、ご自身の事業に最適な制度を選びましょう。
- 業種別のみなし仕入れ率と比較する
簡易課税制度のみなし仕入れ率は、事業の種類によって6段階(第一種事業90%~第六種事業40%)に分かれています。2割特例は、業種に関わらず一律で売上税額の2割を納税額とするもので、これは実質的にみなし仕入れ率が80%であると考えることができます。
そのため、簡易課税制度のみなし仕入れ率が80%よりも低い業種(例:サービス業の第五種事業で50%、不動産業の第六種事業で40%)の場合、2割特例の方が納税額は少なくなり有利です。逆に、卸売業(第一種事業90%)や小売業(第二種事業80%)など、みなし仕入れ率が80%以上の業種では、簡易課税制度の方が有利になる可能性があります。 - 事務負担を考慮する
2割特例は、売上にかかる消費税額さえ把握できれば納税額を計算でき、仕入れにかかるインボイスの保存も不要なため、経理処理の事務負担が大幅に軽減されます。一方、簡易課税制度も仕入税額の計算は簡便ですが、適用を受けるためには事前の届出が必要ですし、売上を事業の種類ごとに区分して経理処理を行う手間が発生する場合もあります。
インボイス制度への対応に不安がある方や、経理の事務負担をできるだけ軽くしたい方にとっては、2割特例が魅力的な選択肢となるでしょう。 - 課税売上高と適用期間を考慮する
簡易課税制度は基準期間の課税売上高が5,000万円以下でなければ適用できません。一方、2割特例の対象者は、インボイス発行事業者として登録した元免税事業者であり、売上高の基準はありません。ただし、2割特例は2026年9月30日までの期間限定の措置です。この期間終了後も課税事業者であり続ける場合は、その後の納税方法(原則課税または簡易課税)を改めて検討する必要があります。
将来的な売上規模の見通しや、2割特例の適用期間終了後のことも視野に入れて、総合的に判断することが重要です。 - 複数の事業を営んでいる場合
複数の事業を営んでおり、それぞれ異なるみなし仕入れ率が適用される場合、簡易課税制度では加重平均してみなし仕入れ率を計算する必要があります。この計算が複雑になる場合は、一律80%とみなせる2割特例の方が計算がシンプルになるメリットがあります。
これらのポイントを踏まえ、ご自身の事業内容、売上規模、事務処理能力、そして将来の事業計画などを総合的に勘案し、税理士などの専門家にも相談しながら、最適な制度を選択するようにしましょう。
Q&A|インボイス制度と「みなし仕入れ率」に関するよくある質問
2割特例から簡易課税の「みなし仕入れ率」への変更は可能?
はい、インボイス制度開始に伴い導入された2割特例の適用を受けている事業者が、簡易課税制度へ変更することは可能です。原則として、変更を希望する課税期間の初日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を所轄の税務署長に提出することで、その課税期間から簡易課税制度の適用を受けることができます。
ただし、一度2割特例の適用をやめて簡易課税制度を選択した場合、その後の課税期間で再度2割特例の適用を受けるためには一定の条件や期間制限が設けられている場合があります。制度変更を検討する際は、ご自身の事業状況や将来の計画を踏まえ、税理士などの専門家や管轄の税務署にご相談いただくことをお勧めします。
簡易課税の「みなし仕入れ率」はインボイスの登録は必要?
簡易課税制度を利用して消費税の納税額を計算するだけであれば、適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)としての登録は必須ではありません。簡易課税制度は、実際の仕入れにかかる消費税額ではなく、売上にかかる消費税額に業種ごとの「みなし仕入れ率」を乗じて仕入税額控除額を算出するため、受け取った請求書がインボイス(適格請求書)であるかどうかにかかわらず、納税額の計算方法に影響はありません。
しかし、ご自身が売手として、取引先(買手である課税事業者)からインボイスの交付を求められる場合には、適格請求書発行事業者としての登録が必要になります。登録を受けていない事業者はインボイスを発行することができません。
簡易課税制度選択者のインボイス登録の要否について、状況別にまとめると以下の通りです。
|
状況 |
インボイス登録の要否 |
主な理由 |
|
簡易課税制度を適用して消費税の納税額を計算する場合(買手としての立場) |
不要 |
納税額の計算上、受け取る請求書がインボイスである必要がないため。みなし仕入れ率を用いて仕入税額控除額を計算します。 |
|
課税事業者として取引先にインボイス(適格請求書)を発行する必要がある場合(売手としての立場) |
必要 |
インボイスを発行できるのは、税務署長の登録を受けた適格請求書発行事業者のみであるためです。 |
したがって、簡易課税制度を選択していても、売上の相手先が課税事業者でありインボイスを必要とする場合には、適格請求書発行事業者の登録を検討する必要があります。
インボイスが発行できない免税事業者からの仕入れは、簡易課税でも不利になる?
簡易課税制度を選択している場合、仕入先がインボイス(適格請求書)を発行できない免税事業者であっても、消費税の納税額計算において直接的に不利になることはありません。
その理由は、簡易課税制度が実際の課税仕入れ等の税額を基に仕入税額控除額を計算するのではなく、課税売上高にかかる消費税額に、事業の種類に応じて定められた「みなし仕入れ率」を乗じて仕入税額控除額を算出する仕組みだからです。つまり、仕入先が免税事業者であるか、あるいはインボイス発行事業者であるかどうかにかかわらず、簡易課税制度における納税額の計算ロジックは変わりません。
これは、仕入れの際に受け取った請求書に基づいて仕入税額控除を行う本則課税(一般課税)とは異なる点です。本則課税の場合は、インボイスの保存が仕入税額控除の要件となるため、免税事業者からの仕入れは原則として仕入税額控除の対象外となります(経過措置を除く)。
ただし、これはあくまで消費税の納税額計算上の話です。取引価格の交渉など、事業運営上の間接的な影響については別途考慮が必要となる場合があります。
まとめ
インボイス制度が始まった今も、簡易課税制度による「みなし仕入れ率」は引き続き利用できます。一方、2割特例は一定の要件を満たす小規模事業者にとって、事務負担を大幅に軽減できる魅力的な選択肢です。それぞれの制度にはメリット・注意点があるため、業種や売上規模、インボイス対応の有無を踏まえて、最適な制度を選ぶことが重要です。適切な制度選択と事前の届出を忘れずに行いましょう。










