消費税課税事業者選択届出書は不要?インボイスとの関係や書き方をわかりやすく解説!
更新日:2025.12.06
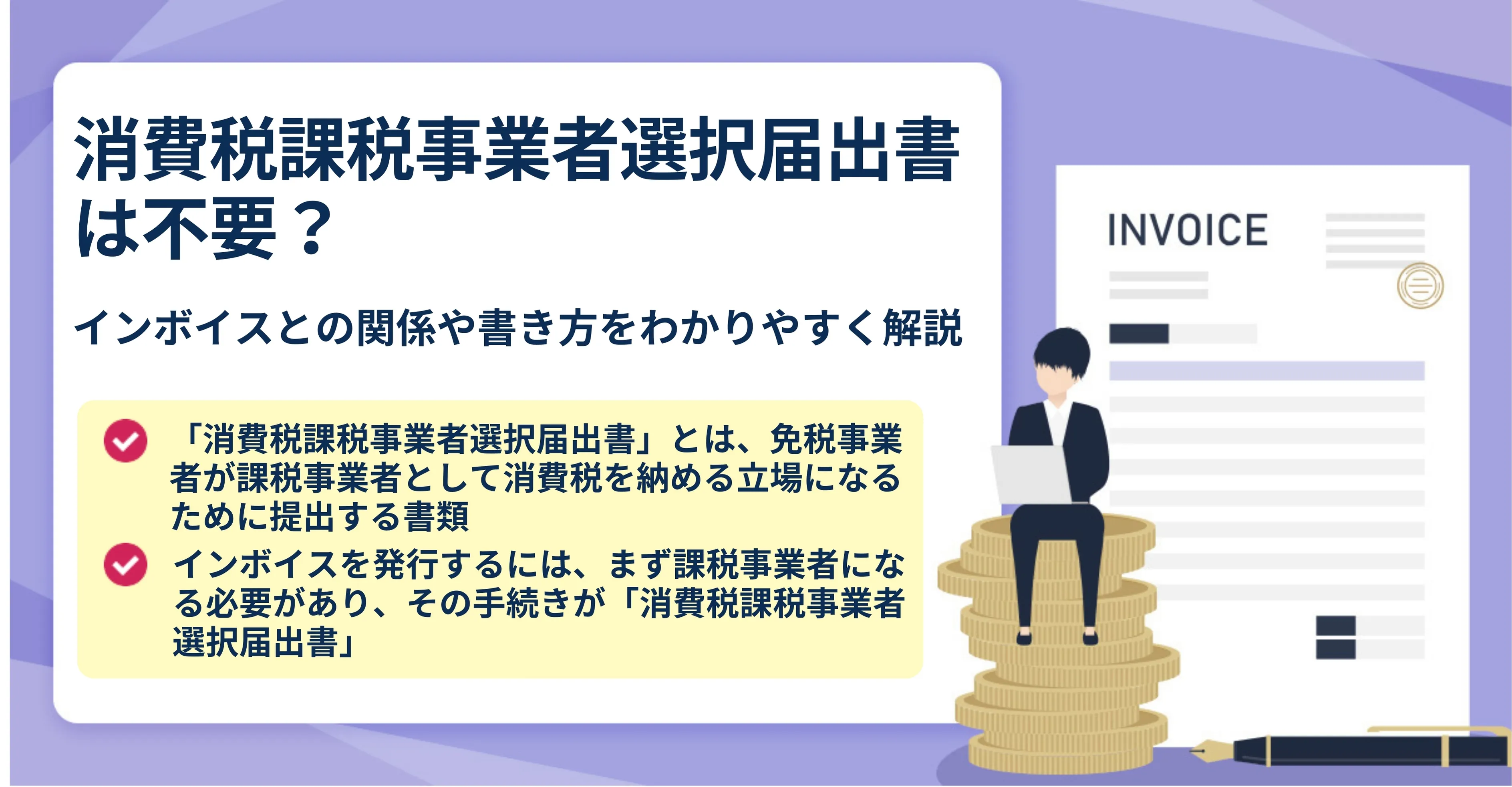
ー 目次 ー
インボイス制度の開始により、フリーランスや個人事業主、中小企業の間で「消費税課税事業者選択届出書」が必要かどうか悩む声が急増しています。この記事では、インボイス発行に届け出が必要なケースや提出時の注意点をわかりやすく解説。結論として、インボイスを発行したい免税事業者は届出書の提出が必須です。制度の全体像と、自社がどう対応すべきか判断できる知識が得られます。
消費税課税事業者選択届出書とは?
そもそも消費税課税事業者とは
「消費税課税事業者」とは、商品やサービスの販売等に対して消費税を課し、消費税の申告・納税を行う義務のある事業者を指します。通常、課税売上高が年間1,000万円を超える場合、翌々課税期間から自動的に課税事業者となります。一方、売上高が1,000万円以下の場合は、原則として「免税事業者」となり、消費税の計算・申告・納税義務はありません。
ただし、免税事業者であっても、任意で課税事業者になることが可能です。これにあたって所轄税務署に提出するのが「消費税課税事業者選択届出書」です。
届出書の提出が必要なケース
消費税課税事業者選択届出書は、次のような場面で提出が必要となります。
|
提出が必要なケース |
説明 |
|
課税売上高が1,000万円以下だが課税事業者になりたい |
本来免税事業者である場合でも、消費税の仕入税額控除の適用などの目的で、任意に課税事業者となる意思がある場合に提出が必要です。 |
|
インボイス発行事業者として登録を行う場合 |
免税事業者がインボイス(適格請求書)制度に対応するためには、本届出を通じて課税事業者になる必要があります。 |
|
資本金1,000万円未満の新設法人が初年度から課税事業者を選択する場合 |
原則免税である設立初年度においても、課税事業者としてキャッシュフロー改善や取引先対応を優先する際に提出します。 |
上記のようなケースでは、意識的に提出タイミングと要件を確認し、正しい届出をすることが求められます。
免税事業者との違い
免税事業者とは、原則として消費税の納税義務が免除されている事業者のことを指し、代表的には以下のような特徴があります。
|
項目 |
課税事業者 |
免税事業者 |
|
消費税の納税義務 |
あり |
なし(原則) |
|
インボイス発行の可否 |
可能(登録が必要) |
不可(インボイス制度導入後) |
|
仕入税額控除 |
可能 |
不可 |
|
帳簿・請求書の保存要件 |
あり |
緩やか |
免税事業者は一見、納税義務がないことから有利であるように思われがちですが、インボイス制度の開始により、取引先が課税事業者からの仕入れを優先する動きもあるため、状況次第では課税事業者になることが有利なケースも存在します。
このように、「消費税課税事業者選択届出書」は、特に免税事業者や新規事業者が「課税事業者」としての地位を選択する際に必須の届出書であり、インボイス制度との関連も非常に強い重要な書類です。
消費税課税事業者選択届出書とインボイス制度の関係!
インボイスを発行するために届出は必要か
インボイス制度(適格請求書等保存方式)は、2023年10月1日から施行された消費税制度の新たなルールで、仕入税額控除を受けるためには「適格請求書(インボイス)」の保存が必要となります。
インボイスを発行するためには、税務署に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、登録を受ける必要があります。しかし、免税事業者のままではこの登録ができず、まず「消費税課税事業者選択届出書」を提出し、課税事業者となる必要があります。
つまり、免税事業者がインボイスを発行したい場合、消費税課税事業者選択届出書の提出が前提条件となるのです。
届出書を出すことでどう変わる?
「消費税課税事業者選択届出書」を提出することで、事業者は免税事業者から課税事業者へと扱いが変更になります。これにより以下の点が変化します。
|
項目 |
免税事業者 |
課税事業者 |
|
消費税の納税義務 |
なし |
あり |
|
インボイス発行の可否 |
不可 |
可能(要登録) |
|
取引先の仕入税額控除 |
不可 |
可能 |
|
帳簿・請求書の整備義務 |
基本のみ |
記載要件の多い帳簿とインボイスが必要 |
特に取引先が仕入税額控除を適用したい場合、免税事業者との取引は敬遠されるケースもあります。そのため、課税事業者になりインボイスを発行可能にするメリットは大きいといえます。
課税売上高1000万円以下の場合の対応
課税売上高が1000万円以下の事業者は、原則として2年前の売上実績に基づき自動的に「免税事業者」となります。ただし、インボイス制度開始後は免税事業者であっても、取引先からインボイス発行を求められることが増えています。
そのため、課税売上高が1000万円を超えていなくても、次のような事業者は消費税課税事業者選択届出書の提出を検討すべきです。
- 取引先が法人や課税事業者で、インボイスが必要とされる業種(例:BtoBの業務委託)
- 顧客から仕入税額控除のためインボイスの発行を求められている
- 今後の事業拡大や信用の向上を目指している
ただし、一度課税事業者を選択すると、原則として2年間は免税事業者へ戻ることができません。この点には十分な注意と将来の見通しが必要です。
なお、2023年10月1日から2026年9月30日までの3年間は、免税事業者から登録したインボイス発行事業者に対して、一定の簡易課税に近い「特例」も用意されています。これは消費税の納税額を段階的に引き上げる制度で、急激な負担増を緩和するものです。
選択届出書を出すメリット・デメリットとは?
メリット:信頼性の向上や仕入税額控除
「消費税課税事業者選択届出書」を提出することで、消費税の課税事業者となり、インボイス制度上の「適格請求書発行事業者」としての登録が可能になります。これにより、以下のような主なメリットが得られます。
|
メリット |
内容 |
|
仕入税額控除の適用 |
課税仕入れにかかる消費税を、納付すべき消費税額から控除できるため、トータルの税負担が軽減されます。 |
|
取引継続の安心感 |
インボイス発行義務がある取引先(法人・課税事業者)に対し、安心して取引を継続でき、発注が減るリスクを回避できます。 |
|
信用力の向上 |
消費税を適正に管理・納税する事業者として、社会的信頼性が高まります。 |
|
経理管理体制の整備 |
帳簿やインボイスの作成・保存を徹底する必要があるため、事業全体の経理水準が向上します。 |
とくにBtoBビジネスを行っている免税事業者が、消費税課税事業者選択届出書を提出してインボイス発行事業者となることにより、取引先が仕入税額控除を継続できるという点は、今後の契約維持や受注確保という観点で非常に重要です。
デメリット:消費税納税義務の発生
一方で、届出書を提出して課税事業者になることには、無視できないデメリットも存在します。主なデメリットは以下の通りです。
|
デメリット |
内容 |
|
消費税の納税義務 |
売上にかかる消費税を計上・申告・納税する義務が発生し、納税額が増える可能性があります。 |
|
事務負担の増加 |
売上・仕入ごとの税区分管理、帳簿記載要件、インボイスの発行・保存など、税務上の手続きが複雑になります。 |
|
最低2年間の課税事業者継続義務 |
一度選択届出書を提出すると、少なくとも2年間の課税事業者としての義務が継続します。途中で変更はできません。 |
たとえば課税売上が少ない個人事業主などは、課税事業者になったことでかえって消費税を納める負担が増え、実質的に手取り収入が減少するケースもあります。特に課税対象外の取引が多い業種では慎重な判断が必要です。
どのような事業者に向いているか
消費税課税事業者選択届出書の提出は、すべての事業者にとって最適な選択とは限りません。以下のような特徴を持つ事業者には特に向いていると言えます。
|
向いている事業者 |
理由・特徴 |
|
BtoB取引が中心 |
取引先がインボイス発行を求めているため、登録しないと取引の継続が困難になる可能性がある |
|
仕入・経費が多い |
仕入税額控除により実質的な納税額を軽減できるため、届出のメリットが顕著になる |
|
将来的な売上拡大が見込まれる |
いずれ課税売上が1,000万円を超えることが予想される場合、あらかじめ制度に対応しておく方が手間が省ける |
|
補助金や融資を視野に入れている |
経営状況や税務管理が公的機関に評価されやすくなり、信用力アップにつながる |
反対に、顧客がほぼ消費税非課税の個人消費者(BtoC)である事業者や、年間の売上が少なく簡易的な経理体制で運営している個人事業主などは、課税事業者になることでかえって納税負担や事務コストが増す傾向にあります。
よって、消費税課税事業者選択届出書の提出を検討する際には、現在の取引先の属性、仕入構成、自社の売上規模や事業戦略を踏まえ、総合的に判断することが肝要です。加えて、届出後の2年間は原則として免税事業者への戻りができないため、短期的な事業変動も見越した検討が必要でしょう。
消費税課税事業者選択届出書の書き方・提出方法!
記載項目の具体的な説明
「消費税課税事業者選択届出書」は、消費税の課税事業者としての適用を開始するために税務署へ提出する書類です。令和5年10月から始まったインボイス制度に関連して提出するケースも多く、以下の各項目は正確に記載する必要があります。
国税庁が提供している様式に基づき、次のような項目を記入します。
|
項目 |
記入内容 |
|
納税地 |
個人事業主の場合は住所、法人の場合は本店所在地を記入します。 |
|
氏名または名称 |
個人事業主は氏名を、法人は商号(登記上の名称)を記入します。 |
|
屋号(法人は記載不要) |
個人で屋号を使っている場合は記入。 |
|
届出の提出日 |
記入日を西暦または元号で明記します。 |
|
課税事業者になる課税期間 |
例:「令和6年1月1日から開始する課税期間」など該当する開始日の属する課税期間を記載。 |
|
提出理由 |
インボイス制度の適格請求書発行事業者登録のためなど、理由を簡潔に記載します。 |
上記以外にも、「整理番号」「提出先税務署名」「電話番号」などの項目がありますが、基本的には税務署から送付される届出書には事前に印字されていることが多いため、記入漏れのないように注意しましょう。
提出先と提出期限
「消費税課税事業者選択届出書」は、納税地を所轄する税務署へ提出する必要があります。例えば、東京都渋谷区に事業所がある場合は「渋谷税務署」が提出先となります。
提出期限については、原則として「課税事業者になろうとする課税期間の初日の前日」までに提出しなければなりません。たとえば、令和6年1月1日から課税事業者になりたい場合は、「令和5年12月31日」までに届出書を提出する必要があります。
ただし、インボイス制度開始(令和5年10月1日)に伴い特例が認められるケースもあります。特例を受けたい場合は、別途「適格請求書発行事業者の登録申請書」の提出期限も確認しましょう。
電子申請(e-Tax)による提出方法
令和になってからは、紙の提出だけでなく「e-Tax(イータックス)」を利用してインターネット上から届出を提出する企業や個人事業主が増えています。特にマイナンバーカードや電子証明書を持っている方は、原則として電子提出が推奨されます。
e-Taxでの提出手順は以下のとおりです。
- e-Taxの利用開始手続き:利用者識別番号を取得し、電子証明書を登録します。
- 届出作成:e-Taxソフトや「確定申告書等作成コーナー」で、消費税課税事業者選択届出書を作成します。
- 署名・送信:電子署名を付けて税務署へ送信。正常に送信されると受付完了のメッセージが表示されます。
- 受信通知の保管:提出証明として受信通知を印刷または保存しておくことが重要です。
なお、電子提出を行った場合も、必要に応じて印刷した控えなどを確認できる状態にしておくことが推奨されます。
届出のタイミングと注意点
「消費税課税事業者選択届出書」は一度提出すると、原則として「2年間」は課税事業者としての状態が継続されます。安易に提出すると経費控除を差し引いたとしても、消費税の納税義務が発生し、キャッシュフローにマイナスの影響が出る可能性もあるため、慎重に判断することが大切です。
特に、次のような点には注意しましょう。
- 登録免税事業者がインボイス制度のために届出をする場合、経過措置として売上高1,000万円以下の事業者でも登録可能(令和5年10月1日〜令和11年9月30日までの間に限る)。
- 一度課税事業者を選択すると、原則として2年間は免税事業者に戻れない(特例を除く)。
- 期限後に届出をしても、当該課税期間には効力が及ばず、次の期間からの適用となる。
- インボイス制度対応の登録と混同しやすいが、届出書とは別に「適格請求書発行事業者の登録申請書」が必要。
提出の前には、税理士や税務署に相談し、適切なタイミングで提出ができるよう準備することが望ましいです。
個人事業主・フリーランスの場合の実務対応
インボイス制度への対応例
2023年10月にスタートしたインボイス制度(適格請求書等保存方式)は、個人事業主やフリーランスといった小規模事業者にも大きな影響を与えています。特に、これまで免税事業者であった場合、インボイスを発行できないため、取引先から仕入税額控除が受けられず、取引継続が困難になるケースもあります。
以下は、個人事業主・フリーランスが検討すべきインボイス制度への対応例です。
|
対応内容 |
概要 |
|
課税事業者となる |
「消費税課税事業者選択届出書」を提出し、課税事業者となることで、インボイス発行事業者の登録が可能になります。 |
|
適格請求書発行事業者の登録申請 |
「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、国税庁の登録を受ける必要があります。 |
|
価格設定の見直し |
消費税の納税義務が発生するため、取引金額に対する価格の見直しや契約内容の調整が必要になります。 |
|
会計処理体制の整備 |
消費税の申告・納付に対応できるよう、帳簿・請求書の管理や税理士との連携が重要になります。 |
届出するかどうかの判断ポイント
「消費税課税事業者選択届出書」を提出するか否かの判断は、個人事業主やフリーランスにとって非常に重要です。以下のポイントを踏まえて慎重に検討しましょう。
- 主要取引先がインボイスを求めているかどうか(特に法人取引先の場合)。
- 年間売上高(課税売上高)が1,000万円未満で、現在は免税事業者に該当しているか。
- 消費税の納税義務が経営に与える影響。
- 価格競争力の確保と継続的な取引のバランス。
たとえば、クライアントが法人で、今後も安定的に取引を続けたい場合は、インボイス発行事業者としての登録と、それに伴う課税事業者の選択が推奨されます。一方、取引先が主に一般消費者である場合は、無理に課税事業者になる必要はありません。
記帳や帳簿の整備との関連
消費税課税事業者としてインボイスを発行し、適正に消費税の納付を行うためには、帳簿の記載内容や記帳方法にも注意が必要です。特に、仕入税額控除を適用するためには、「帳簿保存要件」と「インボイス保存要件」の両方を満たさなければなりません。
帳簿には以下の項目を正確に記載する必要があります。
- 取引年月日
- 相手方の氏名または名称
- 取引の内容(品目、数量、単価など)
- 税率ごとの対価の額
- 消費税額
また、発行したインボイス(適格請求書)は電子的または紙で保存する義務があります。クラウド会計ソフトを活用することで、インボイス対応の請求書発行や帳簿管理がスムーズになります。
さらに、青色申告者である場合は、正確な記帳をもとに65万円の特別控除も適用可能です。消費税の対応とあわせて、所得税の節税効果も視野に入れて記帳体制の整備に取り組むことが大切です。
法人の場合の届出とインボイス対応
設立初年度の課税事業者選択
法人が新たに設立された場合、原則として設立初年度および翌年度は「免税事業者」となります。これは、設立時点では前々年の課税売上高が存在しないため、基準期間における売上高1,000万円未満という条件を自動的に満たすためです。しかし、適格請求書(インボイス)を発行するためには課税事業者として登録される必要があります。
そのため、設立初年度からインボイスを発行したい場合には、税務署に対して「消費税課税事業者選択届出書」を提出し、自ら課税事業者になる必要があります。加えて、「適格請求書発行事業者の登録申請書」も別途提出する必要があります。
届出のタイミングとしては、原則、その事業年度の開始日を含む課税期間の初日の前日までですが、インボイス制度への対応という観点では設立日から速やかに提出することが推奨されます。
既存法人のインボイス対策
すでに法人として事業を開始している場合には、自社がすでに課税事業者であるかどうかを確認するところから始まります。課税売上高が1,000万円を超えている場合は自動的に課税事業者ですが、それ未満の場合は免税事業者である可能性があります。
免税事業者のままではインボイスを発行できず、取引先が仕入税額控除を受けられないことから、業種や取引形態によっては、信頼を保つためにも課税事業者となり、インボイスを発行する必要が生じます。特にBtoB取引を行っている法人では、適格請求書発行事業者としての登録が急務となるケースが多いです。
以下は、既存法人がインボイス制度に対応するためのステップを整理した表です。
|
ステップ |
対応内容 |
関連する提出書類 |
|
1 |
自社が課税事業者か確認 |
不要(内部確認) |
|
2 |
免税事業者なら課税事業者になる決定 |
消費税課税事業者選択届出書 |
|
3 |
インボイス登録申請 |
適格請求書発行事業者の登録申請書 |
|
4 |
請求書・帳簿の様式変更 |
不要(業務フロー変更) |
|
5 |
会計ソフトの設定確認 |
不要(システム調整) |
グループ法人間取引での注意点
複数の法人を保有している企業グループにおいては、グループ間取引におけるインボイス対応も重要なポイントになります。たとえば、親会社が課税事業者でインボイス発行事業者となっていても、子会社が免税事業者でインボイスを発行できない場合、親会社がその仕入取引について仕入税額控除を受けられなくなるリスクが存在します。
このようなケースでは、グループ法人すべてが適格請求書発行事業者として登録しておくことが望まれます。また、法人ごとに個別の消費税申告と管理が必要になるため、経理・財務面での対応が求められます。
特に以下の点に注意が必要です。
- 子会社や関連会社間での役務提供・商品の移動についても課税対象となるケースがある
- 取引額が少額でもインボイスが発行されていないと仕入控除不可
- グループ間でのインボイス発行運用ルールの明文化が重要
また、適格請求書の発行主体が誤っていたり、登録番号が正しく表記されていなかったりすると、税務調査時に否認されるリスクがあるため、インボイスに記載すべき事項の確認や社内研修も必要不可欠です。
消費税課税事業者選択届出書のQ&A
不要ですか?というよくある誤解
「消費税課税事業者選択届出書はインボイス制度では絶対に必要」という認識は、必ずしも正確ではありません。インボイス(適格請求書)を発行したい場合には、まず「適格請求書発行事業者」の登録が必要ですが、登録の前提として消費税課税事業者であることが必要です。
つまり、元々免税事業者である場合、インボイスを発行する意志があるならば、まず「消費税課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者となる必要があります。この手続きを怠ると、たとえ「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出しても、登録は認められません。
一方、すでに課税事業者である法人や個人事業主であれば、改めて「選択届出書」を出す必要は基本的にありません。この点が「不要かどうか」に関するよくある誤解の原因になっています。
「課税事業者」と「インボイス発行事業者」の違いは?
しばしば混同されがちですが、「課税事業者」と「インボイス発行事業者」は別の概念です。下記の表で対比してみましょう。
|
用語 |
意味 |
要件 |
届け出書類 |
|
課税事業者 |
消費税を納める義務のある事業者 |
原則として課税売上高が1,000万円超、または届出による選択 |
消費税課税事業者選択届出書 など |
|
インボイス発行事業者 |
適格請求書を発行できる事業者 |
課税事業者であること・登録申請による登録番号の取得 |
適格請求書発行事業者の登録申請書 |
インボイス制度では、仕入税額控除の要件として、インボイス(適格請求書)の保存が必要です。そのため、取引先から「インボイスを発行してほしい」と言われた場合、インボイス発行事業者になっておくことが重要になります。
誤って申請した場合の対処方法は?
「消費税課税事業者選択届出書」を誤って提出してしまった場合でも、原則としてその撤回は簡単にはできません。一度選択届出書を提出すると、少なくとも2年間は課税事業者としての義務を負うことになります。これは「原則として提出年度の翌々年まで」課税事業者の取り消しができないという制限があるためです。
ただし、以下のような特別な事情がある場合には「消費税課税事業者選択不適用届出書」を提出することで撤回が可能な場合もあります。
- 事業廃止や法人の解散があった場合
- 設立初年度の会社で、届出提出日より前に売上が発生していないケース
しかしそれでも、原則として提出後の取り消しは極めて限定的であるため、提出前に自社の売上見込みや取引先との関係、自社のキャッシュフローへの影響を総合的に検討することが重要です。
一度提出するといつまで有効?
「消費税課税事業者選択届出書」に有効期限はなく、一度提出すると、原則として自動的に翌課税期間以降も課税事業者として取り扱われます。そのため、課税事業者である状況が長く続く可能性があります。
課税事業者から免税事業者に戻るには、「消費税課税事業者選択不適用届出書」を提出しなければなりません。この不適用届出書は、提出日が属する課税期間の翌課税期間から有効となります。つまり、実務上は最低でも1年単位での運用変更になる点に注意が必要です。
消費税課税事業者選択届出書と課税期間の開始時点はどう関係する?
「消費税課税事業者選択届出書」は、提出した課税期間の開始日から適用されます。ただし、その適用には提出期限があるため注意が必要です。
新規開業者(個人・法人)の場合、設立後最初の課税期間から課税事業者になりたいのであれば、原則としてその課税期間の開始の日までに提出する必要があります。つまり、法人であれば設立日、個人事業主であれば開業日の日付が基準です。
既存事業者が途中から課税事業者になるには、原則として「適用させたい課税期間が始まる日の前日まで」に届出が必要です。提出時期が遅れると、その課税期間には間に合わず、次期以降の課税期間からの適用になってしまうため、インボイス対応の事前準備を含め、スケジュール管理が重要です。
インボイス登録申請との関係性でよくある失敗例とは?
消費税課税事業者選択届出書と同時に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出するケースで、以下のような失敗がよくあります。
- インボイス発行事業者の登録申請書のみ提出して、選択届出書を忘れる
- 選択届出書を税務署に郵送したが、インボイス登録申請をe-Taxで行ったため、申請データが紐付かず登録が遅延する
- インボイス制度の開始直前に慌てて提出し、審査が間に合わず登録番号の発行が遅れた
これらのトラブルを回避するためには、以下の対応が有効です。
- 事前にすべての提出書類をリストアップする
- e-Taxを利用する場合は、同一アカウント・同日中にすべての関連届出を行う
- 税理士と相談して、自社のフローに応じてタイミングを調整する
消費税課税事業者選択届出書はどこで手に入れられる?
「消費税課税事業者選択届出書」は、国税庁の公式サイトからPDF形式でダウンロード可能です。また、税務署の窓口でも紙の届出書を配布しています。
電子申請の場合は、e-Taxを利用してオンライン提出が可能です。e-TaxのWeb版やWindows版ソフトを利用して、自宅や事務所のパソコンから届出を行うことができます。
届出書の最新版を必ず確認し、旧様式を使用しないよう注意しましょう。様式が変わることもあるため、複数年度にわたって継続して申請を行う場合には、毎回最新の様式を印刷・確認することが大切です。
まとめ
インボイス制度に対応するには、課税事業者であることが前提であり、そのためには「消費税課税事業者選択届出書」の提出が必要です。免税事業者のままではインボイスを発行できず、取引先からの仕入税額控除が認められないことがあります。届出のメリット・デメリットを正しく理解し、自社の事業形態や今後の取引先の動向を見据えて、適切な判断を下すことが重要です。
>









