香典は経費扱い?インボイス制度との関係や勘定科目の書き方解説!
更新日:2025.12.21
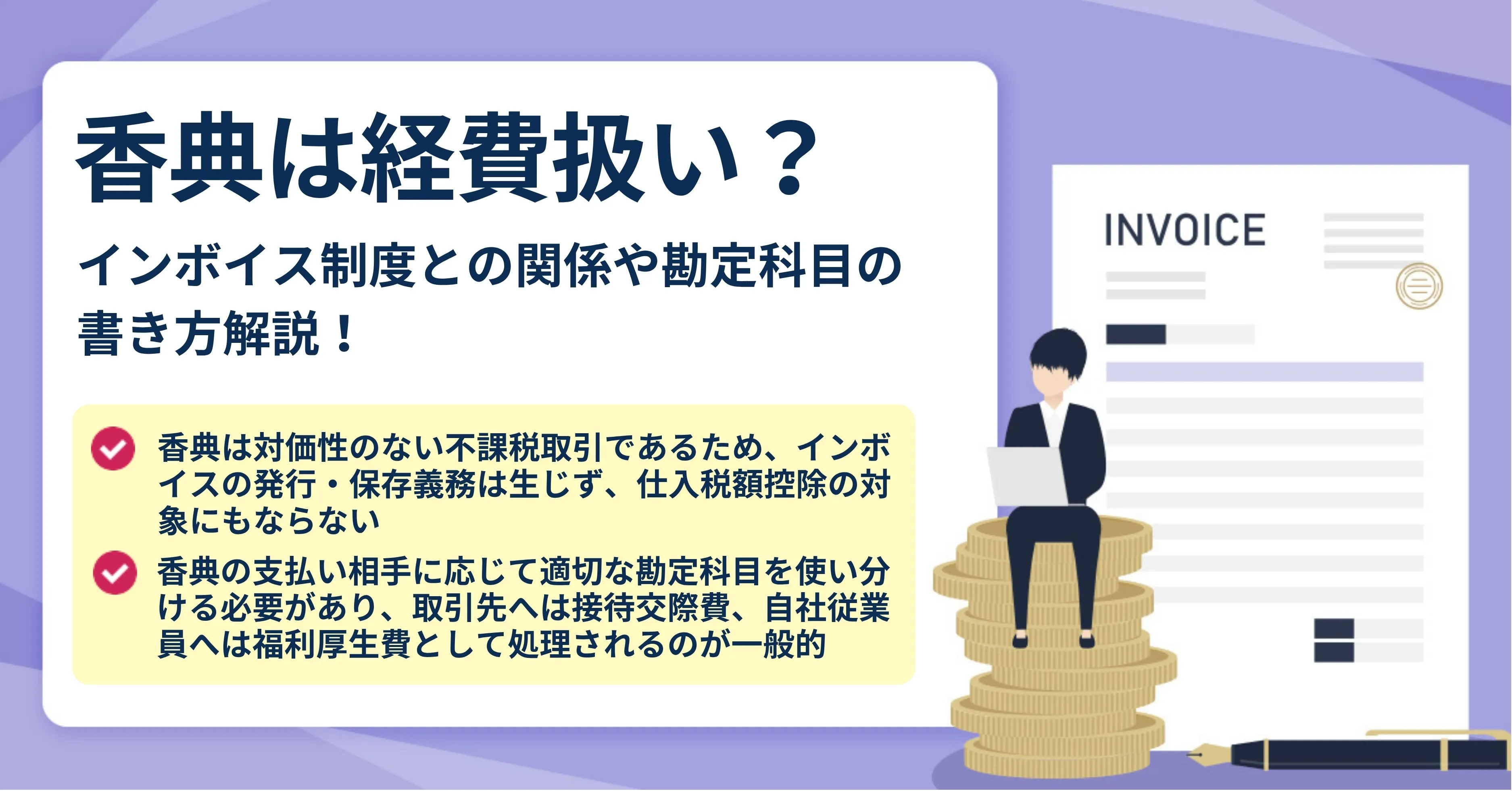
ー 目次 ー
香典に関する経理処理で、「これって経費にしていいの?」「インボイスって必要なの?」と悩まれたことはありませんか?この記事では、香典をめぐる経費処理の基本から、インボイス制度との関係、勘定科目の選び方まで、事例を交えて丁寧に解説いたします。経理担当者や個人事業主の方にも役立つ内容をまとめていますので、ぜひ最後までご覧ください。
香典は経費にできる?基本ルールを確認しよう
事業を運営する上で、取引先や従業員関係で香典を支出する機会は少なくありません。この章では、まず香典が経費計上できるかの基本的な考え方と、インボイス制度の概要について解説します。
そもそも香典とは?経費になる可能性のある支出かを整理
香典とは、故人の霊前にお供えする金品のことを指し、一般的には葬儀の際に遺族に対して贈られます。
事業者が支出する香典が経費として認められるかどうかは、その支出が事業遂行上必要であるかどうかが大きな判断基準となります。具体的には、以下のようなケースで支出される香典は、経費として計上できる可能性があります。
- 取引先の役員や従業員、またはその家族の葬儀に際して支出する香典
- 自社の従業員やその家族の葬儀に際して支出する香典
ただし、高額すぎる香典は、経費として認められない場合があるため注意が必要です。
インボイス制度とは?わかりやすく解説
インボイス制度(正式名称:適格請求書等保存方式)は、2023年10月1日から開始された消費税の仕入税額控除に関する新しい制度です。この制度の導入により、事業者が消費税の仕入税額控除を受けるためには、原則として「適格請求書(インボイス)」の保存が必要となりました。
インボイス制度の主なポイントは以下の通りです。
|
項目 |
内容 |
|
制度の正式名称 |
適格請求書等保存方式 |
|
開始日 |
2023年10月1日 |
|
主な目的 |
複数税率(標準税率10%、軽減税率8%)に対応した消費税の仕入税額控除の適正化 |
|
仕入税額控除の要件 |
原則として、適格請求書発行事業者から交付された適格請求書(インボイス)の保存が必要 |
|
適格請求書(インボイス)とは |
売手が買手に対して正確な適用税率や消費税額等を伝えるための請求書や領収書など。記載要件が定められている。 |
|
適格請求書発行事業者とは |
税務署長の登録を受けた課税事業者。登録を受けると登録番号が通知される。 |
このインボイス制度は、課税取引を伴う多くの取引に影響を与えますが、香典のような性質の支出がどのように扱われるのかについては、後の章で詳しく解説します。
香典とインボイス制度の関係を徹底解説!
2023年10月1日から開始されたインボイス制度(適格請求書等保存方式)は、多くの事業者にとって経理処理の変更を迫るものです。では、日本の慣習として深く根付いている「香典」の扱いは、このインボイス制度によって何か影響を受けるのでしょうか。この章では、香典とインボイス制度の具体的な関係性について、支払う側・受け取る側の両面から詳しく解説します。
香典は非課税?仕入税額控除はどうなるのか
香典は、事業上の取引における対価として支払われるものではありません。そのため、消費税法上、香典のやり取りは原則として「不課税取引」に該当します。不課税取引とは、消費税の課税対象とならない取引のことです。
インボイス制度は、消費税の仕入税額控除の適正化を目的とした制度です。したがって、そもそも消費税が課されない不課税取引である香典については、インボイス(適格請求書)の保存は不要です。支払った香典について、仕入税額控除を受けることもできません。
ただし、香典を経費として計上する場合には、その支出を証明するための書類(例:会葬御礼状、香典袋のコピー、出金伝票など)の保存は引き続き重要です。これはインボイス制度の導入有無にかかわらず、税務上の基本的な要請となります。
ここで注意が必要なのは、葬儀に関連する支出であっても、例えば葬儀社へ支払う供花代や枕花代、斎場利用料などは、役務の提供に対する対価として課税取引に該当するケースが一般的です。これらの費用について仕入税額控除を受けたい場合は、取引先である葬儀社などが適格請求書発行事業者であれば、インボイスの受領と保存が必要になります。香典そのものとは扱いが異なる点を理解しておきましょう。
香典を受け取った側のインボイス対応
香典を受け取った側(故人の遺族や喪家など)は、インボイスを発行する必要があるのでしょうか。結論から言うと、香典の受領に対してインボイスを発行する義務はありません。
前述の通り、香典は対価性のある取引ではないため、受け取った側が個人であるか、法人や個人事業主であるかを問わず、インボイスの発行は不要です。例えば、会社の代表者の親族が亡くなり、会社として取引先などから香典を受け取った場合でも、それは事業上の売上ではなく贈与と同様の扱いとなり、消費税の課税対象外です。
また、香典返しについても、一般的には返礼品としての性格が強く、事業として対価を得て行う取引とはみなされないため、インボイスの発行は通常必要ありません。
インボイス制度は、あくまで課税事業者が行う課税取引に関して、インボイスの交付や保存を求めるものです。香典のような不課税取引や、対価性のない贈答については、インボイスのやり取りは発生しないと覚えておきましょう。
香典の支払いと受領におけるインボイス対応のポイントをまとめると以下のようになります。
|
項目 |
香典を支払った側の対応 |
香典を受け取った側の対応 |
|
消費税の区分 |
不課税取引 |
不課税取引 |
|
インボイス(適格請求書)の要否 |
不要(受領義務なし) |
不要(発行義務なし) |
|
仕入税額控除 |
対象外 |
対象外(売上ではないため) |
|
経費計上時の証拠書類 |
会葬御礼状、香典袋のコピー、出金伝票などを保存 |
特になし(インボイス制度の観点では) |
【ケース別】香典に最適な勘定科目とは?
香典を経費として計上する際、どの勘定科目を使用するかは非常に重要です。支払う相手や状況によって適切な勘定科目が異なります。ここでは、法人と個人事業主のケース別に、香典に最適な勘定科目を詳しく解説します。
接待交際費?福利厚生費?香典の勘定科目の扱い
法人が香典を支払う場合、主に「接待交際費」または「福利厚生費」のいずれかの勘定科目で処理します。どちらの科目を選択するかは、香典を渡す相手が誰であるかによって判断されます。誤った勘定科目で処理すると、税務調査で指摘を受ける可能性もあるため、正しく理解しておきましょう。
取引先関係者の葬儀への香典・供花代などは接待交際費
取引先の役員や従業員、またはその親族の葬儀に際して香典を支出した場合、その費用は「接待交際費」として計上するのが一般的です。これは、事業を円滑に進めるための社会的なお付き合いの一環と考えられるためです。香典だけでなく、供花代や弔電代なども同様に接待交際費として扱われます。
接待交際費は、得意先や仕入先その他事業に関係のある者などに対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用を指します。法人の場合、資本金の額や所得金額によっては損金算入できる上限額が定められている点に注意が必要です。
従業員やその親族への香典の勘定科目は福利厚生費!
自社の従業員やその親族(配偶者、子、父母など)が亡くなった際に会社から支出する香典は、「福利厚生費」として処理します。これは、従業員の福利厚生を目的とした支出とみなされるためです。多くの企業では、慶弔見舞金規程などを設けており、その規程に基づいて支給されます。
福利厚生費として計上するためには、全従業員を対象とした公平な基準で支給されることが求められます。特定の役員だけが高額な慶弔金を受け取るような場合は、給与として扱われる可能性もありますので注意が必要です。
法人が支払う香典の主な勘定科目をまとめると以下のようになります。
|
支払先 |
勘定科目 |
具体例 |
|
取引先の役員、従業員、その親族など |
接待交際費 |
株式会社ABC商事 代表取締役 山田太郎様 御母堂様 葬儀御香典 |
|
自社の従業員、その親族 |
福利厚生費 |
従業員 鈴木一郎様 御尊父様 葬儀御香典 |
個人事業主が香典を支払った場合の勘定科目
個人事業主が香典を支払った場合も、経費として計上できるケースがあります。事業に関連する支出であれば、法人の場合と同様に「接待交際費」として処理することが一般的です。例えば、主要な取引先の社長や担当者の葬儀に参列し香典を渡した場合などが該当します。
ただし、事業とは無関係の友人や知人、親族への香典は、家事按分できるものではなくプライベートな支出とみなされ、事業の経費として計上することはできません。この場合は「事業主貸」として処理します。事業関連性が曖昧な場合は、税務署に経費として認められないリスクもあるため、慎重な判断が必要です。金額が少額で、事業関連の支出と明確に言える場合は「雑費」として処理することも考えられますが、基本的には接待交際費が適切でしょう。
個人事業主が支払う香典の勘定科目の考え方は以下の通りです。
|
支払先 |
勘定科目 |
備考 |
|
取引先(事業遂行上必要な場合) |
接待交際費 |
事業の円滑な運営のため |
|
事業関連の知人(事業遂行上必要な場合) |
接待交際費 または 雑費 |
金額や関係性により判断 |
|
友人、親族(プライベートな関係) |
経費計上不可(事業主貸) |
事業とは無関係の支出 |
個人事業主の場合、法人と異なり接待交際費の損金算入上限は設けられていませんが、あまりに高額な香典は、経費として認められない可能性があるため注意しましょう。
【ケース別】香典の勘定科目の正しい書き方ガイド
香典を経費として計上する際の仕訳は、支払う側(法人か個人事業主か)や、香典を渡す相手によって使用する勘定科目が異なります。ここでは具体的なケース別に、正しい勘定科目と仕訳の書き方を解説します。
法人が取引先に香典を支払った場合の仕訳
法人が事業に関連する取引先の役員や従業員、またはそのご家族の葬儀に際して香典を支払った場合、勘定科目は一般的に「接待交際費」として処理します。供花や弔電なども同様です。
例えば、取引先である株式会社Aの社長のご葬儀に際し、香典として現金10,000円を支出した場合の仕訳は以下のようになります。
|
借方勘定科目 |
借方金額 |
貸方勘定科目 |
貸方金額 |
摘要 |
|
接待交際費 |
10,000 |
現金 |
10,000 |
株式会社A 社長 葬儀 香典 |
摘要欄には、誰の葬儀で、どのような名目で支払ったのかを具体的に記載しておくと、後で見返した際に分かりやすくなります。
法人が従業員に香典を支払った場合の仕訳
法人が自社の従業員やそのご家族の不幸に際して、社内規定などに基づいて香典(慶弔見舞金)を支払った場合、「福利厚生費」として経費計上するのが一般的です。
例えば、従業員Bさんのご家族(例:従業員の父)のご葬儀に際し、社内規定に基づき香典として現金10,000円を支出した場合の仕訳は以下の通りです。
|
借方勘定科目 |
借方金額 |
貸方勘定科目 |
貸方金額 |
摘要 |
|
福利厚生費 |
10,000 |
現金 |
10,000 |
従業員B氏 ご令尊 葬儀 香典 |
従業員への香典は、全従業員を対象とした慶弔見舞金規程に基づいて支給されるものであれば、給与として課税されることはありません。
個人事業主が香典を支払った場合の仕訳
個人事業主が香典を支払った場合も、事業に関連する支出であれば経費として計上できます。勘定科目の考え方は法人と同様で、取引先への香典は「接待交際費」、事業専従者を含む従業員への香典は「福利厚生費」として処理するのが一般的です。
ただし、個人事業主の場合、事業主自身や生計を同一にする親族への香典は、原則として経費に算入できません。これらは家事費(プライベートな支出)とみなされるため注意が必要です。
取引先への香典の例:
取引先であるCデザイン事務所の代表のご葬儀に際し、香典として現金5,000円を支出した場合
|
借方勘定科目 |
借方金額 |
貸方勘定科目 |
貸方金額 |
摘要 |
|
接待交際費 |
5,000 |
現金 |
5,000 |
Cデザイン事務所 代表 葬儀 香典 |
従業員(事業専従者)への香典の例:
事業専従者であるDさんのご家族の葬儀に際し、香典として現金5,000円を支出した場合
|
借方勘定科目 |
借方金額 |
貸方勘定科目 |
貸方金額 |
摘要 |
|
福利厚生費 |
5,000 |
現金 |
5,000 |
事業専従者D氏 ご家族 葬儀 香典 |
個人事業主の場合、家事費との区別を明確にするためにも、帳簿への記録や関連書類の保管をより一層丁寧に行うことが重要です。
香典を経費計上する際のインボイス対応の注意点
香典を経費として処理する際には、インボイス制度の導入に伴いいくつかの留意点があります。適格請求書(インボイス)が発行されない香典の取り扱いを正しく理解し、適切に処理することが求められます。
香典袋や会葬御礼状の保管の重要性
香典は、商品の販売やサービスの提供といった対価性のある取引ではないため、消費税の課税対象外(不課税取引)となります。したがって、香典を支払った側は、インボイス制度における適格請求書(インボイス)を受領することができません。
しかし、法人税法や所得税法上、経費として計上するためには、その支出の事実を証明する書類の保存が不可欠です。インボイスがない場合でも、以下の書類を整理・保管し、帳簿にも取引内容を正確に記載しておく必要があります。
- 香典袋のコピーまたはスキャンデータ(支払先の氏名・名称、支払年月日、金額が確認できるもの)
- 会葬御礼状
- 訃報(新聞のお悔やみ欄のコピーなど)
- 葬儀の案内状
これらの書類は、税務調査が行われた際に、支出の正当性を裏付ける重要な証拠となります。帳簿には、以下の情報を記載することが一般的です。
|
記載項目 |
記載内容の例 |
|
取引年月日 |
香典を支払った日付 |
|
相手方の氏名または名称 |
故人の氏名、または葬儀の喪主名、会社名など |
|
取引内容(摘要) |
「〇〇様 香典代」「〇〇株式会社 △△様 御香典」など |
|
支払金額 |
実際に支払った香典の金額 |
インボイス制度では、3万円未満の公共交通機関による旅客の運送など、一定の取引については帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる特例がありますが、香典の支払いはこれには該当しません。ただし、前述の通り香典は不課税取引であるため、仕入税額控除の対象とはなりません。経費計上にあたっては、あくまで法人税法や所得税法上の損金または必要経費として認められるための証拠書類の保管が重要となります。
社会通念上相当な金額であること
香典を経費として計上する場合、その金額が社会通念上相当と認められる範囲内であることが重要です。社会一般の常識から逸脱するほど高額な香典は、税務調査において経費として認められず、否認されるリスクがあります。
「社会通念上相当な金額」について、法律で明確な基準額が定められているわけではありません。一般的には、以下の要素を総合的に考慮して判断されます。
- 自社と相手方(故人やその企業・遺族)との関係性(重要な取引先、一般的な取引先、従業員、従業員の家族など)
- 自社の事業規模や慶弔に関する社内規定の有無と内容
- 地域的な慣習や相場
- 過去の同様のケースにおける支出実績
例えば、長年にわたり主要な取引関係にある企業の代表者が亡くなった場合と、社員の遠縁の親族が亡くなった場合とでは、香典として支出する金額が異なるのは自然なことです。「接待交際費」または「福利厚生費」として処理されますが、いずれの勘定科目で処理するにしても、その金額の妥当性が問われます。
過度に高額な香典を支出した場合、その全額または一部が接待交際費の損金算入限度額を超過する部分として扱われたり、場合によっては寄付金として認定されたり、あるいは役員や従業員に対する賞与(給与)とみなされたりする可能性も否定できません。
これらの注意点を踏まえ、香典の経費計上においては適切な会計処理と証拠書類の確実な保存を心掛けることが、税務上のリスクを低減し、円滑な企業経営につながります。
香典を経費にするための"証明"や保存書類
香典袋・御礼状・案内状などの保管のしかた
香典を交際費として経費処理するには、「香典を誰に・なぜ渡したのか」を明確にする証拠書類の保管が重要です。 具体的には、香典袋(表書き付き)、通夜や葬儀の案内状、会葬礼状、訃報の通知メールなどを、支出の根拠資料として保管しておくことが推奨されます。
領収書の代替資料として認められるケースも多く、葬儀との関係性や、贈った相手が取引先であることを示すうえでも重要な証拠となります。 香典袋は中袋も含めて残し、支出日・金額・渡した人物の名前などをメモしておくと、後日の確認にも役立ちます。
領収書が出ない場合にどう対応するか
香典に関しては、基本的に領収書は発行されません。 そのため、帳簿に記載するだけではなく、社内で「香典支出報告書」や「支出理由書」などの内部資料を作成し、支出の事実とその目的を説明できるようにするのが望ましい対応です。
また、香典を包んだ相手との関係性(取引先、得意先、元従業員など)を明記し、誰の葬儀だったのか、金額はいくらか、支出者は誰か、会社の業務とどう関係しているかまで、できる限り具体的に記録しておきましょう。 これにより、税務署から否認されるリスクを大幅に減らすことができます。
さらに、現金で支払った場合には、支出時の出金伝票も残しておくと、実務的には非常に安心です。 香典は「証憑が揃わない支出」になりやすいため、事後的な立証責任を見越した記録・保存体制を整えておくことが経理上のリスク回避につながります。
まとめ
香典の経理処理は、「相手が誰か」「どのような目的か」によって、使う勘定科目や対応が変わってきます。インボイス制度が始まった今でも、香典は原則としてインボイス不要で経費にできますが、証拠書類の保存や金額の妥当性には十分注意が必要です。
本記事を通じて、皆さまの実務が少しでもスムーズになれば幸いです。










