開業届とインボイスの登録は同日OK!申請スケジュールと手続きの流れを解説
更新日:2025.12.06
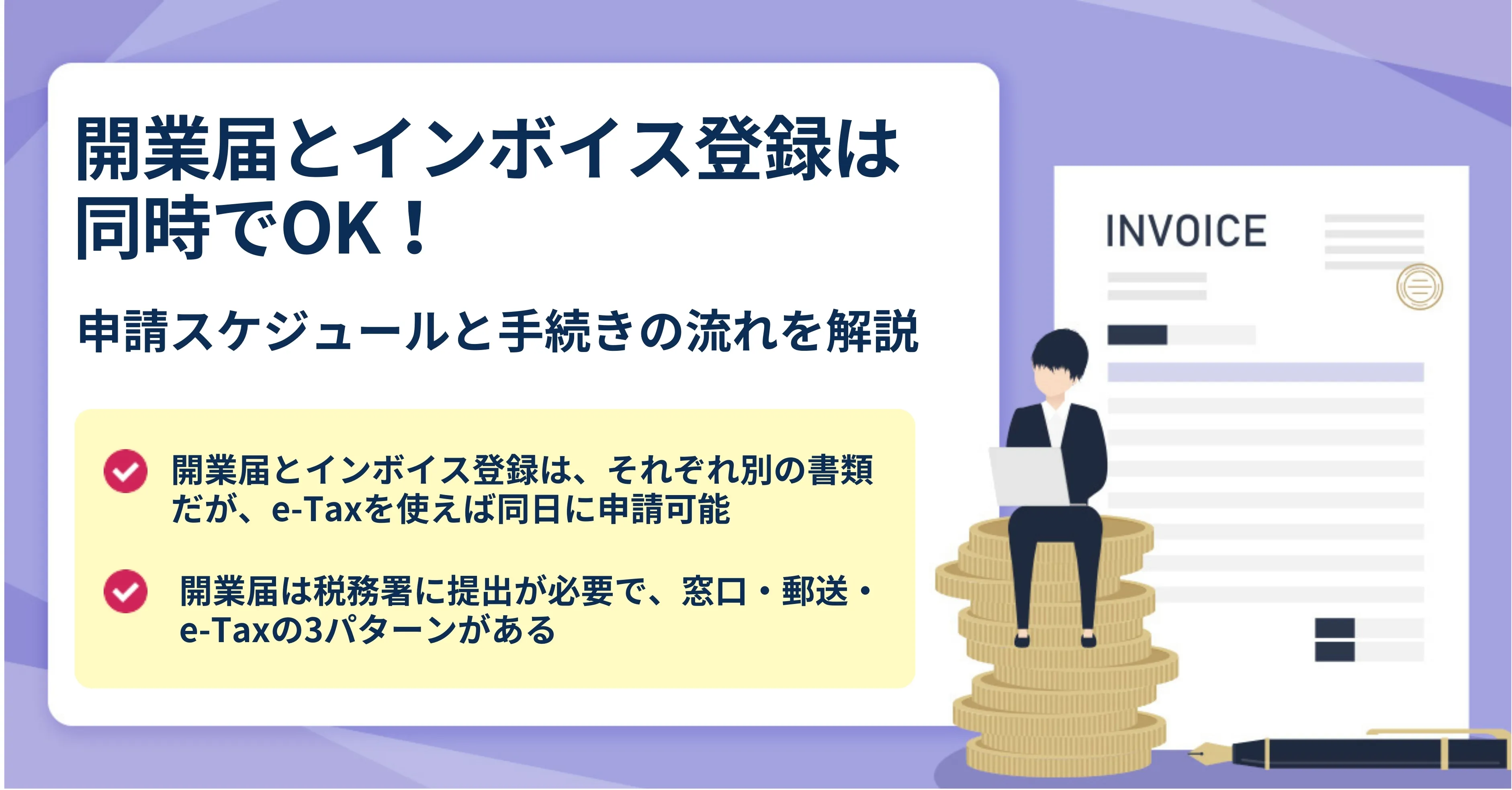
ー 目次 ー
「インボイス制度に登録したいが、開業届はいつ出せばいい?」「同日に申請できるの?」といった疑問を持つ方向けに、この記事では開業届とインボイス制度の基礎知識から、提出順序・方法・スケジュールまでを網羅的に解説します。結論として、開業届とインボイス登録はe-Taxを活用すれば同日申請が可能です。
開業届とインボイス制度の基本を理解しよう
開業届とは何か
開業届とは、正式名称を「個人事業の開業・廃業等届出書」といい、個人事業を始める際に税務署へ提出する書類のことです。これは、所得税法第229条に基づくもので、納税地の税務署長に提出する義務があります。提出することで、税務署がその人が事業を開始したことを把握し、青色申告の申請やインボイス制度の登録手続きなど今後の税務手続きにもスムーズに対応できるようになります。
開業届の提出期限は、原則として事業を開始した日から1ヶ月以内とされています。また、開業届を提出することで屋号を登録できたり、青色申告の承認申請書と一緒に提出することで65万円または55万円の特別控除が受けられたりといったメリットがあります。なお、確定申告の際にも提出済の開業届があると手続きが容易になります。
インボイス制度の概要
インボイス制度とは、消費税の適正な課税と仕入税額控除の制度を整えるために導入された仕組みで、正式には「適格請求書等保存方式」と呼ばれます。2023年10月1日から施行され、消費税の課税事業者が特定の要件を満たした適格請求書(いわゆるインボイス)を交付・保存することが求められるようになりました。
インボイスは、以下の事項が記載されている請求書や納品書を指します。
|
必要記載事項 |
内容 |
|
① 適格請求書発行事業者の氏名・名称及び登録番号 |
国税庁に登録された番号が必要 |
|
② 取引年月日 |
商品やサービスを提供した日付 |
|
③ 取引内容(軽減税率対象かどうかを含む) |
商品やサービスの具体的な内容 |
|
④ 税抜価額または税込価額と適用税率 |
税率ごとに区分した金額と税率(10%・8%) |
|
⑤ 消費税額等 |
税率ごとに差し引かれた消費税額 |
|
⑥ 取引先の氏名・名称 |
顧客の法的名称や屋号 |
この制度に対応するためには、課税事業者が「適格請求書発行事業者」として国税庁に登録する必要があります。この登録が完了すると、自社のインボイスを交付することで取引先が仕入税額控除を行えるようになります。
2023年10月スタートのインボイス制度の背景
インボイス制度の導入は、今までの「帳簿及び請求書等保存方式」による仕入税額控除方式に代わる新しい仕組みとして策定されました。その背景には、消費税の中立性を担保し、仕入税額控除の適用を適正化する目的があります。
従来は、いわゆる免税事業者(課税売上が年間1,000万円以下)の請求書でも、課税事業者である支払側が仕入税額控除をできるようになっていました。しかし、免税事業者からの請求書では消費税が実際に納められていないことから、制度として不公平との指摘がありました。
そこで、消費税を納めていない免税事業者からの取引については仕入税額控除を認めなくするための制度が必要となり、インボイス制度が導入されました。これにより、課税事業者である取引先が仕入税額控除を行うには、インボイス(適格請求書)を受け取ることが必要となるのです。
また、免税事業者も取引先の要望や経済的合理性から、インボイス発行事業者として登録を選択するケースが増えています。これにより実質的に消費税の納税義務が生じることになるため、制度対応には慎重な検討が必要とされています。
開業届とインボイス登録の関係性とは?
個人事業主がインボイス登録するには開業届が必要!
インボイス制度(適格請求書等保存方式)に登録するには、事業者であることが前提条件となります。つまり、インボイス登録を希望する個人が「正式に事業を開始している」と国税庁に認められていなければならず、その証明手段が「開業届」です。
税務署に提出する「個人事業の開業・廃業等届出書」は、事業を開始したことを証明する公式な書類であり、開業届を提出していない場合、適格請求書発行事業者(いわゆるインボイス発行事業者)として登録を受けることができません。
また、開業届と同時に所得税の青色申告承認申請書を提出すれば、節税効果の高い青色申告の適用も可能になるため、インボイス登録とあわせて税務上の管理も一体的に進めることが望ましいです。
開業届を出していない場合の注意点
開業届を出していない状態では、事業としての法的な登録が整っておらず、インボイス制度への参加が認められません。これは、免税事業者であっても同様であり、インボイス制度に参加するためには、課税事業者でなければならないことが原則です。
また、以下のような注意点も考慮する必要があります。
- 開業届の提出がないと確定申告の際に事業所得として認められない場合がある
- 青色申告や各種控除の適用を受けられない
- 税務署側の把握が遅れ、後から是正を求められるリスクがある
事業を開始してから遅れて開業届を提出することは可能ですが、インボイス制度の登録審査過程で開業状況が不明確だと判断される恐れがある点に注意が必要です。
開業届と適格請求書発行事業者登録の連携
インボイス制度は2023年10月に開始され、多くの個人事業主にとって、取引先がインボイス制度に参加していれば自身も登録を求められる実務上の影響があります。この制度下では、開業届を提出して個人事業主となったうえで、適格請求書発行事業者として登録申請する必要があります。
下記の表に、両者の制度的連携と登録の流れを示します。
|
手続き項目 |
提出書類 |
提出先 |
備考 |
|
事業の開始 |
個人事業の開業・廃業等届出書 |
納税地を管轄する税務署 |
原則、開始日から1か月以内に提出 |
|
インボイス登録 |
適格請求書発行事業者の登録申請書 |
国税庁 |
登録には開業届の提出済が求められる |
これにより、「事業としての存在」を開業届で証明し、そのうえで「インボイス発行を希望する旨」を別途専用の登録申請書で提出する、という2段階のプロセスが基本となります。
先に開業届を提出する必要性と理由
インボイス登録をスムーズかつ確実に行うためにも、まずは開業届を提出すべきです。その理由は以下のとおりです。
- インボイス登録申請時に「事業者としての実態」が求められる
- 税務署が申請者を事業者として認識していない状態では審査が進まない
- 電子申請(e-Tax)においても、基礎情報として開業届の内容が紐づけられる
たとえば、e-Taxを利用してオンライン申請する場合、開業届に記載された内容とインボイス登録申請書の情報が合致していないと、審査の過程で確認を求められることがあり、登録完了までに時間を要します。
したがって、開業届を先に提出し、税務署側に事業者としての登録情報が届いたことを確認したうえで、インボイス登録に進むのがもっとも効率的な進め方です。
申請手続きの具体的なスケジュール!
開業予定日から逆算したスケジュール例
個人事業主としての開業にあたり、開業届とインボイス制度(適格請求書発行事業者)の登録申請には、一定の準備期間と提出スケジュールの把握が重要です。開業日を基準にスケジュールを逆算し、余裕を持って手続きを行うことが、スムーズな事業開始につながります。
以下は、開業予定日を「7月1日」とした場合の提出スケジュールの一例です。
|
時期 |
必要な手続き |
備考 |
|
〜5月上旬 |
開業準備(事業計画、業種確認、屋号決定など) |
インボイス制度に登録するには課税事業者選択届出書が必要になる場合があります |
|
5月中旬 |
開業届作成 |
税務署の窓口またはe-Taxで作成可 |
|
5月下旬 |
開業届提出 |
郵送 or e-Taxで提出。消印が提出日となる |
|
6月上旬 |
インボイス登録申請 |
「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出 |
|
6月下旬 |
税務署より登録完了通知 |
e-Taxの場合、メッセージボックスに届く |
|
7月1日 |
事業開始(開業日) |
適格請求書(インボイス)の発行が可能に |
郵送で提出する場合の注意点と所要日数
開業届およびインボイス登録申請書の提出は郵送でも可能ですが、処理に時間がかかるため、余裕を持ったスケジュールで行うべきです。税務署の処理には通常、2週間から3週間程度を要します。
郵送の際の注意点は以下の通りです。
- 提出書類は控えの写しも同封し、自分用に保管すること
- 返信用封筒(宛先記入・切手貼付)を忘れず同封
- 提出日はすべて「消印日」が基準となる
- 開業届と登録申請書はそれぞれ宛先が異なる場合があるため確認
特に、インボイスの登録を特定の期日までに間に合わせたい場合、提出日は厳守する必要があります。郵送では時間の読めない要素もあるため、e-Taxの利用も検討しましょう。
税務署への確認タイミング
申請書を提出したあと、登録が遅れている、または届いていないといったトラブルを防ぐために、適切なタイミングで税務署に確認を取ることが推奨されます。確認のタイミングは以下のとおりです。
- 提出後2週間以内:郵送・窓口の場合、確認は控えたほうが無難
- 提出後3週間経過:税務署へ電話確認可能。宛先部署は「法人課税部門」または「個人課税部門」
- e-Tax提出の場合:メッセージボックス・受付結果のステータスを随時チェック
税務署の窓口では即時対応できない場合があるため、余裕のあるスケジュール管理と事前の確認が大切です。
インボイス登録完了通知の時期
「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出後、税務署による審査を経て「登録通知書」が届きます。この通知は、登録日や登録番号を記載した正式書類です。
- 紙で申請した場合:提出から登録完了までは約1ヶ月
- e-Taxで申請した場合:最短1週間程度で完了通知が届くことも
- 通知の受取方法:e-Taxの場合は電子通知、それ以外は書面郵送
開業届を提出した後すぐにインボイス申請を行う場合、登録が完了するまで時間がかかることがあるため、早めの申請が推奨されます。また、「適格請求書発行事業者公表サイト」に登録番号が掲載されることで、取引先も確認できる状態になります。
登録通知書を受け取ったら、開業届とともに控え保管し、帳簿記帳や請求書発行の際に誤りがないよう反映させる準備をしましょう。
開業届とインボイス登録を同日に行う方法
国税庁の「開業・廃業等届出書」の提出方法
個人事業主として開業する際は、所轄の税務署に「個人事業の開業・廃業等届出書」(以下、開業届)を提出する必要があります。開業届は、開業日から1か月以内に提出することが原則とされており、税務署への提出には以下の手段があります。
|
提出方法 |
必要書類 |
メリット |
注意点 |
|
税務署の窓口へ直接提出 |
開業届、本人確認書類写し |
記入ミスがあればその場で訂正可能 |
平日のみ対応、混雑している可能性あり |
|
郵送 |
開業届、返信用封筒(切手貼付)、本人確認書類写し |
自宅で手続き可能 |
控えの返送まで時間がかかる可能性あり |
|
e-Tax(電子申告) |
電子証明書、マイナンバーカード(後述)、利用者識別番号 |
同日にインボイス登録も可能、時間指定なし |
事前準備が必要、システムの操作に習熟する必要あり |
このように、開業届の提出方法には複数の選択肢がありますが、インボイス制度との同日登録を希望する場合は、e-Taxの利用がもっともスムーズです。
適格請求書発行事業者の登録申請方法
インボイス制度に参加するには、「適格請求書発行事業者」の登録申請が必要です。この申請は国税庁に提出する「適格請求書発行事業者の登録申請書」によって行います。申請方法は次の3通りです。
|
申請方法 |
提出書類 |
提出先 |
|
電子申請(e-Tax) |
適格請求書発行事業者の登録申請書(電子データ) |
国税庁 e-Tax |
|
郵送 |
紙の登録申請書 |
所轄税務署 |
|
窓口(持参) |
紙の登録申請書 |
所轄税務署 |
なお、申請書は国税庁のウェブサイトからダウンロード可能です。電子申請の場合、開業届の提出と同時に登録が可能で、紙での申請より早く審査が完了する傾向があります。
e-Taxを使って同日に提出する方法
開業届とインボイス登録を同日に行いたい場合、e-Taxを利用するのが最適です。e-Taxでは、以下のステップを踏むことでスムーズに両申請を同日に完了させることができます。
- マイナンバーカードとICカードリーダーの用意
- 利用者識別番号の取得
- e-TaxソフトのインストールまたはWeb版の利用
- 電子証明書の登録(住民基本台帳カードまたはマイナンバーカード)
- 「個人事業の開業・廃業等届出書」の作成・送信
- 「適格請求書発行事業者の登録申請書」の作成・送信
同日に完了させるためには、書類の事前準備とe-Taxの初期設定を始業日前までに済ませておくことが重要です。
マイナンバーカードの準備
e-Taxで電子申請を行うためには、マイナンバーカードが必要です。マイナンバーカードには電子証明書が内蔵されており、申請者本人であることを証明するために使われます。マイナンバーカードの取得には、交付申請から受取まで2〜3週間程度かかる場合があるため、開業予定日に間に合うよう早めに申請しておきましょう。
e-Taxの利用開始手続き
e-Taxを使う場合、利用者識別番号の取得が必要です。これはe-Taxの利用登録ページからオンラインで申請できます。利用登録後、取得した識別番号と暗証番号を用いて、ソフトの初期設定を行いましょう。事前に環境設定や電子証明書の登録作業を済ませることで、スムーズに手続きを進めることが可能になります。
また、e-TaxのWeb版を活用すれば、インストール作業なしでブラウザ上から申請が可能であり、操作も視覚的にわかりやすいため初心者でも安心です。
このように、開業届とインボイス登録を同日に行うには、計画的な準備とともに、電子申請の手順を正しく理解することが重要です。
申請時に気をつけたいポイントとは?
開業届とインボイス申請書類の不備例
開業届および適格請求書発行事業者の登録申請では、記載内容や添付書類の不備が原因で受理されない、または処理が遅延するケースがあります。以下は代表的な不備の例です。
|
不備の内容 |
影響 |
対策 |
|
マイナンバー未記載(開業届) |
本人確認ができず、受付保留の場合あり |
必ずマイナンバーを正しく記載 |
|
屋号がブランクまたは異なる名称で記載 |
請求書と登録情報が一致せず不適格となる可能性 |
屋号を決めた上で各申請書に統一して記入 |
|
旧氏名で手続き、住民票と一致しない |
本人確認の照合でトラブルに |
住民票などの公的書類に基づき統一名で記載 |
|
e-Tax利用開始手続き未完了で電子申請できない |
期日内の申請が遅れる |
事前に利用者識別番号と暗証番号を取得 |
手書き・郵送による申請であっても、記載漏れや誤記が目立ちます。国税庁ホームページで配布されている記載例や、入力支援ツールの活用をおすすめします。
開業日と事業開始日のズレに注意
開業届には「開業日」、インボイス登録申請書には「事業の開始日または予定日」を記載する欄があります。これらの日付が一致していない場合、税務署から補足資料の提出を求められる可能性があります。
特に注意すべきは、以下のようなケースです。
- 開業届は提出済みだが、実際の業務開始が遅れた
- インボイス登録を急いで進めたが、開業届の開業日が後日である
このような日付の前後関係に注意し、実際に業務を開始する予定日をもって開業日とし、書類間で整合性を取るようにしましょう。「開業予定日」は自由に設定できますが、余裕を持った日付での申請が望ましいです。
免税事業者がインボイス制度に登録した場合の影響
インボイス制度に登録すると「適格請求書発行事業者」となり、自動的に課税事業者として扱われます。これは、これまで消費税を納める義務のなかった免税事業者が、新たに消費税の申告・納税義務を負うことを意味します。
|
要素 |
インボイス登録前 |
インボイス登録後 |
|
消費税の納税義務 |
免除される |
課税義務が発生 |
|
帳簿・請求書管理 |
簡易記録で可 |
帳簿の保存義務増加、請求書要件厳格化 |
|
課税売上割合の記録 |
不要 |
必要、多段階税額控除の管理が必須 |
判断基準として、「課税事業者になる負担と、発行事業者になった時の取引先対応によるメリット」を天秤にかけ、インボイス登録の有無を決めることが重要です。特に年商が1,000万円未満の小規模事業者は慎重な検討が必要です。
また、課税事業者となった以上、消費税の仕入税額控除を適切に行うために、会計処理や帳簿付けの精度も求められるようになります。会計ソフトの導入や税理士への相談も選択肢となります。
よくある質問とトラブル対策!
インボイス登録後に課税事業者にならなかった場合は?
適格請求書発行事業者(インボイス登録事業者)として登録するには、原則として課税事業者であることが前提となります。ただし、基準期間における課税売上高が1,000万円以下である免税事業者であっても、インボイス制度に対応したい場合は「自由意思」で課税事業者になる旨を選択する必要があります。
仮に、インボイス登録を行ったものの、課税事業者になる届出(課税事業者選択届出書)を提出しなかった場合、適格請求書の発行事業者として認められない可能性があります。この場合、インボイスとしての有効性がなくなり、取引先が仕入税額控除を受けられなくなってしまうため、取引上のトラブルの原因になります。
インボイス登録を考えている免税事業者は、事前に「課税事業者選択届出書」の提出を忘れずに行うことが重要です。なお、届けを提出した場合、2年間は課税事業者である必要があります。
開業届の提出後に事業内容を変更したい場合の手続き方法は?
開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)を提出後に、事業の内容や業種を変更したい場合は、変更届として「所得税の変更届出書」の提出までは不要とされているのが一般的です。しかし、税務署への確認や、税理士の指導のもとで適切な対応を取ることが望ましいです。
また、インボイス制度に登録済みの場合、登録した業種と実態が明らかに異なる場合は、税務署から問い合わせを受けたり、登録内容の変更を求められることがあります。このため、以下の変更があった際には所定の手続きを行う必要があります。
|
変更事項 |
必要な届出・手続き |
提出先 |
|
屋号の変更 |
「納税地の異動に関する届出書」 (必要に応じて) |
管轄の税務署 |
|
業種の大幅な変更 |
適格請求書発行事業者の登録変更届出書 |
国税庁への電子申請または税務署 |
|
主たる事業所の移転 |
「納税地の異動に関する届出書」 |
旧・新いずれかの税務署 |
インボイス制度においては、登録情報(名称、所在地、事業内容など)に変更があった場合、「変更届出書」の提出が義務付けられています。変更の際は速やかに対応することが信頼の維持につながります。
インボイス登録の取消し方法とは?
適格請求書発行事業者としての登録を行った後、事業形態や取引先との関係あるいは収支の状況により、登録の取消しを希望するケースもあります。その場合は、以下の手順で取消し申請が可能です。
取消しに必要な書類と手続き方法
適格請求書発行事業者の登録取消しを希望する場合は、「適格請求書発行事業者の登録取消し申請書」を所轄税務署に提出します。この申請書は、国税庁のホームページからダウンロードでき、e-Taxを通じて電子的に送信することも可能です。
登録取消しの効力は、原則として申請書を提出した日の翌課税期間の初日からとなります。つまり、登録の取消しを希望する日の前日までに手続きを完了させる必要があります。
取消しにおける注意点
登録を取り消した場合、インボイス(適格請求書)の発行ができなくなるため、課税事業者としての仕入控除提供義務がなくなります。これにより、取引先の請求書対応に支障をきたす恐れがあるため、以下のような点に注意が必要です。
- 取引先への周知:事前に取引先に通知して、対応方法を検討してもらう。
- 取消し後の課税区分:年の途中でも取消しは可能だが、帳簿付けや消費税の扱いにズレが生じないようにする。
- 再登録の可否:一度取消しても、再度登録申請をすることは可能。
また、インボイス登録の取消しと同時に、課税事業者から免税事業者への変更を希望する場合は、「課税事業者選択不適用届出書」の提出が必要です。この点も併せて検討しておきましょう。
まとめ
開業届を提出しないとインボイス制度に登録できないため、開業と同時に手続きを進める必要があります。e-Taxを使えば開業届とインボイス登録を同日に完了させることが可能です。正確なスケジュールと書類の準備が重要です。










