10%?8%?適用税率のインボイス記載方法や注意点を徹底解説
更新日:2025.12.06
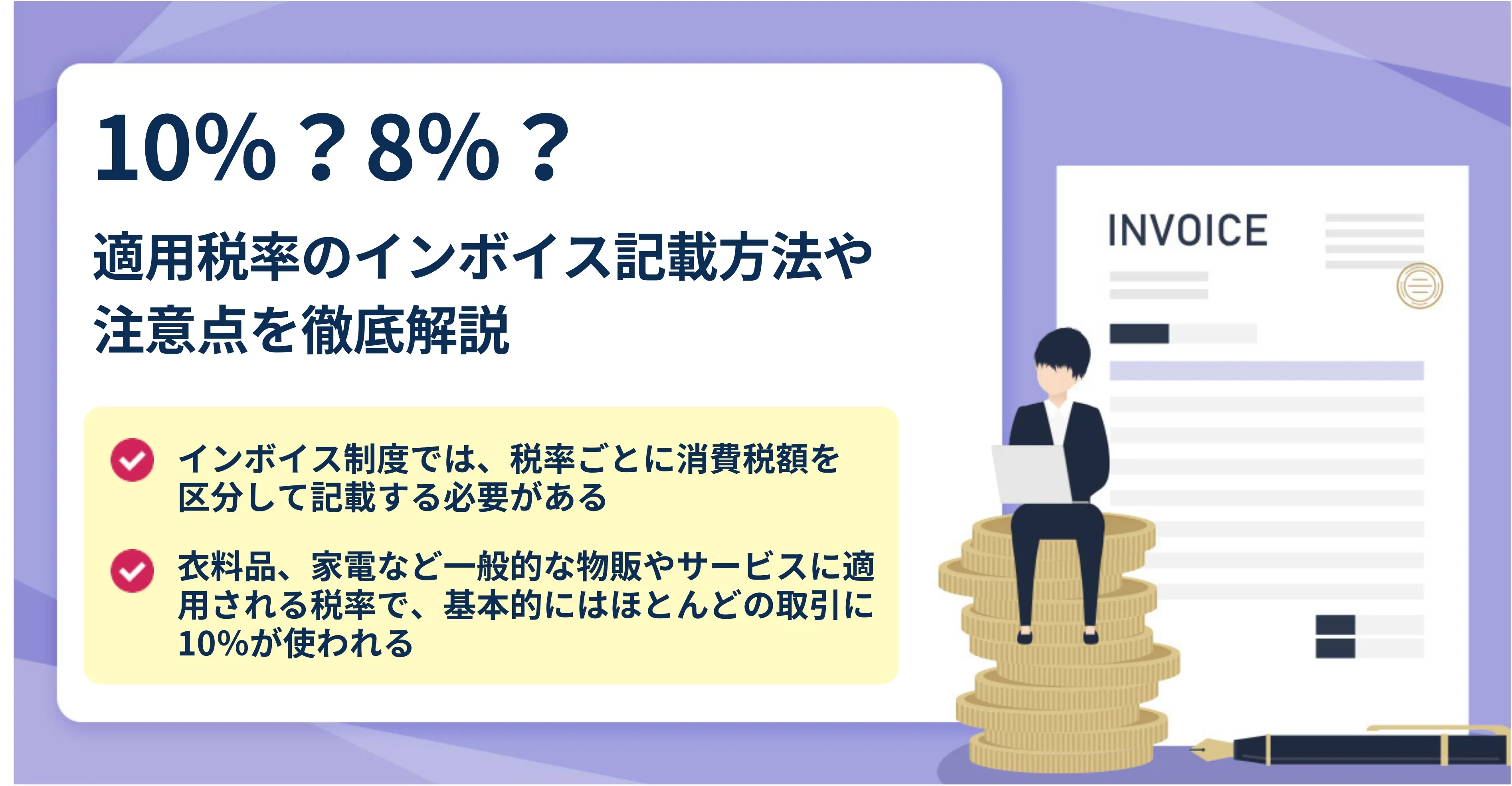
ー 目次 ー
2023年10月より始まったインボイス制度では、商品の種類によって異なる消費税率(10%・軽減税率8%)を正確に請求書へ記載する必要があります。本記事では、標準税率・軽減税率の適用対象やインボイスへの正しい記載方法、複数税率を扱う際の注意点、業種別の対策までを網羅的に解説。記載漏れによる仕入税額控除の否認リスクを回避するためにも、正しい知識を得て確実に対応しましょう。
インボイス制度と適用税率の基本的な仕組みとは?
インボイス制度とは何か
インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは、2023年10月1日から日本で導入された新しい消費税の仕入税額控除の方式です。この制度では、「適格請求書発行事業者」が発行する一定の要件を満たした請求書(インボイス)を取引先が保存することで、仕入税額控除を受けることが可能となります。従来の区分記載請求書等保存方式に代わる制度として、より正確な適用税率の把握や消費税額の管理が求められています。
インボイスには、税率ごとに区分して記載された消費税額や、販売品目、販売日、事業者名、登録番号などの情報が含まれていなければならず、正確な記載がない場合は、仕入税額控除が認められないリスクが生じます。
適用税率制度の概要
日本の消費税制度においては、2019年10月1日より複数税率(複数の適用税率)が導入されています。これにより、標準税率10%に加えて、一定の品目には軽減税率8%が適用されるようになりました。企業や事業者は、これらの税率を取引ごと・商品ごとに正確に区分し、記録・請求書等に反映させる必要があります。
特に、同一取引の中で複数の税率が適用されるケースでは、それぞれの税率に応じた金額を分けて明示しなければならず、帳簿や請求書作成の実務にも大きな影響を与えています。ERPや会計ソフトなどのシステム対応も不可欠となっています。
インボイス制度と軽減税率の関係性
インボイス制度の導入により、軽減税率の適用がある取引については、請求書上でその旨を明確に記載しなければなりません。軽減税率が適用される取引(例:飲食料品など)と標準税率が適用される取引(例:衣料品、電化製品など)とが混在する場合、納税者は下記のように明確に区分して請求書を作成・保存・提出する必要があります。
|
税率 |
品目の例 |
記載の必要性 |
税額の明示 |
|
10%(標準税率) |
電化製品、衣料品、日用雑貨など |
必須 |
税率ごとの合計額を明示 |
|
8%(軽減税率) |
飲食料品、定期購読の新聞(一定条件)など |
必須 |
税率ごとの合計額を明示 |
たとえば、請求書上に「飲料水100本 @100円(税率8%)」「電球10個 @500円(税率10%)」と記載する、もしくは別の明細行で税率区分を分けて表示することが必要です。なお、インボイス制度では、これらの税率を区分して記載しなければ、消費税仕入控除の対象とはなりません。
また、受領側も仕入控除対象の確認がより厳密となるため、取引先が適格請求書発行事業者であることを確認し、登録番号や記載内容に誤りがないか定期的にチェックする必要があります。
消費税の適用税率の種類!
2019年10月1日から、日本の消費税制度においては「複数税率制度」が導入され、従来の一律税率から「10%の標準税率」と「8%の軽減税率」の2種類の適用税率が存在するようになりました。これは、低所得者層への配慮や社会的配慮を目的として設けられた軽減策であり、事業者は対象商品やサービスに応じて適切な税率を判断・適用する必要があります。
標準税率10%とは
標準税率10%は、消費税の基本税率であり、大半の取引がこの税率の対象となります。物販・サービス業など、多くの業種で取り扱うほぼすべての商品・サービスに適用され、軽減税率対象以外の取引に幅広く適用されます。
例えば、衣料品、家電製品、美容院のサービス、電車・タクシー等の交通サービス、不動産賃貸(住宅用以外)などが該当します。
軽減税率8%が適用される対象品目
軽減税率8%は、生活に身近な商品のうち、一定の品目に限定して適用される税率です。以下の2つのカテゴリーが主な対象です。
|
品目分類 |
具体的な対象内容 |
|
飲食料品 |
食品表示法に定める飲食料品。ただし、外食や酒類、医薬品は除外。 |
|
新聞 |
週2回以上発行され、定期購読契約に基づく新聞(政治・経済などを含む一般紙) |
飲食料品とは、テイクアウトやスーパーマーケットなどで販売される食品を含みますが、外食やケータリングサービスは標準税率10%が適用されるため、分類には注意が必要です。
新聞・飲食料品に関する具体例
以下は、軽減税率の具体的な事例を通してその適用可否を示したものです。
|
商品・サービス |
内容 |
適用税率 |
|
テイクアウトの弁当 |
店舗で持ち帰り用に購入した弁当 |
8%(軽減税率) |
|
店内飲食 |
ファストフード店などで座って飲食 |
10%(標準税率) |
|
宅配ピザ |
いわゆるデリバリーサービス |
8%(軽減税率) |
|
生鮮食品 |
スーパーで購入する野菜・肉・魚など |
8%(軽減税率) |
|
ワイン・ビール |
アルコール類は軽減税率の対象外 |
10%(標準税率) |
|
定期購読の朝刊 |
月ぎめ契約による配達型の新聞 |
8%(軽減税率) |
|
駅売店で都度購入する新聞 |
定期購読契約に該当しないため |
10%(標準税率) |
このように、一つの商品ジャンルにおいても、提供方法や利用形態により適用される税率が異なる点は非常に重要です。特に外食とテイクアウト、定期購読と単品購入など、サービスの形態によって区分されるため、消費者のみならず事業者にとっても把握すべきポイントとなっています。
インボイスにおける適用税率の記載基準とは?
区分記載請求書と適格請求書の相違点
2023年10月より、消費税の適用税率を明確に区分し、仕入税額控除の要件を厳格化する「インボイス制度(適格請求書等保存方式)」が導入されました。これにより、従来の「区分記載請求書」では仕入税額控除の要件を満たさないことになります。
下記の表は、区分記載請求書と適格請求書の主な違いを示したものです。
|
項目 |
区分記載請求書 |
適格請求書(インボイス) |
|
発行事業者 |
免税事業者でも可 |
登録済の適格請求書発行事業者のみ |
|
書類への記載義務 |
税率ごとの金額記載で可 |
税率ごとの税額明示が必須 |
|
仕入税額控除への対応 |
可能(インボイス制度導入前) |
制度開始後は原則インボイスが必要 |
|
記載項目 |
簡易的 |
厳格な要件あり |
適格請求書への要件と記載事項
インボイス制度における「適格請求書(インボイス)」には、次に挙げる全ての記載事項が正確に含まれていなければなりません。記載漏れや誤記がある場合には、仕入税額控除を受けられない可能性があるため、特に注意が必要です。
主な記載事項は以下の通りです。
- 適格請求書発行事業者の氏名または名称、および登録番号(Tから始まる13桁)
- 取引年月日(請求日のみでは不十分で、納品日やサービス提供日が必要な場合あり)
- 取引内容(品名やサービス名など具体的に記載)
- 税率ごとに区分した対価の額
- 税率ごとの消費税額
- 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
特に「税率ごとの消費税額」は、8%と10%とで分けて明記することが求められます。1枚の請求書に複数税率の商品が含まれている場合、それぞれの税率ごとに金額と税額を明確にする必要があります。
複数税率がある場合の記載方法
軽減税率導入後の現在、飲食料品や新聞などには8%が、通常の物品・サービスには10%の標準税率がそれぞれ適用されます。このように1枚の請求書に異なる税率の商品やサービスを記載する場合、インボイス制度においては明確な区分が必須です。
以下は、複数税率に対応した記載形式の一例です。
|
商品名 |
数量 |
単価(税込) |
税率 |
税抜金額 |
消費税額 |
|
ペットボトル飲料 |
10本 |
110円 |
8% |
1,019円 |
81円 |
|
ノートパソコン |
1台 |
110,000円 |
10% |
100,000円 |
10,000円 |
このように、税率ごと、商品ごとに「税抜金額」と「消費税額」を分けて明示することで、買手による適切な仕入税額控除が可能になります。
また、書面での請求書だけでなく、電子インボイス(電子帳簿保存法下)でも、同様の記載義務が生じます。フォーマットの選定時にも、上記の要件を満たしているかを必ず確認しましょう。
インボイス記載においては、「税込価格のみ記載」「税率の記載なし」「合計税額の一括表示」などは制度上不備とされる可能性があるため、実務においても税率明示のための仕様変更やシステム対応が求められます。
さらに、返品、値引き、契約解除等によりインボイスの内容に変更が生じる場合は、「適格返還請求書」や「修正インボイス」の発行が必要になるケースもあります。これらの実務対応には、事前の社内整備と継続的なチェック体制が必要です。
実例|具体的な記載方法とフォーマット
商品ごとの適用税率の明示方法
インボイス制度においては、取引ごとに適用される税率を明確に記載する必要があります。特に軽減税率8%と標準税率10%の商品を同時に扱う場合は、それぞれの税率の対象商品がどれであるかを識別できるように分けて記載することが求められます。
例えば、帳票やレシートにおいては、軽減税率対象の商品名の横に「※軽減税率対象」「※8%」などの注釈を加える、または税率別に商品グループをレイアウト上で分けて表示する工夫が必要です。これにより仕入税額控除の対象となるかどうかを判断しやすくします。
インボイス様式の書き方例
以下に、複数税率の商品が含まれる取引における、適格請求書(インボイス)の記載例を表形式で示します。
|
商品名 |
数量 |
単価(税込) |
税率 |
税抜金額 |
消費税額 |
|
ミネラルウォーター(500ml) |
10本 |
110円 |
8% |
1,019円 |
81円 |
|
ボールペン(3本セット) |
2パック |
550円 |
10% |
1,000円 |
100円 |
このような記載により、取引の透明性を確保するとともに、消費税率ごとの課税売上を正確に把握できます。なお、消費税額を税率ごとに合計して明示することも必要です。
|
税率 |
税抜合計 |
消費税額 |
|
8% |
1,019円 |
81円 |
|
10% |
1,000円 |
100円 |
手書き・Excel・会計ソフト使用時の注意点
実務においてインボイスを作成する手段として、手書き、Excel(エクセル)、会計ソフトの3つの方法があります。それぞれにおける注意点は以下のとおりです。
手書きでの作成
手書きでインボイスを作成する場合、記載ミスや記載漏れが生じやすいため、適格請求書の要件を十分に把握したうえで作成する必要があります。特に、消費税率ごとの区分記載、登録番号、取引年月日などの記載が漏れると、仕入税額控除の要件を満たさなくなるため注意が必要です。
また、読みやすい文字で書くことや、2枚複写式の用紙を使用して控えを残すなどの工夫も求められます。
Excelでの作成
Excelを活用する場合、再利用可能なフォーマットを作成し、税率ごとに列を分けることで入力ミスを防ぐことが可能です。税率ごとの集計が自動計算で出るように関数設定を行うと、日々の業務負担軽減にもつながります。
しかし、Excelには請求書番号の自動付番機能がないため、他の管理手段(例:管理台帳や請求ソフトとの併用)を用いることが推奨されます。また、保存形式はPDFで固定化し、不正な改ざん防止のためにも電子署名やパスワード保護を検討すべきです。
会計ソフトによる作成
クラウド会計ソフトを使えば、税率ごとの区分記載や必要記載事項の漏れを自動的に防ぐ入力補助機能を使うことができます。また、インボイス制度対応の請求書テンプレートやPDF出力、電子帳簿保存法との連携機能なども提供されており、導入メリットは非常に大きいです。
ただし、ソフトのバージョンアップ状況や設定ミスによって制度要件を満たさない帳票が出力される可能性もゼロではありません。導入後は初期設定で「適格請求書発行事業者登録番号」「区分税率表示」などが正しく登録されているか確認しましょう。
適用税率変更時におけるインボイスの対応方法!
税率改定時に注意すべき記載日と提供時期
消費税の税率改定が行われる場合には、その適用開始日以前・以後で取引の取り扱いが異なります。インボイス(適格請求書)においても、適用される税率に基づいた正確な記載が不可欠です。特に「課税資産の譲渡等の時期」に着目する必要があり、たとえ請求書の発行日が新税率適用後であっても、役務の提供が旧税率期間中に完了していれば旧税率が適用されます。
税率改定に際しては、以下のようなケースごとの対応が求められます。
|
取引のタイミング |
税率適用の判断基準 |
インボイスへの影響 |
|
改定前に引渡し完了 |
旧税率(例:8%) |
請求書に旧税率で記載 |
|
改定後に引渡し完了 |
新税率(例:10%) |
新税率で記載 |
|
役務提供が継続する場合 |
引渡しまたは完了日が基準 |
分割して記載または契約内容に沿った明細 |
インボイス制度においては、税率ごとの金額を明確に区分する必要があるため、税率変更直後は特に記載内容に注意が必要です。請求書発行のタイミングと取引完了日が異なる場合には、適切な税率判断を行った上で正確に記載することが求められます。
経過措置対象取引の扱いと注意点
税率改定後の一定期間においては、経過措置が講じられることがあります。これにより、実際の提供時期が税率改定後であっても、旧税率が適用されるケースがあります。経過措置の対象となる主な取引は以下のとおりです。
- 公共料金(水道料金、電気料金など)における定例的な継続取引
- 長期請負工事などにおける請負契約が旧税率下で締結されたもの
- 定期購読の新聞、雑誌などの継続的提供サービス
こうした経過措置に該当する場合は、インボイスにも適切な税率を記載する必要があります。また、経過措置を適用した旨を明記することで、仕入税額控除を受ける側にも誤解が生じにくくなります。
経過措置を適用する際に重要となるのが、対象となる「契約日」や「工事着手日」、「提供サービスの期間」の明示です。これらの情報が不明確な場合、税務調査において不適切な税率適用と指摘される可能性があるため、事前に会計ソフトや請求書テンプレートを改訂し、経過措置対象の記載項目を設けておくことが推奨されます。
以下に、主な経過措置の取引とインボイス記載上の留意点をまとめます。
|
経過措置対象取引 |
適用税率 |
インボイス記載時の注意点 |
|
長期請負工事(着工が改定前) |
旧税率 |
契約日・着工日を明記、備考欄に経過措置適用表示 |
|
定期購読新聞(契約が旧税率期間) |
旧税率 |
提供期間・契約内容を請求書に記載 |
|
公共料金(継続的サービス) |
供給期間によって税率が分かれる |
供給期間を明記し、税率ごとに金額を区分 |
このように、税率改定時におけるインボイス対応では「時期の特定」と「経過措置の適用判定」が最も重要なポイントとなります。税率の適用を誤ると、仕入税額控除が認められないケースもあるため、事前に社内でのルール整備やインボイステンプレートの更新を徹底しましょう。
適用税率の記載漏れなどによるリスクと対策
仕入税額控除が認められない可能性
インボイス制度下では、適用税率の記載が不備または漏れているインボイス(適格請求書)を使用した場合、原則として仕入税額控除の適用を受けることができません。これは、制度上インボイスが適切な税区分や税率を明記していることが仕入税額控除の要件とされているためです。
たとえば、軽減税率8%が適用される飲料品にもかかわらず、インボイス上に税率の明記がなければ、税務署はそれを通常の10%課税として取り扱うおそれがあり、控除対象外と判断されます。
特に、軽減税率対象商品と標準税率対象商品が混在する取引においては、税率ごとの明確な区分表示が必須となり、これを怠ると帳簿・請求書の整合性が損なわれ、申告漏れや脱税と疑われるリスクにもつながります。
記載漏れによる仕入税額控除の可否の整理
|
記載状況 |
仕入税額控除の可否 |
備考 |
|
適用税率・消費税額の明記あり |
控除可能 |
インボイスの要件を完全に満たす |
|
適用税率の記載漏れ、但し税額は記載あり |
控除不可 |
適用税率の明示は必須要素 |
|
消費税額の記載漏れ、税率は明記 |
控除不可 |
消費税額の明確な記載が必要 |
税務調査時の指摘リスクと対応策
インボイス制度導入後は、税務調査において請求書や帳簿の記載内容が厳しくチェックされるようになります。とくに適用税率の誤記、記載漏れ、消費税額の不整合などがあると、仕入税額控除の否認や申告是正を求められるケースが報告されています。
税務署は、該当インボイスが適格請求書の形式・要件を満たしていることを前提に調査を行います。記載漏れが複数件に及ぶと、適格請求書発行事業者としての信頼性を損ない、過少申告加算税や延滞税の課税対象になる可能性もあります。
主な指摘事項とその対策
|
発生する指摘内容 |
対策・対応方法 |
|
適用税率の記載不備 |
発行前にチェックリストを使用し税率ごとの正確な表記を徹底 |
|
軽減税率対象の商品を10%表記 |
商品単位で税率マスタを整備して会計ソフトと連携 |
|
消費税額と税率が整合していない |
定期的な会計システムの税率更新を実施 |
適格請求書保存義務の徹底
記載漏れによるトラブルを未然に防ぐためには、帳簿保存義務を担保する体制管理の徹底が不可欠です。対象取引ごとの適格請求書の発行・受領・保管が義務であるため、自社だけでなく仕入先にもインボイスの確認・修正依頼を積極的に行う体制を整えましょう。
特に取引件数の多い小売業や飲食業などでは、インボイスの電子保存やスキャンデータによるアーカイブを用いて、検索性と長期保存性を高めることも有効です。税務調査に備えたファイル管理ルールを設け、記載不備・紛失を防止する仕組みづくりを推進することが重要です。
教育と業務フロー改善の必要性
経理担当者や営業担当者など、請求書の作成・確認に関わるすべての社員に対し、インボイス制度と適用税率に関する教育を行うことは、長期的にリスクを軽減するために欠かせません。
また、業務フローにおいても、請求書発行前の内容確認プロセス、修正フロー、得意先との確認連絡体制などをマニュアル化しておくことが推奨されます。制度を正しく理解し、仕組みに則った運用を徹底することで、適用税率の記載漏れや税務上のリスクを最小限に抑えることが可能です。
業種別の適用税率と注意ポイント
飲食業における適用税率の注意事項
飲食業では提供形態によって適用される消費税率が異なるため、インボイス作成時には細かな区別が求められます。店舗内での飲食(イートイン)は標準税率10%が適用されますが、テイクアウトや宅配は軽減税率8%の対象となります。
例えば、コーヒーショップでのコーヒー提供において、店内で飲む場合と持ち帰りでは税率が変わります。このため、会計時及びインボイスの記載時には、消費者の利用意図を確認し、適切な税率を適用し記載する必要があります。
また、お弁当屋やパン屋などでも軽減税率の対象となる商品が多いため、一部に標準税率の商品(酒類や外食扱いの商品)が含まれている場合は、区分記載が不可欠です。
小売業での税率混在商品の対応方法
スーパーマーケットやコンビニエンスストアなどの小売業では、軽減税率8%と標準税率10%の商品が同時に販売されていることが一般的です。例えば、ペットボトル飲料(軽減税率対象)と紙おむつ(標準税率対象)を同時に販売する場合、インボイスにはそれぞれの税率ごとに区分して記載する必要があります。
POSレジとの連携が進んでいる店舗では自動的に税率区分がされるようになっていますが、レジ設定の誤りやマスタデータの不備により税率適用ミスが生じる可能性があります。定期的なチェックとスタッフへの周知が必要です。
商品の分類と同様に、値引きやセット販売の際にも注意が必要です。複数の商品をまとめて販売する際に、軽減税率と標準税率の商品が混在している場合、それぞれの税率で適切に按分して税額を表示する対応が求められます。
代表的な混在商品の分類例
|
商品例 |
税率 |
注意点 |
|
牛乳 |
8%(軽減税率) |
飲食料品に該当 |
|
紙おむつ |
10%(標準税率) |
生活必需品だが軽減税率の対象外 |
|
新聞(日刊、定期購読) |
8%(軽減税率) |
条件付きで軽減税率適用 |
|
ビール |
10%(標準税率) |
酒類は軽減税率対象外 |
卸売業・サービス業における事例と対策
卸売業においては、取引先が消費税課税事業者か免税事業者かによって適用税率だけでなく、請求書の記載内容にも影響が出るため注意が必要です。また、取引先が最終消費者向けに販売するか業務用に使用するかによっても税率にズレが生じることがあります。
卸売業では、自社が扱う商品ごとに税率を正確に把握することが重要であり、特に複数税率の対象となる飲料・食品・書籍類などを多く扱う業者は、SKU単位での税率管理体制が求められます。また、インボイス発行時は、各商品の税率別の合計金額と適用税率を明確に記載する必然があります。
一方、サービス業は基本的に標準税率10%が適用されますが、例外としてサービスに付随する物品(例:教材、資料、お茶などの軽減税率商品)が伴う場合には、それぞれの税率に応じた記載が求められます。たとえば、オンラインセミナー受講料と事前送付の資料(食品および書籍)がある場合、8%と10%の混在になります。
サービス業における税率混在の例
|
取引内容 |
税率 |
インボイス記載時のポイント |
|
美容室で施術と飲料提供 |
施術:10% 飲料:8%(ただし原則は施術に付随として10%) |
飲料提供が独立している場合は8%記載 |
|
学習塾で授業料と教材販売 |
授業料:10% 教材(書籍):8% |
教材の明確な価格表示・区分が必要 |
|
ビジネスセミナーと弁当付き |
セミナー:10% 弁当:8% |
弁当代を明示し、税率を分けて記載 |
いずれの業種でも、インボイス制度においては「商品の正確な税率区分記載」「税率ごとの合計額」「消費税額の明示」といった記載義務があります。業種独自の商慣習や商品構成を加味した運用が求められます。
適用税率の誤記載は、取引先の仕入税額控除の否認や自社への信頼問題に発展する可能性があるため、正確な税率分類と記載は非常に重要な経理実務です。
まとめ
インボイス制度では、標準税率10%と軽減税率8%の適用区分を正確に記載することが求められます。適格請求書における記載漏れは仕入税額控除の否認や税務調査リスクにつながるため、業種や取引内容に応じた対応が重要です。制度変更や経過措置にも適切に対応しましょう。










