法定福利費は請求書に記載が必要?計算方法や書き方の例を解説
更新日:2025.03.03
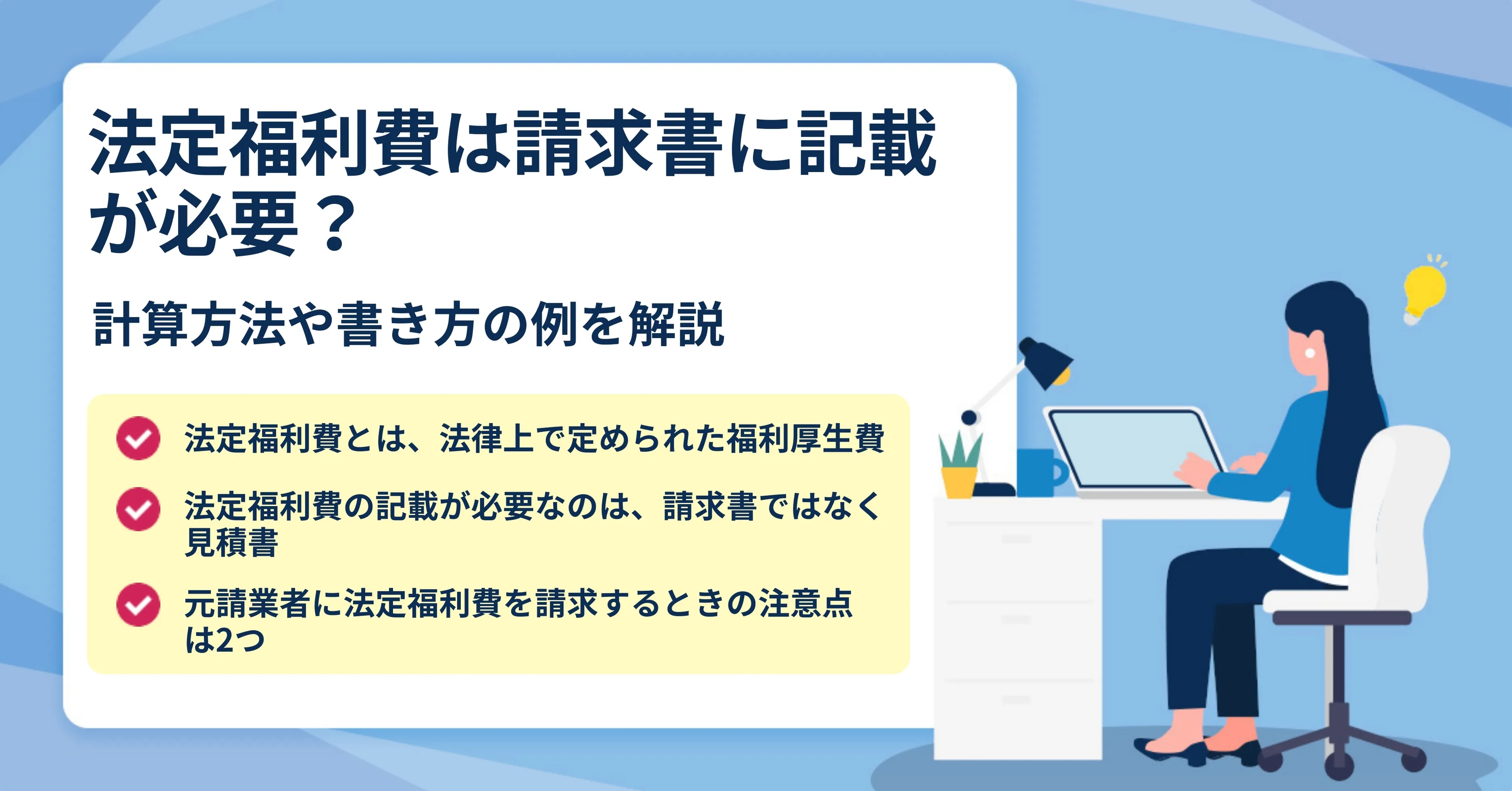
ー 目次 ー
建設業では元請業者に法定福利費を請求する際に、見積書への記載が義務付けられています。見積書には法定福利費を計算したうえで記載する必要があるものの、計算方法は請求する項目によって異なります。
計算方法に誤りがあれば、取引先から見積書の再発行を求められる以外にも、金銭的なミスを原因に信用を失う場合もあるでしょう。
このことから、法定福利費を見積書に記載する際は計算方法や記載方法を理解しておく必要があります。
本記事では、法定福利費を請求書に記載する必要性について、項目ごとの計算方法や書き方を解説します。
法定福利費とは、法律上で定められた福利厚生費
企業は社員の雇用にともなって、従業員とその家族が安心して暮らすことを目的として福利厚生を提供しています。福利厚生は企業が独自に定めるものと、法律で義務付けられているものにわかれます。
このような中で「法定福利費」とは、上記のような法律上で企業が従業員に対して提供することが定められている保険や費用のことです。法定福利費にあてはまる内容は下記のとおりです。
- 健康保険
- 厚生年金保険
- 介護保険
- 雇用保険
- 労災保険
- 子ども・子育て拠出金
法定福利費はさまざまな業界で企業が支払うものですが、書類で使用されやすいのは建設業界です。建設業界は下請業者が元請業者に法定福利費を請求できることから、見積書段階で記載して先方に伝える必要があります。
【注意】法定福利費の記載が必要なのは、請求書ではなく見積書
建設業界は下請業者が元請業者に法定福利費の請求が可能です。その際に、下請業者は元請業者に対して、請求書ではなく、法定福利費を明記した見積書の提出が義務付けられています。
元請業者側としても、下請業者から法定福利費を記載した見積書の提出がなければ、安心して依頼できません。正しい書類を作成することで、必要な保険に加入していることが理解でき、受注につながる可能性があります。
元請業者に法定福利費を請求するときの2つの注意点とは?
元請業者に法定福利費を請求する際は、会社独自の福利厚生の扱いや消費税の計算方法などの注意点があります。注意点を理解しておかなければ、見積書の再発行を求められる可能性があるでしょう。
ここでは、元請業者に法定福利費を請求する際の2つの注意点を解説します。
①会社独自の福利厚生は請求できない
元請業者に請求できる費用は、法律上で定められた法定福利費のみです。
企業によっては、従業員へ向けて住宅手当や通勤手当などの会社独自の福利厚生を用意しています。しかし、会社独自の福利厚生は法律上で支給が義務付けられているわけではないため、元請業者への請求はできません。
会社独自の福利厚生の一般例は下記のとおりです。
- 住宅手当・家賃補助
- 通勤手当
- 社員食堂・ランチ費用の補助
- 退職金制度
- 旅行や宿泊施設の優待
- 託児施設の利用料
- 資格取得支援
元請業者に請求する際は、誤って記載しないように注意しましょう。
②法定福利費は消費税の対象になる
下請業者に支払う法定福利費は、元請業者から見れば「外注費」になるため、課税対象になります。このことから、取引先に送付する見積書では法定福利費に消費税を含めて計算する必要があります。
消費税を計算し忘れると、書類の再発行だけでなく取引先との金銭的なミスにつながり、信用を失ってしまう可能性があるため注意しましょう。
元請業者に請求する法定福利費の計算方法を簡単に紹介!
法定福利費の計算は、企業が従業員に支払う労務費をもとに計算されます。実際の保険料率は年度や都道府県によって異なるため、自社にあわせて計算することが大切です。
ここでは、計算しやすいように労務費を10万円として、各項目の簡単な計算方法を解説します。
①健康保険料
健康保険の保険料の割合は、健康保険組合によって異なります。たとえば、全国健康保険協会東京支部では、従業員の労務費に対して約10%が保険料として請求されます。
なお、社会保険は企業と従業員で保険料を折半しているため、会社が支払うべき金額は約5%です。このことから労務費が10万円の場合は、元請業者に請求する健康保険料は5,000円となります。
参考:全国健康保険協会「令和7年度保険料額表(令和7年3月分から)」
②厚生年金保険料
厚生年金保険料は、2025年2月現在で18.3%です。厚生年金保険料は健康保険料と同じく、企業と従業員で折半して支払うため、企業が負担するのは9.15%になります。
このことから、労務費が10万円の場合に下請業者が元請業者に請求する厚生年金保険料は9,150円です。
③介護保険料
介護保険は40歳以上から加入が義務付けられている保険で、老化が原因の怪我や病気で介護が必要になった際に利用できます。
介護保険料は、健康保険の種類や都道府県で異なる可能性があります。たとえば、全国健康保険協会では、令和7年3月以降の介護保険料が1.59%です。
介護保険料は企業と従業員が折半で支払うことから、会社が負担する金額は約0.8%であり、労務費が10万円の場合には元請業者に請求する介護保険料は800円ほどになります。
④雇用保険料
雇用保険料は業種や年度によって保険料率が異なり、建設業では2025年3月まで従業員の労務費に対して11.5%を支払う必要があります。雇用保険料は全額を企業が負担するため、満額を元請業者に請求できます。
このことから、労務費が10万円の場合に下請業者が元請業者に請求できる雇用保険料は11,500円です。
⑤労災保険料
労災保険料は、従業員が業務中に怪我をした際や業務が原因となる病気になった場合に適応される保険です。
労災保険料は建設業のなかでも事業内容によって保険率が大きく異なり、2025年2月現在の建築事業の9.5%を基準にすれば、労務費が10万円の場合に元請業者に請求できる労災保険料は9,500円になります。
⑥子ども・子育て拠出金
子ども・子育て拠出金とは子育て支援を目的とした保険で、従業員の子どもの有無にかかわらず、事業者は負担が求められています。
子ども・子育て拠出金は事業者がすべての保険料を負担する必要があり、2025年2月現在の割合は3.6%です。このことから、労務費が10万円の際に下請業者が元請業者に請求する、子ども・子育て拠出金は3,600円になります。
参考:日本年金機構「子ども・子育て拠出金率が改定されました」
法定福利費を含めた見積書の例
法定福利費を含めた見積書の例を理解しておくことで、元請業者に発行する際にわかりやすい書類が作成できます。事前に自社にあわせたテンプレートを用意しておき、必要な場合にすぐ発行できるよう準備しましょう。
ここでは、法定福利費を含めた見積書の例を解説します。なお、保険料率は前述した「元請業者に請求する法定福利費の計算方法を簡単に紹介!」の章で解説した数字を基準にしています。
|
見積書 発行日:〇年〇月〇日 株式会社〇〇 御中 お見積もり金額 ¥339,550-
自社の企業名 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参考:国土交通省「「法定福利費を内訳明示した見積書」について」
まとめ|法定福利費は請求書に記載せず見積書で元請業者に伝えよう
本記事では、法定福利費を請求書に記載する必要があるのか、項目ごとの計算方法を解説しました。
下請業者が法定福利費を元請業者に伝える書類は、請求書ではなく見積書を使用します。見積書で法定福利費を記載しておかなければ、元請業者から再発行を求められたり、発注を断られたりする可能性があるため注意しましょう。
法定福利費を含んでいる書類を作成する際は、本記事を参考に書類を作成しましょう。










