個人事業主の請求書は屋号のみで問題ない?屋号のメリット・デメリットも解説
更新日:2025.01.30
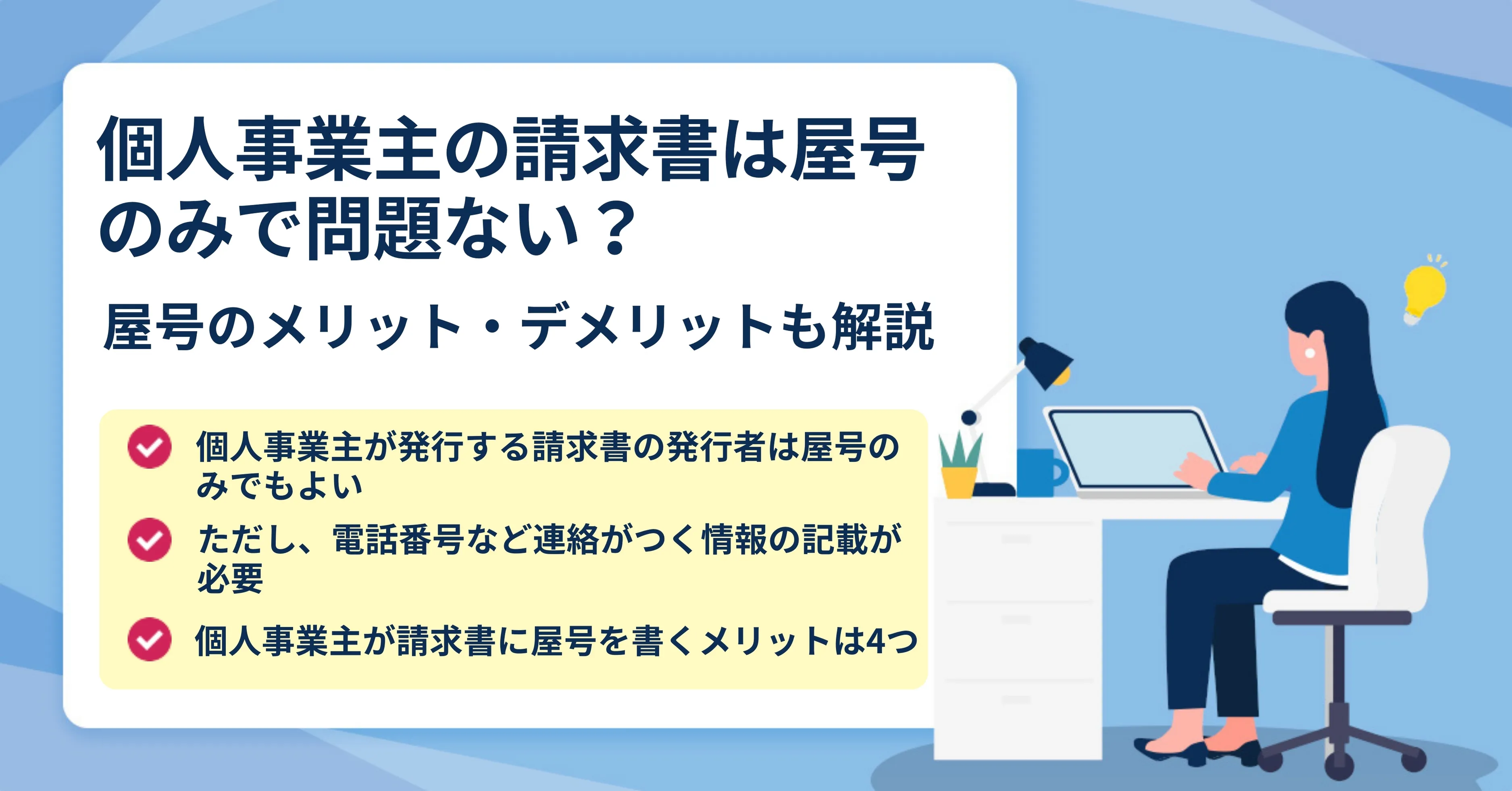
ー 目次 ー
個人事業主とは税務署に開業届を提出し、法人ではなく反復・継続かつ独立しておこなう事業者のことです。事業名は開業者の氏名、または「屋号」をつけられます。この「屋号」をつけるべきかどうかの判断は、個人事業主やフリーランスがよく悩まれるポイントです。
屋号をつける理由として「副業をしていて本業の会社に知られたくない」「個人名よりも屋号のほうが信頼感を得やすい」などがあります。ほかにもメリットがある一方で、デメリットも存在するため、これから個人事業主として開業する場合には屋号の有無も検討しておくと良いでしょう。
本記事では、個人事業主の請求書の記載方法について、屋号のメリット・デメリットを交えて解説します。
【結論】個人事業主の請求書の発行者は屋号のみで問題なし!
請求書の発行者情報は、必要な時の連絡先を明確にする目的があります。発行者が特定できれば、請求書の発行者は屋号のみで問題ありません。ただし、問い合わせや確認が必要になる場合もあるため、電話番号やメールアドレスなど、連絡先情報の記載が望ましいです。
副業で会社に知られたくない場合や、本名を出すのに抵抗がある場合は、屋号を活用することで安心して請求書を発行できます。
ここでは、個人事業主の請求書の発行者情報や屋号について解説します。
請求書の発行者情報は、発行者の特定が目的
請求書の発行者情報は、屋号でも個人名でも問題ありません。発行者の住所や電話番号に記載義務はありませんが、住所や電話番号を記載すると「送り先がわからない」「連絡がつかない」などのトラブルを未然に防げます。
そのため、発行者情報は発行者名だけでなく、取引先の安心・信頼を重視して、連絡先や捺印した社判などの情報も記載しておくことが良いでしょう。
屋号とは、個人で事業をする際のビジネス上の名前
屋号は法人でいう「会社名」であり、個人事業主やフリーランスが使用する事業用の名称です。使用は義務ではないため、設定するかどうかは任意で決められます。
屋号は個人名と異なり、対外的にわかりやすい名前をつけられる点が特徴です。
たとえば、飲食店や小売店であれば店舗名を、事務所であれば事務所の名前を屋号とすることで、顧客にも認識されやすくなります。名刺や請求書のような書類全般、事業のホームページを作るならサイト名やドメインにも反映できるため、事業の「看板」としての役割を担っています。
インボイス(適格請求書)では発行者は屋号のみで問題ない?
インボイス制度は事業者が消費税を正確に納めるためのルールであり、適用税率や消費税額などを記載したインボイス(適格請求書)の発行や保存、計算が定められています。
このインボイス(適格請求書)は、電話番号の記載で交付する事業者を特定できれば、発行者情報は屋号の記載で問題ありません。適格請求書発行事業者公表サイトに屋号の公表も可能で、希望する場合は「適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出手続」をおこないましょう。
個人事業主が請求書を発行する際の注意点
請求書は、取引完了後に対価を受け取るために、受注者が発注者に対して発行する重要な書類です。正確でわかりやすい請求書を作成し、スムーズに印象良く対応することで取引先からの信用を得られるため、次回以降の取引にもつながりやすくなります。
ここでは、個人事業主やフリーランスが請求書を発行する際の注意点を解説します。
①金額の書き方
金額を記載する際には、以下の2点に注意しましょう。
- 3桁ごとに「,」をいれる 桁違いを防ぎやすくなります。
- ¥2,000-や金2,000円也と記載する 金額の前後に文字を書き、不正を防止する目的があります。
また、電子データで請求書を送る場合は、不正防止のためPDFのような編集しづらいデータで送りましょう。
②源泉徴収税の有無
源泉徴収とは所得や報酬から事前に所得税を差し引き、支払側が本人に代わって税務署へ納付する仕組みです。個人事業主は以下の点に注意しましょう。
- 源泉徴収の対象業種であるかを確認する
- 取引先に源泉徴収税の有無を確認する
源泉徴収税の把握が不十分な場合、確定申告でミスが発生する可能性があります。確定申告時に二重納税にならないよう、早めに確認しておくのが安心です。
個人事業主が請求書に屋号を書く4つのメリット
個人事業主が屋号を利用すると、より信頼を得られる場合があります。ほかにも屋号を利用しておくと得られるメリットがあり、これから個人事業主として開業を予定していれば、屋号の利用も検討しておくと良いでしょう。
ここでは、個人事業主が請求書に屋号を書く4つのメリットを解説します。
①事業をアピールしやすい
屋号に事業内容がわかる言葉を取り入れると、自然に事業形態や内容をアピールできます。
たとえば、Webデザイナーなら「◯◯デザイン事務所」、写真家なら「〇〇スタジオ」など、事業内容を想像しやすい屋号はアピールにもなり、印象に残りやすくなります。本名がありふれた姓でも、個性的でインパクトの強い屋号をつけられます。
覚えやすくアピールできる屋号を検討しましょう。
②屋号付きの口座が開設できる
金融機関によって「個人名+屋号名義の口座」が開設できる場合があります。開設可能な銀行は以下のとおりです。
- 楽天銀行
- PayPay銀行
- GMOあおぞらネット銀行
- みずほ銀行
- 三菱UFJ銀行
- ゆうちょ銀行
- 三井住友銀行
- りそな銀行
ほかに、都市銀行や信用金庫でも開設可能な場合があります。
金融機関によって対応が異なるため、必要書類や手続方法などを事前に確認しましょう。銀行によっては口座の審査があるため、開設が難しい場合もあります。
③公私の区別がしやすい
事業を運営するにあたって、屋号付きの口座を開設できます。開設すれば、事業とプライベートのお金の流れを別々に管理でき、会計の管理をスムーズに進められます。このように屋号を設定し活用することで、公私の区別がしやすくなります。
また、スタッフや税理士とお金の管理を共有する場合も、その内容を明確にできます。会計ソフトを使った銀行口座の連携も容易になるでしょう。
④法人化する際、屋号を商号に引き継げる
事業を法人化する際には商号が必要で、屋号は商号に引き継げます。引き継ぐと、発行書類や名刺の名称変更の手間を省けることもメリットの1つです。
さらに、屋号でつちかった信用やブランドイメージを、そのまま商号に活用できる点も大きなメリットとして挙げられます。法人化を見越して屋号を設定する際は、商号登記に使用できる文字や記号の定めがあるため注意しましょう。
個人事業主が屋号をつける2つのデメリット
屋号は便利で信頼感を得やすい反面、いくつかのデメリットも存在します。屋号でのトラブルや手間が生じる可能性があります。屋号は後から変更もできますが、屋号を登録している先への手続き、屋号を使用した名刺や書類の書式を変更しなければならなくなります。手間がかかるため、デメリットを把握しておきましょう。
ここでは、個人事業主が屋号をつける2つのデメリットを解説します。
①屋号をつけるのに時間がかかる
屋号は事業内容をわかりやすく伝え、覚えてもらいやすい名前が理想です。しかし、適切な名前を考えるために時間がかかる場合があります。ほかの事業者と名称がかぶると、混同されるリスクやトラブルの可能性があります。法律的には同じ屋号を使用することは問題ありませんが、意図的に似た名称にするとトラブルに発展するおそれがあるため、避けたほうが良いでしょう。
また、ネット検索時にほかの事業者と混同され、不利益が生じる場合があります。類似した名称がないか事前に確認して屋号をつけましょう。
②屋号でイメージが限定される
屋号は事業内容をアピールする効果がありますが、事業の成長や方向性の変化にともない、逆に足かせとなる場合もあります。たとえば、特定の業種を示す屋号をつけると、新たな事業分野に進出した際に、違和感の原因になる可能性があります。
屋号は変更可能であるものの、屋号を変更をする際は変更に付随した作業に手間がかかります。事業の内容や将来性を考慮して、屋号を選ぶことが重要です。
まとめ|事業を大きくするつもりなら、屋号を活用しよう
本記事では、個人事業主の請求書の記載方法について、屋号のメリット・デメリットを交えて解説しました。
屋号は個人事業主にとって大きなメリットをもたらします。経理の効率化やスムーズな法人化など、事業を大きくしていく際に、より効果的にメリットを発揮するでしょう。
一方で、屋号の設定には慎重さも必要です。事業の方向性や名前の独自性を十分に考慮する必要があります。屋号は個人事業主の看板ともいえる大事なものです。設定した屋号は、事業を大きくするために、積極的に活用していきましょう。










