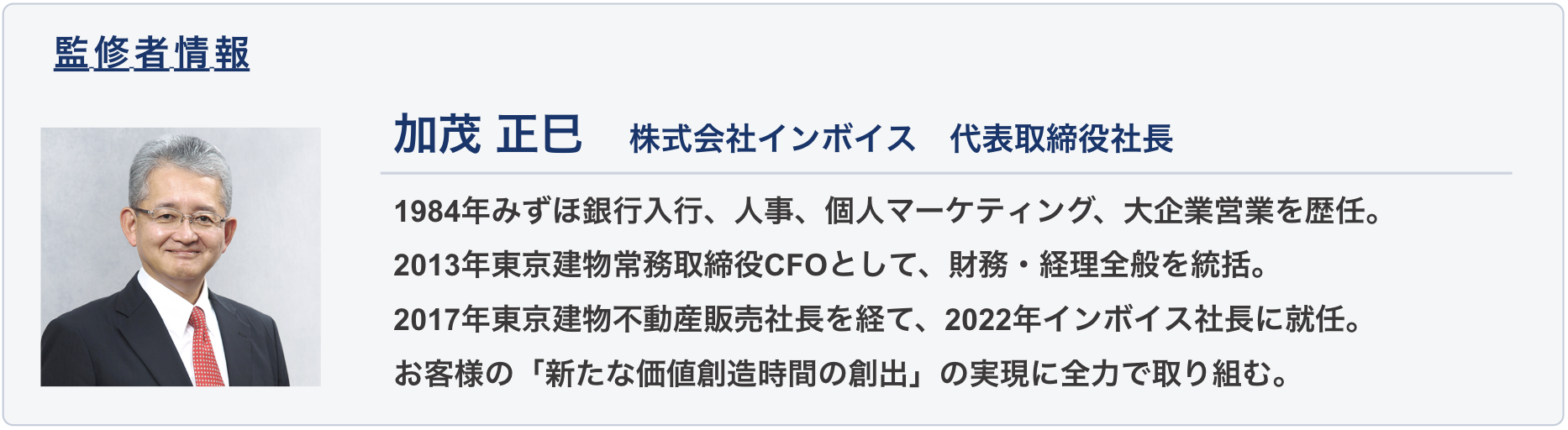「電子インボイスの国際規格「Peppol(ペポル)」とは?料金や導入によるメリットを解説。
更新日:2025.09.05
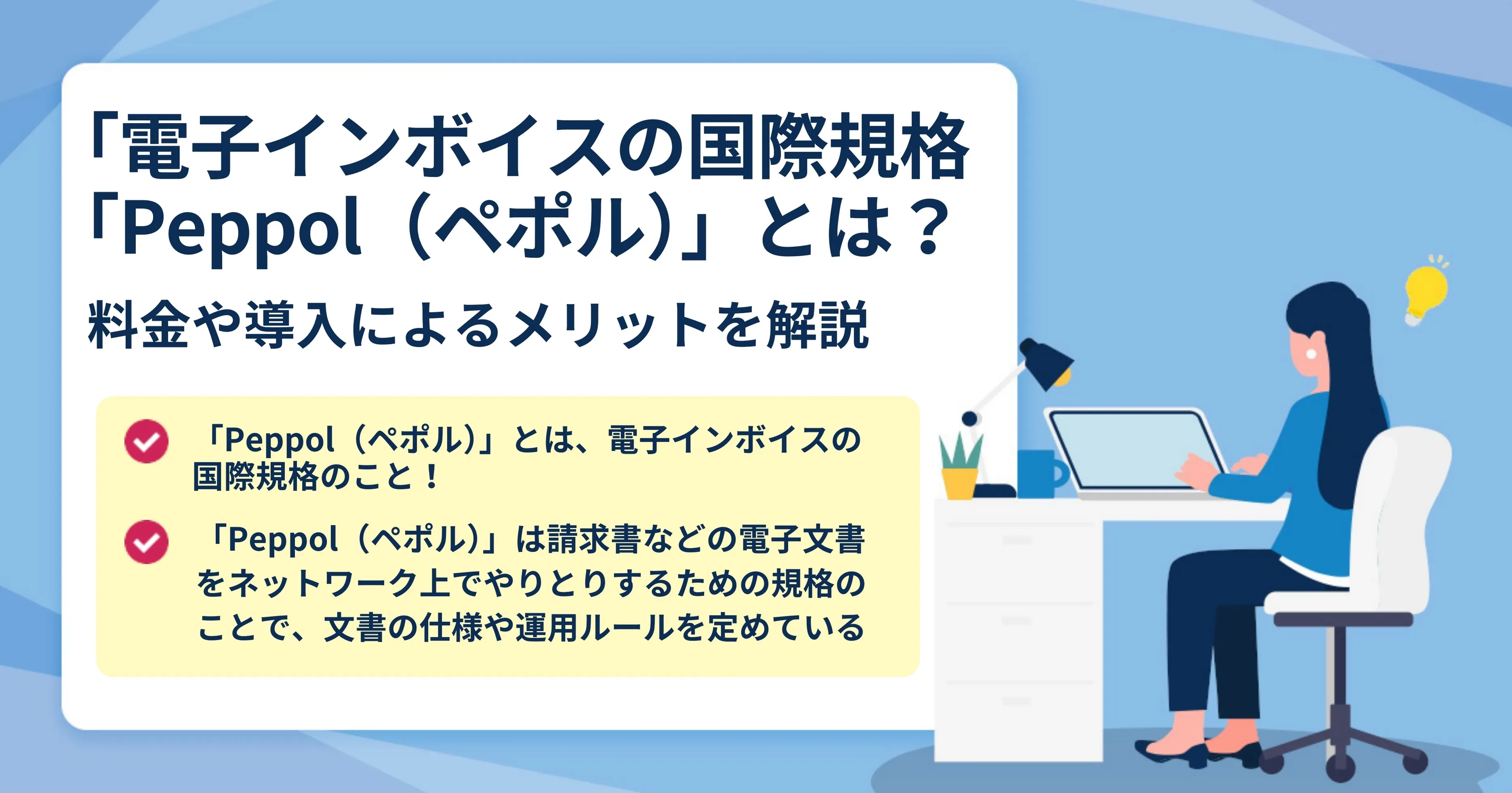
ー 目次 ー
近年注目を集めているのが、電子インボイスの国際標準規格である「Peppol(ペポル)」です。 Peppolは、異なる国やシステム間で電子インボイスを安全かつ効率的に交換するための共通の枠組みを提供します。 Peppolを導入することで、企業は国やシステムの違いを気にすることなく、電子インボイスをやり取りすることができ、業務効率の向上、コスト削減、コンプライアンス強化など、様々なメリットを享受できます。
本記事では、Peppolの概要、導入のメリット、料金体系に加え、日本における標準仕様である「Peppol BIS Billing JP」についても解説します。 また、電子インボイス導入のために企業が今からできる準備についても具体的に説明します。
- 電子インボイスとは
- Peppolとは
- Peppolの導入メリット
- Peppolの料金体系
- 日本におけるPeppolの標準仕様
- 電子インボイス導入のために今からできること
「Peppol(ペポル)」とは、電子インボイスの国際規格のこと!
電子インボイスとは?
電子インボイスとは、紙の請求書ではなく、電子データの形で発行・送受信される請求書のことです。 従来の紙の請求書に比べて、以下の様なメリットがあります。
- 業務効率の向上
- コスト削減
- 紛失・誤送のリスク軽減
- 保管スペースの削減
近年、多くの国で電子インボイスの導入が進んでおり、日本でも2023年10月1日からインボイス制度が開始されました。 インボイス制度では、適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者のみが、仕入税額控除の適用を受けるための適格請求書を発行することができます。
「Peppol(ペポル)」とは?
Peppol(ペポル)とは、汎欧州オンライン調達を意味する「Pan-European Public Procurement Online」の略称で、電子インボイスをはじめとした電子文書をやり取りするための国際標準規格です。 ヨーロッパを中心に世界各国で導入が進められており、日本でも2020年10月から利用が開始されました。
Peppolは、オープンネットワークとして設計されており、誰でも参加することができます。 参加者は、「アクセスポイント」と呼ばれるサービスプロバイダーを通じて、Peppolネットワークに接続します。 アクセスポイントは、Peppolの仕様に準拠したシステムを提供し、参加者間の電子文書の送受信を仲介します。
Peppolを利用することで、企業は、異なる国やシステム間で、電子インボイスを安全かつ効率的に交換することが可能になります。 例えば、日本の企業がPeppolに対応したシステムを導入すれば、ヨーロッパの企業と電子インボイスを直接やり取りすることができます。
日本では「Peppol BIS Billing JP」が標準仕様になる
電子インボイスでは、海外で利用されているペポルがそのまま使われるわけではなく、日本語版に仕様変更されたものが導入されます。
日本ならではの商習慣や法令に準拠した「Peppol BIS Billing JP」は現在もバージョン更新が繰り返されており、最新の動向はデジタル庁のホームページから確認できます。[注2]
[注2]デジタル庁:電子インボイスの標準仕様策定・普及
日本国内でも、電子インボイスの標準仕様としてペポルが普及すれば、経理のようなバックグラウンド業務の効率化も可能です。さらに、より自由な働き方の選択もできるようになります。
適格請求書(インボイス)の種類と違い
ここでは電子インボイスと通常の適格請求書に違いはあるかを解説します。
インボイス制度とは、正式名称を「適格請求書等保存方式」といいます。所定の要件を満たし、正しい消費税計算を行うために導入された制度のことです。
2023年10月の制度開始以降は、適格請求書(インボイス)でなければ、消費税の仕入控除を受けられなくなるため、売り手・買い手、双方に影響のある制度です。
ここでは、それぞれの請求書の種類と違いについて詳しく解説していきます。
- 紙ベースの適格請求書(通常のインボイス)
- ペポル経由の電子インボイス
- ペポル以外の電子インボイス
紙ベースの適格請求書(通常のインボイス)
紙ベースの適格請求書は、従来の請求書と同様に紙に印刷して発行されるものです。 インボイス制度に対応するためには、以下の記載事項が必要です。
- 請求書発行事業者の登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(商品名やサービス名など)
- 税率ごとに区分された消費税額など
紙ベースの請求書は、従来から慣れ親しんだ形式であるため、導入が容易というメリットがあります。 一方で、印刷、郵送、保管などのコストがかかり、業務効率の面では課題が残ります。 また、紛失や破損のリスクも考慮する必要があります。
ペポル経由の電子インボイス
ペポル経由の電子インボイスは、Peppolという国際標準規格に準拠した方法で発行される電子請求書です。 Peppolは、異なる国やシステム間で電子インボイスを安全かつ効率的に交換するための共通の枠組みを提供します。
ペポル経由で電子インボイスを発行する場合、送信側の企業はPeppolアクセスポイントを通じてインボイスデータを相手の企業に送信します。 受信側の企業もPeppolアクセスポイントを通じてインボイスデータを受信します。 Peppolアクセスポイントは、Peppolネットワークへの接続、データの送受信、セキュリティの確保などの役割を担います。
ペポル経由の電子インボイスは、国際標準規格に準拠しているため、セキュリティが高く、信頼性が高いというメリットがあります。 また、異なるシステム間でのデータ変換が不要になるため、業務効率の向上も期待できます。
ペポル以外の電子インボイス
ペポル以外の電子インボイスは、Peppol以外の方法で発行される電子請求書です。 例えば、EDI(電子データ交換)やメール添付などで請求書を送信する方法があります。
これらの方法で電子インボイスを発行する場合、取引先との間でデータのフォーマットや送受信方法などを個別に調整する必要があります。 そのため、Peppolに比べて導入や運用に手間がかかる場合があり、セキュリティ面でも注意が必要です。
電子インボイスのPeppol(ペポル)を導入する利点
Peppol導入の利点として、具体的にどのようなものがあるのか、詳しく見ていきましょう。
- 経理業務を紙ベースから電子データに移行できる
- 保管や管理がしやすく、またテレワークへの対応が容易
- 国内だけでなく、海外との取引も円滑に進められる
経理業務を紙ベースから電子データに移行できる
Peppolを導入することで、経理業務を紙ベースから電子データに移行できます。 従来の紙の請求書処理では、印刷、郵送、保管などの作業に多くの時間とコストを費やしていました。 Peppolを利用することで、これらの作業を電子化し、大幅に効率化することができます。
例えば、従来は請求書の発行、郵送、受領、確認、データ入力、ファイリングといった一連の作業に数日かかっていたものが、Peppolを導入することで、システム上で請求書を発行し、即時に相手先に送信、受領と同時にデータがシステムに反映されるため、作業時間を大幅に短縮することが可能になります。
保管や管理がしやすく、またテレワークへの対応が容易
電子データでの請求書管理は、紙の請求書に比べて、保管や管理が容易になります。 紙の請求書の場合、保管スペースが必要となるだけでなく、紛失や破損のリスクもあります。 一方で、電子データであれば、これらのリスクを回避できるだけでなく、検索や参照も容易に行えます。
また、Peppolはテレワークにも対応しやすいという利点があります。 電子データで請求書をやり取りすることで、場所を選ばずに業務を行うことが可能になります。
国内だけでなく、海外との取引も円滑に進められる
Peppolは国際標準規格であるため、国内だけでなく、海外との取引も円滑に進められます。 従来、海外との取引では、異なる請求書フォーマットやシステムに対応する必要があり、多くの時間と手間がかかっていました。 Peppolを利用することで、これらの問題を解決し、海外との取引をスムーズに行うことができます。
例えば、日本の企業がPeppolに対応したシステムを導入すれば、ヨーロッパやシンガポールなど、Peppolを導入している国の企業と、簡単に電子インボイスをやり取りすることができます。 これにより、海外取引における業務効率の向上、コスト削減、コンプライアンス強化などが期待できます。
電子インボイス導入のために今からできること
インボイス制度の開始は、2023年10月1日からです。また、電子インボイスのペポルは2022年の秋頃、各企業でシステム運用できるように調整されています。ここでは、電子インボイス導入のため、企業があらかじめできることを解説します。
適格請求書事業者の登録申請
インボイス制度を導入するためには、「適格請求書発行事業者」にならなければいけません。申請の受付は、2021年10月1日から開始され、書面またはe-Taxソフトで行えます。
なお郵送の場合は管轄する税務署ではなく、「インボイス登録センター」へ送付が必要です。[注3]
またe-Taxソフトは、法人か個人事業主かで利用できる方法が異なるため注意しましょう。
● 法人 :e-Taxソフト、e-Taxソフト(Web版)
● 個人事業主:e-Taxソフト、e-Taxソフト(Web版、SP版)
なお、インボイス制度の始動と同時に適格請求書が発行できるようにするためには、2023年3月31日までに登録申請を行う必要があるため、余裕をもって取り組みましょう。
[注3]国税庁:郵送による提出先のご案内
請求書の仕様変更
適格請求書事業者の登録申請をしたら、請求書も事前に適格請求書に適用できるように変更しましょう。
適格請求書では、下記の内容が記載されていないといけません。
- ● 適格請求書発行事業者の登録番号
- 適格請求書発行事業者の氏名または名称
- 取引年月日
- 取引内容
- 税率ごとに区分された対価の額と適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
- 書類を受け取る事業者の氏名または名称
法人番号が既に指定されている場合、先頭に「T」を付けたものが登録番号です。
また消費税は1つの適格請求書につき、異なる税率ごとに1回計算し端数処理を行います。現行の請求書は「区分記載」のため、明細ごとに消費税計算を行っているときは請求書やシステムの変更が必要です。
インボイス制度と電子帳簿保存法の理解を深める
電子インボイスを導入する際は、インボイス制度だけでなく、電子帳簿保存法の理解も必要です。理由として、インボイス制度で消費税の仕入額控除を受けるためには適切な方法で適格請求書を保管している必要があるためです。電子インボイスの場合、適切な保管は、電子帳簿保存法に準じた方法でなければいけません。
そのため電子インボイスを導入するには、インボイス制度だけでなく、電子帳簿保存法の理解もある程度深めておく必要があります。
電子インボイスの保存方法を導入する
デジタル庁の「よくある質問」によると、現行のPeppol(ペポル)には、ネットワーク中でやりとりした電子インボイスを保存する仕組みがありません。[注3]
しかし前述のとおり、電子インボイスは電子帳簿保存法に準じた方法で保存する必要があります。
そのため、タイムスタンプを押せるなど、適切な方法で保存できるクラウドサービスを事前に導入する必要があります。
[注3]デジタル庁:よくある質問:Peppolネットワークでの電子インボイスのやり取りについて(概要)
電子インボイスやPeppol(ペポル)導入のために、準備を進めよう
インボイス制度は、2023年10月よりスタートします。それと同時に電子インボイスやペポルも導入できるよう、EIPAで調整が進められています。
企業の対策としては、まずインボイス制度開始半年前までに、適格事業者の申請を済ませること。次に、電子インボイス導入に必要な仕組みの整備や知識を身に着けることが求められます。