請求書に印紙税はかかる?収入印紙のルールや対応方法を解説
更新日:2025.03.03
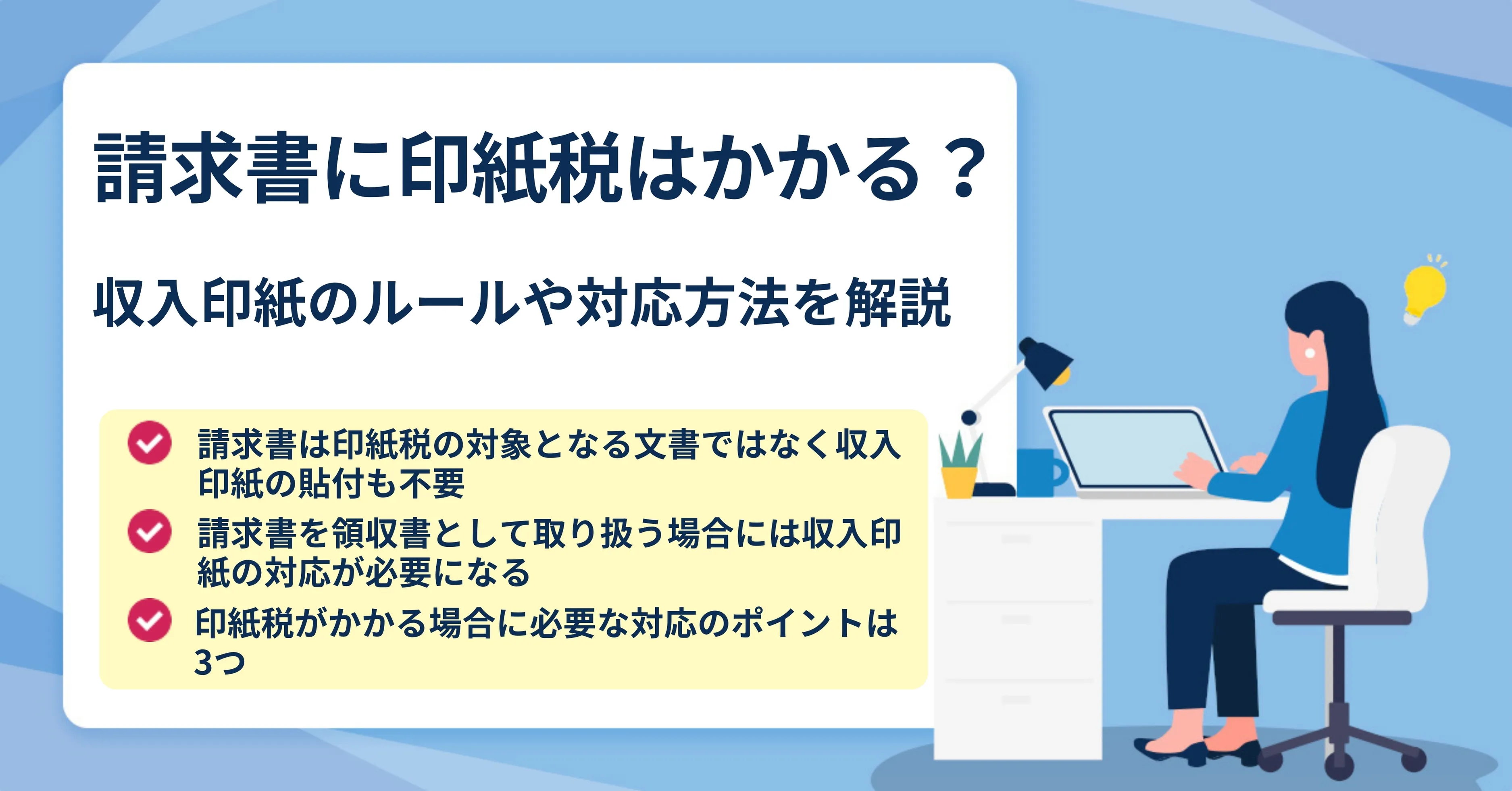
ー 目次 ー
「請求書」は取引による対価の支払いを求める大切な書類であり、ビジネスで多用されるものとなっています。
請求書は所得税や消費税などのさまざまな税金のルールにおいても大きな役割を担っているため、その扱い方を知っておかないと多方面でのトラブルになりかねません。これは「印紙税」も同様であり、請求書と似たような書類を対象とする印紙税との兼ね合いで疑問を抱く方も少なくありません。
税金によるトラブルを避けるためにも、印紙税法が定めるルールを把握しておくことが大切です。
本記事では、請求書における印紙税の対応について、収入印紙のルールや対応方法を解説します。
【原則】請求書に印紙税はかからない!収入印紙も不要!
そもそも「請求書」とは取引の完了にともなって商品・サービスを提供したことによる対価の支払いを依頼する書類です。このような役割から請求書は、印紙税の対象となる文書ではなく、収入印紙の貼付も不要です。
請求書と似たような書類が多くあり、書類によっては収入印紙が必要なものも存在します。また、請求書においても収入印紙が必要なケースもあるため、基本的な印紙税法のルールをおさえておくと良いでしょう。
【例外】請求書を領収書と兼ねる場合は印紙税の対象になる!
例外的に、請求書を領収書として取り扱う場合には収入印紙の対応が必要となります。これは請求書が領収書の役割を果たし、印紙税法のルールの対象の書類となるためです。
具体的には「代金を受領した旨」と「印鑑」が備わっていれば、領収書として認められます。仮に、書類のタイトルが「請求書」とあったとしても、記載内容で領収書となるケースもあるため注意が必要です。
印紙税とは?対象となる文書や印紙税額も解説
印紙税とは、「印紙税法」に定める文書を取り扱う取引をおこなった場合に発生する税金のことです。
印紙税法には日常的な取引にともなって使用する契約書や領収書などを含め、20種類の文書を対象としています。対象となる税額は文書や取引金額によって異なっており、「印紙税額の一覧表」で定めています。
印紙税は多くの取引で対象となる可能性があるため、経理に携わる場合には基本的なルールを把握しておくことが大切です。
ここでは、印紙税について、対象となる文書や印紙税額を解説します。
対象となる文書は、印紙税法で定められたもの
印紙税の対象となる文書は、日常的な取引で使用する基本的な文書が対象です。ただ、印紙税法の規定が文書ごとに細かく定められており、また文書によっても印紙税額が異なります。
このようなことから、実際の取引シーンにおいてはそれぞれの文書が対象となるかの確認が必要です。
- 領収書(金銭・有価証券などの受取書)
- 契約書
- 約束手形・為替手形
- 株券
- 定款
- 預金証書
- 貨物引換証・倉庫証券・船荷証券
- 保険証券
もし取り扱っている文書が対象となるかが不明な場合には、税理士をはじめとした専門家に確認することが大切です。
印紙税額は、200円〜60万円
印紙税額は対象となる文書や取引金額によって異なっており、最小額は200円、最高額は60万円と定められています。詳細は国税庁が提供する「印紙税額の一覧表」に記載されているため、取引ごとに確認しておくと良いでしょう。
<例>
|
号 |
文書の種類 |
|
|
1 |
不動産、鉱業権、試掘権、無体財産権、船舶もしくは航空機または営業の譲渡に関する契約書 |
〜1万円:非課税 1〜10万円:200円 10〜50万円:400円 50〜100万円:1,000円 100〜500万円:2,000円 500〜1,000万円:1万円 1,000〜5,000万円:2万円 5,000万〜1億円:6万円 1〜5億円:10万円 5〜10億円:20万円 10〜50億円:40万円 50億円〜:60万円 記載なし:200円 |
|
2 |
請負に関する契約書 |
〜1万円:非課税 1〜100万円:200円 100〜200万円:400円 200〜300万円:1,000円 300〜500万円:2,000円 500〜1,000万円:1万円 1,000〜5,000万円:2万円 5,000万〜1億円:6万円 1〜5億円:10万円 5〜10億円:20万円 10〜50億円:40万円 50億円〜:60万円 記載なし:200円 |
参考:国税庁「No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで」
印紙税がかかる場合に必要な対応のポイントとは?
印紙税がかかる文書を取り扱う場合には、収入印紙の貼付が必要です。ただ、慣れないうちは「どのような文書や取引金額で対応すべきか」の判断がつきづらいかもしれません。
そのため、印紙税がかかる文書を取り扱う場合のポイントをおさえたうえで対応するようにしましょう。
ここでは、印紙税がかかる場合に必要な対応のポイントについて、解説します。
①記載金額にあった収入印紙を貼付する
印紙税は国税庁の「印紙税額の一覧表」で定められており、文書に記載されている金額によって異なっています。
もし、貼付する収入印紙の金額が誤った場合には取引先とのトラブルになったり、誤納における手間がかかったりするため注意が必要です。
このような事態を避けるためにも、事前に国税庁の一覧表を確認し、印紙税額に対応した収入印紙を貼付するようにしましょう。
②消印をする
収入印紙を貼付したあとに、再利用を防止する目的で消印が必要です。消印は文書と収入印紙をまたがって押印する方法が一般的です。ほかにも署名での代用も可能であるため、取引や取引先の状況に応じて対応しましょう。
なお、消印がない場合には印紙税を納めたことにならないため、印紙税の対象となる文書を扱った際にはダブルチェックで消印の有無も確認することが大切です。
③誤った場合には、収入印紙をはがさない
収入印紙を誤って貼付した場合には、国税庁のルールによる然るべき対応が求められます。具体的には、「印紙税過誤納手続書」の作成と提出が必要です。記載された内容・提出物に問題がなければ、誤って添付した収入印紙分の印紙税が還付されます。
そのため、収入印紙の貼付を誤った場合でも、収入印紙をはがさないようにしましょう。
なお、手続きに必要な書類は国税庁のホームページからダウンロードできます。
>国税庁「D2-6 印紙税過誤納[確認申請・充当請求]手続」
電子契約書では印紙税が不要!これからの時代に対応しよう
昨今、IT技術やインターネットサービスの進化にともなって、文書の電子化による対応が推進されています。
現行のルールに則れば、電子化された文書には印紙税が不要です。従来、収入印紙の対応で発生していた業務も不要となり、コストや手間の削減、不要なトラブルの防止などのメリットがあります。ほかにもデータとして簡単に社内や取引先などに共有でき、利便性も高まることでしょう。
このように電子化が求められる昨今において、電子書面に対応したシステムやサービスの導入が必要となります。別記事では電子帳簿保存法のルールをまとめた記事もあるため、あわせて参考にしてください。
関連記事:電子帳簿保存法|見積書のよくある疑問を解決!どこまで保存が必要?
まとめ|請求書や印紙税のルールを理解して、トラブルのない対応を!
本記事では、請求書における印紙税の対応について、収入印紙のルールや対応方法を解説しました。
印紙税は領収書をはじめとして、さまざまな文書に関係するルールです。請求書においても影響のあるケースが存在するため、その扱い方には注意が必要です。
また、近年ではインボイス制度の施行や電子帳簿保存法の改正など、ビジネスで使われる書類のさまざまなルールが変更となっています。
このようなルールを把握しておかないと、大きなトラブルに巻き込まれるかもしれません。経理に携わる場合には本記事や本メディアの情報などを参考に、税金に関するルールを理解しておくことが大切です。










