請求書・納品書・領収書は役割が異なる!それぞれ代用できるかも解説
更新日:2025.03.03
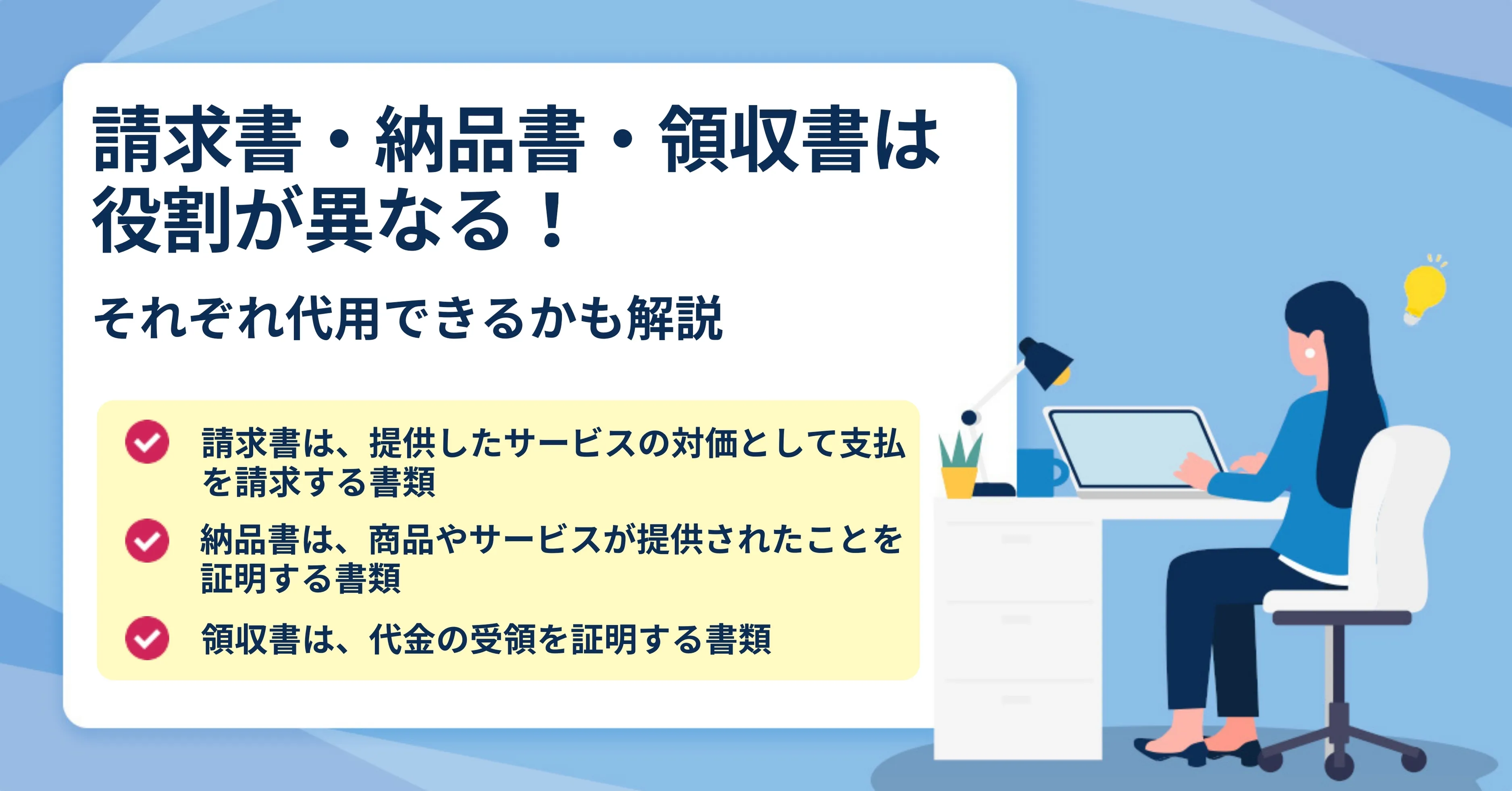
ー 目次 ー
取引をスムーズに進めるうえで、請求書・納品書・領収書は重要な書類です。各書類の役割をきちんと理解していないと、適切な処理ができないだけではなく、取引の証明ができずに取引先との信頼関係が損なわれる可能性があります。
したがって、取引を円滑に進めるためにも、各書類の役割を正しく理解して、適切なタイミングでの発行や保存が大切です。
本記事では、請求書・納品書・領収書の異なる役割について、それぞれ代用できるかもあわせて解説します。
【重要】請求書・納品書・領収書のそれぞれの役割
請求書・納品書・領収書は取引に関連する書類ですが、それぞれ異なる役割を持っています。これらの書類は税法上の「証憑書類」として扱われるため、適切に保管しないと税務調査で問題となるかもしれません。
書類の作成タイミングに関しては、一般的に以下の流れで書類が発行されます。
- 納品
- 請求
- 入金確認
- 領収書発行
この順序が入れ替わって書類の発行が遅れると、取引先との認識の違いが生じて支払いの遅延につながる可能性があります。そのため、各書類の役割と適切な発行タイミングを理解しておくことが重要です。
ここでは、請求書・納品書・領収書のそれぞれの役割について解説します。
①請求書の役割
請求書は、商品やサービスの対価として支払いを請求するための書類です。取引の最終的な金額や支払期限、支払方法などを明確にする役割があります。
請求書は通常、月に一度の月締めで発行します。同じ取引先と複数回の取引がある場合でも、月末にまとめて1枚の請求書として発行するのが一般的です。基本的には請求書を送付しなければ支払ってもらえないため、送付漏れのないようにしましょう。
②納品書の役割
納品書は、商品やサービスが提供されたことを証明する書類です。納品された商品やサービスの品名や数量、納品日などを確認できる重要な書類です。
納品書は、商品やサービスを納品する都度発行します。発注側にとっては商品を確かに受け取った証明に、受注側にとっては商品を正しく納めた証明となるため、取引の正確性を担保する重要な役割を果たします。
③領収書の役割
領収書は、代金の受領を証明する書類で支払証明として機能するため、取引先からの二重請求を防ぐという重要な役割があります。
また、領収書を入金確認前に発行してしまうと、実際には代金を受け取っていないにもかかわらず、受け取った扱いになってしまうため注意しましょう。
請求書・納品書・領収書はお互いに代用できるのか?
基本的に、請求書・納品書・領収書はそれぞれ異なる目的で発行されるため、相互に代用できません。書類の代用は条件によっては代用が認められる場合もありますが、各書類の果たす役割が異なるため、可能な限り個別に適切な書類を発行するのが望ましいです。
ここでは、請求書・納品書・領収書はお互いに代用できるのかについて解説します。
①請求書の場合
請求書と納品書は、異なる目的を持つ書類です。納品書は商品やサービスの提供を証明する役割があり、請求書は支払いを請求する役割があるため、請求書は納品書の代用にはなりません。
また、請求書は支払い前、領収書は支払完了後に発行される書類という性質の違いから、請求書は領収書としても処理できません。
ただし、銀行振込やカード支払いの場合は、振込明細と請求書がセットであれば、領収書がなくても経理処理上は領収書として認められます。この場合でも、請求書と明細は保管しておく必要があります。
②納品書の場合
納品書は、請求書の代用にはなりません。納品書は商品やサービスの納品事実を証明する書類であり、請求書とは発行目的が異なるためです。
また、納品書は基本的に領収書としても処理できません。ただし、納品書兼領収書として発行されている場合は、料金の支払いが完了している場合に限り領収書として使用できます。
納品書兼領収書は、取引の効率化のために一定数の取引先が使用しているため、取引先から提示された場合は内容をよく確認したうえで受け取りましょう。
③領収書の場合
領収書は代金受領の証明書類であり、発行タイミングや目的が大きく異なることから納品書や請求書の代用にはなりません。
民法486条で「弁済を受領した者に対して受取証書の交付を請求することができる」と規定(※)されており、支払完了を証明する重要な法的意味を持っています。納品書や請求書にはこのような意味はありません。
したがって、取引の透明性を確保して後々のトラブルを防ぐためにも、各書類は本来の目的に沿った適切な発行・保管が大切です。
(※)参考:e-Gov 法令検索「民法486条」
領収書の代用として認められる書類もある
領収書が発行されない場合でも、代用できる書類がいくつか存在します。具体的には以下のような書類が代用可能です。
- レシート
- 支払完了メール
- 銀行の振込明細
- 出金伝票
- 受領書
ただし、記載すべき項目が不足している場合は認められない可能性があります。書類を受け取る際には、宛て先や日付、金額などの必要事項が明記されているかを確認することが重要です。
請求書・納品書・領収書の作成におすすめな帳票発行システム3つ
帳票発行システムの利用で、書類作成の手間を大幅に削減でき、転記ミスや記載漏れの防止が可能です。とくに取引量が多い場合は、システムの導入がおすすめです。
また、2023年10月から始まったインボイス制度への対応も、帳票発行システムの利用で効率的に進められます。多くのシステムがインボイス制度に対応した適格請求書の発行機能を備えており、電子帳簿保存法にも対応しているため、法令順守の面でも安心です。
ここでは、請求書・納品書・領収書の作成におすすめな帳票発行システムについて解説します。
①OneVoice明細
OneVoice明細は、現在使用しているレイアウトがそのまま使える帳票発行の自動クラウドシステムです。OneVoice明細では、以下の書類の作成に対応しています。
- 請求書
- 納品書
- 支払明細
- 支払通知書
- 領収書
OneVoice明細はWeb発行機能による素早く確実な発行が可能で、1件からでも郵送代行に対応しています。また、取引先のダウンロード状況も確認できるため、書類の到達確認も簡単です。
導入時には2か月間の専任スタッフによる伴走サポートがあり、はじめての方でも安心して利用を開始できます。
②マネーフォワードクラウド請求書
マネーフォワードクラウド請求書は、テンプレートから簡単に各種帳票を作成できるサービスです。作成した書類はPDF形式でのメール送信が可能で、必要に応じて郵送もできます。
また、マネーフォワードクラウド会計・確定申告と連携して売掛金の仕訳を自動反映する機能も備えており、経理業務全体の効率化が図れます。さらに、インボイス制度の要件を満たした適格請求書の作成にも対応しています。
③Misoca
Misocaは、月10枚までの請求書作成が無料で利用できるクラウドサービスです。「取引先」「品目」「税率」などをテンプレートの入力フォームに記入・選択するだけで、簡単にきれいな帳票が作成できます。
Misocaは、見積書から納品書・請求書への変換や、請求書から領収書・検収書の作成もクリック操作でスムーズにできます。また、固定の取引は請求書の自動作成・自動メール機能を使えば、作成から送付まで手間の大幅な削減が可能です。
さらに、インボイス制度や電子帳簿保存法にも対応しているため、法令順守の面でも安心です。
まとめ|請求書・納品書・領収書の役割を理解して適切に発行・管理しよう
本記事では、請求書・納品書・領収書の異なる役割について、それぞれ代用できるかもあわせて解説しました。
請求書・納品書・領収書はそれぞれ異なる役割を持ち、原則として相互の代用はできません。これらの書類の適切なタイミングでの発行と管理が、取引先とのトラブルを防ぎ、円滑な取引関係を維持するために重要です。
とくに取引量が多い場合は、帳票発行システムの導入がおすすめです。システムの利用で、書類の作成や管理にかかる時間を大幅に削減できるだけではなく、記載漏れの防止やインボイス制度への対応も効率的に進められます。










