請求書の一般的な支払期限とは?よくあるトラブルや対処法も解説
更新日:2025.09.06
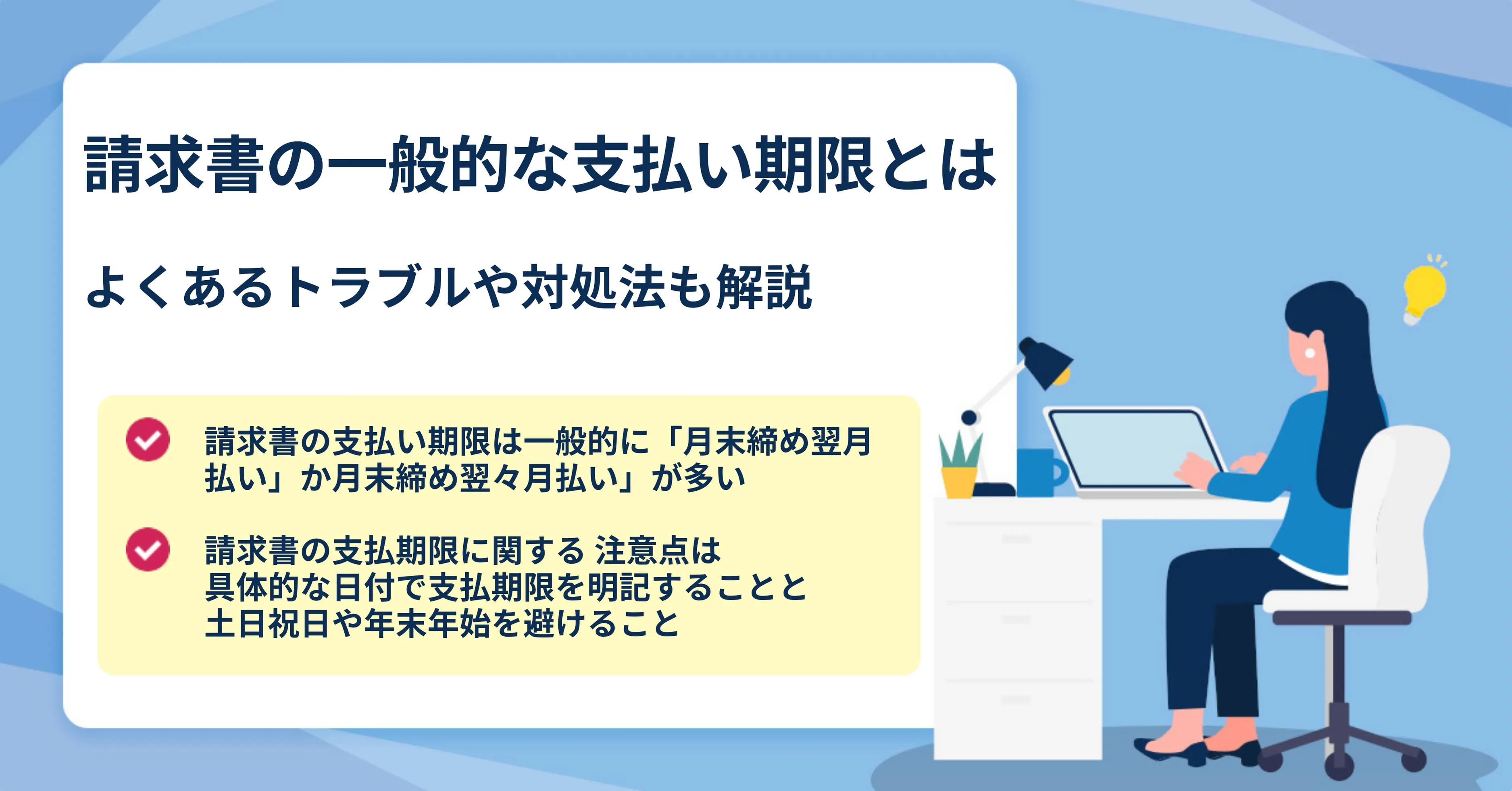
ー 目次 ー
請求書の支払期限は企業によって異なるため、混乱を避けるためにも自社の規定を決めておくと取引先とのやり取りがスムーズになります。取引開始前に支払期限の認識のズレをなくしておけば、安心して取引を進められます。
しかし、事前に支払期限を決めておいても、トラブルを完全に防げるわけではありません。
本記事では、請求書の一般的な支払期限でよくあるトラブルを解説します。実際にトラブルが発生した場合に焦らずに済むよう、事前に対処法を理解しておきましょう。
請求書の支払期限は企業によって異なる
請求書の支払期限は、企業が自由に設定できる項目です。ただし、資本金が1,000万円を超えている企業が業務を依頼する場合は、下請代金支払遅延等防止法によって請求が確定してから60日以内の支払いが義務付けられています(※)。
そのため、請求書の支払期限は一般的に「月末締め翌月払い」か「月末締め翌々月払い」が多くなっています。
また、請求書の支払期限がそれぞれ異なる場合、取引先を混乱させてしまう可能性があります。請求書の支払期限を決めるときは、毎月同じ日に設定し、取引先の負担を減らしましょう。
(※)参考:e-Gov 法令検索「下請代金支払遅延等防止法」
請求書の支払期限に関する2つの注意点とは?
請求書の支払期限を決めるときは、勘違いを避けるためにも取引先にわかりやすいよう配慮する必要があります。あいまいな記載をしてしまうと、お互いの認識の誤りが原因でトラブルに発展する可能性も否定できません。
また、安全に取引を進めるためには、請求書を発行する前に、取引先と支払期限をすり合わせておくと安心です。
①請求書に具体的な日付で支払期限を明記する
請求書に支払期限を記載するときは、「〇月〇日」と明確な日付を指定しましょう。「取引終了から翌月末」や「請求書発行日の翌々月末」などのあいまいな表現で記載すると、取引先の認識と齟齬が生まれる可能性があります。
また、会計ソフトで請求書を発行するときは、支払期限の欄を明記しましょう。支払期限を空欄のまま発行してしまうと、取引先は支払期限がわからず、未払いなどのトラブルに発展する可能性があります。万が一支払期限を記載し忘れてしまった場合は、取引先へ連絡して明記した請求書に差し替えをお願いしましょう。
②土日祝日や年末年始を避ける
毎月15日や月末などを支払期限に設定していると、支払期限が土日祝日になってしまう場合もあります。土日祝日や長期休暇に振込がおこなわれると、金融機関の休業日と重なってしまい、入金確認まで時間がかかるかもしれません。
取引先から日付の指定がないときは、土日祝日や年末年始、ゴールデンウィークなどの長期休暇を避けて設定すると明確な日付が取引先に伝わります。もしくは、請求書のやりとりをする前に、土日祝日や長期休暇に支払期限が重なった場合は、「直近の平日に支払う」といったルールを決めておく方法もおすすめです。
請求書の支払期限でよくあるトラブル3選
請求書の支払期限をきちんと設定していても、取引先の状況や設定した内容によってトラブルに発展する可能性があります。事前にどのようなトラブルが発生するかを理解しておくと、適切な対策を講じて取引先と良好な関係を築けるでしょう。
ここからは、請求書の支払期限でよくあるトラブルや対処法を3つ解説します。
- 請求書で指定された支払期限が短すぎる
- 請求書の支払期限を過ぎても支払われない
- 受け取った請求書に支払期限が書いていない
①請求書で指定された支払期限が短すぎる
支払期限は下請代金支払遅延等防止法によって、請求が確定してから60日以内の支払いが義務付けられています。しかし、期間内であれば好きな日を企業が設定できるため、短めに設定されることもあります。
請求書に記載された支払期限が3日後、1週間以内など明らかに短い場合は、取引先に延長が可能か確認しましょう。早めに相談しておくことで、今後の取引でも急な支払期限に焦る心配が少なくなります。
②請求書の支払期限を過ぎても支払われない
請求書に明確に支払期限を記載したにもかかわらず、期限内に支払いがおこなわれない場合は、取引先のミスが考えられます。
請求書の支払期限を過ぎたからといって、ただちに支払能力がないとは判断できません。まずはメールで取引先に連絡しましょう。メールなら記録が残るうえ、取引先のミスであれば連絡後すぐに支払われる可能性があります。
連絡をしてから一定期間様子を見ても支払われない場合は、取引先が意図的に支払いを無視しているかもしれません。何度か取引先に連絡しても支払われない場合は、法的措置も検討しましょう。
③受け取った請求書に支払期限が書いていない
自社が支払う側だったときは、請求書が届いたタイミングで支払期限の記載が漏れていないか確認することをおすすめします。万が一、受け取った請求書の支払期限が未記入の場合は、速やかに取引先へ連絡しましょう。
取引先とやり取りしたうえで「指定なし」と言われた場合は、下請代金支払遅延等防止法に合わせて60日以内に支払うことが求められます。しかし、トラブルを避けるためにも、取引先から指定がない場合でも支払期限をあらかじめ決めておくと安心です。
請求書の支払期限を過ぎても支払いがないときの対処法4つ
請求書の支払期限を過ぎても取引先から支払いがないときは、以下の手順に沿って対応しましょう。
- 自社のミスをチェックする
- 取引先に連絡を取る
- 内容証明を送る
- 支払督促を申し立てる
順序を間違えると取引先とのトラブルが大きくなり、今後の関係性を維持することが難しくなります。支払いがおこなわれていない場合でも、冷静に対処することが大切です。
①自社のミスをチェックする
支払期限までに支払いがないときは、まずは自社のミスがないか確認しましょう。自社にミスがあったにもかかわらず取引先へ先に確認してしまうと、トラブルが大きくなる可能性があります。
請求書に支払期限を記載したつもりでも、予定とは違う日を記載していないか、未記入で発行していないかを確認しましょう。
また、請求書を送付したつもりでもメールが送信できていないケースも考えられます。さらに、送信先が誤っており、ほかの会社に送っている可能性も確認しましょう。
②取引先に連絡を取る
自社のミスを確認して思い当たる点がなければ、取引先に連絡しましょう。連絡はメールでおこない、記録に残る形にすることがおすすめです。
また、取引先が支払いを忘れているだけの可能性もあるため、連絡時は丁寧な言い方を意識しましょう。責めるような言い方をしてしまうと、取引先が不快に感じてしまい、今後の取引に支障が出るかもしれません。
何度か連絡してもつながらない場合や、支払いが行われない場合は、法的措置も選択肢として考えましょう。
③内容証明を送る
請求書の支払期限が過ぎており、何度連絡しても取引先から支払いがおこなわれない場合は、内容証明を送付しましょう。内容証明とは、郵送した書面の内容や日付、送付先を郵便局が証明する発送方法です(※)。
内容証明には、契約内容や取引内容の詳細、再度の支払期限を設け、支払いがなければ法的処置を取る旨を記載しましょう。内容証明を事前に送付すると、裁判になったときに再度の請求日を定めていることが法的に証明され、自社の立場を守ることができます。
(※)参考:日本郵便株式会社「内容証明」
④支払督促を申し立てる
内容証明を送付しても記載期日に支払いがおこなわれない場合は、裁判所に支払督促を申し立てることができます。支払督促を申し立てると、裁判所が自社に代わって取引先へ支払いの催促をおこなってくれます。
支払督促は書類で審査されるため、訴訟のように裁判所へ足を運ぶ必要がなく、手間が少ない点がメリットです。取引先に支払督促が届いてから2週間以内に異議申立てがおこなわれなければ、強制執行となります。
参考:最高裁判所「支払督促」
請求書は支払期限を過ぎても有効期限が存在する
請求書は支払期限を過ぎても、支払期日の翌日から5年間の有効期限が存在します。この有効期限が過ぎると、取引先からの支払いがなくても請求できなくなるため注意しましょう。
また、時効の日が近づいているからといって、請求書を再発行しても有効期限は延びません。請求書の時効までの期間を延ばしたい場合は、内容証明を送付するか、支払督促をおこないましょう。
内容証明を送付すれば取引先の手元に到着してから6カ月間、支払督促によって権利が確定すれば、有効期限が更新されます。
なお、請求書の有効期限は2020年の民法改正時に変更となっています。2020年4月1日以降発行の請求書は5年間の有効期限ですが、2020年3月31日までに発行された請求書は2年間が有効期限のため注意しましょう。
まとめ|請求書は支払期限を明記してトラブルを防ごう
本記事では、請求書の一般的な支払期限や請求書の支払期限でよくあるトラブルを解説しました。
請求書の支払期限は、下請代金支払遅延等防止法によって60日以内で設定されることが一般的です。支払期限の記載がされていないと、取引先もいつ支払えば良いのかわからず、トラブルに発展する可能性があります。
請求書の支払期限に関するトラブルを避けるために、まずは自社のミスを防ぎましょう。他社に迷惑をかける機会を減らすことが円滑な取引につながります。
また、請求書を発行する際は具体的な支払期限が明記されているか確認し、取引先と認識のズレがないようにしましょう。










