請求書を年度またぎで経費精算できる?処理方法や計上まで解説
更新日:2025.03.03
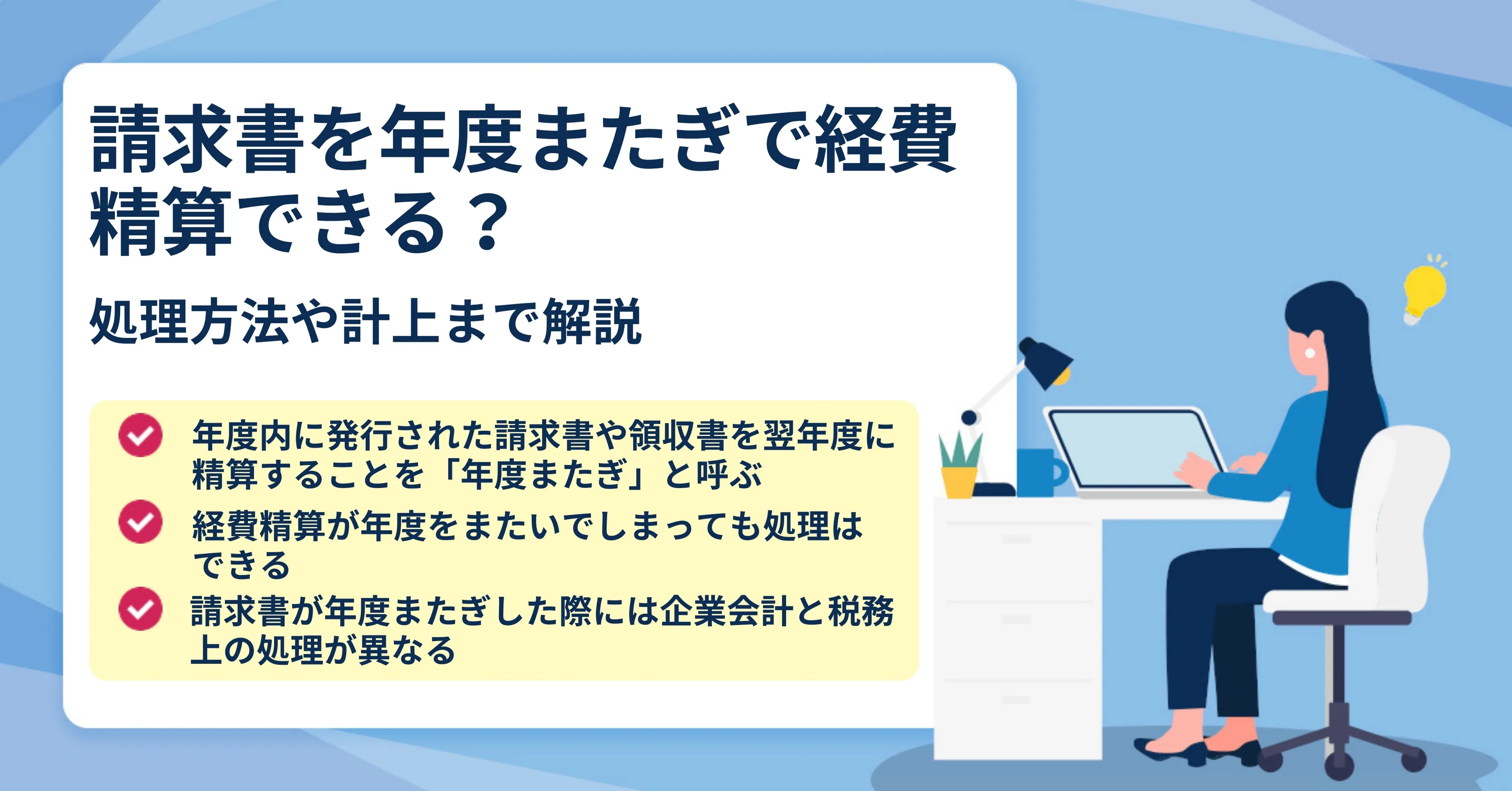
ー 目次 ー
基本的に、請求書の精算は同一年度内に完了させなければなりません。しかし、やむを得ず年度をまたいで精算になることもあるでしょう。
年度をまたぐ経費精算では、通常と異なる計上方法や税務処理が求められるため、正確な対応が必要です。
適切に対応ができないと確定申告の際に正しく計上できない可能性があります。また、決算書に影響すると外部の企業からの信頼性が損なわれるおそれもあるでしょう。
本記事では、請求書が年度またぎした際の経費精算について、処理や計上の方法を交えて解説します。
請求書の経費精算は年度またぎでも処理は可能!
年度内に発行された請求書や領収書を翌年度に精算することを「年度またぎ」と呼びます。
税法において、経費は発生した年度内に計上することが原則です。
しかし、法的には翌年度に経費精算しても問題ありません。これは、民法第166条にて定められている「経費精算は5年または10年以内であれば期限内に精算できる」といったルールが要因となります。
|
第百六十六条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。 一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。 二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。 |
請求書が年度またぎしたとき経費はどう処理するのか?パターン別に解説
請求書が年度またぎした際には企業会計と税務上の処理が異なります。計上漏れを防ぐためにも事前に理解しましょう。
ここでは、請求書が年度またぎしたときの処理についてパターン別に解説します。
企業会計としての処理
企業会計は発生主義の原則にしたがって、実際の支払いの時期ではなく取引が発生したタイミングで費用を計上します。
発生主義とは、現金の受け取りや支払いのタイミングに関わらず、取引が発生した時点で会計上の認識・記録する方式です。
たとえば、1月を事業の新年度としている企業で、以下のような状況が発生したとします。
- 12月に商品やサービスの提供を受けた(取引発生)
- 1月に請求書を受け取り、経費精算した
このような状況では発生主義の考え方にもとづき、実際の支払いが翌年度の1月でも、取引が発生した前年度の会計として処理します。
税務上の処理
税務上の処理も基本的には企業会計と同様に、発生主義にもとづいて年度内に損金計上することが原則です。
一方で、年度をまたいでしまった場合には、税務上は経費精算した年度の損金として処理する必要があります。
たとえば、1月を事業の新年度としている企業で、以下のような状況が発生したとします。
- 12月に取引が発生
- 1月に経費精算を実施
この場合、税務上は経費精算した新年度の損金として計上することになります。税務上では、経費精算したタイミングでの処理となるため会計と混同しないように注意しましょう。
年度またぎした請求書の会計の計上方法とは?
年度をまたぐ請求書の精算では、支払いのタイミングにより計上方法が変わります。計上方法を誤ると、会計処理の不整合が生じてトラブルにつながる可能性があるでしょう。
ここでは、年度またぎした請求書の会計の計上方法を解説します。今回紹介する例は1月から12月までを事業年度の区切りとしている企業のケースです。
先払いの場合
事業年度末の12月末から新年度の1月頭にかけて6日間開催するイベントに会社として出展することになり、費用として30万円を支払う際には以下のように処理します。
|
借方 |
貸方 |
|||
|
12月 |
広告宣伝費 |
150,000円 |
現金 |
300,000円 |
|
前払費用 |
150,000円 |
|||
|
1月 |
広告宣伝費 |
150,000円 |
前払費用 |
150,000円 |
後払いの場合
12月下旬〜1月上旬に受けたコンサルティングを受けて1月末に費用を支払います。コンサル費用として50万円を支払う場合、以下のように処理します。
|
借方 |
貸方 |
|||
|
12月 |
コンサルティング費 |
250,000円 |
現金 |
250,000円 |
|
1月 |
コンサルティング費 |
250,000円 |
前払費用 |
500,000円 |
|
未払費用 |
250,000円 |
|||
年度またぎした請求書を処理する2つの注意点
年度またぎした請求書を処理する際に、いくつかの注意点があります。注意点を理解しないと精算処理の影響で、取引先の企業からの信用問題につながるおそれがあるでしょう。
ここでは、年度またぎした請求書を処理する際の注意点を解説します。
①確定申告を超えてしまうと損金計上ができない
法人の確定申告は、事業年度終了後、2か月以内が提出期限となります。例として、12月末決算の企業は、1月から12月までの事業年度分を翌年2月28日(閏年は29日)までに申告しなければなりません。
確定申告で計上する金額は、その対象年度内に発生した経費に限定されます。前年度12月発生の経費を翌年1月に精算した場合は、翌年度の損金として計上する処理が必要です。
さらに、次年度としての計上を怠った場合は、損金としても認められなくなるため適切に管理しましょう。
②年度またぎをすると信用問題に影響する
年度をまたぐ請求書精算は、決算の修正や遅延を引き起こす可能性があり、決算書に影響します。決算書は公的な書類であることから、決算書の不備によって周囲からの信用を失うおそれがあります。
決算書は、企業の成績や財政状況を表す重要な書類です。決算書に影響が出ると、報告を受ける外部の取引先や銀行から「適切な会計管理ができていない企業」との評価を受けるリスクがあります。
このような信用低下の可能性を考慮すると、できる限り年度をまたぐ経費精算は避け、適切な時期に処理するようにしましょう。
請求書を年度またぎで処理しないための対策
年度またぎで請求書の処理をすると社内の問題のみに限らず、社外との信用問題にもつながります。年度またぎを防ぐためにも対策しておくことがおすすめです。
対策しておくことで、ミスの予防や修正発生の迅速な対応もできるでしょう。
ここでは、請求書を年度またぎで処理しないための対策を解説します。
①社内のルールを見直す
請求書が年度またぎになる理由として、従業員の提出遅れが多い場合は、社内のルールを見直すことがおすすめです。たとえば、以下のような社内ルールを設定します。
- 月全体では25日までに提出
- 出張後の精算は3営業日まで
ルールを決めたら、役職者のみではなく従業員全体に情報を共有して周知徹底しましょう。また、毎月末に社内メールなどで納期が近づいていることを連絡することで提出忘れを防止できます。
②管理システムを導入する
もし社内で請求書を手書きで作成していたり、印鑑をもらうために時間がかかったりする場合はシステムを導入することがおすすめです。システムを導入することで、従業員はデータの入力のみの短時間で請求書を作成できます。
また、電子データを使用して社内の承認フローを確立させることで、印鑑をもらう手間などが軽減します。
進捗が進まない場合も原因が分かるため、担当者に声をかけるなどの対応もできるため効率化が図れるでしょう。
まとめ|計上のルールを覚えて請求書の年度またぎでもスムーズに対応しよう!
本記事では、請求書が年度またぎした際の経費精算について、処理や計上方法を交えて解説しました。
税法において、経費は発生した年度内に計上することが原則です。しかし、翌年度に経費精算しても法的には、問題ありません。ただし、企業会計と税務上の処理で対応が異なるため、正しく計上しましょう。
年度またぎにより決算書に影響が生じると、関係のある企業や銀行からの信用問題につながるため、発生させないよう対策することも大切です。具体的には、社内のルール見直しや、管理システムの導入などの検討が必要でしょう。










