【テンプレートあり】請求書の表紙の作り方とは?記載項目も詳しく解説
更新日:2025.09.05
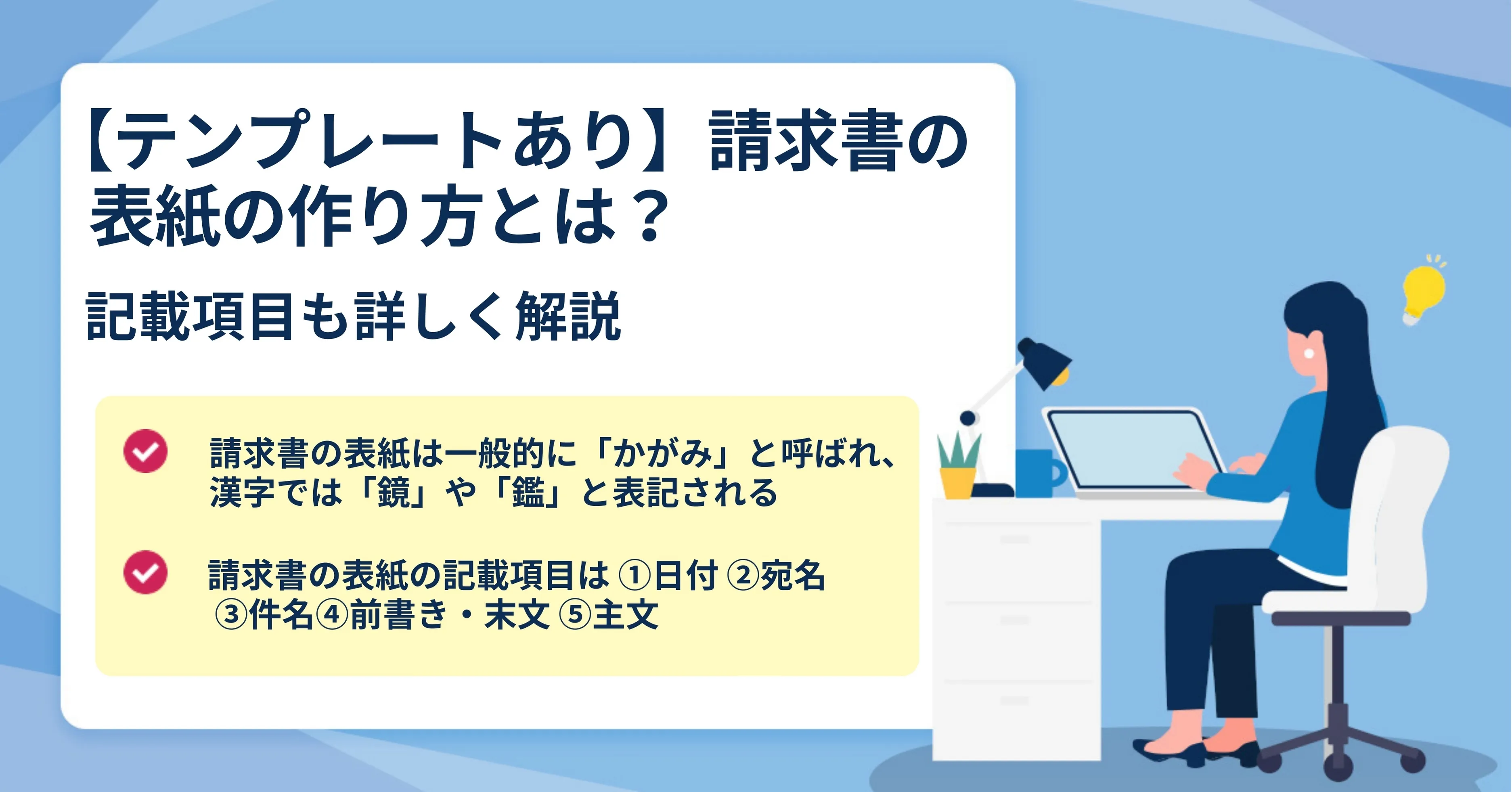
ー 目次 ー
請求書の表紙は、「かがみ」や「頭紙」と呼ばれており、郵送やFAXで書類を送るときに使用されます。表紙は、郵送やFAXで請求書を送るときに同封書類の内容が一目でわかるため、おさえておきたいビジネスマナーのひとつです
本記事では、請求書の表紙の作り方や作成例を解説します。郵送・FAXで書類を送る機会が多い企業は、ぜひ参考にしてください。
請求書の表紙は一般的に「かがみ」と呼ばれる
請求書の表紙は「かがみ」とも呼ばれ、ビジネスマナーのひとつです。請求書を郵送やFAXで取引先に送るときに使用されます。
表紙には同封した書類の内容が記載されており、取引先が送付内容を一目で確認できることが目的です。
請求書のかがみは、漢字で「鏡」もしくは「鑑」と記載されます。ほかにも、「送付状」「頭紙」などと呼ばれる場合もあるため、表紙をつけたときは同じ用途の書類を同封する必要はありません。
請求書の表紙の作り方とは?
請求書の表紙を作るには、一から自分で作成する方法と、Officeソフトのテンプレートを使用する方法があります。それぞれのメリットを理解したうえで、自社に合った方法を選びましょう。
ここでは、請求書の表紙の作り方を解説します。
①手書き・文書作成ソフトで作成する
自分で一から請求書の表紙を作る場合は、手書きあるいはWord・Googleドキュメントなどの文書作成ソフトを利用しましょう。
パソコンを使用できない方以外は、文書作成ソフトの利用がおすすめです。自分で一から作成する場合は、手間がかかる分自社に合った内容で作成できます。文書作成ソフトを利用すれば一度作成したフォーマットは翌月以降も使用できるため、表紙を作成する手間が減らせるでしょう。
②テンプレートを利用する
自分で一から作成する時間がない場合は、WordやExcelなどのOfficeソフトに用意されているテンプレートを使用しましょう。大まかな作成項目がすでに入力されているため、「宛名」や「差出人」など必要な部分のみ変更すれば使用できます。
ただし、テンプレートを使用する場合は書き換えるべき項目の変更忘れに注意が必要です。別の取引先のデータが残ったまま送信してしまえば、情報漏洩となり信用を失う可能性があります。
請求書の表紙の記載項目
請求書の表紙を一から作るなら、必要な項目を理解しておくと作成がスムーズに進みます。テンプレートを使用する場合は、必要な項目が揃っているかあわせて確認しておきましょう。
ここからは、請求書の表紙に記載する項目を解説します。
- 日付|書類発送日
- 宛名|取引先の情報
- 件名|送付書類の名称
- 前書き・末文|挨拶文
- 主文|請求書の内容
①日付|書類発送日
請求書の表紙には、書類を発送する日を記載しましょう。請求書の発行日と発送日が異なる場合は、日付がずれていても問題ありません。
記載時は、書類の日付を和暦・西暦で統一することで書類が見やすくなります。なお、西暦は「2024年」を「24年」のように略して記載してしまうと、取引先に和暦と誤解を招く可能性があります。
②宛名|取引先の情報
請求書の表紙には、宛名として会社名・部署名・電話番号・担当者名などの情報を記載しましょう。
テンプレートを使用する場合は、前回記載した取引先の情報が記載されていないか確認することが大切です。情報を変えないまま発行してしまうと情報漏洩につながり、取引先の信用を失う可能性があります。
③タイトル|送付書類の名称
表紙には、送付書類が請求書とわかるようタイトルを記載しましょう。さらに、「〇年〇月分」のようにいつの請求書か記載することで、取引先が請求月ごとに管理しやすくなります。
なお、表紙を作成するときはタイトルをほかの文字よりも大きくすることで、取引先が見やすくなります。
④前書き・末文|挨拶文
表紙の文章を記載するときは、本題から入るのではなく、季節の挨拶や普段のお礼を記載しましょう。さらに、「拝啓」や「敬具」などの頭語と結語をつけることで、ビジネスマナーを守ったものとなります。
内容の最後には、「今後とも何卒よろしくお願いいたします」のような文章を記載しておくことで、取引先に丁寧な印象を与えます。
⑤主文|請求書の内容
表紙には、何の取引の請求書か理解できる内容を記載しましょう。取引の内容が明確でないと、取引先が書類を確認する手間を増やしてしまいます。
なお、請求金額の内訳は請求書内で確認できるため、表紙に記載する必要はありません。
【テンプレート】請求書の表紙(かがみ)の作成例
請求書の表紙の作り方に悩んだら、以下のテンプレートを利用して作成しましょう。自社にあわせて必要な部分を変えて、ぜひ使用してください。
|
〇〇年〇月〇日 〇〇株式会社 御中 取引先住所 取引先電話番号 担当者名 △△株式会社 自社住所 自社電話番号 担当:〇〇 請求書|〇〇年〇月分 拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 先日納品させていただきました、〇〇の商品に関しまして、請求書を同送いたします。 ご多忙の中とは存じますが、ご確認の程宜しくお願い申し上げます。 今後とも何卒よろしくお願いいたします。 敬具 記 ・請求書(〇〇年〇月分) 一式
|
表紙の最後には、「以上」をつけることで書類の記載事項が終了したと取引先に伝わります。
請求書の表紙を作成する手間を減らすなら電子化がおすすめ!
表紙は請求書を郵送やFAXするときに送付されるため、電子メールで請求書をやりとりする場合は不要です。このことから、表紙の作成業務を減らすのであれば請求書を電子化すると経理の業務軽減につながります。
ほかにも、請求書の電子化は郵送のコストを減らせ書類管理も楽にできる可能性があります。
請求書を電子化することで「取引先に負担をかけるのではないか」と思ってしまい、電子化を前向きに考えられない場合もあるでしょう。しかし、近年は請求書を電子化する企業が増えているため、自社が変更しても大きな負担をかける心配は少ない可能性があります。
請求書を電子化する3つのメリット
請求書を電子化するか悩む場合は、メリットを理解しておくことで検討しやすくなります。請求書の電子化は無料でできるとは限らないため、自社が損をしないために、メリット面を理解しておきましょう。
ここからは、請求書を電子化する3つのメリットを解説します。
- 請求書の作成・管理業務を楽にできる
- 郵送にかかるコストを減らせる
- ペーパーレス化につながる
①請求書の作成・管理業務を楽にできる
請求書を電子化することで、保管も電子データとなるため、将来的に請求書を検索するときもクラウドデータの利用が可能です。
ほかにも、請求書を作成するときに同じ取引先であれば前月の内容を書き換えて発行ができ、一から請求書を作成する手間が少なくなります。請求書の宛先や差出人などは、毎月書き換えているとミスが起きかねないため、前月の内容を使用できれば取引先の信用を失う可能性も減らせます。
さらに、請求書を発行したかどうかが電子データ上で管理でき、発行忘れも防げるでしょう。
②郵送にかかるコストを減らせる
請求書を電子化してメールで送信することで、郵送の必要がなくなり切手代を減らせます。毎月請求書の発行件数が多い企業だと、取引先ごとに郵送代が発生してしまい、大きなコストになる可能性があります。
さらに、郵送によるトラブルの心配がなくなり、再度郵送代がかかる心配もありません。
ただし、請求書の電子化に料金がかかる場合は、郵送代がかからない点以外にもメリットを見つけ、コストに見合った業務軽減が可能かを検討しましょう。
③ペーパーレス化につながる
請求書を電子化することで、自社で請求書を紙で発行する機会が減り、ペーパーレス化の推進につながります。ペーパーレス化が推進できれば、社内で書類を保管するスペースが必要なくなり、限られた空間を使いやすくなるでしょう。
また、紙の請求書ではないことから、内容に誤りがあってもすぐに修正・再発行が可能です。
まとめ|請求書の表紙はビジネスマナーとして用意しよう
本記事では、請求書の表紙の作り方や作成例を解説しました。
郵送やFAXで請求書を送る場合、「かがみ」と呼ばれる表紙を送付することがビジネスマナーです。請求書の表紙を作成するときは、Officeソフトのテンプレートを利用すれば、スムーズに作成ができます。
さらに、請求書の表紙を作成する業務自体を減らすなら、請求書を電子化する方法もあります。本記事を参考に請求書を電子化するメリットを理解して、自社に導入するか決めましょう。









