請求書の締め日と発行日は異なる!発行時の注意点や業務効率化のポイントも解説
更新日:2025.03.03
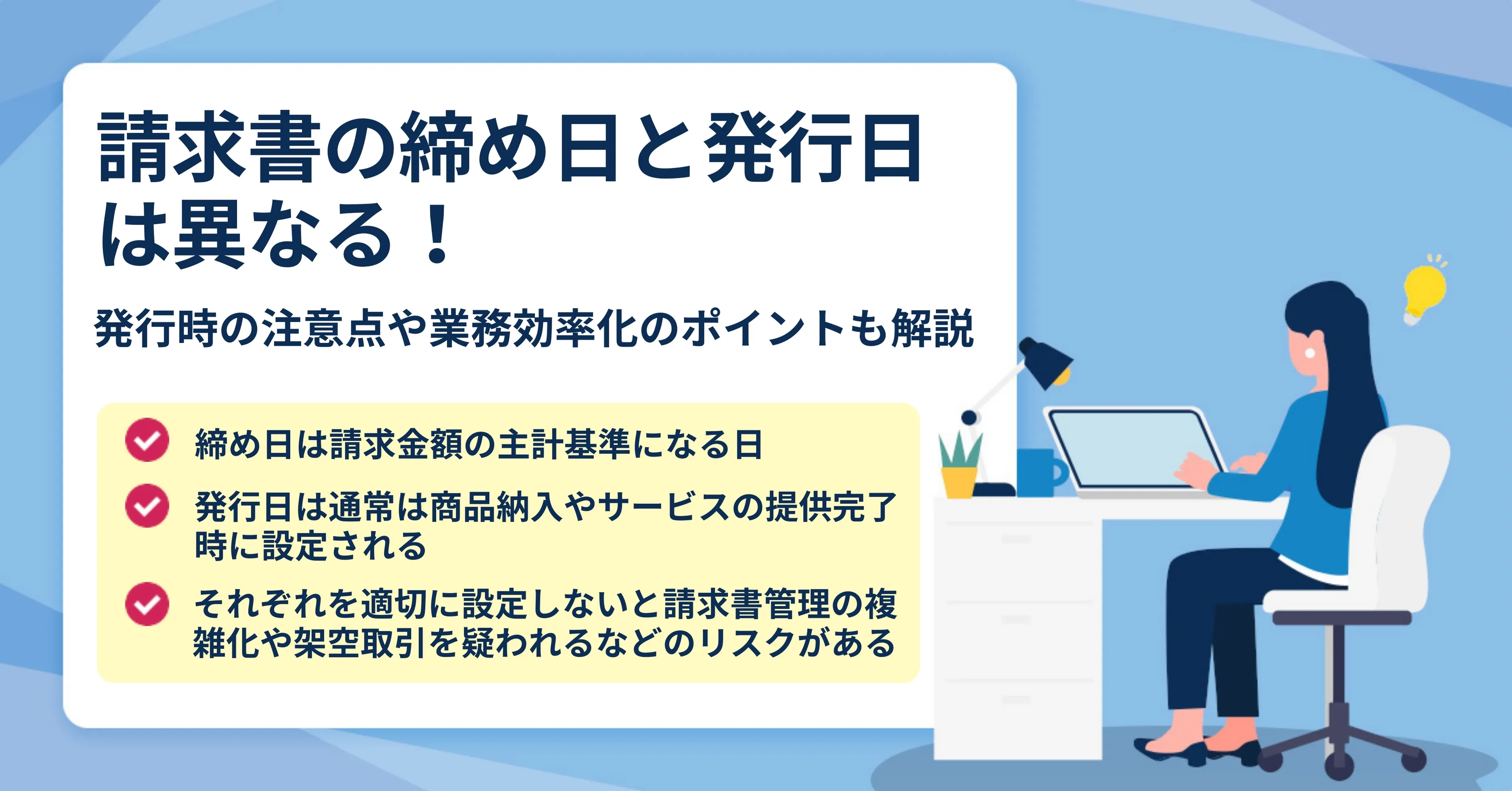
ー 目次 ー
請求書の「締め日」と「発行日」は混同してしまいがちな用語ですが、明確な違いがあります。取引先も関係する重要な項目であるため、これらの意味を誤って理解してしまうと、自社の利益を損なう大きな問題に発展する可能性があります。
締め日と発行日は、ビジネスでは常識とされる基本的な要素であるため、それぞれの違いを理解して、正しい設定方法や記載方法を知っておくことが大切です。
本記事では、請求書の締め日と発行日の違いについて、発行時の注意点や業務効率化のポイントもあわせて解説します。
【結論】請求書の締め日と発行日は異なる日付
請求書の締め日と発行日は、それぞれ異なる役割を持つ重要な日付です。締め日は取引をまとめて区切る日で、発行日は請求書を作成した日です。
一般的には「月末締め」が多く採用されており、その場合は月末日付で請求書を発行します。これにより、取引先との代金の精算を効率的に進められるため、支払期日の管理が容易です。
締め日と発行日を適切に設定することで、取引先との良好な関係維持にもつながります。
ここでは、請求書の締め日と発行日について、それぞれ解説します。
締め日は取引完了の区切りとなる日
締め日は、取引の締め切り日であり請求金額の集計基準となる日です。一般的には「10日」「15日」「20日」「月末」などに設定されます。
締め日を設けることで同一期間内の取引をまとめて請求できるため、管理の手間を削減できます。また、過去の取引が請求済みかが明確になり、二重請求や請求漏れなどのミスを防ぐことが可能です。
たとえば、月末締めの場合は、1日から月末までの取引を一括して請求書にまとめることで、取引先との代金の精算を効率的に進められます。
発行日は請求書の作成日
発行日は、取引先の支払うべき金額が確定した日です。通常は商品の納品やサービスの提供完了後に請求書を発行して、掛売方式の場合は取引先の締め日にあわせて発行日を設定します。
請求書に記載する発行日は、取引内容と請求金額を証明するために重要です。とくに毎月の継続的な取引では、発行日の記載がないと「いつの取引に対する請求書なのか」がわからなくなり、支払い漏れや遅延などのトラブルを引き起こす可能性があります。
請求書における締め日と発行日の決め方
締め日は事務処理の都合で設定する一方で、発行日は取引先の締め日にあわせて設定します。ただ、取引先との良好な関係を維持するためには、締め日と発行日を事前に取り決めをしておくことが重要です。
ここでは、請求書における締め日と発行日の決め方について、それぞれ解説します。
締め日は会社の事情にあわせて自由に決められる
締め日の設定は、会社の事情にあわせて自由に決められます。従業員の給与計算や支払業務など、ほかの事務手続きの負担を考慮して設定するとよいでしょう。
ただし、締め日の設定は取引先にも配慮が必要です。月末以外の締め日を設定したい場合は、あらかじめ取引先に相談するのが良いでしょう。
取引完了後の締め日設定の申し出では、取引先の都合が悪くなる可能性があります。
発行日は取引先の締め日にあわせて決める
発行日は、取引先の締め日にあわせて設定します。月末締めの場合は月末日付、15日締めの場合は15日付で請求書を発行するのが一般的です。
発行が遅れると取引先の入金サイクルに問題が生じる可能性があります。とくに、決算期をまたぐ場合は「期ずれ」が発生し、決算処理に影響を与えるため注意が必要です。
また、会計システムの処理上、発行日が翌月にずれ込むと売上計上の時期がずれてしまい、決算書類の修正が必要になる場合もあります。そのため、締め日までに確実に発行できる体制を整えることが重要です。
請求書を発行する際の注意点とは?
請求書の発行にはさまざまな注意点があります。日付の記載ミスは取引先との関係悪化につながるため、保存期間の管理は法令遵守の観点から重要です。
ここでは、請求書を発行する際の注意点について、解説します。
①日付は正確に記載する
請求書の日付は、取引の根拠となる重要な情報です。とくに発行日は支払いを求める権利の証明となるため、正確な記載が欠かせません。
なお、請求書を再発行する場合は、元の請求書と同じ発行日を使用して、請求書番号で区別する必要があります。発行日を変更すると、二重支払いや支払い漏れなどのトラブルを引き起こす原因となります。
また、支払期日の設定は取引先の営業日を考慮することが重要です。金融機関が休業日の場合、取引先は振込対応ができないため、事前に支払日の調整をおこないましょう。
②発行した請求書は一定期間の保存が必要
請求書は、法定期間の保存が必要です。請求書の保存期間は以下のとおりです。
- 法人:7年間(欠損金の繰越控除適用は10年)
- 個人事業主:5年間(消費税課税事業者は7年)
保存期間の起算日は、確定申告書の提出期限の翌日から始まります。なお、2024年1月からは電子取引の請求書は電子保存が義務化されます。電子保存をおこなう場合は、検索機能の確保やデータの改ざん防止など、電子帳簿保存法で定められた要件を満たさなければなりません。
③インボイス制度へは別途の対応が必要
インボイス制度は、消費税の計算をより正確におこなうための制度です。2023年10月から開始されたインボイス制度では、請求書に新たな記載項目が必要となりました。
- 登録番号
- 適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額
これらの項目がない請求書では、取引先は仕入税額控除を受けられない場合があります。また、制度を利用するには事前に税務署への登録申請が必要です。
【厳選】業務効率化におすすめな請求書発行システム3つ
請求書業務の効率化のため、システムの導入は有効な選択肢です。適切なシステムの使用で、日付管理や請求書の作成・管理が自動化できます。
ここでは、業務効率化におすすめな請求書発行システムについて、解説します。
①OneVoice明細
OneVoice明細は、複数の帳票を一括で作成・管理できるシステムです。請求書や見積書、納品書など異なる種類の帳票をまとめて管理できることが特徴です。
OneVoice明細の導入を検討する際は、まず無料トライアルを活用して自社の業務にあうか確認するとよいでしょう。
②バクラク請求書発行
バクラク請求書発行は、請求書の作成から送付までを自動化できるシステムです。取引先情報の管理や入金消込機能も備わっており、請求業務全体の効率化が実現できます。
バクラク請求書発行はとくに入金管理機能が充実しており、資金繰りの改善にも役立ちます。
③freee請求書
freee請求書は、40種類以上のテンプレートから選んで簡単に請求書を作成できる無料サービスです。また、インボイス制度に対応した適格請求書の作成機能があり、自動計算により入力ミスを防止します。
freee請求書は無料で利用できる基本機能が充実しており、請求書業務のデジタル化を始めるきっかけに最適です。
まとめ|締め日と発行日の違いを正しく理解して請求書を発行しよう
本記事では、請求書の締め日と発行日の違いについて、発行時の注意点や業務効率化のポイントもあわせて解説しました。
締め日は取引の集計期間を区切る日であり、発行日は請求書を作成した日です。それぞれを適切に設定するためには、日付が持つ意味や役割の理解が大切です。
また、請求書を作成する際には、システムの活用で日付管理を含めた請求書業務全体の効率化を実現できます。自社の規模や業務内容にあわせて、適切なシステムの選択を検討しましょう。










