請書と請求書の違いとは?ほかの類似書類の違いを徹底解説!帳票作成サービスも紹介
更新日:2025.01.30
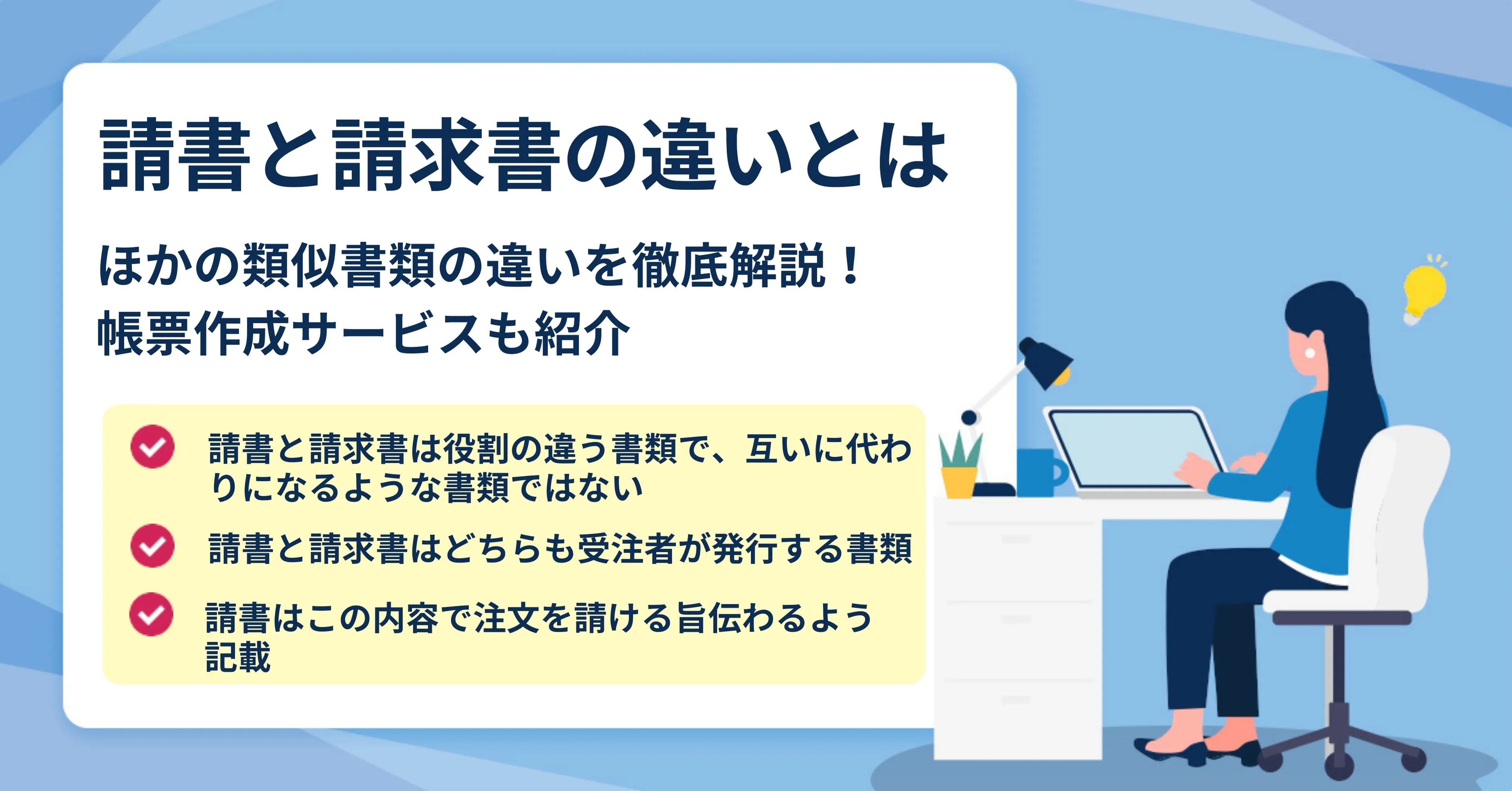
ー 目次 ー
ビジネスシーンにおいては、請求書や納品書、見積書などのさまざまな書類を使用します。このような書類のなかには内容の似た書類も多く、「請書(うけしょ)」は請求書とよく混同されてしまう書類となっています。
このようなことは基本的なビジネスマナーとなっているため、あらかじめ書類の書き方や内容などの基本的な知識を知っておくことが大切です。
本記事では、請書と請求書の違いについて、ほかの類似書類との違いや帳票作成サービスも交えて解説します。
【結論】請書と請求書は違うもの!代わりにはならない
請書と請求書は異なる役割の書類であり、互いに代わりになるような書類ではありません。
請書は注文に対して承諾を示す書類、請求書は商品やサービスの対価として支払いを求めるための書類です。どちらも取引があったことを証明する書類の役割も担っています。
この請書と請求書は、どちらも受注者が発行する書類で名称が似ており、よくビジネスシーンで混同されてトラブルになるケースがあります。取引先とのトラブルにならないためにも、請書と請求書の違いを正確に把握し、適切に書類の作成・対応をおこないましょう。
請書と請求書の違いとは?それぞれの役割と利用されるシーンを解説
請書と請求書は、それぞれ役割や発行のタイミングが異なる書類です。請書は注文書を受け取った後に発行する書類であり、請求書は納品やサービスの提供後に発行する書類です。
|
書類名 |
役割 |
発行のタイミング |
|---|---|---|
|
請書 |
注文を承諾した旨を示す |
注文書を受け取った後 |
|
請求書 |
支払いを請求する |
納品やサービス完了後 |
どちらの書類も、一定期間の保存が義務付けられています。
ここでは、請書と請求書の役割、利用されるシーンを解説します。
請書(うけしょ)の役割
請書は受注する旨を発注者に伝える書類で、「注文請書」や「発注請書」とも呼ばれます。
受注者は、発注者から注文書を受け取った後に、返答の意味合いで請書を発行します。注文書と請書を交わすことで受注が成り立ち、その内容の把握と共有が可能です。また、請書は、納品後に納品内容と注文内容を比較して確認する際にも役立ちます。
発行義務はなく、請書を発行せずに取引をおこなう場合もあります。
請求書の役割
請求書は納品やサービス提供後、対価として支払いを請求するために金額や期日・振込先などを発注者に知らせる書類です。インボイス制度においては発行・保存が定められています。
請求書は支払いのトラブルがあった際に、取引があったことや取引内容の証明ができます。ほかにも確実に取引の対価を回収するためやインボイス制度への対応するため、またトラブルに備えるためなどの理由から、請求書を発行するケースが多いです。
請書と請求書のおもな記載項目とは?
請書や請求書の書式は、インボイス制度や商慣習上において決まっているため、ルールにしたがった対応が必要です。
具体的には記載や保存、また消費税の計算方法が決まっており、とくに記載事項は頻繁にトラブルになりやすい問題となっています。そのため、書類を作成するにあたり、どのような項目を記載するのか把握しておきましょう。
ここでは、請書と請求書のおもな記載項目を解説します。
請書の記載項目
請書は発注者に対し注文承諾を示す書類で、記載事項は商慣習上決まっています。請書のおもな記載項目は以下のとおりです。
- 発行日
- 宛先
- 発行者情報
- 受注内容
- 金額
- 納期
- 納品方法
- 支払条件
請書は注文内容を正確に、伝わるよう記載する必要があります。発注先と条件や内容に齟齬がないよう、事前に合意した内容で作成しましょう。
請求書の記載項目
請求書は納品やサービスの完了後に対価を求める書類で、インボイス制度で定められている記載事項があります。請求書のおもな記載項目は以下のとおりです。
- 宛先
- 発行者情報(適格請求書発行事業者の登録番号)
- 請求年月日
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象である旨も)
- 振込情報(期日や振込先など)
- 税率ごとに区分して合計した対価の額および適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額
※太字の項目はインボイス制度の適格請求書等保存方式で定められたもの
請求書は、仕入税額控除の要件や債権の証明となるなど、税務処理や法的根拠に関連します。記載漏れがないように注意しましょう。また、振込手数料の負担者を書き添えておくことをおすすめします。
請書や請求書に類似する書類の役割とは?
取引に関連する書類は多く、その内容が類似している書類が存在します。請書や請求書も同様に、取引があったことの証明となる書類である点は共通している一方で、役割や発行されるタイミングが異なります。
これらの書類の違いを理解しておかなければ、取引の際にトラブルになる可能性があるため、基本的な知識として書類の役割を知っておきましょう。
ここでは、請書や請求書に類似する書類の役割を解説します。
見積書の役割
見積書は、取引前に受注側がサービスや商品の内容、金額を提示する書類です。この書類をもとに発注するかを考慮したり、値段交渉がおこなわれたりします。
注文書の役割
注文書は取引先に注文の意思を伝える書類で、数量・単価・期日などを記載します。注文書は「発注書」とも呼ばれ、両者で大きな違いはありません。下請法の対象となる取引では、発行義務があります。
納品書の役割
納品書は、納品やサービスの提供時に、商品と同梱する書類です。納品される側は、納品書と照らし合わせ、受け取ったものの数や内容などをチェックします。継続的な取引では、納品状況の追跡に役立ちます。
領収書の役割
領収書は、金銭を受け取ったことを証明する書類です。基本的に、金銭を受け取るタイミングで発行します。必ず発行する定めはありませんが、取引先に領収書を求められた場合、民法にもとづき対応が必要です。
検収書の役割
検収書は、納品されたものが間違いないか確認した旨の書類です。発注側が納品された商品やサービスをチェックし、問題ない場合に発行されます。時間が経って破損・不足が発覚した場合、検収書があると責任の所在が明確になり、不良品が納品されるようなトラブルの防止に有効です。
さまざまな書類作成業務をスムーズにできる帳票作成サービスとは?
取引に必要な書類の作成は、多くの手間と時間がかかります。とくに、取引先で書式が異なる場合もあり、その対応はさらに複雑です。
このような課題に対して、多くの企業が帳票作成サービスを導入しています。もし書類作成業務で課題を感じる場合には、自社の課題やニーズに合ったサービスの導入を検討してみましょう。
ここでは、書類作成をスムーズにする帳票作成サービスを紹介します。
①One Voice明細
One Voice明細は書類を作成後、請求先の要望に応じた方法で発行作業を代行しています。
また、無料トライアルがあるため、試用で実際の使用感やサポート体制を確かめた後に導入できるメリットがあります。導入後の2か月間は専任スタッフのサポート体制が充実しており、使い方を学びながら使用可能です。
費用対効果を検討しやすいサービスといえるでしょう。
②楽楽明細
楽楽明細は、オンライン発行と紙発行の両方に対応したサービスです。
現在使用しているシステムがあれば、そのデータをアップロードすると数クリックで発送されます。書式を使用しているなら、複数のテンプレートからの書類作成ができ、項目や位置を希望通りにして今までの書式に近いものが作れます。
また、取引先の請求書の確認状況がわかり、ダウンロードを促す通知の送信が可能です。
まとめ|書類の役割の違いを理解し、しっかり対処をしよう
本記事では、請書と請求書の違いについて、ほかの類似書類との違いや帳票作成サービスも交えて解説しました。
取引に関する証憑書類は、それぞれの書類に重要な役割があります。また、書類ごとに書き方や内容が異なることから、これらを把握し、適切に作成・対応することでトラブルを防げます。書類の保存期間は、関連する法律や欠損金の有無で異なるため注意しましょう。
一方で、書類作成には手間と時間がかかるのも事実です。制度の変更や新しい制度がはじまれば、その対応も求められます。書類発行の負担は、帳票作成サービスを利用すると大幅に軽減できるため、検討してみてください。










