キャッシュフロー計算書は作成義務がない!作り方や営業・投資・財務の3つの区分について解説
更新日:2025.09.04
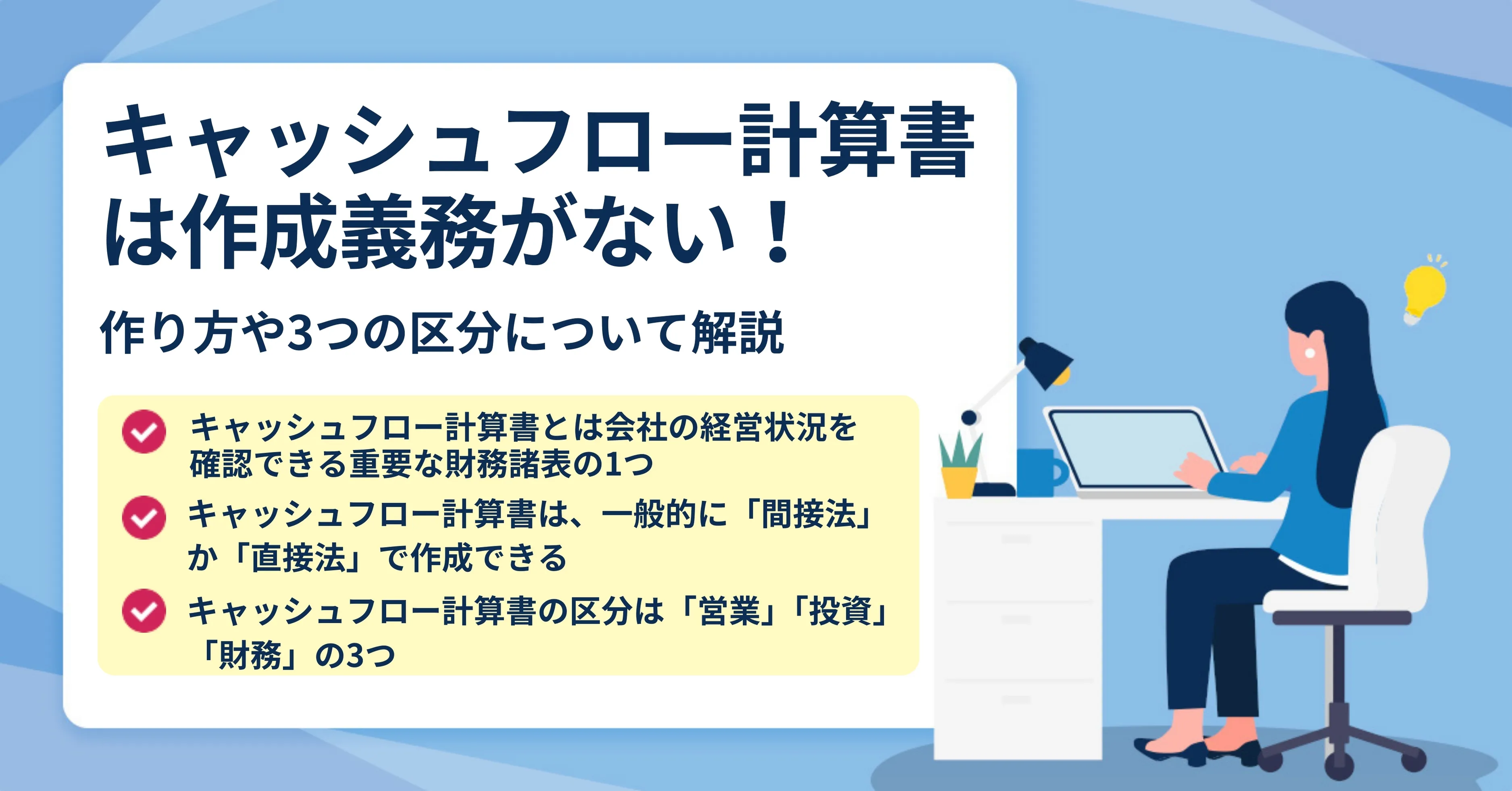
ー 目次 ー
企業が経営を行う上で重要なのは、しっかりと利益を上げることでしょう。ただ、「キャッシュの流れを正しく理解しておくこと」も企業が長く経営を続ける上では、重要な点です。その際に必要になるのがキャッシュフロー計算書です。
キャッシュフロー計算書とは、企業の経営や財務の状態を把握するための重要な会計書類の1つです。キャッシュフロー計算書は、必ずしも作成義務はありません。しかし、キャッシュフロー計算書の役割や目的を考えると、義務はなくとも作成しておいた方が企業のためになる可能性が高いです。
そこで、本記事でキャッシュフロー計算書の目的や、作成するメリットなどを紹介します。キャッシュフロー計算書の作り方についても紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
キャッシュフロー計算書(C/F)とは?作成の目的も解説
キャッシュフロー計算書は、会社の経営状況を確認できる重要な財務諸表の1つです。この章ではまず、キャッシュフロー計算書が何を表しているのか基本的な概要を紹介します。
キャッシュフロー計算書とは?【お金の流れを示した会計書類】
キャッシュフロー計算書は、企業のお金の流れを示した会計書類となり、「C/F」とも呼ばれます。一定期間に、企業にどのような理由でどれくらいの額のお金が入ってきて、どれくらいの額のお金が出ていったのかが表されます。
キャッシュとは現金だけでなく、換金性が高く、容易に換金可能な資産も含まれます。例えば、取得してから満期がくるまでの期間が3ヶ月以内の定期預金や譲渡性預金、公社債投資信託なども対象です。
キャッシュフロー計算書の目的
貸借対照表や損益計算書からでも、現金の流れや会社の利益は確認できます。しかし、損益計算書上で利益があったとしても、現金が増えているとは限らないため、実際のお金の動きまでは把握できないのが難点です。
例えば損益計算書上、商品を販売した後で代金をもらうことになった場合、まだ代金をもらっていなくても「売り上げ」として計上されます。貸借対照表では「売掛金」の増加になります。この2つの書類だけでは、実際のお金の流れを正確に把握できません。
取引の成立と、実際にお金を得るタイミングにはズレが生じるケースが多くあります。これが、会計書類上の情報と現状とでズレが生じる原因です。このズレを把握するためにも、キャッシュフロー計算書の作成が重要です。貸借対照表や損益計算書だけでは追いきれないお金の流れを確認でき、経営実績や財務状況をより詳しく把握できます。
キャッシュフローの把握によって、現金が不足する事態を防止することができ、売上債権の貸倒にいち早く気付くことも可能となるため、経営を円滑に進められるでしょう。また、金融機関が借入を行う際は健全な資金繰りをしている企業に融資したいと考えるため、キャッシュフロー計算書が判断材料の1つになります。
キャッシュフロー計算書に作成義務はない
財務三表と呼ばれる以下の3つの書類は、どれも会社がどのような経営がなされているのかを表した会計書類です。
- 貸借対照表
- 損益計算書
- キャッシュ・フロー計算書
3つの中で、貸借対照表と損益計算書には作成の義務があります。キャッシュフロー計算書は、上場企業では作成が義務付けられています。しかし、上場していない中小企業や個人事業主には作成義務がありません。
しかし、キャッシュフロー計算書は、自社の経営状況をより詳しく把握する際に有効な書類となります。したがって、作成義務はございませんが作成する企業が多いのが現状です。
キャッシュフロー計算書を作成する2つのメリット
前述の通り、キャッシュフロー計算書の作成義務は無くとも、作成することで、企業にとって良い効果をもたらすケースが多くあります。この章ではキャッシュフロー計算書を作成するメリットを紹介します。
安定的な経営ができる
キャッシュフロー計算書によって、潤沢な資金繰りが実現し、資金不足からなる倒産を防ぐことができます。キャッシュフローからは、企業に入ってきたお金や出ていったお金を詳細に把握でき、最終的に会社にいくら現金が残ったのかを知ることができます。
キャッシュフローを把握していなかった場合、思っていた以上に資金がなく、企業が使えるお金が足りなくなってしまう可能性があります。その結果、従業員への給料の支払いや、税金の支払いなどができなくなる恐れもあるでしょう。
キャッシュフロー計算書を作成することで、企業に実際に残っているお金を知ることができます。したがって、資金不足による倒産のリスクを避けることが可能となります。健全な資金繰りを行い、経営を安定させるためにも、作成義務がなくとも作っておく事をお勧めします。。
金融機関からの借入がしやすくなる
金融機関は貸付を行う際、「相手先の企業が安定的な経営をしているのか」「利益を確保できそうなのか」を判断します。このとき、キャッシュフロー計算書が役に立つケースがあります。
金融機関が企業の経営状態を判断する際に重要な指標になるのが、貸借対照表・損益計算書・キャッシュフロー計算書の3つの会計書類です。金融機関は財務三表を見て、経営成績や財務状況を把握して、貸付するかを決定します。
もし、キャッシュフロー計算書がなければ、潤沢な資金繰りができている企業なのかを判断しづらく、貸付の決定までに時間がかかってしまい、最悪の場合、貸付を行わないと判断するケースもあるでしょう。そのため、将来的に資金調達を考えているなら、作成しておく必要があります。
キャッシュフロー計算書の3つの区分
キャッシュフロー計算書は、「営業」「投資」「財務」の3つの区分から成り立っています。それぞれの区分がプラスかマイナスかによって、企業の大まかな経営状態を把握できます。
この章では、上記3つの区分において何が示されているのか、またプラス・マイナスの状態が何を指しているのかを紹介します。
営業活動によるキャッシュフロー(営業CF)
営業活動によるキャッシュフローとは、主に本業の営業活動で出入りのあったお金を表します。例えば、以下のような取引が該当します。
- 商品を販売して得た現金
- 材料の仕入れのために支払った現金
- 広告宣伝費で支払った現金
- 人件費として支払った現金
- 税金の支払い
- 災害に伴う保険金の受取
営業活動によるキャッシュフローは以下のような項目で構成されます。各項目の額を差し引きした最終の金額が、営業活動によるキャッシュフローとして表されます。
- 税引前当期純利益
- 減価償却費
- 有価証券売却損益
- 売上利息および受取配当金
- 支払利息
- 売掛金の増加額
- 棚卸資産の減少額
- 買掛金の減少額
営業活動によるキャッシュフローがプラスの数値になっている企業は、本業でしっかりと利益を出してキャッシュを残している状態だと考えられます。したがって、プラスであれば経営が順調だと判断できます。
一方、マイナスの場合は、「利益が出ない商品やサービスを売っている」もしくは「売り上げているものの現金の回収ができていない」などの状態です。この場合、商品の価格の見直し、またはほかの投資活動や財務活動で現金を得てマイナスを補うなどの対策が必要です。
投資活動によるキャッシュフロー(投資CF)
投資活動によるキャッシュフローからは、会社が将来的な成長を見据えて、どれだけ投資ができているのかがわかります。表では、以下のような区分に分けて記載されます。
- 有形固定資産の購入
- 有形固定資産の売却
- 投資有価証券の取得
- 投資有価証券の売却
新たな設備や有価証券を購入した場合、キャッシュフローはマイナスになります。逆に、設備や有価証券を売却した場合はプラスとなります。企業成長のために投資をしている場合、通常はマイナスになります。自社への投資がなければ現状維持となるため、企業の成長において投資は必要な要素です。したがって、キャッシュフローがマイナスであったとしても、悪い状態であるとは言えません。
財務活動によるキャッシュフロー(財務CF)
財務活動によるキャッシュフローからわかるのは、会社の資金調達の状況です。資金調達をして現金が増えればプラスに、借りたお金の返済を行ったらマイナスになります。
財務活動によるキャッシュフローは、以下の区分に分けて記載されます。
- 短期借入による収入
- 短期借入金の返済による支出
- 長期借入による収入
- 長期借入金の返済による支出
- 社債の発行による収入
- 社債の償還による支出
- 配当金の支払額
財務活動によるキャッシュフローがプラスの場合、企業の状況としては「新たな設備投資のために資金調達を行っている」もしくは「本業での利益のマイナスを補うために資金調達を行っている」などが考えられます。前者の場合は、企業にとってポジティブな要因ですが、後者の場合は運転資金が足りていないのでネガティブな要因です。
したがって、プラスかマイナスかだけでは会社の経営状態の判断は難しく、その根拠や、ほかの2つの区分と合わせて、総合的に考える必要があります。
キャッシュフロー計算書からわかる企業のパターン
営業CF、投資CF、財務CFの3つが「プラスかマイナスか」を確認すれば、企業のおおまかな経営状態を把握できます。この章では、代表的な5つのパターンを紹介します。
- 安定企業型
営業CF:+
投資CF:ー
財務CF:ー
本業で得たお金を新たな設備投資や借入金の返済に使っている状態です。安定している企業だと考えられます。
- 成長企業型
営業CF:+
投資CF:ー
財務CF:+
本業で得たお金と借入で得たお金を、設備の購入など企業の成長のための投資にあてている企業です。積極的な投資によって事業拡大を行い、成長中の企業だと考えられます。
- ベンチャー・スタートアップ企業型
営業CF:ー
投資CF:ー
財務CF:+
将来性がありますが、まだ利益を生み出せていない状態です。投資会社や金融機関などから資金調達したお金を使い、積極的に投資を行っているベンチャー企業やスタートアップ企業がこのパターンに該当します。
- 事業縮小企業型
営業CF:+
投資CF:+
財務CF:ー
本業で得たお金と、資産の売却で作ったお金を、借入金の返済に使っている状態です。投資をしていないので成長が止まり、事業縮小を考えている企業だと言えます。
- 倒産の危険がある企業型
営業CF:ー
投資CF:+
財務CF:+
本業の赤字を設備の売却や借入金でまかなっています。本業で黒字を出せないままの状態が長く続くと、倒産の危機に陥るでしょう。
キャッシュフロー計算書の作り方2パターン
キャッシュフロー計算書には、一般的に間接法と直接法の2つの作り方があります。この章では、それぞれの作り方や、メリット・デメリットを紹介します。
間接法
間接法は、貸借対照表と損益計算書から必要な項目を集計し、加減をして作成する方法です。以下のようなキャッシュに関わる部分を、貸借対照表と損益計算書で確認して、金額を調整して作成します。
- 税引前当期純利益
- 減価償却費
- 貸倒引当金
- 受取利息
- 支払利息
間接法のメリットは、貸借対照表と損益計算書を調整するだけで、時間や労力をかけずに作成できる点です。一方、デメリットは、取引ごとに記載しないので、現金の流れを詳細には把握できない点が挙げられます。
直接法
直接法は、売り上げや仕入れなどの現金の流れを項目別に集計して、表を作成する方法です。すべての取引を勘定科目ごとに記録した帳簿である「総勘定元帳」から、キャッシュフロー計算書の項目に関連する金額をピックアップして作成します。例えば、総勘定元帳からは以下のような項目を集計します。
- 商品の販売による収入
- 仕入れによる支出
- 給料や賞与などの人件費
取引の項目ごとに金額を記載するので、具体的にどのような収支の増減があったのかを把握できるのがポイントです。デメリットは、確認する項目が多く、取引ごとにデータが必要なので、作成に手間がかかる点です。
まとめ
キャッシュフロー計算書(C/F)は、企業のお金の流れを示した会計書類です。一定期間に企業にどのような理由でどれくらいのお金の出入りがあったのかを表します。
貸借対照表や損益計算書からでも現金の流れや会社の利益は確認できます。しかし、キャッシュフロー計算書があれば、より詳しいお金の流れを把握でき、経営実績や財務状況の把握に役立てられるのがポイントです。
キャッシュフロー計算書は、上場企業は作成が必須ですが、非上場の中小企業や個人事業主には作成義務がありません。しかし、資金不足による倒産のリスクを抑えることが可能となり、金融機関からの借入の際に役立つため、作成義務がなくとも作っておく事をおすすめします。
キャッシュフロー計算書は、一般的に「間接法」か「直接法」のどちらかで作成します。どちらの方法にもメリット・デメリットがあるので、特徴を正しく把握した上で、自社に適した方を採用しましょう。








