【廃止?必要?】請求書の郵送について解説!郵送廃止の案内文例やおすすめのシステムも紹介
更新日:2025.01.30
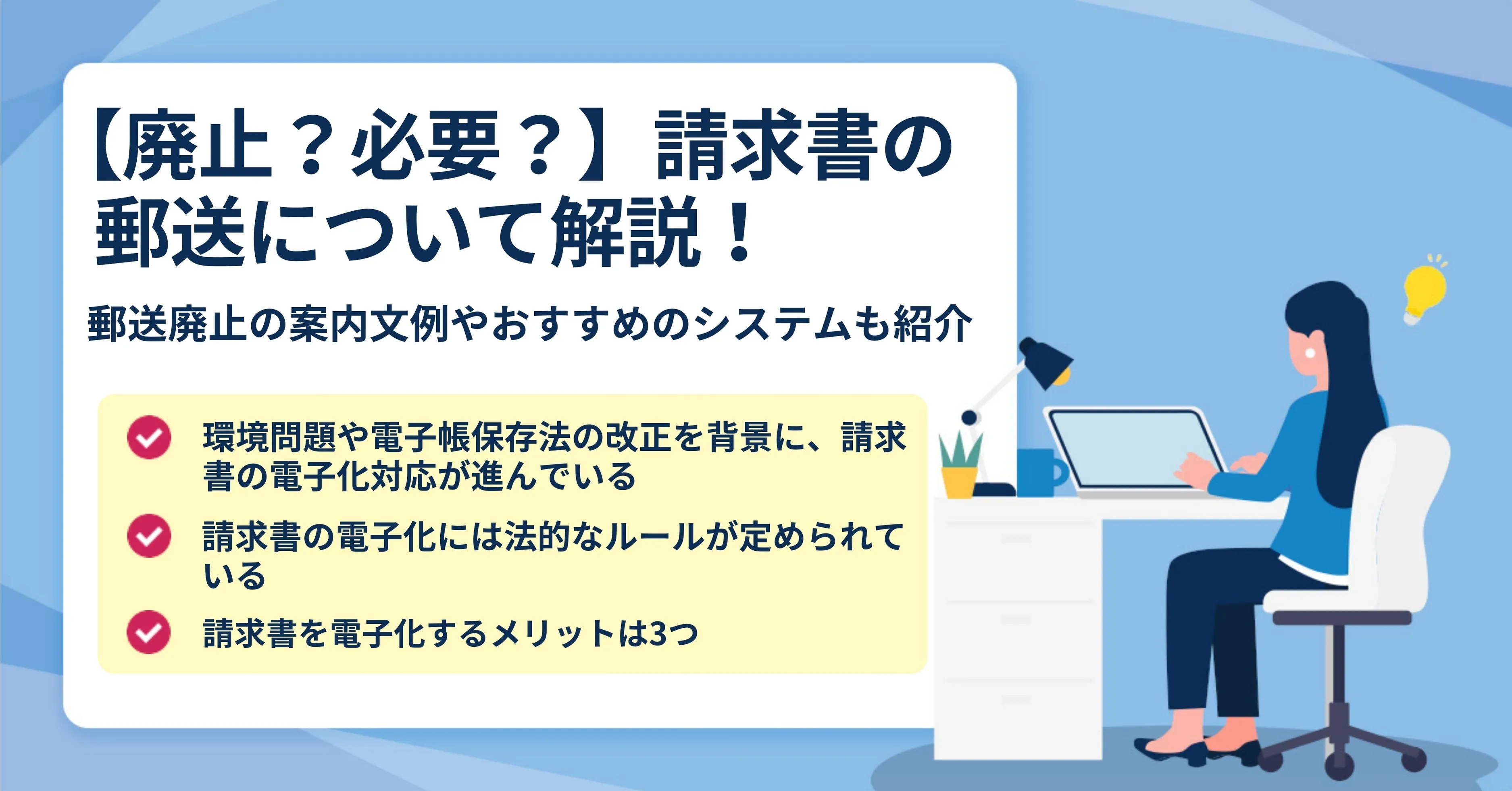
ー 目次 ー
環境問題や電子帳簿保存法の改正を背景に、ビジネスで利用される書類の電子化が進んでいます。とくに、電子帳簿保存法の改正にともなって、電子取引データの保存が義務化されており、事業者は電子請求書への対応をしなければなりません。
多くの企業が書類の電子化に取り組んでいるなか、電子帳簿保存法が定めるルールに対応できていない事業者も少なくありません。
このような問題は取引先にも影響することもあるため、請求書の電子化にともなう対応のメリットやデメリット、注意すべき点を知っておく必要があるでしょう。
本記事では、請求書の郵送について、電子化するメリットや注意点、おすすめのシステムを交えて解説します。
【結論】請求書のルールをおさえ、電子化に対応していこう!
請求書の保存に関するルールは法人法や消費税法、所得税法などによって定められています。また、電子化については「電子帳簿保存法」にも定められており、複数のルールが存在することを知っておかなければなりません。
請求書は、受領方法によって取るべき対応が異なります。紙の請求書を受領した場合、紙のまま保存、電子化して保存のどちらでも問題ありません。一方で、請求書を電子データで受領した場合は、電子帳簿保存法にしたがって電子データのまま保存する必要があります。
また、インボイス制度では請求書を発行する側も保存が義務付けられています。請求書を電子データで発行した際は、電子帳簿保存法により電子データでの保存が必要です。
請求書はインボイス制度により原則7年間保存する必要があり、電子データでも紙でも同じです。ルールにしたがって適切に請求書を保存しましょう。
請求書の電子化には法的なルールが定められている!
電子化には法律で定められたルールがあります。請求書をはじめとした書類の電子化に関係する2つの法律と、ルールや要件は以下のとおりです。
|
名称 |
電子帳簿保存法 |
e文書法 |
|
概要 |
帳簿や書類の電子保存の方法を定めた法律 |
保存を義務付けられた書類の電子保存を認める法律 |
|
内容 |
原則的な電子取引データ保存のルール
|
電子保存の基本要件
|
請求書を電子化する3つのメリット
請求書の電子化は、コストや業務効率面でのメリットがあります。また、時間や場所を選ばず働ける環境づくりにもつながり、近年求められている働き方の多様化にも役立ちます。
請求書に限らず、書類の電子化に多くの企業が対応しており、今後も対応する企業は増えていくでしょう。
ここでは、請求書を電子化する3つのメリットを解説します。
①請求書の印刷・郵送にかかるコストの削減
電子請求書になると、印刷や郵送、また物理的な保存場所が不要です。それにともなって印刷費や郵送費、家賃などのコスト削減が可能になります。
とくに、郵送費は2024年10月に郵便料金が1通あたり26円上がっているため、長期的に見ても大幅なコスト削減の実現といえるでしょう。今後、郵送費の値上がりを心配する必要もなくなります。
②請求書関係の業務効率化
請求書が紙の場合、書類や宛先を印刷して書類を折る、封筒に入れて切手を貼る、投函する作業などのアナログで手間のかかる対応が必要です。
一方で、電子化した場合、会計ソフトや表計算ツールなどで請求書を作成し、メールやチャットで送付するだけで送付が完了します。また、データとして格納するため、請求書データの検索が容易で、簡単に社内に共有できます。
このように、請求書の電子化をおこなえば、請求書関係の業務効率化が実現可能です。
③情報の安全性の確保
セキュリティに強いストレージやシステムを導入すると、安全性を確保できます。
また、書類を電子化して発行することで、閲覧履歴の追跡や改ざんの防止が可能です。ほかにもファイル・フォルダの権限機能を利用し、閲覧者・編集者を限定することも可能です。
クラウドシステム上にデータを保存したり、帳票作成システムでデータが管理されたりすることから、災害時やミスによる消失も防止できます。
請求書を電子化する際、注意が必要なポイント
請求書を電子化して発行するためには、関連する法律に対応する必要があります。紙で対応していた際とは異なる注意が必要です。
電子化が進まない理由の上位に、セキュリティ面の不安があります(※)。おさえるべきポイントを把握し、事前準備や社内での周知徹底をしましょう。
ここでは、請求書を電子化するのに注意が必要なポイントを解説します。
(※)参考:総務省「令和3年版 情報通信白書|デジタル化が進んでいない理由」
①改ざんしにくいデータで送る
電子請求書はPDFのような改ざんしにくいデータで送付しましょう。書類作成によく使われるWordやExcelデータは、誰でも編集が可能であるため、取引先への送付は避けてください。
また、国税庁は、改ざん防止の措置としてタイムスタンプや履歴が残るシステムの導入などを挙げています。電子請求書は、タイムスタンプを付与したデータを送るのが望ましいでしょう。
電子帳簿保存法に対応したシステムを導入すると、システムが対応してくれるので、対応の手間が省けます。
②セキュリティ対策をとる
請求書にパスワードを設定してメールを添付し、別メールでパスワードを送信する方法があります。しかし、過去に内閣府ではこの方法による対応について、脆弱性を指摘していたこともありました(※)。
そのため、セキュリティ対策には、クラウドシステムを利用する方法をとりましょう。クラウドシステムはインターネット上にファイルを保存する方法です。URLを共有し、取引先と双方で更新可能にしたり、制限をかけ閲覧のみにしたりできます。
(※)参考:内閣府「平井内閣府特命担当大臣記者会見要旨 令和2年11月24日」
なお、「自動暗号化ZIPファイルの廃止」についての回答
③「日付・金額・取引先」の3つの要素で検索できるようにする
書類データのファイル名を、ルール化することで検索可能です。「20250108_36000_〇〇産業」のように「取引日」「金額」「取引先の会社名」をファイル名にすると、3つの要素で検索できるようになります。
ほかに、Excelで索引簿を作る方法もあります。3つの要素のほかに、請求書のような書類の種類別項目や、リンクを貼っておくこともできるため、誰でも確認しやすい方法です。
請求書の郵送を廃止、電子化する案内文例
請求書の郵送を廃止し、電子化する際には取引先に事前通知の必要があります。ポイントは下記のとおりです。
- いつから電子化するのかを伝える
- 自社が請求書を電子化する理由を伝える
- 取引先にもメリットがある旨を伝える
以下は上記を踏まえた案内文例です。
件名:請求書の郵送廃止・請求書電子化のご案内
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
この度、弊社では環境保護に対する取り組みや電子帳簿保存法への対応としまして、郵送にて送付しておりました請求書の発行を、電子請求書へ切り替えることとなりました。
変更にともないお手数をおかけいたしますが、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
開始時期:◯◯年◯月請求分より
概要:
- インターネット上のサービスで、請求書を確認・ダウンロードが可能
- 電子データでの保存や検索が容易になる
- インターネット環境にあれば、どこにいても、いつでも受け取り可能
本件につきまして、ご不明な点がございましたら、お問い合わせください。
何卒よろしくお願いいたします。
電子帳簿保存法に対応した請求書を保存するシステムや、インボイス制度に対応した請求書の発行をおこなうシステムはたくさんあり、多くの企業で導入されています。
請求書を保存するシステムは、電子帳簿保存法の要件を満たす形式で請求書を保存します。また、発行システムは、請求書のみならず書類の電子化、WEB上での発行が可能です。
なお、多くの企業に導入されている請求書の電子化におすすめのシステムは以下のとおりです。
- Gi通信
- One Voice公共
- One Voice明細
- 楽楽明細
サービスのなかには無料トライアルを実施しているものもあり、実際の使用感やサービス内容を踏まえて導入の検討が可能です。
まとめ|請求書の郵送廃止、電子化導入は段階的に進めよう
本記事では、請求書の郵送について、電子化するメリットや注意点、おすすめのシステムを交えて解説しました。
請求書やほかの書類において、電子化に対応していかなくてはなりません。とくに、保存に関しては、既に対応が求められています。
書類を電子化する際、社内の業務フローは大きく変化します。そのため、電子化導入は段階的に進める必要があります。また、社外に対する請求書の郵送廃止、電子化の案内は時間に余裕を持って進めましょう。










