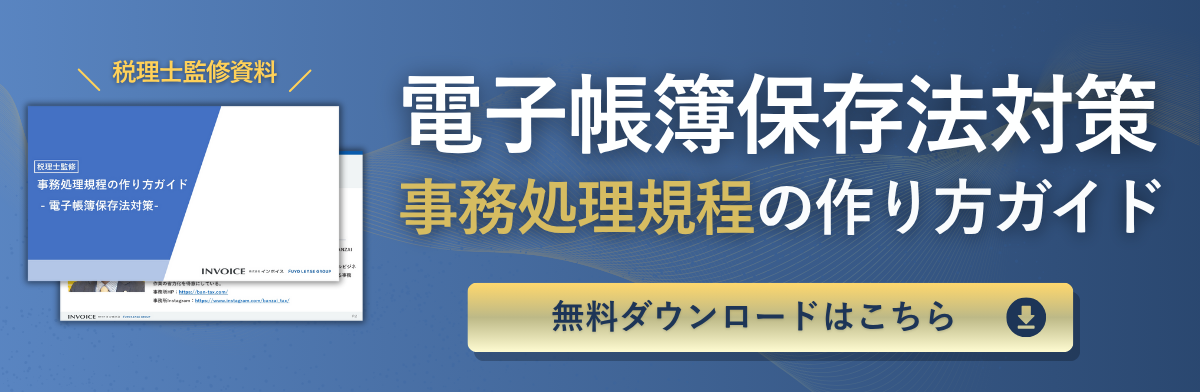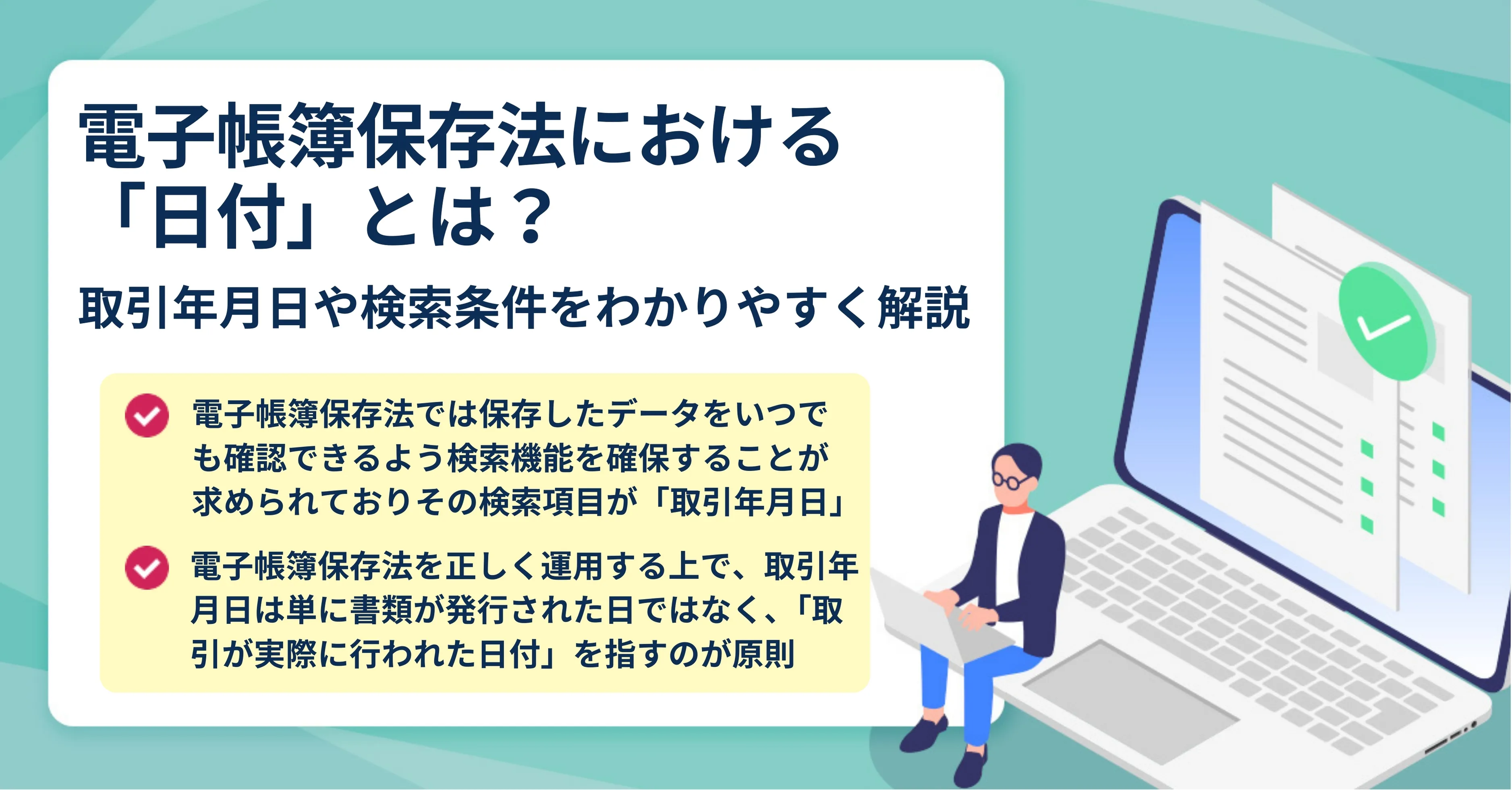電子帳簿保存法対応に欠かせない「事務処理規程」とは?基本と作成方法を分かりやすく解説
更新日:2025.08.25

ー 目次 ー
電子帳簿保存法への対応が本格化し、多くの企業で経理・総務部門の業務負荷が高まっています。
特に、電子保存の根拠となる「事務処理規程」の整備は、対応の土台となるにもかかわらず、後回しになっている企業も多いのではないでしょうか。
事務処理規程は、単なる社内ルールではなく、電子帳簿保存法の要件を満たすうえで欠かせない存在です。正しく整備されていなければ、後から「保存要件を満たしていない」と判断される可能性もあります。
本コラムでは、株式会社インボイスが発行した『事務処理規程の作り方ガイド - 電子帳簿保存法対策 -』から一部を抜粋し、事務処理規程の役割や基本的な考え方、そして実務に落とし込むための第一歩を解説していきます。
電子帳簿保存法対応を進めたい方は、ぜひ参考にしてください。
■ 電子帳簿保存法とは?
電子帳簿保存法は、紙ではなく電子データで帳簿を保存することを法的に認めた制度です。これにより、業務の効率化やペーパーレス化が進む一方で、改ざん防止や保存期間の管理といった新たな対応も求められます。法令では、電子保存を行うための具体的なルールも定められています。

■ 事務処理規程の役割とは
事務処理規程は、企業における業務処理のルールや手順を定めた文書です。電子帳簿保存法における「真実性の確保」の要件を満たす手段の一つとして位置づけられており、適切な電子データ管理を実現するための指針となります。また、全従業員が共通のルールで業務を進められるため、効率化やミス防止にもつながります。

■ 事務処理規程の必要性
事務処理規程は、電子帳簿保存法への対応だけでなく、業務効率化やミスの防止、コンプライアンス強化、情報セキュリティの向上といった多くのメリットをもたらします。
特に、電子データによる帳簿保存では、データの改ざん防止や保存期間の確保が重要となります。事務処理規程によって、これらの課題に対する具体的な対策を定めることで、企業は法令遵守と業務効率の両立を実現することができます。

■ 事務処理規程の作成方法
事務処理規程を作成する際には、以下の基本的な構成要素を盛り込む必要があります。
①電子取引の範囲を明確にする
まずは、どの業務を「電子取引」として事務処理規程に含めるかを明確にすることが重要です。契約の締結や発注、請求、支払いなど、幅広い業務が該当しますが、その中でも電子データで保存すべき取引を特定し、規程にきちんと記載する必要があります。
②データ保存期間の設定
電子データを保存する際は、その保存期間を税務要件に基づいて正しく設定する必要があります。たとえば売上帳や仕入帳などは、原則7年間保存することが必要です。業務の実態や法令に即した保存期間の管理が求められます。
■ まとめ
電子帳簿保存法への対応において、事務処理規程の作成と運用は欠かせないステップです。法令遵守と業務効率化を両立させるうえで、事務処理規程は企業の電子データ管理を支える重要なツールとなります。
とはいえ、一度作成すれば終わりというものではありません。電子取引の拡大や技術の進化、さらには法改正などに対応するため、企業は常に最新の情報をキャッチし、規程の内容を定期的に見直していく必要があります。
また、電子帳簿保存法だけでなく、個人情報保護法や不正競争防止法といった関連法規への理解と対応も欠かせません。
実際の業務に合ったルールを整えて運用していくことが、これからの時代に安心して対応するためのポイントになってきます。
本コラムで紹介した内容は、株式会社インボイスが発行した『事務処理規程の作り方ガイド - 電子帳簿保存法対策 -』の一部です。
さらに
- 事務処理規程を作成する際に押さえておくべきポイント
- 事務処理規程を運用する上で重要なポイント
- 電子帳簿保存法の効率化のヒント
など、事務処理規程を運用していく上で重要な情報をまとめて記載しております。より詳しい作成手順については、ぜひ資料をダウンロードしてご覧ください。