電子帳簿保存法で個人事業主のレシートはどうする?対応する方法や保存要件を解説
更新日:2025.06.04
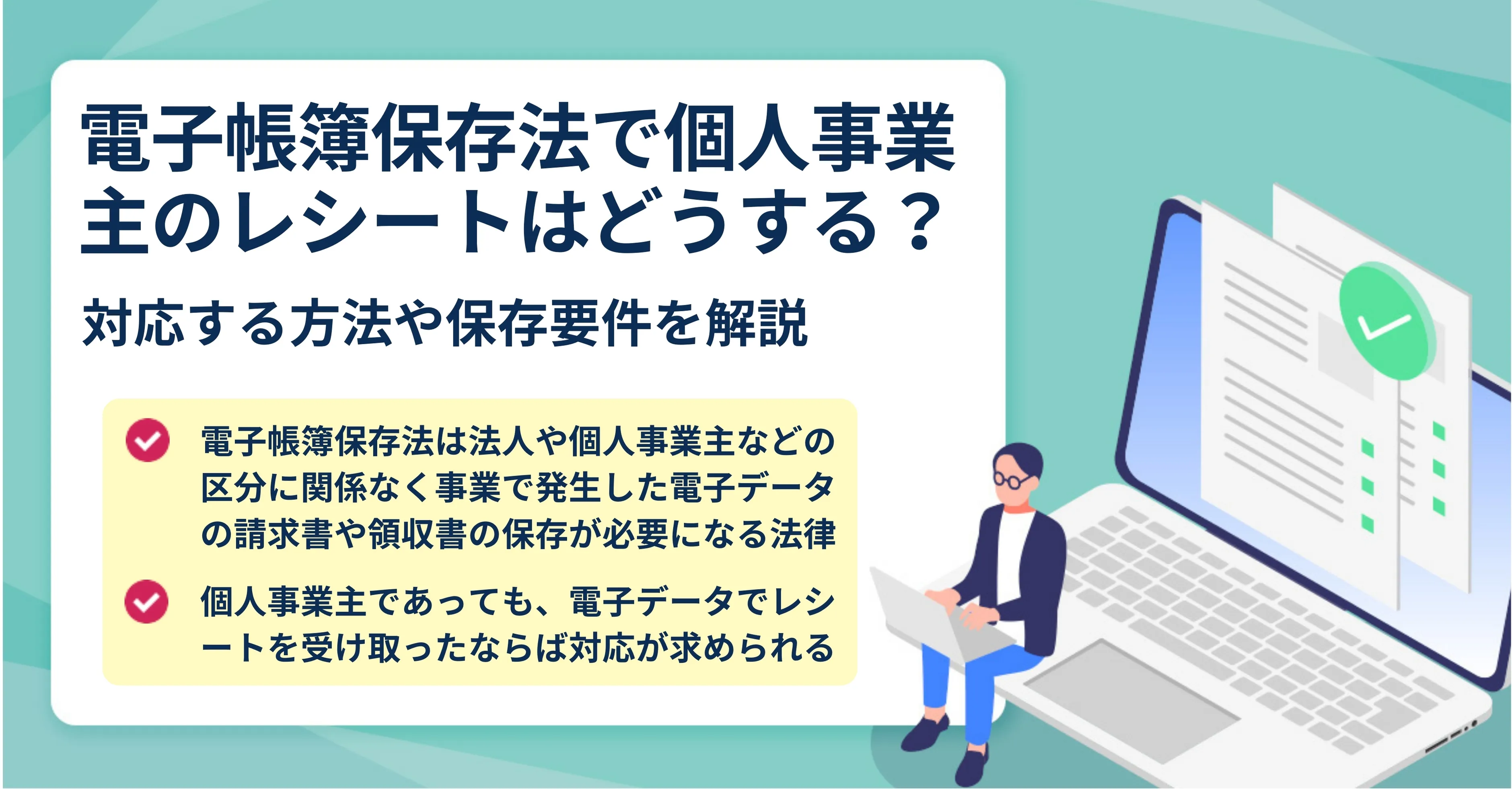
ー 目次 ー
電子帳簿保存法は、税務関係の帳簿や電子データを介した書類の電子保存のルールを定めた法律です。この法律はこれまでに何度も改正を繰り返しており、2024年1月の法改正では電子データで受け取った書類のデータ保存が義務づけられました。
電子帳簿保存法ではすべての事業者を対象としており、個人事業主が受け取ったレシートであっても例外ではありません。対応については紙で受け取った場合と電子データで受け取った場合で異なるため、細かなルールを把握しておく必要があります。
本記事では、電子帳簿保存法では個人事業主が受け取ったレシートをどうするべきなのかについて、対応方法や保存する際の要件を解説します。
【結論】電子帳簿保存法では個人事業主でもレシートの対応が求められる!
電子帳簿保存法は、法人や個人事業主などの区分に関係なく、税務関係の帳簿や事業で発生した電子データの請求書・領収書などをデータで保存することを定めた法律です。
このことからレシートを電子データで受け取った際は、電子帳簿保存法に則った対応が求められます。一方で、紙のレシートは必ずしも電子化する必要はないため、状況にあわせて対応するか考えましょう。
ここでは、レシートの受け取り方による電子帳簿保存法への対応方法を解説します。
電子データで受け取った場合に保存が必要!
個人事業主がECサイトや電子レシートを導入している店舗を利用した場合、レシートを電子データで受け取るケースがあります。電子帳簿保存法では、電子データで受け取ったレシートは、データで保存しなければいけません。
電子データで受け取ったレシートは印刷して保存できないため、電子帳簿保存法に則って対応する必要があります。
紙のままであれば、そのままの保管でもOK!
個人事業主の場合、経費の支払いを実店舗でおこない紙のレシートをもらう機会も多くあります。紙で発行されたレシートは、電子帳簿保存法の対象に含まれず、必要な場面ですぐ取り出せるようにしていれば、紙のまま保管しても問題ありません。
一方で、紙のレシートを電子帳簿保存法に対応させるためには、スキャナ保存の要件を満たす必要があります。スキャンした後の原本は破棄できるため、紙の保管と都合が良いほうを選びましょう。
なお、スキャナ保存の要件は電子データとは異なるため、対応方法を理解しておく必要があります。
電子帳簿保存法で個人事業主がレシートを保存する際の要件とは?
電子帳簿保存法の保存要件は、データがシステムに入力された後に改ざん・削除されていないことを証明する真実性の確保と必要時にすぐ表示・検索できる可視性の確保にわかれます。
ただ、電子帳簿保存法の要件は細かく、複雑な内容も多いため、それぞれがどのように異なるのか理解して対応を進めることが大切です。要件を正しく理解していなければ、青色申告の取り消しや追徴課税などの法的な罰則を受けるおそれがあるため注意しましょう。
ここでは、個人事業主がレシートを保存する際の要件を解説します。
真実性の確保とは、電子データが改ざん・削除されていないこと
真実性の確保は、電子データが保存後に改ざん・削除がされていないと証明することです。真実性を確保する措置は4種類あり、そのうちひとつに対応すれば問題ありません。
真実性の確保のために、必要な措置は以下の4つです。
- タイムスタンプが付与された書類を受け取り・保存する
- 受け取った書類にタイムスタンプを速やかに付与し、情報が確認できるようにする
- 訂正削除の記録が残るか、訂正削除ができないシステムを利用する
- 訂正・削除を防止する事務処理規程を備え付け、運用する
自社の業務や状況にあわせて、どの措置を選ぶか検討しましょう。
可視性の確保とは、保存した書類を表示・検索できるように準備しておくこと
可視性の確保は、保存した書類を必要なときにすぐ表示・検索できるように準備しておくことです。可視性の確保では、以下の内容が求められています。
- システムのマニュアル概要書を備え付ける
- パソコン・プログラム・ディスプレイ・プリンターとそれぞれの操作説明書を備え付ける
- 「取引年月日」「取引先」「取引金額」の3項目か、「取引年月日」または「取引金額」の範囲指定で検索できるようにする
可視性の確保は漏れなく対応する必要があるため、真実性の確保と混同しないように注意しましょう。
電子帳簿保存法で個人事業主のレシートはスキャナ保存がおすすめな理由
電子帳簿保存法に対応する際は、個人事業主のレシートもスキャナ保存での対応・管理がおすすめです。スキャナ保存を導入することで、保管スペースの削減や紛失のリスクがなくなるなどのメリットがあります。
ここでは、個人事業主のレシートはスキャナ保存がおすすめの理由を解説します。
- 保管スペースに悩まずに済む
- 紛失のリスクを減らせる
- 感熱紙の印字が消える心配がなくなる
- 経理業務を楽にできる
- 検索しやすくなる
①保管スペースに悩まずに済む
電子帳簿保存法に則ってスキャナ保存することで、原本を破棄できることから保管スペースに悩まずに済みます。データを保管する場所はクラウド上になり、余計なスペースは発生しません。
紙のままレシートを保管する場合、ファイリングをしても場所をとってしまう場合が多いでしょう。青色申告の個人事業主であればレシートを7年保管する必要があり、長くなるほど量が増えてしまいます。
②紛失のリスクを減らせる
レシートのデータをクラウド上に保管すれば、引越しや掃除のタイミングで起きる紛失のリスクを減らせます。
個人事業主が紙のレシートを保管する期間は、白色申告の場合で5年間、青色申告の場合で7年間です。万が一期間が過ぎる前に紛失してしまえば、税務調査の際に費用を支払った証明をすることが難しくなります。
個人事業主は自宅で作業する場合も多いからこそ、紛失リスクの少ない方法がおすすめです。
③感熱紙の印字が消える心配がなくなる
個人事業主がスキャナ保存することで、感熱紙の印字が消える心配を減らせます。一般的に、感熱紙は3〜5年ほどで印字が消える可能性があります。
個人事業主はレシートを5〜7年保管しなければならず、印字が消えてしまうと税務調査時に費用の説明が難しくなるかもしれません。
スキャンしておけば内容が消える心配はなく、数年後の税務調査でも焦らずに対応できます。
④経理業務を楽にできる
レシートをスキャンして保存することで、レシートを貼り付ける、ファイルにまとめるなどの作業がなくなり、経理業務を楽にできます。個人事業主は経理業務を自身で対応するケースも多く、作業が減ることで収入を確保するための業務に時間を割けます。
会計ソフトによっては、スキャンすることで日付や項目を自動で読み取り、仕分けまでしてくれるシステムがあり、業務軽減に役立つでしょう。
⑤検索しやすくなる
個人事業主がスキャナ保存することで、検索性が高まり必要時に確認しやすくなります。
紙のままレシートを保管する場合、内容の確認や税務調査時に探す際、時間がかかる可能性があります。一方で、スキャンしておくことで日付や金額などの項目で検索が可能です。
スキャナ保存の要件には検索機能の確保も定められているため、電子帳簿保存法に対応もできます。
まとめ|電子帳簿保存法では個人事業主のレシートもスキャナ保存できる!
本記事では、個人事業主が受け取ったレシートを電子帳簿保存法に則って保存する際の要件やスキャナ保存がおすすめの理由を解説しました。
電子帳簿保存法では、電子データを介した取引情報はデータでの保存を求めています。
個人事業主のレシートが紙で発行されている場合は、紙のままで保存できるものの、スキャナ保存の要件を満たすことでクラウド上で保管が可能です。スキャナ保存に対応することで、保管場所の削減や紛失のリスクを減らせるなどのメリットも多くあります。
個人事業主がレシートをスキャナ保存するか悩む際は、本記事を参考に決めましょう。










