電子帳簿保存法は業務効率化が目的!保存方法や罰則も解説
更新日:2025.03.27
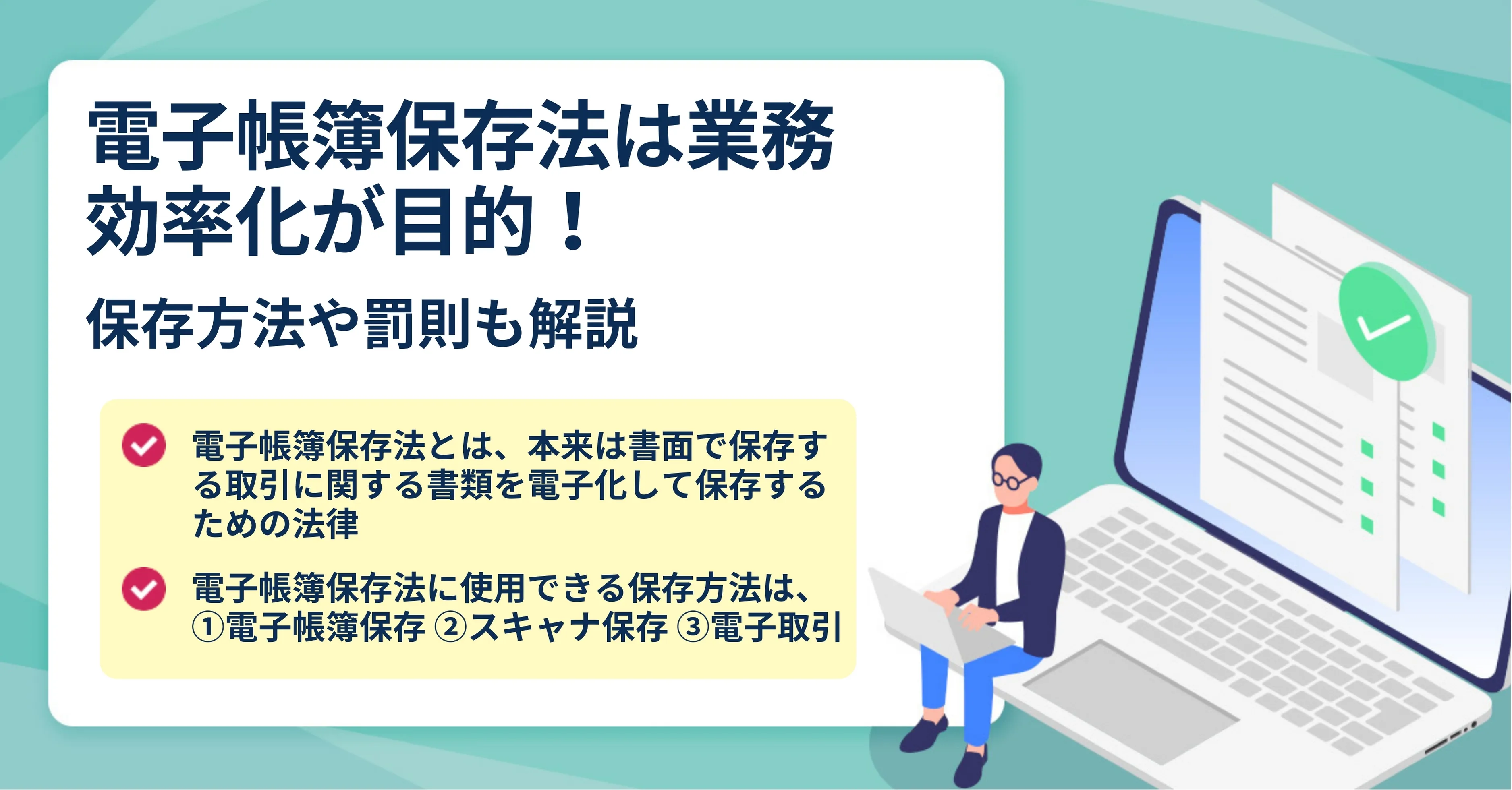
ー 目次 ー
電子帳簿保存法(電帳法)とは、税務に関連する文書をデジタル化して保存する方法や要件などを定めたルールです。経済社会におけるデジタル化の発展を踏まえて、業務効率化や業務の負担軽減などの目的から施行されています。
電子帳簿保存法は施行されてから複数回の法改正がおこなわれており、2022年1月では電子取引データの保存要件が変更され、2024年1月では電子取引データの電子保存が義務化されました。このような背景もあることから、事業者は法律に定められたルールを確認し、適切に管理しなければなりません。もし違反した場合、青色申告の承認取消しや、追徴課税などの行政処分が課されるおそれがあります。
このような状況を防ぐためにも税務に関する文書や書類を使う事業者は、法令を適切に理解して対応することが大切です。
本記事では、電子帳簿保存法の目的について、管理する区分方法や罰則などを交えて解説します。
【前提】電子帳簿保存法とは、電子化した会計書類を保存するためのルール
電子帳簿保存法とは、税務に関連する文書をデジタル化して保存する方法や要件などを定めたルールです。
電子帳簿保存法は直近では2022年と2024年で大きな法改正がありました。2022年1月の法改正では、電子取引データの保存要件が変更されています。また、2024年1月には電子でおこなった取引に対するデータ保存が義務化されました。
このように、電子帳簿保存法は時代の変化に対応すべく、何度も改正されています。税務に関する文書を使うすべての事業者に適用されるルールであるため、経理担当者の方は改正されたら、都度その内容を把握しましょう。
なお、電子帳簿保存法が定める保存方法として、3種類の区分があります。
|
①電子帳簿等保存(電子的に作成した帳簿・書類をデータのまま保存) ②スキャナ保存(紙で受領・作成した書類を画像データで保存) ③電子取引(電子的に授受した取引情報をデータで保存) |
電子帳簿保存法の目的は、業務効率化や業務の負担軽減
電子帳簿保存法は、経済社会におけるデジタル化の発展を踏まえて1997年に施行されました。この当時はIT技術の発展によってコンピューターを使った業務が増えつつある一方で、電子に対応したルールがありませんでした。
このような背景を踏まえて、政府は文書のデジタル化をおこなえば以下のようなメリットを受けられるのではないかと考えました。
- 迅速な経理処理が可能
- デジタル化による生産性の向上
- 対面での処理が不要となるためテレワークの推進が可能
上記のようなメリットを踏まえ、電子帳簿保存法は事業者の業務効率化や業務の負担軽減を目的として施行されています。
電子帳簿保存法で定められている要件とは?
電子帳簿保存法では、文書を適切に管理するための要件が定められています。ここで定められている要件は細かい内容も多く、誤った認識をしてしまうと大きなトラブルになりかねません。
このようなことから、電子保存の導入を検討しているならば、基本的な電子帳簿保存法の要件について、適切な理解を深めることが大切です。
ここでは、要件として定義された項目について解説します。
①真実性
「真実性」とは、実際の情報に対して改ざんや不正がされていない状態のことを指した要件となります。
電子帳簿保存法では、デジタル化した文書が改ざんされておらず、取引した実際の情報と誤差がない状態で管理している必要があるとし、以下のような真実性の要件を定めています。
|
①タイムスタンプが付された後、取引情報の授受を行う ②取引情報の授受後、速やかに(又はその業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに)タイムスタンプを付すとともに、保存を行う者又は監査者に関する情報を確認できるようにしておく ③記録事項の訂正・削除を行った場合に、これらの事実及び内容を確認できるシステム又は記録事項の訂正・削除を行うことができないシステムで取引情報の授受及び保存を行う ④正当な理由がない訂正・削除の防止に関する事務処理規程を定め、その規程に沿った運用を行う |
②可視性
「可視性」は電子帳簿保存法の要件の1つであり、目で見て確認ができる状態のことを指します。
電子帳簿保存法の保存対象となる文書は基本的に税務に関するものであり、税務調査などの際に保存した文書をすぐに確認できる状態であることが求められます。そのため、以下のとおり、検索を用いて確認ができるようにしたり、ディスプレイで表示させたりする対応が必要です。
|
電子帳簿保存法に使用できる3つの保存方法
電子帳簿保存法では、保存方法として3つの方法から選択が可能です。この保存方法は、デジタルで管理する文書に応じて異なっています。
保存方法が適切でない場合には、税務署から不正と判断され、トラブルに発展しかねません。このようなトラブルにならないためにも、電子帳簿保存法に定められたそれぞれの方法を把握しておきましょう。
ここでは、文書を保存する際の3つの方法について解説します。
①電子帳簿保存
文書をパソコンなどで作った場合、紙に印刷しなくてもデータのままで保存できる方法を「電子帳簿保存」と呼びます。
保存できる文書は、以下のとおりです。
|
•会計ソフトで作成している仕訳帳、総勘定元帳、経費帳、売上帳、仕入帳などの帳簿 •会計ソフトで作成した損益計算書、貸借対照表などの決算関係書類 •パソコンで作成した見積書、請求書、納品書、領収書などを取引相手に紙で渡したときの書類の控え |
②スキャナ保存
書面で取引した文書などを現物の代わりに、専用の機器で読み取り保存する方式を「スキャナ保存」と呼びます。書面で受領した文書以外にも、自身が発行した場合の写しでもこの方式で保存が可能です。
保存状態がよくない場合、データの読み取りができないといった問題が発生してしまうため注意が必要です。機器で文書を読み取る際には、以下のルールを守って保存状態をよくしておく必要があります。
- 解像度が200dpi以上
- 赤・緑・青がそれぞれ256階調以上(24ビットカラー)
③電子取引
管理が必要な文書に該当するデジタルデータを発行または受領した場合、そのまま保存する方式を「電子取引」と呼びます。メールやクラウドサービスで受領・発行した帳簿書類だけに限らずネットショッピングを利用した際の領収書なども対象となります。
保存する際のルールとして、以下の要件を遵守しなければなりません。
|
①改ざん防止のための措置をとること ②保存データを確認するためのディスプレイやプリンタ等を備え付けること ③「日付・金額・取引先」の3つの要素で検索できること |
要件に違反した場合、「青色申告の取消」や「重加算税」などの罰則が発生する
電子帳簿保存法において、デジタルで管理しているデータが「真実性」と「可視性」を満たさない場合、税務署から不正と判断されるリスクがあります。もし不正と判断されると、以下のようなペナルティを受けるおそれがあるため注意が必要です。
- 青色申告の取消
- 重加算税が課される
- 100万円以下の過料
青色申告が剥奪されると最大65万円の税金控除や、赤字を翌年に繰り越して税金を減らすといった税制上の恩恵もなくなります。また、重加算税や過料は、企業の財務状況を圧迫するリスクがあるでしょう。
電子帳簿保存法に活用できるシステム
罰則のリスクを軽減させるためには、要件にあったシステムを活用しましょう。システムを活用することで電子帳簿保存法の要件を満たした保存が可能です。
また、システムを業務に組み込むことで業務効率化を向上させられるといったメリットもあります。
ここでは、電子帳簿保存法に活用できる3つのシステムを紹介します。
①OneVoice明細
OneVoice明細とは、帳票発行業務を自動化させるクラウド型の管理システムです。電子帳簿保存法にも対応しているため、安心して帳票のデジタル化を進められます。
請求書や納品書などのデータをアップロードすると、自動でPDF化して発行が可能となります。帳票の種類も豊富に用意しているため、請求書や納品書などさまざまなニーズに対応が可能です。
従来かかる帳票発行業務と比較して、9割もの作業時間の削減が実現できるシステムです。
②TOKIUMインボイス
TOKIUMインボイスは、上場企業が250社以上も導入している実績が豊富な請求書受領クラウドシステムです。
電子帳簿保存法やインボイス制度などの最新の法令にも完全対応しているため、法改正がおこなわれても、最小限の労力で法令に則った対応ができます。また、請求書の事務業務を代行してもらえるため、作業にかかる書面・Excelの作成から管理までの時間を20%まで削減が可能です
セキュリティにも力も入れているため、社内の情報を安心して管理できるシステムです。
③楽楽電子保存
楽楽電子保存は電子帳簿保存法に特化した文書の一元管理システムです。
取引の際に使用した文書を読み込ませることで、システムが自動で文字を読み取ります。また読み取った情報から自動でファイル名もつけてくれるため、後々の書類検索も手軽になります。
シンプルな操作方法や管理画面であるため、誰でも使い始めやすく、社内に浸透させたいと考えている経理担当者の方におすすめなシステムです。
まとめ|電子帳簿保存法の目的を理解して適切に管理しましょう
本記事では、電子帳簿保存法の目的について、管理する区分方法や罰則などを交えて解説しました。
電子帳簿保存法とは、税務に関連する文書をデジタル化して保存するルールであり、対象となる文書には細かな要件を定めています。もし、この要件を満たしていない場合、税務署から違反と判断されてしまい、罰則として「青色申告の取消」や「重加算税」などが課されてしまうおそれがあります。
このように電子帳簿保存法に定められたルールは、会計や経理に大きな影響を与える内容です。大きなトラブルにならないためにも、基本的なルールの理解だけでなく、電子帳簿保存法に対応したシステムの活用を検討しましょう。










