すぐ分かる!電子帳簿保存法の事務処理規程サンプル|作成の流れと注意点ガイド
更新日:2025.03.03
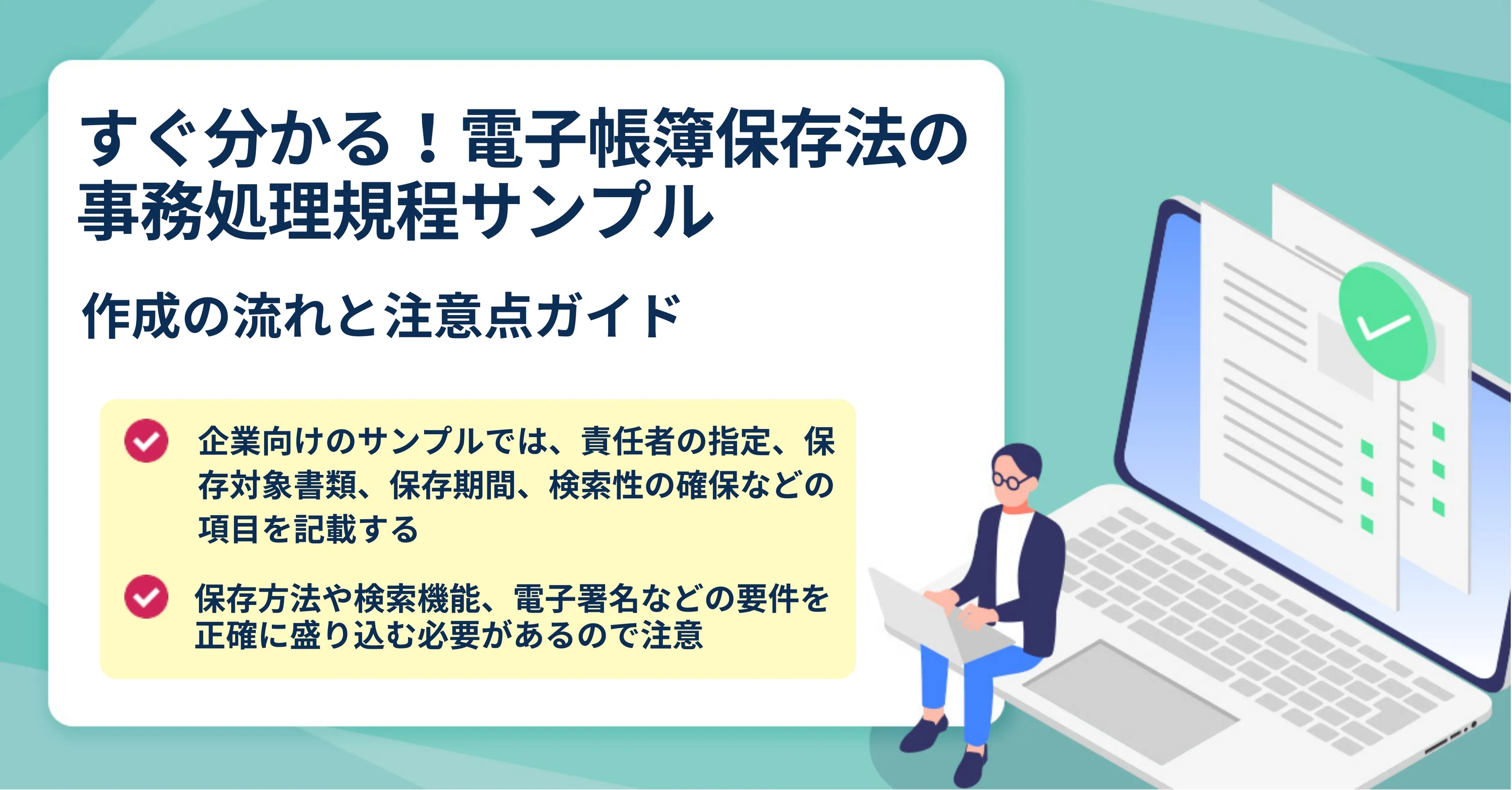
ー 目次 ー
電子帳簿保存法に対応するために、企業や個人事業主は「事務処理規程」を適切に作成し、運用する必要があります。しかし、どのように作成すればよいのか、具体的なサンプルがないと不安に感じる方も多いでしょう。本記事では、電子帳簿保存法の基本を押さえた上で、事務処理規程のサンプルを提供し、作成のポイントや注意点を分かりやすく解説します。この記事を読むことで、法律の要件を満たした事務処理規程をスムーズに作成し、企業のコンプライアンス強化に貢献できます。また、実運用時の課題や法改正への対応方法も紹介するため、実務担当者にとって実践的なガイドとなるでしょう。
電子帳簿保存法の事務処理規程とは
電子帳簿保存法の概要
電子帳簿保存法は、企業や個人事業主が税務関連の帳簿や書類を電子データとして保存する際のルールを定めた法律です。従来、紙での保存が義務付けられていた帳簿や請求書、領収書などを電子的に保存できるようにし、業務効率化やコスト削減を支援する目的で制定されました。
この法律では、電子帳簿やスキャナ保存、電子取引データの保存などのルールが定められており、企業はこれに従って適切な方法で電子データを管理する必要があります。
事務処理規程の目的と役割
電子帳簿保存法に基づく事務処理規程とは、電子データの保存・管理に関する社内ルールを明文化したものです。企業や組織が法令に適合した運用を行うために、具体的な業務フローや責任範囲を明確に示す目的で策定されます。
事務処理規程を整備することで、以下のようなメリットがあります。
- 税務調査時にスムーズな対応が可能になる
- 電子データの保存・運用に関する社内ルールを統一できる
- 法令違反による罰則リスクを回避できる
- 担当者ごとの業務・責任範囲を明確にできる
事務処理規程の必要性
電子帳簿保存法の適用を受ける企業は、電子データを適切に保存・運用することが求められます。しかし、単にデータを電子化するだけでは法的要件を満たすことはできず、適切な手順とルールを定めておく必要があります。
特に、以下のような企業においては、事務処理規程を策定して明確なルールを設けることが推奨されています。
|
企業の種類 |
事務処理規程が必要な主な理由 |
|
大企業 |
電子帳簿保存の対象データが多く、部門間での統一ルールが必要 |
|
中小企業 |
事務手続きの省力化と法的リスクの低減を図るため |
|
個人事業主 |
税務調査時の説明責任を果たしやすくするため |
また、税務署への事前承認が不要となった一方で、電子データの適切な管理が問題となるケースも増えています。そのため、適用企業は事務処理規程を策定し、運用ルールを明確にすることが求められています。
電子帳簿保存法の事務処理規程サンプル
事務処理規程の基本構成
電子帳簿保存法の事務処理規程は、企業が電子データを適切に保存・管理するためのルールを明文化したものです。一般的に、以下のような構成で作成されます。
|
項目 |
内容 |
|
目的 |
電子帳簿保存法に基づくデータ保存・管理のルールを明文化し、法令順守を徹底する |
|
適用範囲 |
本事務処理規程の対象となる帳簿や書類、対象となる部門や担当者 |
|
電子データの保存要件 |
保存形式、保存期間、検索機能の確保の方法 |
|
データ入力および管理 |
入力担当者の指定、入力手順、訂正や削除の禁止事項 |
|
承認・監査手順 |
社内監査の実施方法、外部監査の対応方針 |
|
変更および更新 |
法改正や業務変更に伴う規程の更新方法 |
企業向けの具体的なサンプル
企業規模が大きく、経理部門がある企業向けに適した事務処理規程のサンプルを以下に示します。
電子データ保存の基本ルール
本規程において、電子帳簿保存法に準拠した保存業務の流れを以下に定める。
- すべての電子データは所定のシステム(例:電子帳簿保存システム)に登録し、外部メディアでの保管は禁止する。
- 入力時のミス防止のため、Wチェック体制を整備し、誤ったデータの訂正には記録を残す。
- ファイル名には「日付_取引先名_取引内容」を含め、検索時の利便性を確保する。
保存データの検索・管理
以下の条件を満たす形で電子帳簿を管理し、必要な際に検索できるようにする。
- 日付検索、取引先検索、金額帯検索ができるシステムを導入する。
- 検索履歴を最低5年間保存し、監査対応に備える。
- バックアップデータを月次で作成し、社内サーバーおよびクラウドストレージで二重保管する。
税務監査への対応
電子帳簿保存法に基づき、税務監査時には以下の対応を行う。
- 税務署からの問い合わせに備え、監査専用のデータ抽出機能を用意する。
- 監査時には、IT部門が対応し、必要な検索環境を保証する。
中小企業や個人事業主向けのサンプル
中小企業や個人事業主では、複雑な管理体制を維持するのが難しいため、シンプルなルールを設けることが重要です。
電子データ保存の基本ルール
本規程では、最低限のルールとして以下を定める。
- 請求書・領収書などのスキャンデータは、フォルダ別にまとめて保存する。
- クラウドストレージ(例:Google ドライブ、Dropbox)を活用し、バックアップを確保する。
- 保存する際は「YYYYMMDD_取引先_金額.pdf」の形式で統一する。
検索と管理のシンプル化
以下の方法を用いることで検索の手間を省く。
- ファイル検索機能を活用し、日付・キーワードで探せる状態にする。
- 重要書類については、ルール化したフォルダで整理し、利便性を高める。
- 月ごとに整理したフォルダを作成し、取引内容別に仕分ける。
税務監査への簡易対応策
中小企業や個人事業主でも税務調査の対象になる可能性があるため、必要な準備を行う。
- 税理士と連携し、調査が入った際の対応フローを定める。
- 電子帳簿を見るための簡単なマニュアルを作成し、すぐに対応できるようにする。
電子帳簿保存法の事務処理規程の作成手順
事前準備と必要な情報の整理
電子帳簿保存法の事務処理規程を作成するには、まず事前準備として必要な情報を整理することが重要です。適切な準備を行うことで、法律の要件を満たしたスムーズな運用が可能になります。
基本的な事前準備
- 電子帳簿保存法の最新の法令を確認する
- 自社の会計・経理業務のフローを洗い出す
- 使用している会計ソフトや文書管理システムの仕様を確認する
- 電子保存する対象となる書類やデータの種類を整理する
必要な情報の整理
電子帳簿保存法に対応するためには、以下の情報を整理し、適切な管理体制を設計する必要があります。
|
整理すべき情報 |
詳細内容 |
|
保存対象の文書 |
請求書、領収書、注文書、契約書、日報など |
|
保存方法 |
PDF、スキャンデータ、クラウドストレージなど |
|
保存期間 |
原則7年間(法人税法・所得税法に基づく) |
|
運用担当者 |
経理部門責任者、情報システム担当者 |
各項目の具体的な記載方法
事務処理規程では、明確なルールを定めることが求められます。具体的な記載方法を以下に示します。
基本的な記載項目
- 適用範囲(どの部署・書類が対象か)
- 電子保存の方法(データフォーマット・管理体制)
- 入力・承認フロー(誰が登録し、誰が承認するか)
- 保存ルール(保存期間・管理方法)
- 定期的なチェック体制(監査や社内検査の頻度)
具体的な記載サンプル
以下に、事務処理規程の一例を示します。
作成後の社内周知と承認プロセス
事務処理規程を作成したら、社内展開を行い、関係者に周知することが不可欠です。また、経営層や監査担当者の承認も必要になります。
社内周知のポイント
- 全社向けに説明会を実施する
- 従業員向けのマニュアルを作成する
- イントラネットや社内掲示板に掲載する
承認プロセスの流れ
適切な承認を得ることで、実施後のトラブルを防ぐことができます。以下のフローを参考にしてください。
|
ステップ |
内容 |
担当者 |
|
1. 作成 |
事務処理規程を作成する |
経理担当者 |
|
2. 部門内レビュー |
関係部署の担当者とともに内容を確認 |
経理・情報システム担当者 |
|
3. 経営層の承認 |
経営陣の承認を得て正式に規程を策定 |
経営層・管理部門 |
|
4. 社内展開 |
全社へ周知を図り、遵守を促進 |
総務・管理部門 |
|
5. 実施・運用 |
規程に基づいた業務を実行 |
各部門 |
以上の手順を踏むことで、電子帳簿保存法に適した事務処理規程を適切に作成し、組織内で円滑に運用することができます。
電子帳簿保存法の事務処理規程作成時の注意点
法律の要件を満たすためのポイント
電子帳簿保存法に基づく事務処理規程を作成する際には、法的要件を十分に理解し、適切に反映させる必要があります。以下のポイントを押さえて作成を進めましょう。
電子取引データの保存要件
電子取引データは、一定の保存要件を満たす必要があります。特に、以下の要件に適合させることが求められます。
- 真実性の確保(訂正・削除履歴の記録、タイムスタンプの付与、電子署名の活用)
- 可視性の確保(検索機能の実装、画面表示・書面出力の確保)
業務フローに即した規程の策定
法律の要件を満たすだけでなく、自社の業務フローに沿った実用的な事務処理規程とすることが重要です。そのため、帳簿の管理や承認フロー、システムの操作手順などを細かく記載しましょう。
実際の運用時に企業がつまずきやすいポイントと解決策
事務処理規程が適切に運用されないと、税務調査時に問題となる可能性があります。企業が陥りがちな課題と解決策を把握し、スムーズな運用を目指しましょう。
電子データの適切な保存が徹底されない
従業員が適切に電子データを保存しないと、税務調査時に指摘を受ける可能性があります。これを防ぐために、社内での教育とモニタリング体制を整えることが重要です。
検索機能の確保が不十分
電子帳簿保存法では、保存したデータを迅速に検索できることが求められます。しかし、市販のシステムを導入しても適切な検索機能が確保されていないことがあります。システム選定時には、検索条件(取引日、取引先、金額など)が適切に指定できるかを確認しましょう。
従業員のコンプライアンス意識不足
事務処理規程を作成しても、従業員が理解し、適切に運用できなければ意味がありません。定期的な社内研修を実施し、電子帳簿保存法の遵守を促進しましょう。
電子データの保存方法と管理ルール
電子取引データの保存方法については、法令に準じて適切なルールを策定する必要があります。以下の管理ルールを定めることで、適正な保存を実現できます。
|
項目 |
ポイント |
|
保存対象データ |
電子取引に関するすべての証憑(請求書・領収書・契約書など) |
|
保存期間 |
原則7年間(法人税法・所得税法に基づく) |
|
保存場所 |
クラウドストレージや社内サーバーなど、安全性の高い環境を確保 |
|
アクセス権限 |
必要な従業員のみに限定し、適切な権限管理を実施 |
|
バックアップ |
定期的にバックアップを取得し、災害時でも復元可能な体制を整備 |
バックアップ体制の強化
電子データの消失リスクを回避するため、バックアップ体制を確立することが重要です。クラウドストレージとローカルストレージの両方に定期的なバックアップを行うことで、万一の事態に備えましょう。
監査や税務調査時の対応策
電子帳簿保存法に基づいた事務処理規程を適切に維持し、監査や税務調査に対応できる体制を整えることが求められます。
監査対応のポイント
- 保存された電子データが法要件を満たしているか定期的に点検する
- 監査時に求められる情報をスムーズに提供できるよう、フォルダ構成を整理する
- 監査対応マニュアルを作成し、社内の関係者が適切に動けるようにしておく
税務調査時のスムーズな対応
税務調査の際には、電子帳簿保存法に準拠した運用がなされていることを証明する必要があります。以下の対策を講じることで、スムーズな対応が可能となります。
- 電子データの検索機能を担当者が簡単に操作できるよう、事前に研修を実施
- タイムスタンプ付与や改ざん防止措置が適正に行われていることを確認
- データの訂正・削除履歴が適切に記録されているか、定期チェックを実施
電子帳簿保存法の事務処理規程の変更や更新のポイント
法改正対応のチェック方法
電子帳簿保存法は法改正が頻繁に行われるため、企業は最新の要件を満たすために適宜事務処理規程を見直す必要があります。ここでは、法改正に対応するためのチェック方法を解説します。
最新の法改正情報を把握する
法改正情報を見逃さないためには以下のような方法が有効です。
- 国税庁の公式サイトを定期的に確認する
- 税理士や社労士などの専門家に相談する
- 法律改正に関するセミナーや研修に参加する
- 業界団体のガイドラインを参照する
法改正時の実務対応フロー
法改正が発表された際にどのように対応するか、以下のフローを参考にしましょう。
|
ステップ |
対応内容 |
|
1 |
法改正情報の収集(国税庁サイト・専門家の情報など) |
|
2 |
社内の関係部署と情報共有 |
|
3 |
影響範囲の確認(システム・運用・事務処理規程の見直し) |
|
4 |
必要な修正内容の検討と改訂作業 |
|
5 |
関係者への通知と周知 |
|
6 |
新しいルールでの運用開始および監査体制のチェック |
社内ルール変更時の見直し基準
企業の内部統制や経理・会計のルールが変更された場合、事務処理規程も見直す必要があります。そのための基準を明確にしておきましょう。
変更が必要となるケース
- 会計処理のルールが変更された場合
- 業務フローの変更(例:経費精算システムの導入)
- 組織変更(例:経理部門の統廃合、担当者の変更)
- ITシステムのアップデートによる業務プロセスの変更
見直しのプロセス
- 変更点の把握(社内通知や会計監査報告書を確認)
- 影響範囲の分析(既存の事務処理規程と比較)
- 関係部署と協議し、必要な修正点をまとめる
- 規程の改訂案を作成する
- 経営陣や監査部門の承認を得る
- 社内で周知し、運用を開始する
定期的な更新と管理の重要性
電子帳簿保存法の事務処理規程は、一度作成すれば終わりではありません。変化する法規制や業務環境に対応し、定期的に見直すことが不可欠です。
定期的なチェックの推奨頻度
事務処理規程を最新の状態に保つためには、以下の頻度での見直しが推奨されます。
|
チェック頻度 |
内容 |
|
年1回 |
全体のルールを確認し、運用に問題がないかを検討 |
|
法改正時 |
最新の法令に準拠しているかをチェックし、必要に応じて改訂 |
|
組織変更時 |
担当部署や担当者の変更を反映 |
|
ITシステム変更時 |
電子帳簿管理システムの仕様にあわせて運用ルールを見直し |
維持・管理のためのポイント
電子帳簿保存法の事務処理規程を適切に維持するために、次のポイントを押さえておきましょう。
- 規程の更新履歴を記録し、改訂時の根拠を明確にする
- 監査や税務調査時にスムーズに対応できるよう、関係者への周知を徹底する
- 電子帳簿やシステムの取り扱いに関する定期的な勉強会を開く
- 必要に応じて、専門家のアドバイスを受けながら法令遵守を確実にする
まとめ
電子帳簿保存法に基づく事務処理規程の作成は、適切な電子データ管理を行い、法的要件を満たすために不可欠です。事務処理規程を策定することで、企業は監査や税務調査に対応しやすくなり、業務の効率化にもつながります。
作成時には、法律の要件をしっかり確認し、社内業務フローに即したルールを定めることが重要です。また、法改正や社内ルールの変更に合わせて定期的に見直しを行い、適切な管理を維持しなければなりません。
電子帳簿保存法の遵守は企業の信用にも関わるため、適切な規程を整備し、確実に運用することが求められます。本記事を参考にしながら、自社に合った事務処理規程を作成し、コンプライアンス強化に役立ててください。










