電子帳簿保存法の導入方法とは?手順や注意点を解説
更新日:2025.04.30
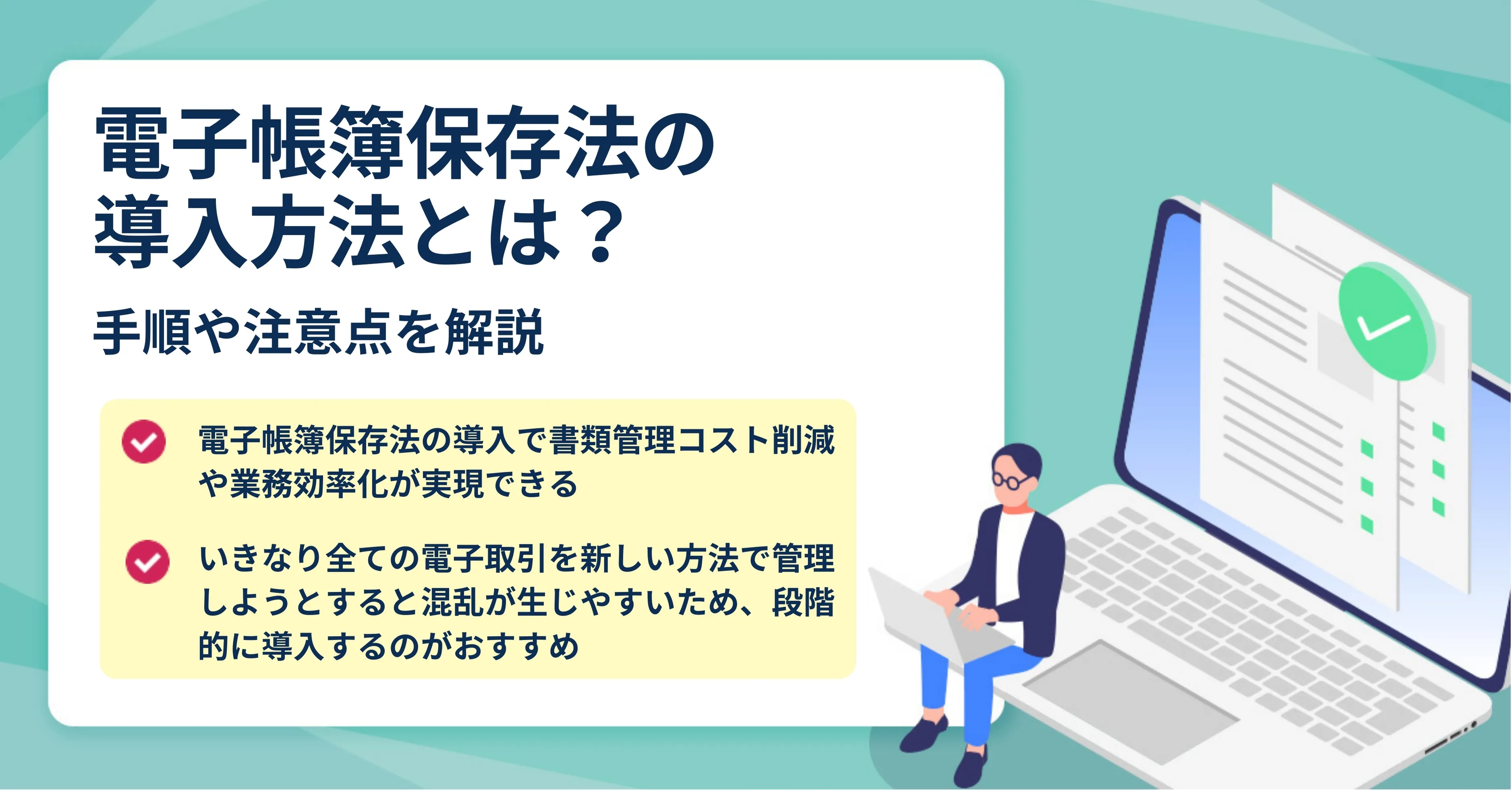
ー 目次 ー
電子帳簿保存法の改正により、2024年1月から電子取引データの電子保存が完全義務化され、企業規模を問わずすべての事業者が対応する必要が生じています。これにより、多くの企業が従来の紙の保存から電子データでの保存へ移行を余儀なくされています。
しかし、導入方法や法律の要件、必要な対応などがわからず悩む経理担当者や事業主が増加しているのが現状です。電子帳簿保存法への対応を誤ると税務調査で指摘を受けて、最悪の場合、税務上の控除が認められなくなるリスクもあります。
本記事では、電子帳簿保存法の基本的な内容から導入手順について、実際の運用方法や注意点を交えて解説します。
電子帳簿保存法とは、帳簿や書類の電子データ保存に関する法律
電子帳簿保存法は、国税関係の帳簿や書類の電子データでの保存を定めた法律です。時代の変化にあわせて数回の改正がおこなわれており、とくに、2024年1月からは電子取引データの電子保存が完全義務化されています。
電子帳簿保存法に適切に対応することで、保管スペースの削減や検索性の向上、業務効率化などのメリットが得られます。紙の書類を保管するためのキャビネットやスペースが不要になり、必要な書類を素早く検索できるようになるため、業務の効率化を図ることが可能です。
一方で、システム導入コストや業務フロー変更などへの対応も必要です。自社の規模や取引状況にあわせた対応方法の検討が求められます。
電子帳簿保存法を導入しなければならない3つの理由
電子帳簿保存法への対応は、単なる「法律だから仕方なく」という対応ではなく、デジタル時代のビジネス基盤を整える好機と捉えることが重要です。自社の規模や状況にあった方法で、計画的に導入を進めていきましょう。
電子帳簿保存法を導入すべき理由はおもに3つあり、ビジネス環境の変化への対応や経営改善の機会としても重要な意味を持っています。
ここでは、電子帳簿保存法を導入しなければならない3つの理由について解説します。
- 電子取引データの電子保存が義務化されているため
- 社会全体でデジタル化への対応が不可欠なため
- 業務効率化とコスト削減を図れるため
①電子取引データの電子保存が義務化されているため
2024年1月から、電子取引で受け取ったデータは、電子データのままの保存が法律で義務付けられています。これは企業規模や業種を問わず、すべての事業者に適用されており、紙に印刷して保存する方法は認められなくなりました。
法的義務に違反すると税務調査の際に指摘を受けて、最悪の場合、税務上の控除が認められないリスクがあります。
②社会全体でデジタル化への対応が不可欠なため
ビジネス環境は急速にデジタル化が進んでおり、取引先からの電子データでのやり取りが一般的になっています。政府もデジタル化を推進しており、電子帳簿保存法もその一環です。
この流れに対応しないと、取引先とのやり取りに支障が生じて、業界内での競争力が低下する可能性があります。したがって、社会全体のデジタルトランスフォーメーション(DX)に乗り遅れないためにも導入が必要です。
③業務効率化とコスト削減を図れるため
法対応の側面だけではなく、電子データでの管理は多くのメリットをもたらします。電子帳簿保存法への対応で、以下のようなメリットが期待できます。
- 紙の保管スペースやファイリングの手間が不要になり、検索性も向上する
- リモートワークでも書類確認が可能になる
- 印刷コストや保管コストが削減できる
初期投資は必要ですが、中長期的に見れば業務効率化とコスト削減につながる重要な経営改善の機会となるでしょう。
電子帳簿保存法の導入手順をわかりやすく5ステップで紹介!
電子帳簿保存法の導入、とくに電子取引データの電子保存への対応は、すべての事業者が避けられない課題です。適切な対応で、単なる法令遵守だけではなく、業務効率化やペーパーレス化などのメリットも得られます。
導入を成功させるためには、段階的かつ計画的に進めることが重要です。
ここでは、電子帳簿保存法の導入手順を、5つのステップに分けて解説します。
- 現状を把握して目的を明確にする
- 対象書類を洗い出す
- 導入方法の検討
- 業務フローを整備する
- 運用を開始して定着化させる
①現状を把握して目的を明確にする
自社で電子的に受け取っている書類を把握します。メールで受け取るPDF請求書やクラウドからダウンロードする領収書、EDIシステムでのデータなど、どのような電子取引があるかをリストアップしましょう。
そして、リストアップした電子取引が月にどれくらいの量があるかを確認します。また、書類検索の効率化や保管スペース削減などの導入の目的も明確にします。
②対象書類を洗い出す
電子取引に該当する書類を具体的にリストアップします。リストアップの際には、自社が電子的に発行している書類も忘れずに確認します。
また、それぞれの書類の保存期間を確認しておきましょう。法人の場合は基本7年間(欠損金がある場合は10年)、個人事業主の場合は書類により5〜7年間、インボイス関連書類は7年間保存が必要です。書類ごとに分類して、保存期間を明確にしておくことで、後々の管理が楽になります。
③導入方法の検討
どのように電子データを保存するか方法を決めます。大きく分けて「システムを導入する方法」と「自社でフォルダ管理する方法」の2つがあります。
2つの導入方法の違いは、以下のとおりです。
|
システムを導入する方法 |
・専用の電子帳簿保存システムを検討する |
|
自社でフォルダ管理する方法 |
・データを受け取ってから保存するまでの具体的な手順を決める |
取引量が多い場合や、より効率的に管理したい場合は専用システム導入の検討がおすすめです。
④業務フローを整備する
電子データを受け取ってから保存するまでの一連の流れを具体的に決めます。たとえば、以下のような流れを整理します。
- メールで請求書PDFを受信
- 内容確認
- 所定のフォルダに保存
- 経理システムに情報入力
- 定期的にバックアップを取る
業務フローは複雑にしすぎず、日常業務に自然に組み込むことが大切です。担当者がいない場合の代行者も決めておくと安心です。
⑤運用を開始して定着化させる
関係者に新しい手順を説明して、簡単なマニュアルやチェックリストを用意すると理解が深まります。最初は一部の取引や部門からはじめて、問題点を洗い出し、必要に応じて手順を調整する方法がおすすめです。
いきなりすべての電子取引を新しい方法で管理しようとすると混乱が生じやすいため、段階的に導入するのがおすすめです。
【重要】小規模事業者なら簡易的な方法で要件を満たせる
取引量が少ない小規模事業者であれば、高額なシステムを導入せずとも、基本的なパソコン操作と整理されたフォルダ管理で法的要件を満たせます。これは、国税庁が小規模事業者向けに電子取引データの保存要件を緩和しているためです。
具体的な導入手順は以下のとおりです。
- パソコンに「電子帳簿保存」というフォルダを作成する
- その中に年度ごとのフォルダを作成する
- 年度フォルダの中に取引先ごとのフォルダを作成する
- 電子データを受け取ったら、次のような命名規則でファイルを保存する
- 月に一度、外付けハードディスクにバックアップを取る
- 簡単な「電子取引データ管理規程」を作成する
取引量が増えて、より効率化したい場合は専用システムの導入がおすすめです。
電子帳簿保存法を導入する際の注意点
電子帳簿保存法を導入する際には、以下のような注意点があります。
- 保存要件を正確に理解して遵守する
- データの安全性とバックアップ体制を確立する
- 業務フローを見直して社内教育を徹底する
法令への対応は、初期段階は手間に感じるかもしれませんが、適切な導入で長期的には業務効率化につながります。
自社の規模や業務内容にあわせた導入計画を立てて、段階的に進めていくようにしましょう。
ここでは、電子帳簿保存法を導入する際の3つの重要な注意点について解説します。
①保存要件を正確に理解して遵守する
電子帳簿保存法では、電子データを保存する際に「真実性の確保」や「可視性の確保」などの満たすべき要件が定められているため、それらを正確に理解して、適切に対応しなければなりません。
また、電子帳簿保存法には「電子帳簿等保存」「スキャナ保存」「電子取引」の3つの区分があり、それぞれで要件が異なります。電子帳簿保存法の要件を満たさない保存方法では、税務調査の際に否認される可能性があるため、要件を正確に理解し遵守することが不可欠です。
②データの安全性とバックアップ体制を確立する
電子データは便利である一方で紛失・破損のリスクがあるため、適切なセキュリティ対策とバックアップ体制の整備が重要です。法定保存期間(多くの場合7年間)にわたってデータの完全性と可用性を確保することで、電子帳簿保存法に対応できます。
③業務フローを見直して社内教育を徹底する
電子帳簿保存法への対応は、単にシステムを導入するだけではなく、業務フローの見直しと社内教育が重要です。適切な業務フローの構築と社内教育がなければ、せっかくのシステム導入も形骸化してしまう可能性があります。
とくに、導入初期は手厚いサポート体制を整えて、定着を図ることが重要なため、全従業員が新しい方法を理解し、正しく実践できるように継続的な教育が必要です。
まとめ|電子帳簿保存法の基本を理解して計画的に導入しよう
本記事では、電子帳簿保存法の基本的な内容から導入手順について、実際の運用方法や注意点を交えて解説しました。
電子帳簿保存法に適切に対応することで、書類管理コストの削減や業務効率化、検索性の向上といったメリットが得られます。とくに小規模事業者は、高額なシステム導入ではなく、整理されたフォルダ管理と明確なルール作りでも対応可能です。
無理のない範囲で段階的に対応を進めて、必要に応じて税理士などの専門家のサポートを活用しながら、自社に最適な電子帳簿保存法の導入を進めましょう。










