電子帳簿保存法でのメール本文の保存方法とは?PDF化や索引簿での方法を紹介
更新日:2025.06.04
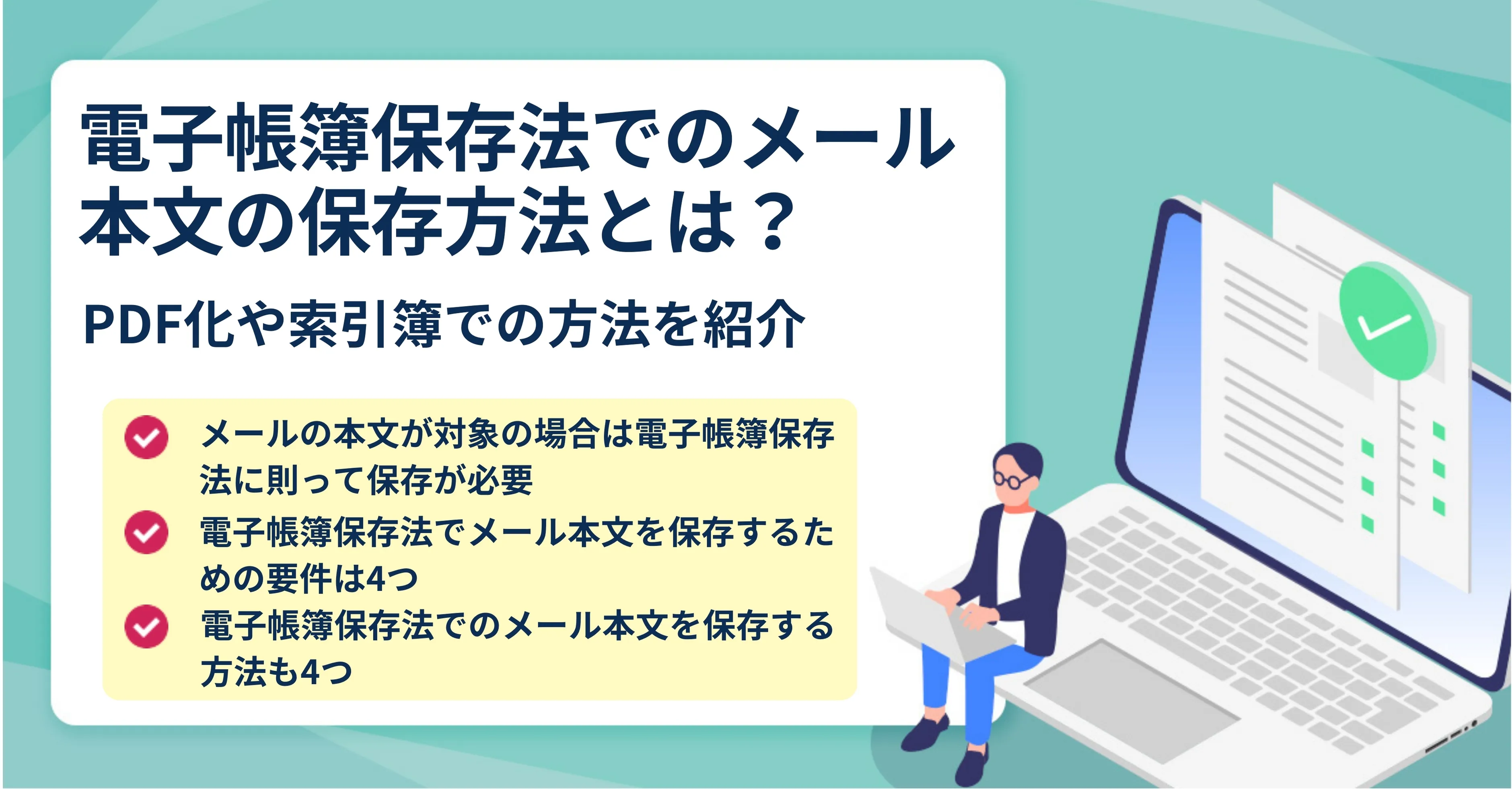
ー 目次 ー
ビジネスシーンでは、メールに請求情報や発注詳細などの取引に関する内容が記載されているケースがあります。取引情報が記載されている場合は、メール本文も電子帳簿保存法の対象となり、ルールに則った対応が必要です。
電子帳簿保存法とは、税務関係の帳簿や電子データで送受信した取引情報を保存する際のルールを定めた法律です。電子帳簿保存法には保存要件が定められているため、理解したうえで対応をおこないましょう。
メール本文が電子帳簿保存法の対象にもかかわらず、適切な対応がされていない場合、法的な罰則を受ける可能性があるため注意が必要です。
本記事では、メール本文が電子帳簿保存法の対象になる状況や具体的な方法を解説します。
【前提】電子帳簿保存法では、メール本文も保存の対象になる!
電子帳簿保存法では、取引先に電子データを介して送受信した書類や内容が対象です。このことから、メールの本文に請求情報や発注金額などが記載されている際は、電子帳簿保存法に則った保存が必要です。
そもそも電子帳簿保存法は、税務関係の帳簿や電子データで送受信した書類などのデータ保存を可能にする法律です。2024年の改正にともない電子データを利用した取引の情報はすべてデータでの保存が義務づけられ、メールの本文も対象になりました。
ほかにも、メールに請求書や納品書などのデータが添付されている場合は、電子帳簿保存法の保存要件を満たした対応が求められます。
メールが電子帳簿保存法の対象となる状況とは?
電子帳簿保存法ではメールそのものも保存対象になります。ただ、保存方法は本文に取引情報が記載されている場合と添付情報が取引情報の場合にわかれています。
細かなルールではあるものの、それぞれのケースでの対応方法を理解しておくことで、法令を遵守した適切な対応が可能です。
ここでは、メールが電子帳簿保存法の対象となる状況を解説します。
①メール本文に取引情報が記載されている
メール本文に請求情報や発注詳細などの取引内容が記載されている場合は、電子帳簿保存法の対象になります。
メール本文の内容がデータとして削除・紛失しないよう、電子帳簿保存法のルールに則って保存しましょう。
②メールに取引情報が記載された添付ファイルがある
請求書や領収書などを添付したメールを送受信する際は、電子帳簿保存法に則って保存が必要です。
ただし、添付ファイルが保存対象の際は、メール本文の保存は求められないため、ファイルをダウンロードした後はメールを削除して問題ありません。
電子帳簿保存法でメール本文を保存するための4つの要件とは?
電子帳簿保存法には保存要件が定められているため、メール本文や添付ファイルに取引内容が記載されているならば対応が必要です
電子帳簿保存法の保存要件は、大まかに真実性の確保と可視性の確保の2つにわかれています。電子帳簿保存法では、下記の要件に則って保存されていないと法律上の罰則を受けるおそれがあるため注意しましょう。
ここからは、電子帳簿保存法でメール本文を保存するための4つの要件を解説します。
- 書類の改ざんができないよう対策する
- 電子計算機処理システムのマニュアルを用意する
- 検索機能を備える
- 必要なときに書類を表示・印刷できる用意をする
①書類の改ざんができないよう対策する
電子帳簿保存法では保存後の内容が改ざん・削除されていないことを証明するために、以下の措置が求められます。
- タイムスタンプが付与された書類を受け取り・保存する
- 受け取った書類にタイムスタンプを速やかに付与し、情報が確認できるようにする
- 訂正削除の記録が残るか、訂正削除ができないシステムを利用する
- 訂正・削除を防止する事務処理規程を備え付け、運用する
上記はすべてを網羅する必要はなく、自社の取りやすい方法や状況にあわせて選んで問題ありません。
②電子計算機処理システムのマニュアルを用意する
自社で電子計算機処理システムを開発した際は、操作方法をマニュアルにして、パソコンの側においておきましょう。
他社から購入した電子計算機処理システムを利用する場合は、購入時にマニュアルが付属しているため、自社で制作する必要はありません。
③検索機能を備える
可視性の確保では、必要時にデータをすぐ取り出せる状況で管理しなければなりません。具体的には、検索機能を備え、取引年月日や金額、取引先名で探せる状態にしておく必要があります。
なお、検索に対応する際は下記の3点を満たすことが求められています。
- 取引年月日、取引金額、取引先名の記録項目により検索できること
- 日付または金額の範囲指定により検索できること
- 2つ以上の任意の記録項目を組み合わせた条件により記録できること
④必要なときに書類を表示・印刷できる用意をする
メール本文を電子帳簿保存法に則った形で保存する際は、必要時にすぐディスプレイへ表示できるよう準備が必要です。
たとえば、パソコンとディスプレイを接続し、求められた際にすぐ表示できるよう準備しなければなりません。ほかにも、印刷が必要な場面に備えてプリンターを設置や設定をしておきましょう。
なお、パソコンやプリンターの操作に誤らないよう操作マニュアルも用意しておくことも求められています。
電子帳簿保存法でのメール本文を保存する方法4選
メール本文や添付ファイルを電子帳簿保存法に則って保存する場合、システムへの保存や索引簿の作成などの方法があります。企業によって適切な保存方法は異なるため、自社にあったものを見つけましょう。
ここでは、電子帳簿保存法でのメール本文を保存する方法を解説します。
- メールシステムに保存する
- 検索要件を満たしたファイルに振り分ける
- メール本文をPDFに変換して保管する
- PDFファイルで索引簿を作成する
①メールシステムに保存する
使用しているメールシステムにメール自体を保存しておけば、誤操作がない限りデータの保存が可能です。添付ファイルが存在する場合は、本文以外もあわせて保存しておきましょう。
ただし、電子帳簿保存法に則るためには保存要件を満たす必要があるため、該当メールを検索できるようにする必要があります。
たとえば、「取引年月日」「取引先名称」「取引金額」でタグ付けし、検索を可能にしましょう。
②検索要件を満たしたフォルダに振り分ける
「取引年月日」「取引先名称」「取引金額」を設定したフォルダにメールを振り分ければ、電子帳簿保存法に対応が可能です。
たとえば、「240401_株式会社〇〇_10000」のように、作成したフォルダに関係のあるメールを振り分けておくことで、必要な際に検索できます。
③メール本文をPDFに変換して保管する
本文に取引情報が記載されている際は、メール内容をPDFに変換しておくことで電子帳簿保存法の保存要件を満たせます。
PDFに変換後は、ファイル名を「240401_株式会社〇〇_10000」にしておき、「取引年月日」「取引先名称」「取引金額」で検索できるようにしましょう。
④PDFファイルで索引簿を作成する
フォルダやメール本文を変換したPDFの名前に、「取引年月日」「金額」「取引先名称」の記載が難しければ、Excelを利用して索引簿を作成する方法があります。
方法としては、メールを振り分けたフォルダに連番をつけておき、Excelで作成した索引簿に保存要件である「取引年月日」「取引先」「取引金額」を記載します。この方法を利用すれば、連番で検索してすぐに必要な情報の検索が可能です。
ただし、取引先が多い場合は入力作業の手間が増えるため、自社にあっているか検討したうえで対応しましょう。
まとめ|電子帳簿保存法ではメール本文の内容次第で保管が求められる
本記事では、メール本文が電子帳簿保存法の対象になる状況や具体的な方法を解説しました。
電子帳簿保存法では、取引情報が記載されている場合はメール本文の保存が求められます。本文を保存する際は、メールシステムの機能を利用するか、PDFに変換する方法などがあります。
取引情報を確認する方法がメールのみであれば、本文が電子帳簿保存法に則って保存されていないと、法的に罰則を受ける可能性があるため注意が必要です。
メール本文の保存方法は企業によって適切な方法が異なるため、悩む場合はこの記事を参考に選びましょう。










