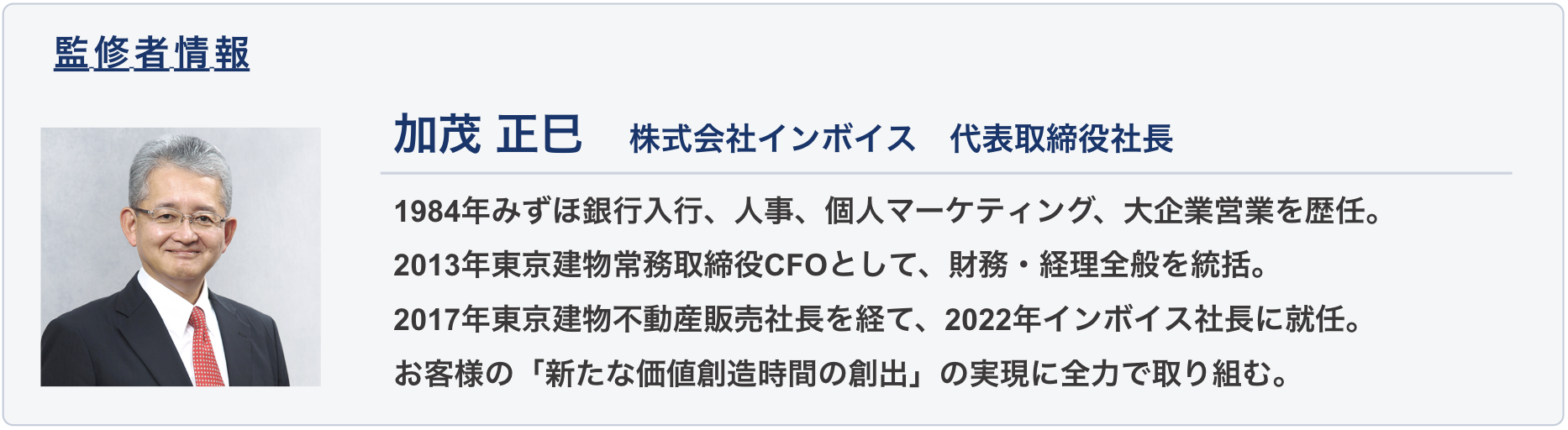【2024年から義務化】電子帳簿保存法のデータ保存はどうすれば良い?猶予措置も含めて解説
更新日:2026.01.10
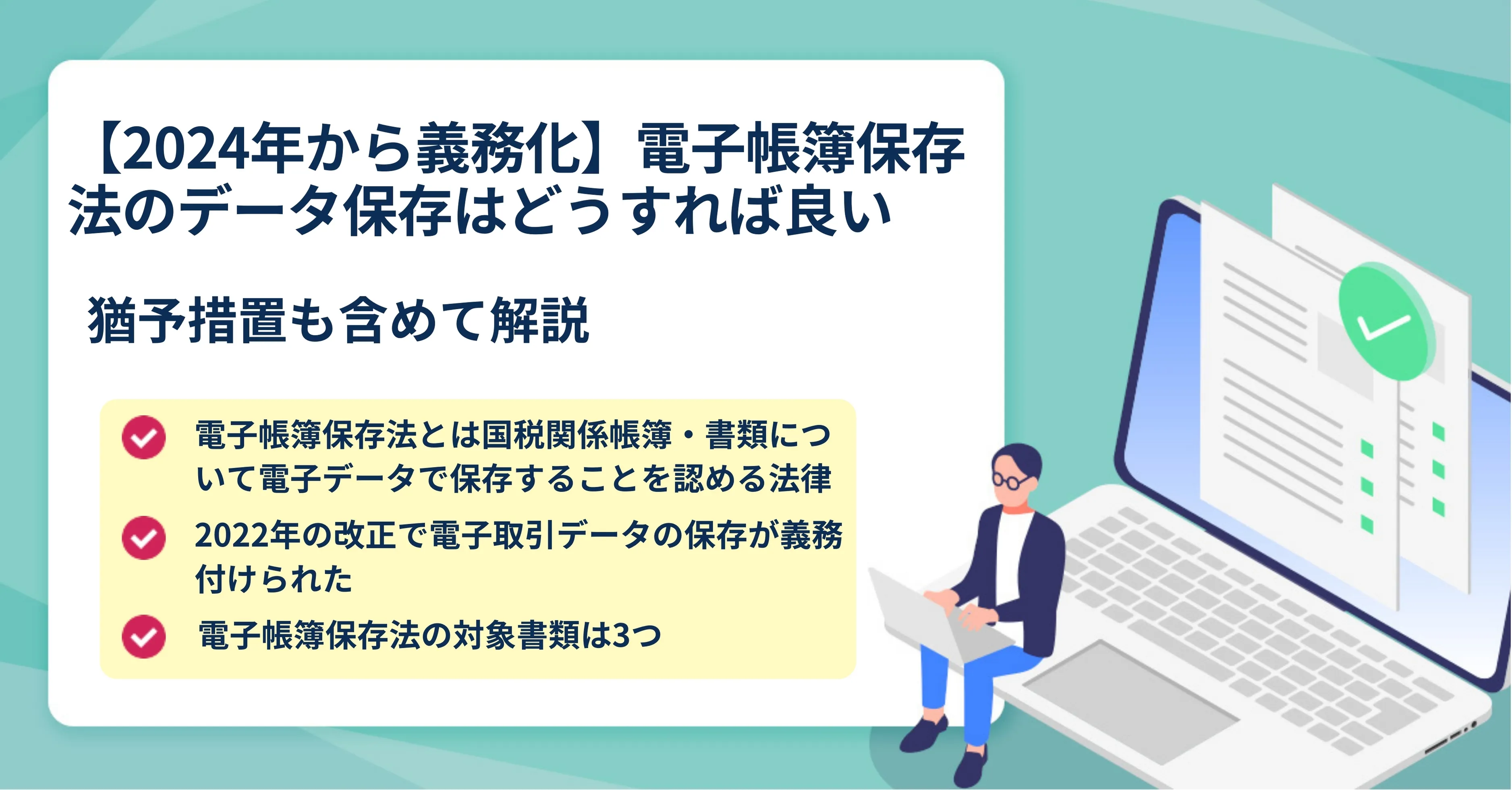
ー 目次 ー
電子取引データの保存方法についてどう対応すべきか、お悩みの方がいらっしゃるのではないでしょうか。2024年1月から「電子帳簿保存法」の電子取引データの保存義務化が施行されます。2022年の法改正から2年間は任意でしたが、今後はすべての事業者が対応しなければなりません。
そこで本記事では、電子帳簿保存法の概要や、対象書類、電子取引データの保存方法について解説します。「電子帳簿保存法」の電子取引データの保存義務化について、どう対応したらよいか理解できるようになりますので、ぜひ最後までお読みください。
電子帳簿保存法におけるデータ保存は2024年1月から完全義務化
電子帳簿保存法は、国税関係帳簿書類を電子データで保存する場合の要件を定めた法律です。 今回の改正は、企業の業務効率化とペーパーレス化を促進し、脱炭素社会の実現に貢献することを目的としています。
改正のポイントは以下の点が挙げられます。
- 電子取引データの紙保存の廃止
- 電子データでの保存の義務化
- タイムスタンプ要件の緩和
- 猶予措置の導入
従来は、電子取引で授受したデータを紙に印刷して保存することが認められていましたが、2024年1月1日以降は、原則として電子データでの保存が義務付けられました。 ただし、一定の要件を満たす場合は、紙での保存も認められる猶予措置が設けられています。
企業は、電子帳簿保存法の改正に対応するために、電子データの保存方法や管理体制を見直す必要があります。 電子データの保存には、適切なセキュリティ対策を施し、データの改ざんや紛失を防ぐことが重要です。 また、税務調査に対応できるよう、データの検索や閲覧が容易なシステムを構築する必要があります。
電子帳簿保存法の罰則
2022年の改正にて電子保存の手続きや要件が緩和されました。要件が緩和される代わりに、不正防止として不正が発覚した場合の罰則が厳格化されています。
電子帳簿保存法の規則に違反した場合、罰則が科せられる可能性があります。
青色申告の取り消し
青色申告を事前に行うと、所得から最大65万円の特別控除を受けられ、さらに事業で出た赤字を3年間繰り越すことができます。事業者にとって大きなメリットがある制度ですが、電子帳簿保存法に違反すると、青色申告が取り消されてしまう恐れがあります。
課税金額の増加
国税に関する帳簿や書類に不備が多い場合、推計課税が科せられる場合があります。推計課税とは、税務調査の際に直接資料によらず、推計により所得金額を認定する方法です。推計課税の場合、実際に支払うべき税額より多く支払う恐れもあります。
さらに電子データの改ざんや仮装が発覚した場合、申告漏れなどに課される重加算税に10%加重して納税しなければなりません。
会社法での過料
会社法第976条に「帳簿や書類の記録保存に関する」規定があります。国税関係の帳簿および書類を適切に保存しないと、100万円以下の過料が科せられる可能性があるので注意が必要です。
【2022年施行】電子帳簿保存法の改正内容
電子帳簿保存法は1998年に施行され、複数回改正されています。直近の2022年に改正されたポイントは以下のとおりです。
- 電子保存における事前の承認申請制度の廃止
- タイムスタンプ要件、検索要件の緩和
- 電子データに不正があった場合の税金加重
- 電子取引のデータ保存の義務化
「電子保存における事前の承認申請制度の廃止」について、これまで電子的に作成した国税関係の帳簿や書類を保存する際には、事前に税務署長に申告し、承認を得ることが必要でした。今回の改正により、事業者の事務負担を軽減するため、事前承認申請制度が廃止されました。
「タイムスタンプ要件、検索要件の緩和」については、タイムスタンプの付与期間が、3営業日であったのが、最長2ヶ月と概ね7営業日以内に延長されました。電子取引のデータ保存において、基準期間の売上高が5,000万円以下の事業者は、検索要件の全てが不要となりました。ただし、税務職からのダウンロードの求めに応じられるようにしておくことが条件です。
「電子データに不正があった場合の税金加重」については、国税関係の帳簿や書類の電子データに改ざんや仮装があることが発覚した場合、重加算税が10%加重されます。
「電子取引のデータ保存の義務化」については全ての事業者が対象となり、電子取引のデータ保存が義務付けられました。そのため、電子データで受領した書類(納品書や領収書など)を出力して紙ベースで保存している場合は、電子データでの保存に変更する必要があります。
電子帳簿保存法のデータ保存義務化はいつから?猶予措置についても解説
2022年の改正で電子取引データの保存が義務付けられました。ここでは、その日程や猶予措置について解説します。
義務化の開始時期
2024年1月から電子取引データの保存が義務化されます。対象となるのは、すべての事業者が対象法人税や消費税の納税義務がある事業者、および青色申告者で給与などの支払額が500万円を超える場合)です。
新たな猶予措置
2024年1月以降も一定の要件を満たす場合、電子保存の猶予が認められます。国税庁の「電子帳簿保存法一問一答」によると「相当の理由があり、あわせてダウンロードの求めや出力書面の提出に応じられる場合」と判断された場合とありますが、詳細については明確な発表がありません。
電子帳簿保存法の3つの対象書類
電子帳簿保存法は、帳簿や書類の作成方法や受領方法により保存方法が異なります。対象書類は、「スキャナ保存」「電子帳簿等保存」「電子取引データ保存」の3つに区分されます。ここでは、詳細や注意点について解説します。
スキャナ保存
スキャナ保存とは、取引先から紙で受領した書類や自社で作成した書類をスキャンして画像データで保存する方法です。ただし、改ざん防止のため一定の要件を満たさなければなりません。例えば、タイムスタンプの付与や履歴が残るシステム・クラウドの導入などです。なお、スキャン後の元本は廃棄可能となっています。
電子帳簿等保存
電子帳簿等保存とは、パソコンやタブレットなどの電子媒体に作成した帳簿や書類を、そのままのデータとして保存することです。具体例は以下のとおりです。
- 貸借対照表
- 仕訳帳
- 損益計算書
つまりメディアやサーバーに保存したものが、すべて電子帳簿等保存の対象となります。
電子取引データ保存
電子取引データ保存とは、取引先とのやり取りで発生する請求書や領収書などの書類や電子明細を、電子データのまま保存することです。クラウドサービス利用の場合は訂正・削除の記録が残り、改ざんができないため、タイムスタンプは必要ありません。
電子帳簿保存法の対象外の書類
電子帳簿保存法の対象外の書類もあります。手書きで作成した国税関係帳簿や書類は対象外であり、書面で保存する必要があります。たとえば「売掛帳」や「買掛帳」「固定資産台帳」「現金出納帳」「棚卸表」「賃借対照表」などです。
電子帳簿保存法の対応手順
電子帳簿保存法において、授受した請求書データの保存・管理方法が特に重要です。電子取引データを適切に保存するための手順を、わかりやすく解説します。
電子取引を確認・分類する
まず、現在のすべての取引を確認し、電子取引か否かに分類します。例を挙げると以下のとおりです。
- 電子メール
- インターネットのホームページ
- クレジットカード、スマートフォンアプリ交通系ICカード
- EDI(電子データ交換)システム
- ペーパーレス化されたFAX
- DVDやUSBメモリなどの記録媒体
以上の方法を使用し、授受した請求書や領収書が電子取引の対象となります。書類の授受方法や保存方法、保存場所や月間取引数なども確認が必要です。
保存方法を決定する
取引の分類が完了したら、データの保存方法を決定します。保存方法は以下に示した、2つの要件を満たしている必要があります。要件の1つが「真実性」であり、内容は以下のとおりです。
- タイムスタンプが付与された取引情報を授受する
- 取引情報の受領とタイムスタンプ付与、保存の責任者や監視者の記録の管理を迅速かつ適切に行う。
- 訂正や削除の記録が残るシステム、もしくは訂正や削除ができないシステムを利用する
- 訂正や削除を防止するためのルールを定め、それに沿って運用する
もう1つの要件が「可視性」で、以下の内容となっています。
- 保存しているデータをすぐに見られるように、操作用の機器やソフトウェア、出力機器を揃え、操作説明書とともに整理しておく
- 概要書や基本設計書等を用意し、システムの使い方がわかるようにしておく
- 検索機能付きのシステムを利用する(「日付」「取引金額」「取引先」で検索できること)
以上の要件を満たした保存方法を選択する必要がありますが、会社の規模や予算に合わせて文書管理システムを導入するか検討すると良いでしょう。
保存場所を決定する
データの保存を自社サーバ内かシステムで行うかを検討・決定します。その際、改ざん防止と検索機能を確保できるものを選ばなければなりません。
一定の要件を満たす事業者については、検索機能に関する要件が免除される場合があります。例えば「保存義務者が税務職員によるダウンロードの求めに応じられる場合」などです。税務職員からダウンロードやプリントアウトを求められた場合に、データの紛失や検索の遅延がないよう注意が必要です。
承認・業務フローを見直す
システムの変更にともない、承認・業務フローの見直しが必要です。例えば、電子データとして受領した請求書を紙に印刷して、上司の承認や経理へ渡している場合。電子データはそのまま保管する必要があります。
メールやシステムを通じて電子データの状態で上司や経理に送ることで、紙を再び電子保存する必要もなくなり、業務時間の短縮が可能です。さらに新たに採用した保存方法について、関係者への周知徹底を行うことで業務の効率化や改善にもつながります。
まとめ
電子帳簿保存法が2022年に改正されたことにより、保存要件が緩和され、電子データの保存を行いやすくなりました。電子取引のデータ保存については、2024年1月から義務化されます。
全ての事業者が対象となり、適切な保存ができていない場合には罰則が科せられる恐れもあります。自社が利用しているシステムが電子帳簿保存法の要件に対応しているか確認し、早急に備えましょう。