電子帳簿保存法で検索要件が緩和された?不要になるケースやほかの変更点も解説
更新日:2025.07.28
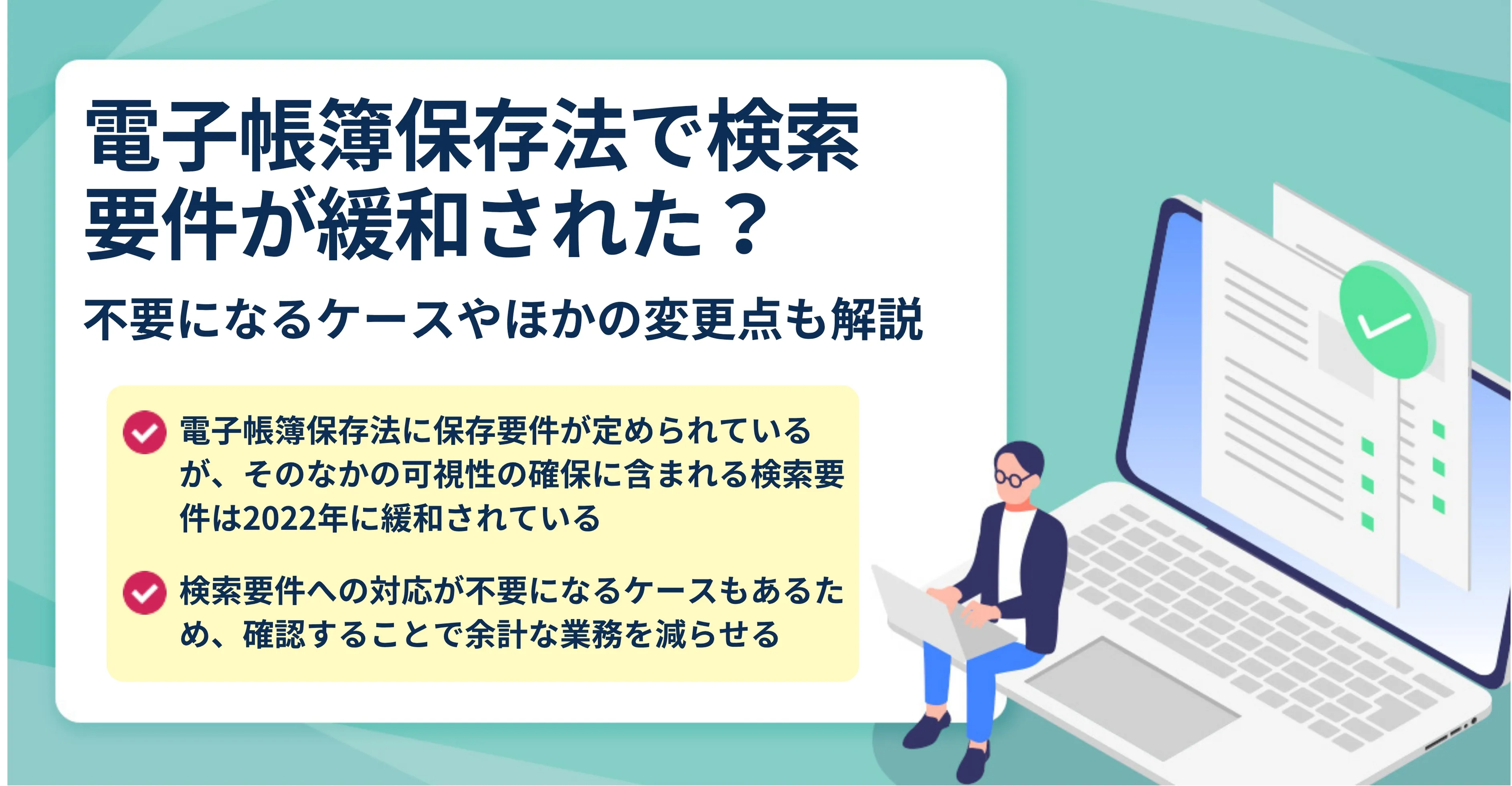
ー 目次 ー
電子帳簿保存法は、国税関連の帳簿や書類を電子データで保存する際のルールを定めた制度です。保存する際は、「真実性の確保」と「可視性の確保」という2つの保存要件を満たす必要があります。
ただし、2022年の法改正によって、「可視性の確保」に含まれる検索要件の一部が緩和されています。
電子帳簿保存法は、法改正によって検索要件以外にもさまざまな点が変更されているため、理解したうえで対応を進めることで、法令違反のリスクを抑えられるでしょう。
本記事では、電子帳簿保存法で検索要件が緩和されたのかについて、不要になるケースやほかの変更点も交えて解説します。
【前提】「検索要件」とは、電子帳簿保存法の保存要件のひとつ
電子帳簿保存法は、データを保存する際に「真実性の確保」と「可視性の確保」という2つの保存要件を定めています。
検索要件はこの「可視性の確保」に含まれる項目であり、税務調査時に必要なデータをスムーズに取り出せることが目的です。2022年の改正では、この検索要件が一部免除される条件が定められました。
なお、この検索要件は下記の条件を満たすことで免除も可能です。
- 前々年の売上高が5,000万円以下の事業者
- 電子的に受け取った書類を印刷して、取引年月日や取引先ごとに整理した状態で提示・提出が可能
ただし、免除を受ける際にも閲覧用機器の設置や、タイムスタンプの付加などの対応は必須のため、データ自体は破棄しないように注意しましょう。
2022年に緩和された電子帳簿保存法の検索要件とは?改正前と比較!
電子帳簿保存法における検索要件は、2022年の法改正のタイミングで緩和されました。
改正後の検索要件では、「取引年月日」「取引金額」「取引先名称」で検索できるようにフォルダの設定や索引簿の用意の対応が必要です。そのため、ファイル名を「取引年月日」「取引金額」「取引先名称」に設定するか、索引簿の活用によって可視性の確保の要件の1つを満たすことが可能です。
なお、改正前と改正後の検索要件の違いは、以下のようになっています。
|
改正前(2021年以前) |
・「取引年月日」「勘定科目」「取引金額」「その帳簿の種類に応じた主要な記録項目」で検索できる ・日付か金額の範囲指定により検索できる ・2つ以上の任意の記録項目を組み合わせた条件で検索できる |
|
改正後(2022年以降) |
・「取引年月日」「取引金額」「取引先名称」で検索できる ・日付か金額の範囲指定により検索できる ・2つ以上の任意の記録項目を組み合わせた条件で検索できる |
参考:
国税庁「法第4条((国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等))関係」
国税庁「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則」
【2025年最新】検索要件以外にも!法改正で変更された項目
電子帳簿保存法は1998年の施行以降何度も改正されており、事業者は常に最新の法令を理解しておかなければなりません。誤って以前の内容のまま電子帳簿保存法の対応を進めてしまえば、法令違反とみなされ、青色申告の取り消しや追徴課税などの罰則を科せられるリスクがあります。
このような事態を避けるためにも、2025年現在の検索要件以外の変更点への理解を深めておきましょう。
ここでは、検索要件以外にも法改正で変更された電子帳簿保存法の項目を解説します。
- 検索要件が大幅に緩和された
- スキャナ保存の要件が変更された
- 重加算税の適用対象変更
- 青色申告特別控除65万円の条件見直し
①検索要件が大幅に緩和された
電子帳簿保存法では、保存要件の1つとして検索機能の確保が求められていました。
しかし、2024年以降は下記の条件にあてはまる場合、検索機能の確保の義務が免除されています。
- 前々年の売上高が5,000万円以下の事業者
- 電子的に受け取った書類を印刷して、取引年月日や取引先ごとに整理した状態で提示、提出が可能
このことから、個人事業主や小規模事業者でも電子帳簿保存法への対応が容易になりました。
なお、税務調査時も求められた際に必要なデータをダウンロードできれば、システム側で検索機能を有していなくても問題ありません。
②スキャナ保存の要件が変更された
スキャナ保存に関しても改正が入り、2024年1月以降は下記の点が変更になっています。
- 解像度・階調・大きさに関する情報の保存が不要
- 入力者情報の確認要件が不要
- 帳簿との相互関連性の確保が必要な書類は重要書類に限定
この改正により、一般書類をスキャナ保存する場合は相互関連性の確保が不要になり、経理担当者の負担が軽減しました。
満たすべき項目も少なくなっており、スキャナ保存の保存要件自体が緩和されたといえます。
③重加算税の適用対象変更
従来、電子帳簿保存法への対応が不十分であり、税務調査で修正申告を求められた際は重加算税が課せられていました。しかし、2027年以降は一定の要件を満たすシステムで記録・保存し、税務署への届け出を提出することで、重加算税が免除されます。
重加算税が免除されるための項目は、以下のとおりです。
- 記録の訂正・削除履歴が確認できるシステムでの保存
- 請求書や納品書などの取引情報と帳簿記録との関連性の確保
- 税務署長への事前届出の提出
このことから、電子帳簿保存法に対応したシステムを利用することの重要性がより高まっています。
④青色申告特別控除65万円の条件見直し
従来では、青色申告特別控除65万円を利用する際に、「優良な電子帳簿」か「e‑Tax申告」が求められていました。
2027年からは従来の条件に加えて、「特定電子計算機処理システム」対応が要件となります。これは、国税庁長官が指定した仕様に適合したシステムで取引データを送受信・保存できる環境を指します。
この改正により、既存の会計ソフトやシステムが要件を満たしているか、早めの確認・見直しが必要になりました。
電子帳簿保存法で検索要件を満たす3つの方法
電子帳簿保存法で検索要件を満たすためには、ファイル・フォルダの作成ルールを決めたり、索引簿を作成したりするなどの方法があります。
自社の規模や業務フローにあった方法を選ぶことで、経理担当者の作業負担を抑えながら電子帳簿保存法に対応できる環境が整います。
それぞれの方法について理解を深め、自社にあったやり方を見つけましょう。
ここでは、電子帳簿保存法で検索要件を満たす3つの方法を解説します。
- ファイル・フォルダの作成ルールを決める
- 索引簿を作成する
- 会計システム・クラウドサービスなどでデータを管理する
①ファイル・フォルダの作成ルールを決める
保存するデータに検索性を持たせるためには、ファイルやフォルダの作成時に、ルールを定めることがおすすめです。
たとえば、「20250601_株式会社〇〇_100000円.pdf」といった形式に統一することで、「取引年月日」「取引先名」「金額」などの検索条件を満たせます。
保存時は取引種別や年度ごとにフォルダを分類できれば、税務調査時にも必要書類を迅速に提示できます。
②索引簿を作成する
ファイル名の統一が難しい場合は、ExcelやGoogleスプレッドシートなどを使用して索引簿を作る方法もあります。
保存したデータのファイル名には通し番号を設定し、索引簿に「取引年月日」「取引先名」「金額」などの情報をまとめることで、該当ファイルへアクセスしやすくなります。
索引簿であれば、普段業務に使用するシステムを利用できるため、新たにコストが発生する心配もありません。
③会計システム・クラウドサービスなどでデータを管理する
電子帳簿保存法に対応した会計ソフトやクラウドサービスを活用することで、システム内で要件を満たせるため、自社で検索性について対応を進める必要は少なくなります。
このようなシステム・サービスは帳票の分類やバックアップ体制が整備されており、今後も法改正があっても対応してくれる点が大きなメリットです。
電子帳簿保存法に対応したシステムで書類を発行するなら、OneVoice明細がおすすめです。OneVoice明細は取引先が希望する方法で書類を発行できるため、自社でおこなう業務内容に変更が生じません。
導入後もサポート体制が手厚く、使用してから疑問点が発生した場合は相談が可能です。無料のトライアル期間も設けられているため、まずは使用してみて、自社にあうか判断しましょう。
まとめ|電子帳簿保存法の検索要件の緩和への理解を深め、自社にあった対応方法を見つけよう
本記事では、電子帳簿保存法で検索要件が緩和されたのか、不要になるケースやほかの変更点も交えて解説しました。
検索要件の緩和は、電子帳簿保存法へ対応するハードルが下がるという大きなメリットがあります。事業者によっては免除を受けられるケースもあり、自社が対象にあてはまるのか判断は欠かせません。
電子帳簿保存法は法改正によりルールが煩雑なため、常に最新の法令を理解しておくことが、罰則のリスクを減らすポイントです。
電子帳簿保存法の検索要件の緩和について疑問点が発生した際は本記事を参考に、自社の取るべき対応を確認しましょう。










