電子帳簿保存法を導入しない場合の罰則は?5つのデメリットと対応策
更新日:2025.09.05
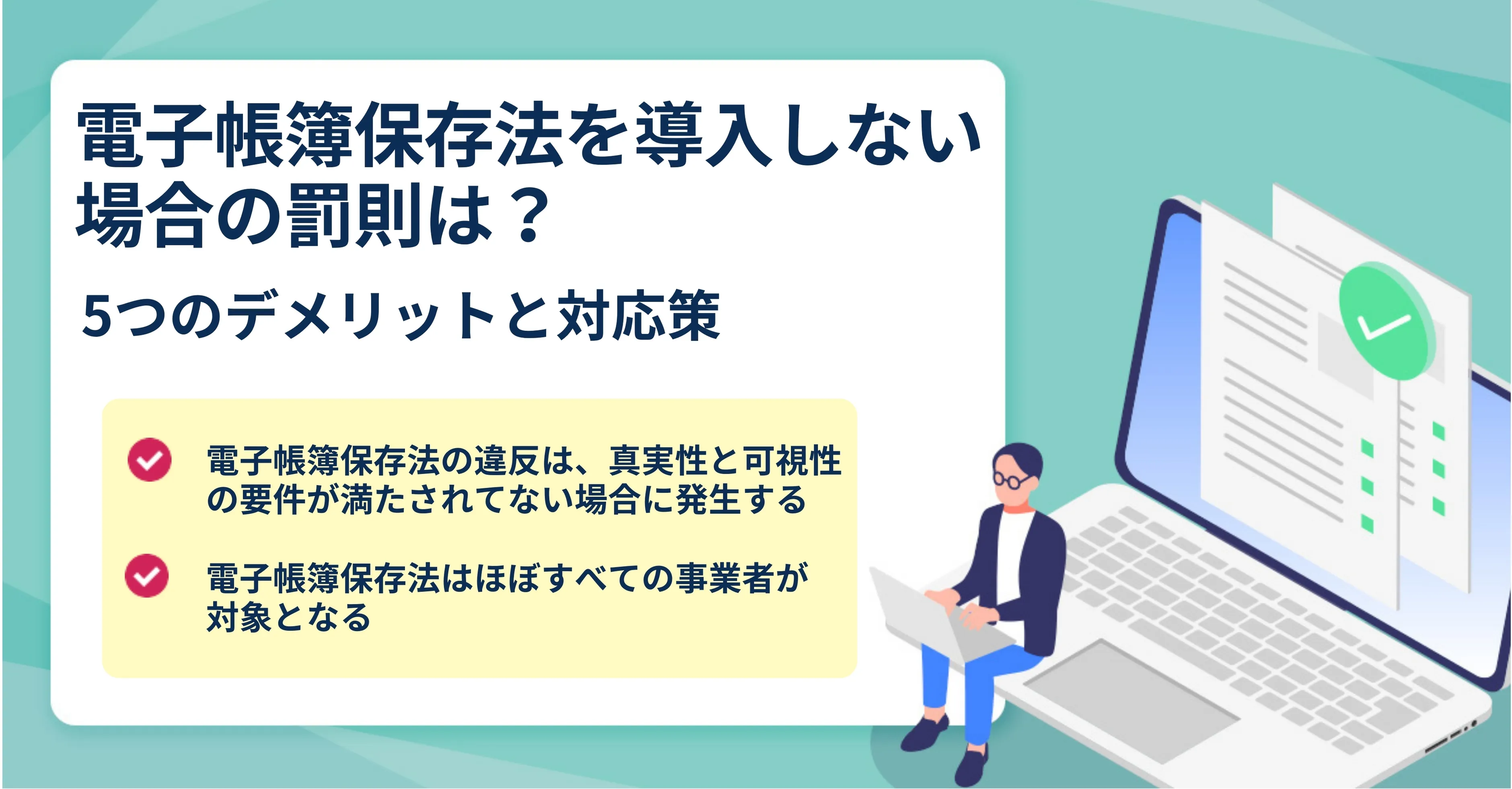
ー 目次 ー
電子帳簿保存法とは、国税関係の帳簿・書類を電子データとして保存することを認める法律です。法改正により、2024年1月から電子取引における電子データの保存が義務化されました。
そのため、電子帳簿保存法を導入しない場合、税務調査で罰則や指摘を受けるリスクがあります。また、紙のまま保存すると多くのデメリットも生じます。
本記事では、電子帳簿保存法を導入しない場合の罰則、5つのデメリット、さらに違反を防ぐための対策を解説します。
電子帳簿保存法を導入しない場合の罰則
電子帳簿保存法を導入しない場合の科せられる罰則について、具体的に解説します。
青色申告が取り消される
電子帳簿保存法を導入せずに違反があった場合は、青色申告の承認が取り消される可能性があります。例えば、電子取引の情報を紙で保存していたケースが該当します。
青色申告が取り消されると、55万円(一定の要件を満たす場合は65万円)または10万円の特別控除が受けられません。さらに、欠損金の繰越ができなくなる可能性もあります。
青色申告の取り消しは、会社の信用を失うリスクにもつながるため、細心の注意が必要です。
参照:国税庁「No.5762 青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除」
推計課税が課せられる
電子帳簿保存法を導入せずに帳簿や書類に違反があった場合は、推計課税が課せられる可能性があります。推計課税とは、正確な納税額が把握できない場合に、収入や経費をもとに税額を推計して算出する方法です。
青色申告者は推計課税の対象ではありませんが、青色申告の承認が取り消され白色申告者となると推計課税が適用されることがあります。推計課税は、本来の課税額よりも高額になるケースもあるため注意しましょう。
重加算税10%が課せられる
電子帳簿保存法の改正により、スキャナ保存された電磁的記録に不正があった場合の重加算税の加重措置が整備されています。
通常、税務調査等で仮装や隠ぺいによる不正が見つかった場合は、追徴課税の35%の重加算税が課されます。法改正後は、この税額にさらに10%上乗せして加算される厳しい措置が取られています。そのため、スキャナ保存においても適切な対応が必要です。
参照:国税庁「法人税の重加算税の取扱いについて(事務運営指針)」
会社法違反により100万円以下の罰金が科せられる
電子帳簿保存法を導入しない場合は、会社法違反に問われる可能性があります。会社法第976条では、帳簿や書類の適切な保存が義務付けられており、不正や改ざんなどの違反が発覚すると100万円以下の罰金が科せられます。
会社法違反は、企業の社会的な信用を損なうリスクもあるため、帳簿や書類の保存方法には慎重な対応が求められます。
電子帳簿保存法の違反の要件
電子帳簿保存法の違反は、主に真実性と可視性の要件を満たしていない場合に発生します。真実性の確保は、次のいずれかを満たせば電子データの信頼性を証明できます。
- タイムスタンプが付与されたデータを受け取る
- 受領した電子データは速やかにタイムスタンプを付与する
- データの修正や削除の記録が残るシステム、または削除訂正ができないシステムを使用する
- 記録の訂正・削除防止に事務処理規程を定めて運用する
タイムスタンプの付与や、電子データの原本をそのままの状態で保存できるシステムの整備が必要です。システムの導入が難しい場合は、事務処理規程を定めることで要件を満たせます。
可視性の確保は、保存された電子データをいつでも迅速に検索できるように、以下の条件をすべて満たさなければなりません。
- 電子システムの操作説明書や仕様書などの概要書類を備え付ける
- 電子データを閲覧できるディスプレイやプリンタなどの出力装置を備える
- 電子システムには保存データの検索が行える機能を備え付ける
これらの要件を遵守しない場合は、電子帳簿保存法違反となり、罰則が科せられる可能性があります。
電子帳簿保存法の対象者
電子帳簿保存法は、ほぼすべての事業者が対象です。会社の規模に関わらず、法人や個人事業主など、事業を営むすべての事業者に適用されます。
副業の場合でも、収入金額によっては電子帳簿保存法の対象となるため注意が必要です。前々年の副業収入が300万円を超えた場合、請求書や領収書などの現金預金取引等関係書類は、電子データでの保存が義務付けられています。
電子帳簿保存法の対象書類
電子帳簿保存法の対象書類は、以下の書類に分類されます。
- 国税関係帳簿
- 国税関係書類
- 電子取引で受領した書類
国税関係帳簿と国税関係書類は、国税に係る法律で保存が義務付けられた書類です。主に以下のような書類が該当します。
|
国税関係帳簿 |
国税関係書類 |
|
|
請求書や領収書は、受領した書類と自社が発行した書類の控え、両方が対象です。
電子取引で受領した書類は、以下のような取引が対象となります。
- EDI(電子データ交換)取引
- 電子メールによる取引
- インターネットのホームページからダウンロードしたデータ取引
- クラウドサービスによる取引
- ぺーパーレスFAXを利用した取引
- DVD等の記録媒体を介した取引
これらの書類は、すべて電子帳簿保存法の対象書類となります。
電子帳簿保存法の対象とならない書類
以下の書類は、電子帳簿保存法の対象とならない書類に該当します。
- 手書きで作成した国税関係帳簿や国税関係書類
- 紙で受領した国税関係書類
- パソコンで作成した書類に手書きで情報を追加した場合
上記はいずれも、電子データとして保存する義務はありませんが、紙の原本を保存する必要があります。また、紙で受け取った領収書や請求書などの国税関係書類は、一定の要件を満たせばスキャナ保存が認められます。スキャナ保存をした帳簿や書類は、電子帳簿保存法の対象となるため注意しましょう。
【2024年最新】電子帳簿保存法の猶予措置と導入しない場合の注意点
令和5年度の税制改正により、2024年1月1日から電子帳簿保存法に新たな猶予措置が設置されています。以下の要件を両方満たす場合、電子取引による電子データを紙に出力して保存することが可能です。
- 保存時に満たすべき要件に従って電子取引データを保存できなかったことについて、相当の理由があると所轄税務署⻑が認める場合
- 税務調査等の際に、電子取引データの「ダウンロードの求め」及びその電子取引データをプリントアウトした書面の提示・提出の求めにそれぞれ応じることができる場合
ただし、注意すべき点は、紙での保存が認められるものの、電子データは引き続き保存しておく必要があることです。税務調査の際に提示の求めに応じるためには、取引情報の電子データをいつでも提示できる状態で保存しておかなければなりません。
そのため、元となる電子データは削除せず、適切に保管しましょう。
参照:国税庁「電子帳簿保存法の内容が改正されました」〜令和5年度税制改正による電子帳簿等保存制度の見直しの概要〜
電子帳簿保存法を導入しない場合の5つのデメリット
電子帳簿保存法では猶予措置が設けられているものの、導入しない場合にはいくつかのデメリットが生じます。ここでは、電子帳簿保存法を導入しない場合の5つのデメリットを解説します。
1.経理業務が非効率になる
電子帳簿保存法を導入しない場合、経理業務が非効率になる点がデメリットです。例えば、紙の請求書を発行・受領する際は、封入作業や切手、保存用のファイリングの準備などの手間がかかります。
書類が大量にある場合は、特定の書類を探し出すのに時間がかかり、作業効率が低下します。また、手作業での書類管理は計算ミスなど人的ミスのリスクもあり、取引先とのトラブルに発展するケースも少なくありません。
そのため、電子帳簿保存法に対応すれば、これらの手間やリスクを大幅に削減できるでしょう。
2.書類の劣化や紛失のリスクが高まる
電子帳簿保存法を導入しないと、書類の劣化や紛失などのデメリットが生じます。紙での保管は、紫外線や湿気などの影響を受けやすく、適切な状態での保存が難しくなります。
また、書類の閲覧後に戻し間違いが生じると、紛失のリスクも高まるでしょう。
さらに、災害時や盗難に備えてセキュリティー対策を万全に整えることも大切です。クラウドなどで書類を一元管理しておけば、万が一の災害時などでも紛失の心配がありません。
3.紙の保管スペースが必要になる
紙での保管は、物理的なスペースが必要になることもデメリットのひとつです。特に、取引先の多い企業では、書類を保管するためのスペース確保が必要となります。
電子帳簿保存法を導入すると、紙の書類をデータ化して保存できるため、物理的な保管スペースが不要になります。空いたスペースは、他の業務に有効活用できるでしょう。
さらに、印刷代やファイル代、キャビネット費用などの維持費が削減でき、企業全体のコスト削減にもつながります。
4.取引先からの評価に影響を与える
電子帳簿保存法を導入していない企業は、取引先からの評価に影響を与える可能性があります。
実際、電子契約を求められるケースも増えています。そのため、取引先が発行した電子書類を受領できない場合、取引先からの信頼を損ねる恐れもあるでしょう。
取引先との良好なビジネス関係を維持するためにも、電子化への対応が求められます。
5.コストがかさむ
電子帳簿保存法を導入しない場合、コストがかさむこともデメリットのひとつです。紙での書類管理では、紙やインク、封筒、切手、ファイル代、さらには物理的な保管スペースの確保など、さまざまなコストが発生します。
一方、電子化に向けてシステムを導入する際は、初期費用や運用コストがかかります。しかし、業務効率化による人件費削減や保管スペースが空くなど、長期的にみるとコストカットにつながるケースが多いです。
また、ペーパーレス化による環境負荷の低減など、企業価値向上にもつながります。
電子帳簿保存法を効率的に導入する方法
電子帳簿保存法を導入するには、いくつかのポイントがあります。ここでは効率的に導入する方法を詳しく解説します。
導入目的を明確にする
導入目的を明確にすると、システムの選定や電子帳簿保存法の導入がスムーズに進みます。
そのため、現在の経理業務での課題を把握することが大切です。例えば、「紙の保存で書類を探す手間がかかる」「書類作成に時間がかかる」など、経理業務の負担を洗い出し、業務の効率化を目的として電子帳簿保存法を導入しましょう。
対象書類を理解し保存方法を決める
電子帳簿保存法を導入する際は、自社で取り扱う対象書類を理解し、保存方法を事前に決めておくと効率的に対応できます。電子帳簿保存法には、書類の種類に応じて以下の3つの保存方法が求められます。
- 電子帳簿等保存
- スキャナ保存
- 電子取引における電子データ保存
電子帳簿等保存やスキャナ保存の導入は任意ですが、電子取引データの保存は義務化されています。社内での混乱を防ぐためにも、事前に明確な保存方法を決めて導入しましょう。
業務フローを見直す
業務フローを見直し、電子化に対応した体制を整えることで電子帳簿保存法の導入がスムーズになります。現状の業務プロセスを整理して分析し、電子化に伴う業務フローの改善に取り組みます。
また、社員一人ひとりの業務内容や役割を明確にすると、導入後も組織全体がスムーズに電子化に対応できるでしょう。
取り扱いの多い書類から取り掛かる
電子帳簿保存法を導入する際、すべての書類を一度に電子化するのではなく、取り扱いの多い書類から取り掛かると効率的です。
優先度が高い文書から電子化を進めておくと、電子化に伴う改善点や課題が把握しやすく、全体的な電子化への移行もスムーズになります。
請求書や領収書など、取り扱う頻度の多い帳簿や書類から電子化に対応しましょう。
対応システムを導入する
電子帳簿保存法に対応したシステムやクラウドサービスを導入することで、業務効率化が実現できます。それぞれの規定に準じたシステムを活用すれば、罰則のリスクも軽減できるでしょう。
デジタル化の推進に伴い、電子帳簿保存法は改正が頻繁に行われているため、電子化への対応が煩雑になるケースもあります。しかし、クラウドシステムを導入すれば改正内容に沿ったアップデートが実施されるため、スムーズに対応でき、罰則対象となるリスクも減らせるでしょう。
電子帳簿保存法に関するよくある質問
電子帳簿保存法に関する、よくある質問と回答をまとめました。
個人事業主や小規模企業も導入した方がよい?
電子取引が発生している場合は、個人事業主や小規模企業など企業規模に関係なく電子データの保存が義務付けられています。現在、紙の書類のみを扱っている場合は、電子帳簿保存法の導入は必須ではありません。
ただ、日々デジタル化が進んでいることから、近い将来、電子取引が標準的な取引手段となる可能性は高いといえるでしょう。スムーズな移行のためにも、早めの準備が大切です。
文書の保存期間は?
電子帳簿保存法における文書の主な保存期間は、以下のように定められています。
|
事業者区分 |
保存期間 |
補足 |
|
法人 |
7年 |
欠損金の繰越控除を受ける場合は最長10年 |
|
個人事業主(青色申告) |
7年 |
帳簿や決算関係書類、現金預金等取引関係書類は7年、その他の書類(請求書、見積書、契約書、納品書、送り状など)は5年 |
|
個人事業主(白色申告) |
5年 |
ー |
事業者の区分や帳簿、書類によって保存期間は異なります。必要な保存要件を満たし、適切に保管しましょう。
電子帳簿保存法による罰則のリスクを回避して業務効率化を進めよう
電子帳簿保存法への対応は、業務効率化やコスト削減にもつながり、取引先からの信頼性も高まります。しかし、導入しない場合は青色申告の取り消しや、会社法違反による罰則だけではなく、さまざまなデメリットも生じます。
電子取引の普及が進むなかで、デジタル化への対応はさらに重要視されています。電子帳簿保存法を速やかに導入し、業務効率化を進めましょう。









