EDI取引と電子帳簿保存法の関係は?保存要件や対応方法を解説
更新日:2025.04.30
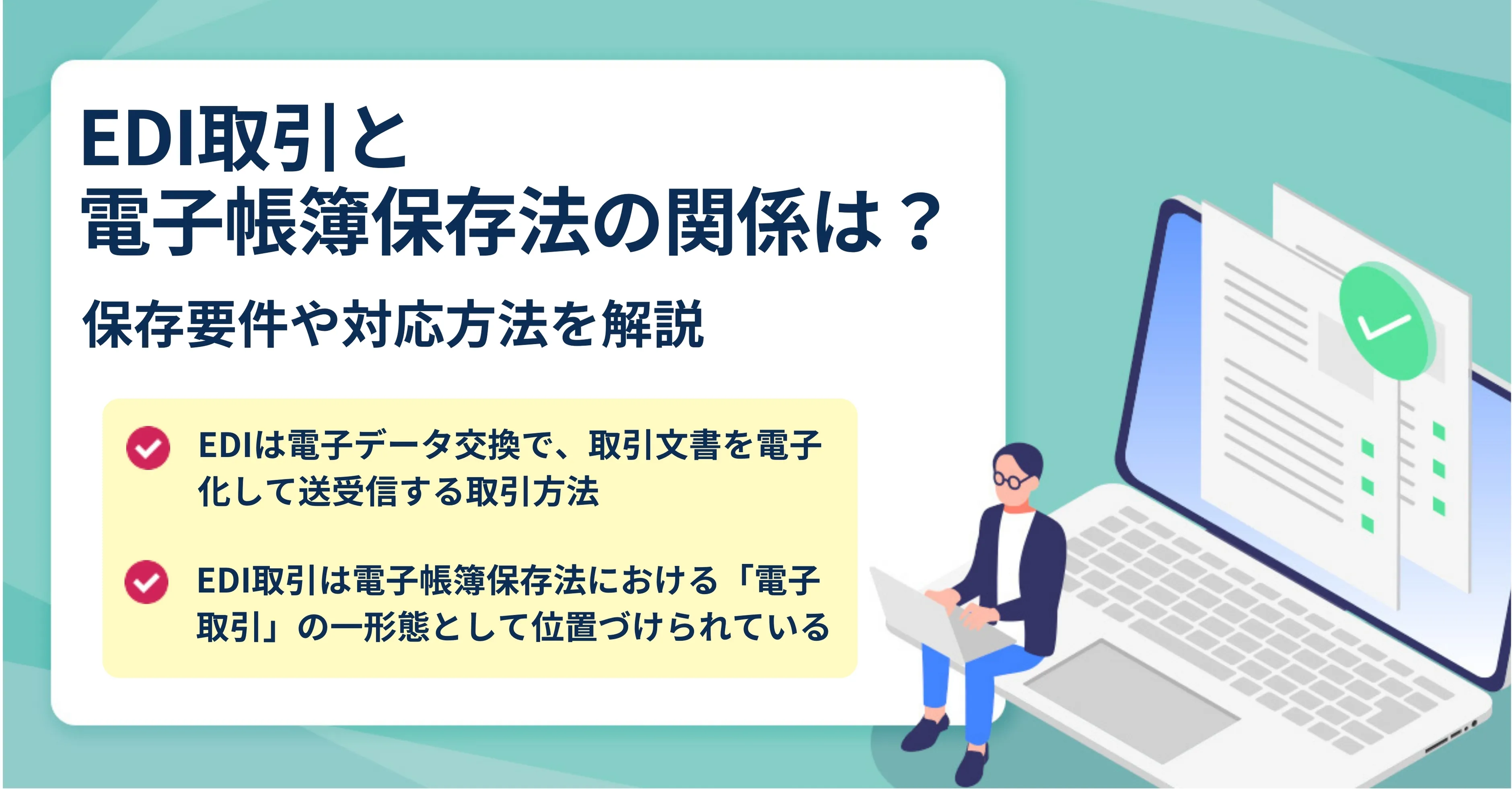
ー 目次 ー
EDI取引の普及によって業務効率化が進む一方で、電子帳簿保存法への対応に悩む担当者が増えています。とくに「どのデータを保存すべきか」「どのような方法で保存すればよいか」の点でコンプライアンス違反のリスクが懸念されています。
電子帳簿保存法の改正により、2022年1月からEDI取引を含む電子取引データの電子保存が義務化されました(2023年12月末までは猶予期間あり)。この法改正に対応できていない場合、青色申告の承認取り消しなどの重大なリスクが生じるおそれがあります。
本記事では、EDI取引と電子帳簿保存法の関係について、保存すべきデータや具体的な対応方法もあわせて解説します。
EDIとは、取引文書を電子化して業務を効率化するシステム
EDI(Electronic Data Interchange)とは、商取引で発生する発注書や納品書、請求書などの証憑類を電子化して、取引先と専用回線やインターネットを通じてデータでやり取りする取引方法です。
EDIシステムの導入で、取引先同士の販売管理システムに直接取引データを送受信できます。これにより、紙の書類の印刷・郵送や手作業で自社システムに入力する必要がなくなり、業務効率が大幅に向上します。
EDIのおもな種類は、以下のとおりです。
- 個別EDI:通信方法やデータ形式などのルールを取引先ごとに取り決めるもの
- 標準EDI:運用ルールや取引規約が標準化されたもの
- 業界VAN(標準EDI):特定の業界に特化・標準化されたEDI
- Web-EDI:インターネットを介して利用できるEDI
EDIの導入で人的ミスの削減やデータ入力作業の効率化、ペーパーレス化によるコスト削減など多くのメリットが得られます。一方で、EDI取引をおこなう際には、電子帳簿保存法の規定を理解した適切なデータ保存が求められます。
電子帳簿保存法は、電子データでの国税関係書類の保存ルールを定めたもの
電子帳簿保存法は、帳簿・書類の電子データでの保存ルールを定めた法律です。この法律のおもな目的は、企業のIT化・デジタル化の促進と、適正な課税の両立を図ることです。
なお、電子帳簿保存法の対象となる書類は以下のものがあります。
- 国税関係帳簿(仕訳帳、総勘定元帳など)
- 国税関係書類(決算関係書類、取引関係書類など)
- 電子取引データ(EDIデータ、電子メールで受領した請求書など)
上記のうち電子取引データは、2024年1月の法改正で電子保存が義務化され、紙での保存が不可となりました。また、事前承認制度が廃止され、タイムスタンプ要件や検索要件の緩和など、要件が大幅に緩和されています。
【結論】EDI取引は電子帳簿保存法の「電子取引」に該当する!
電子帳簿保存法では「取引情報の授受を電磁的方法によりおこなう取引」という電子取引に関する定義が決められており、EDI取引はまさにこの定義に該当します。
具体的には、商取引に関する証憑類(発注書・納品書・請求書など)を紙ではなく、EDIシステムを通じて電子データとして送受信するEDI取引は、法的に重要な「電子取引データ」の扱いです。そのため、EDI取引をおこなう企業は、電子帳簿保存法にしたがったデータの適切な保存が必要です。
ここでは、EDI取引と電子帳簿保存法の関係について、以下のポイントを具体的に解説します。
- EDIデータは電子保存が義務化されている
- 保存対象のEDIデータが決められている
- データと一緒に保存すべき情報がある
①EDIデータは電子保存が義務化されている
2022年1月の電子帳簿保存法改正により、EDIデータを含む電子取引データは、電子データのままの保存が義務づけられました。これまでは電子データを紙に出力して保存も認められていましたが、法改正後は原則として電子保存が必要です。
また、以前は電子保存をおこなうためには税務署長の事前承認が必要でしたが、電子帳簿保存法改正により事前承認制度が廃止されて、要件を満たせば自動的に電子保存が認められるようになりました。
②保存対象のEDIデータが決められている
EDI取引で保存すべきデータは、実際に取引先との間で送受信されたEDIデータそのものです。具体的には、以下のようなデータが該当します。
- 商品やサービスの発注内容を記録した発注データ
- 納品の事実と内容を証明する納品データ
- 請求内容を示す請求データ
- 商品やサービスの受領を証明する受領データ
- 支払いに関する支払通知データ
重要な点として、実際に取引先とやり取りしたデータ形式で保存する必要があります。
③データと一緒に保存すべき情報がある
EDIデータを保存する際には、取引内容を特定するための情報も一緒に保存する必要があります。具体的には、以下のような情報が必要です。
- 取引年月日
- 取引金額
- 取引先情報
- 商品・サービス情報
- 取引条件等
これらの情報は、保存したデータを後から検索するための検索キーとしても重要です。電子帳簿保存法では、取引年月日・取引金額・取引先の3つの項目で検索できることが要件とされているため、これらの情報は保存する必要があります。
EDIデータの保存に必要な2つの要件
EDIデータを保存する際には、取引の信頼性と透明性を確保するために、電子帳簿保存法で定められた保存要件を満たさなければなりません。具体的には、「真実性の確保」と「可視性の確保」の2つの要件が定められています。
もし、これらの要件を満たしていないと、電子帳簿保存法違反や青色申告の承認取り消しなどを受けるリスクがあります。
一方で、適切に要件を満たせば、企業はコンプライアンスを保ちながら、電子取引のメリットを最大限に活用できるでしょう。
ここでは、EDIデータを保存する際に必要な2つの要件について解説します。
- 真実性の確保
- 可視性の確保
①真実性の確保
「真実性の確保」とは、保存されているEDIデータが改ざんされていないことを証明するための要件です。この要件には、以下のいずれかの方法で対応する必要があります。
- タイムスタンプが付与されたデータを受領する
- 授受後、速やかにタイムスタンプを付与する
- データの訂正・削除をおこなった場合にその記録が残るシステム、または訂正・削除ができないシステムを利用する
- 正当な理由がない訂正・削除の防止に関する事務処理規程を策定・運用・備付けする
これらの方法は、税務調査の際にEDIデータの信頼性を証明するために重要です。
②可視性の確保
「可視性の確保」とはEDIデータを税務調査で求められた際に閲覧・検索できるようにするための要件です。具体的には以下の対応が求められます。
- 電子計算機処理システムの概要を備え付けること
- 保存データの閲覧方法や検索等の方法が記載されている操作マニュアルを備付けすること
- 検索機能を確保すること
ただし、税務職員による質問検査権にもとづくデータのダウンロードの対応が可能な場合には、範囲指定と組み合わせ検索の要件は不要です。
電子帳簿保存法に対応したEDIシステムを選ぶ際の3つ
EDI取引をおこなううえで、単なる取引の電子化ツールではなく、法令遵守と業務効率化を同時に実現する戦略的な投資が求められます。電子帳簿保存法に対応したEDIシステムを選べば、法令遵守の自動化や業務効率の向上などのメリットを得ることが可能です。
ここでは、電子帳簿保存法に対応したEDIシステムを選ぶ際の3つのポイントについて解説します。
- 電子帳簿保存法に対応したシステム機能を確認する
- 既存システムとの連携性を重視する
- 標準EDIへの対応状況を確認する
①電子帳簿保存法に対応したシステム機能を確認する
EDIシステムを選ぶ際は、電子帳簿保存法の要件を満たすための機能が備わっているかの確認が重要です。具体的には、以下のような機能を確認する必要があります。
- データの訂正・削除履歴を記録する機能
- タイムスタンプ付与機能
- 法定の検索要件を満たす検索機能
- データの長期保存(7年間以上)
- 暗号化データの適切な処理機能
②既存システムとの連携性を重視する
新たに導入するEDIシステムは、現在使用している販売管理・会計システムとスムーズに連携できるかの確認が重要です。アプリケーションやサービス間での連携が可能で、標準EDIに対応したシステムを選ぶことで、データの二重入力を防ぎ、業務効率を大幅に向上できます。
とくに、Web-EDIへの移行を検討する場合は、販売管理システムとの連携方法や通信プロトコルの対応状況を事前に確認しておくことが必須です。
③標準EDIへの対応状況を確認する
取引先ごとに異なるルールに対応するのは非効率なことから、できるだけ「中小企業共通EDI」や「流通BMS」などの標準EDIに対応したシステムを選ぶことが重要です。
標準EDIに対応したシステムを選ぶことで、複数の取引先と効率的にEDI取引をおこなえます。
まとめ|EDI取引と電子帳簿保存法の適切な対応で業務効率化を図ろう
本記事では、EDI取引と電子帳簿保存法の関係について、保存すべきデータや具体的な対応方法も含めて解説しました。
EDI取引は電子帳簿保存法上の「電子取引」の一形態として位置づけられており、取引で送受信されるEDIデータは適切な方法で電子保存する必要があります。保存する際には「真実性の確保」と「可視性の確保」の2つの要件を満たさなければなりません。
これらの要件を満たさないと、税務調査での信頼性や正確性が疑われ、青色申告の承認が取り消されるなどのリスクがあります。一方で、適切に対応することで、コンプライアンスを保ちながら電子取引のメリットを最大限に活用できます。
適切なシステムと運用ルールの整備で、業務効率化とコンプライアンスの両立を目指しましょう。










