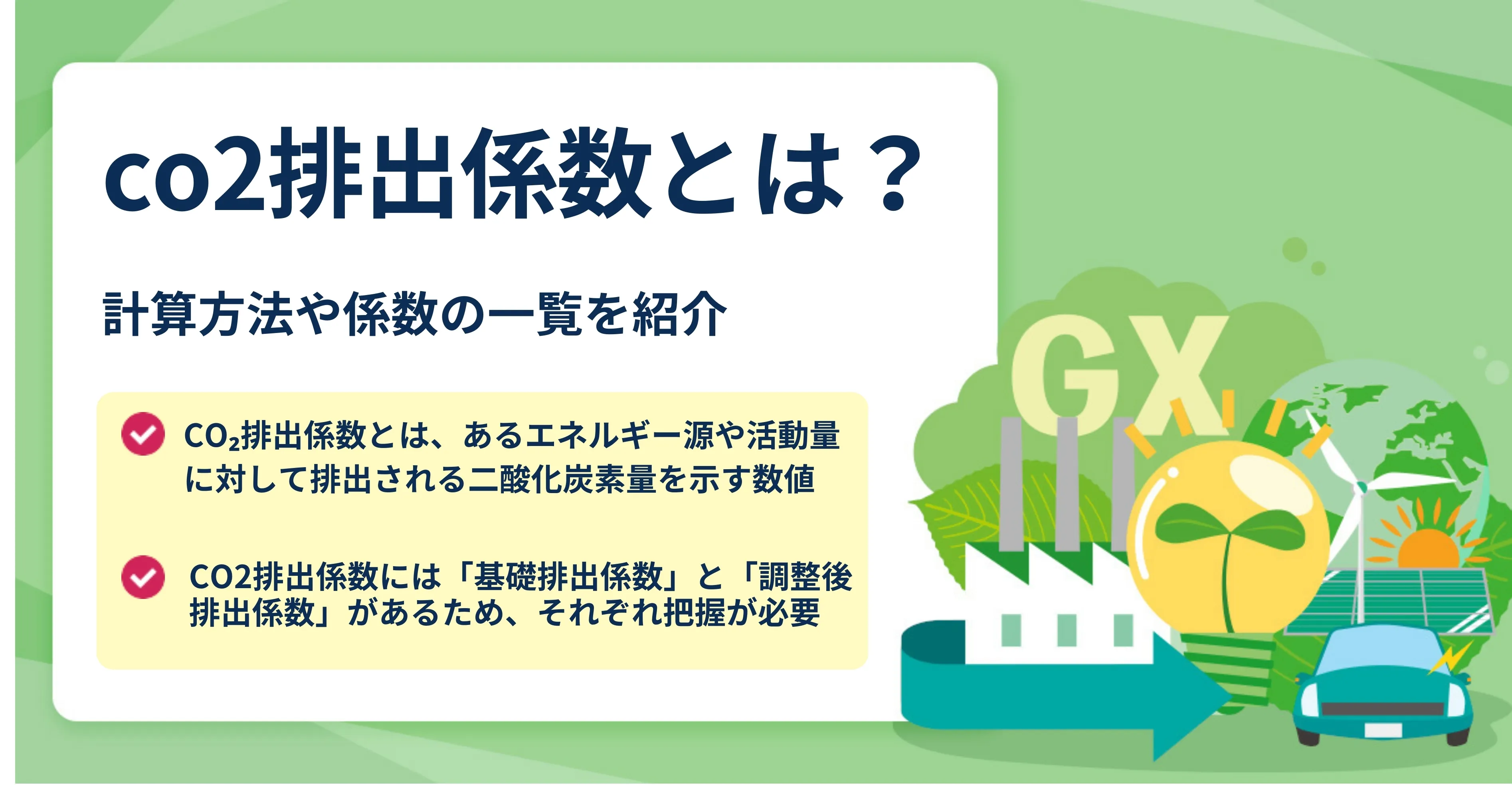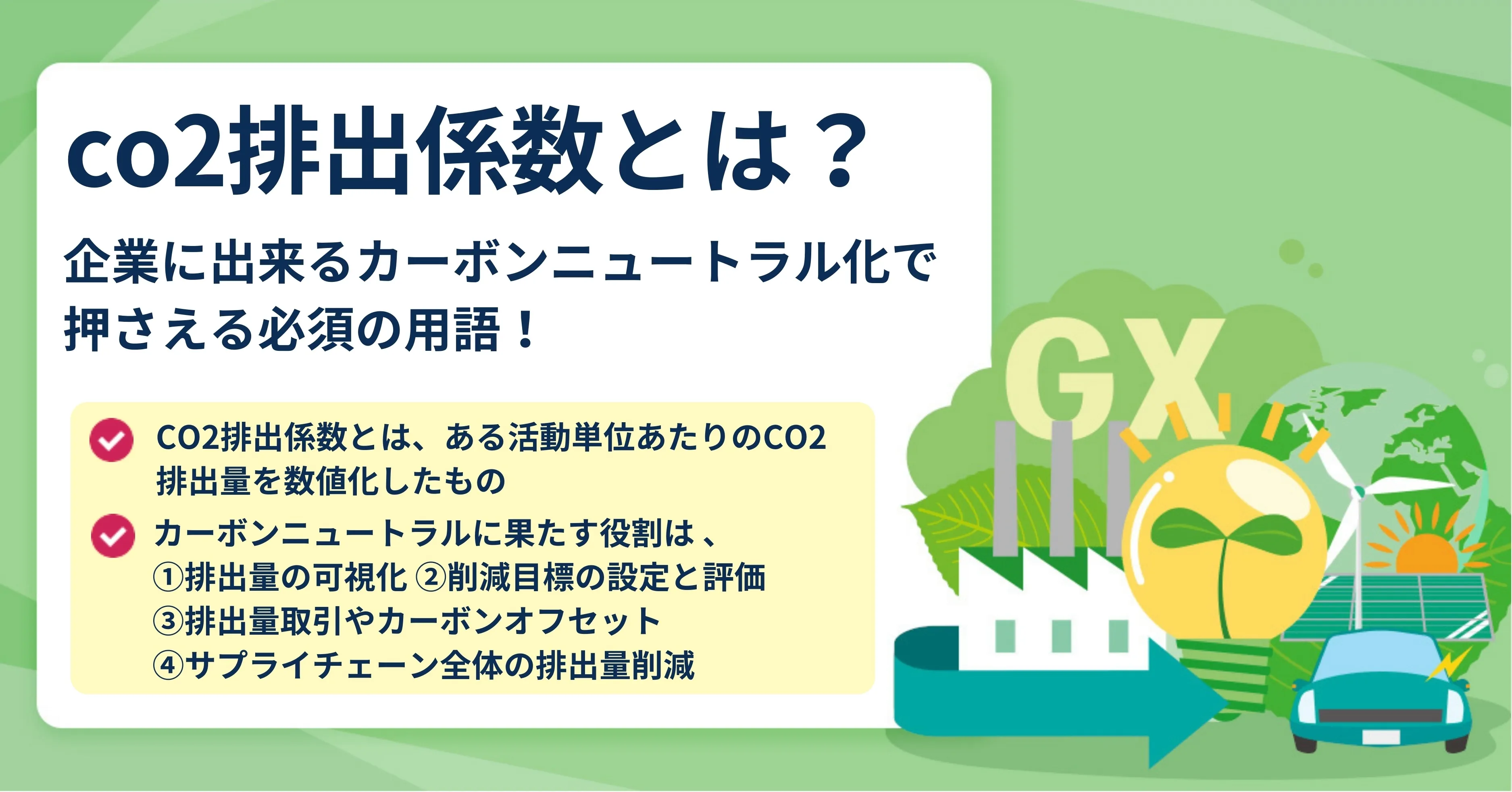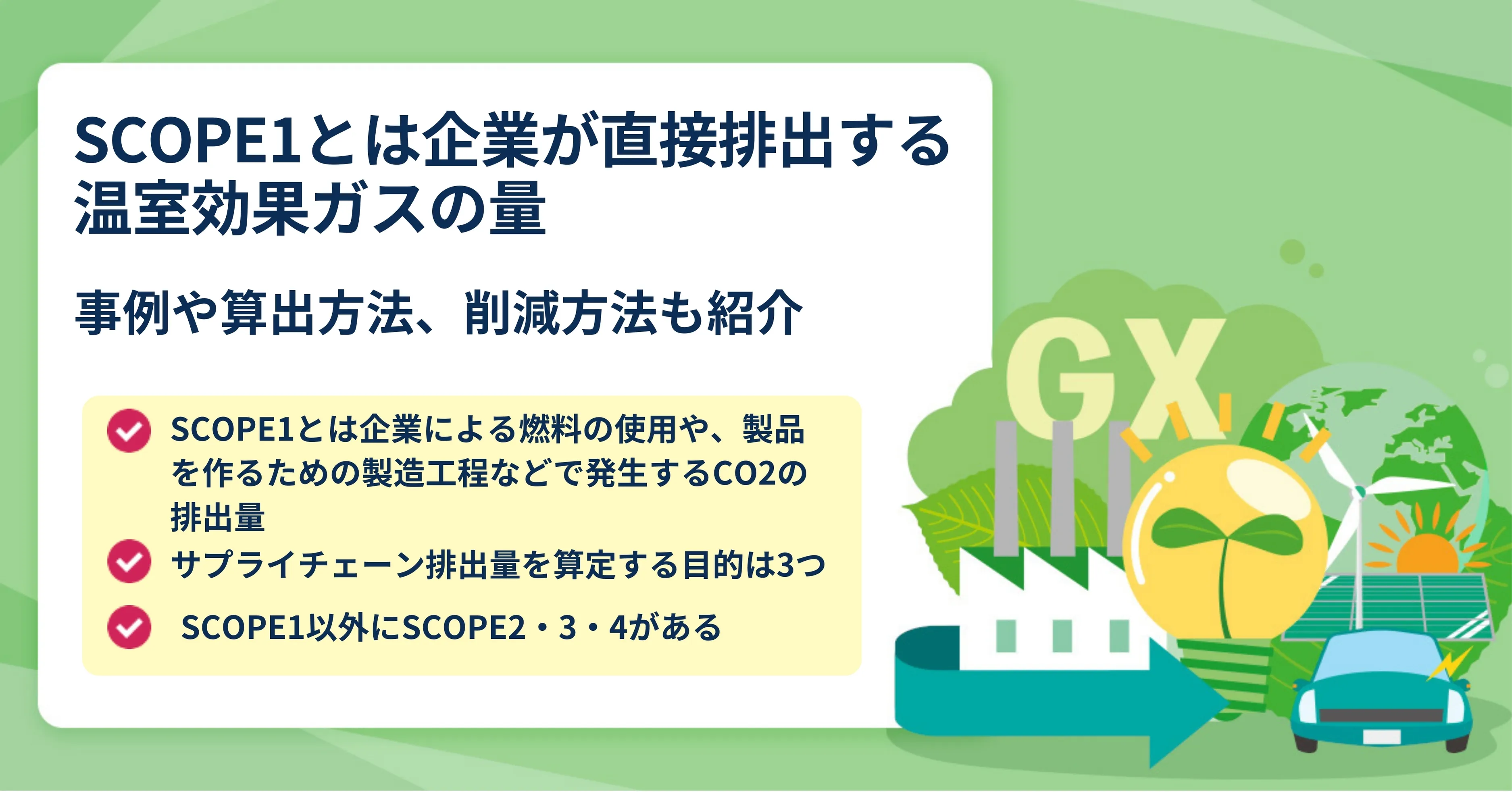LCA(ライフサイクルアセスメント)とは?計算方法や分析の事例についてわかりやすく解説。
更新日:2025.09.04
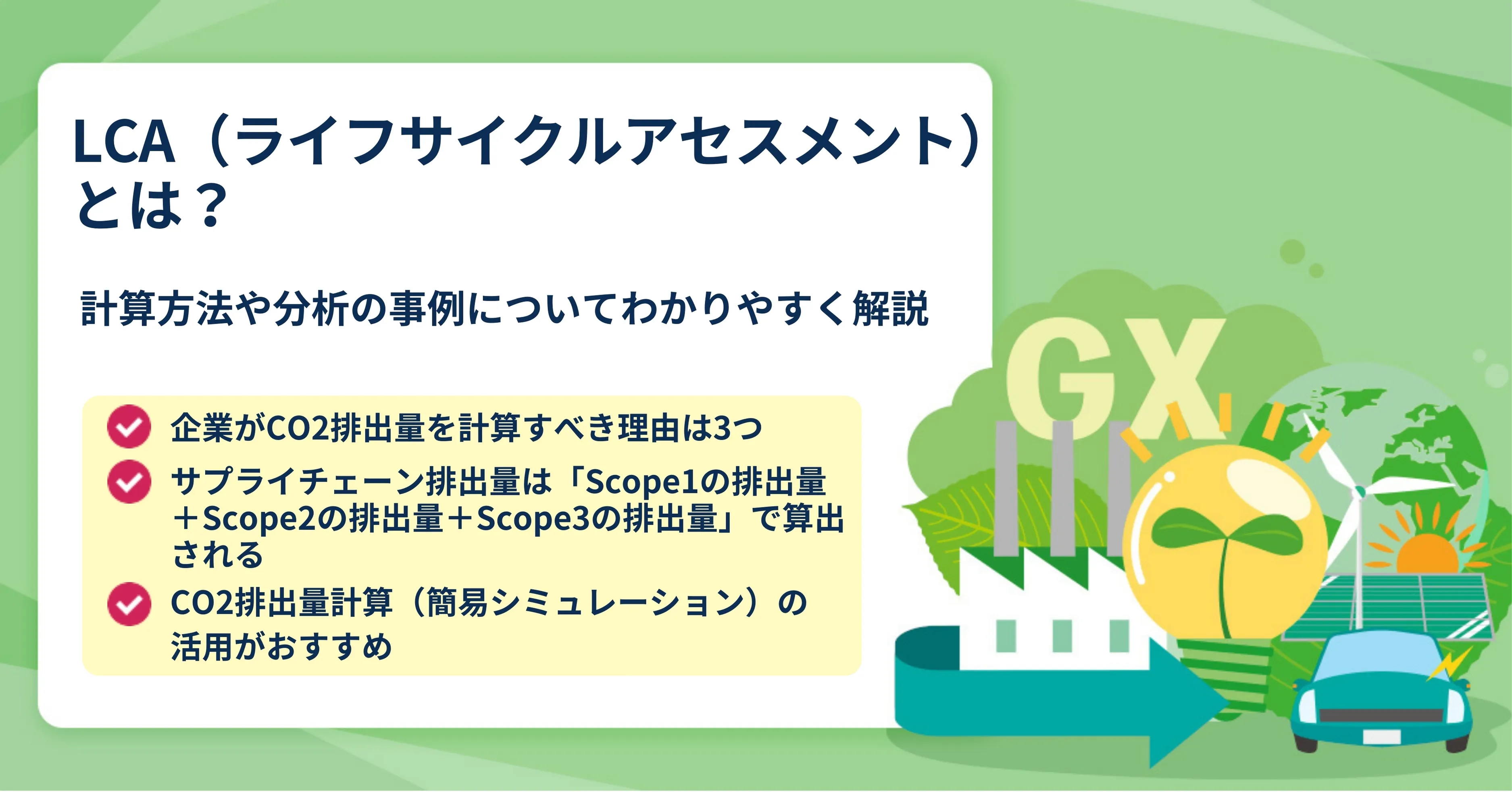
ー 目次 ー
LCAとは、原材料調達から製造、流通、使用、廃棄・リサイクルに至るまでの製品ライフサイクル全体における環境負荷を定量的に評価する手法です。
LCAを実施することで、製品やサービスの環境負荷を包括的に把握し、改善ポイントを特定することができます。これにより、環境負荷の低減に向けた効果的な対策を講じることが可能になります。
本記事では、LCAの概要、企業がLCAを実施するべき理由、算定方法、分析の事例などをわかりやすく解説します。LCAの導入を検討している企業担当者様や、環境問題に関心のある方々にとって、有益な情報となるでしょう。
- LCAとは何か、その定義と目的
- 企業がLCAを実施するべき理由
- LCAとScopeの違い
- LCAの実施方法
- CO2排出量の計算方法
LCA(ライフサイクルアセスメント)とは
LCA(ライフサイクルアセスメント)とは、製品やサービスのライフサイクル全体における環境負荷を定量的に評価する手法です。
製品やサービスのライフサイクルとは、原材料の調達から製造、流通、使用、廃棄・リサイクルに至るまでの全過程を指します。LCAでは、このライフサイクル全体を考慮することで、環境への影響を包括的に把握することができます。
| 項目 | 説明 |
| 資源の消費量 |
原材料の採掘や製造に必要なエネルギー、水などの資源の消費量を評価します。
|
| 環境への排出量 |
大気汚染物質、水質汚染物質、温室効果ガスなどの排出量を評価します。
|
| 環境への影響 |
資源の消費や環境への排出が、地球温暖化、酸性雨、水質汚濁などの環境問題に与える影響を評価します。
|
企業がCO2排出量を計算すべき3つの理由
なぜ企業がCO2排出量の計算に取り組む必要があるのか、理由は以下の3つです。
- 排出量やエネルギーの使用状況などを国に報告する必要があるから
- 企業の信頼問題に繋がるから
- 自社が行うべきCO2削減対象がわかるから
それぞれ詳しく解説していきます。
排出量やエネルギーの使用状況などを国に報告する必要があるから
日本には「地球温暖化対策の推進に関する法律(温対法)」と「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(省エネ法)」という法律があり、排出量やエネルギーの使用状況などを国に報告しなければいけません。
「温対法」により、多量の温室効果ガスを排出する企業は、排出量を算定して国に報告する義務があります。また「省エネ法」では、一定基準を超えるエネルギーを使用する事業者を特定事業者とし、中長期計画の提出とともに、エネルギーの使用状況の報告が必要です。
企業の情報開⽰の⼀環として、排出量の情報は事業や業種・都道府県別などに集計され、サイトや報告書で公表されます。
企業の信頼問題に繋がるから
顧客や投資家は、環境保全活動を企業の評価基準にしていることがあります。サイトや報告書などに自社が排出したCO2について掲載することで、環境対応企業としての立場を明確にできます。
例えばトヨタ自動車は、2035年までに世界の自社工場でCO2の排出を実質ゼロにする目標を発表しました。他にも三菱重工グループやSMBCグループといったさまざまな企業が、温室効果ガス削減に向けた取り組みを行っています。
このような公表はSDGsへの活動アピールとなり、多くの顧客や投資家・株主からの信頼獲得が期待でき、企業のイメージアップにも繋がるでしょう。
自社が行うべきCO2削減対象がわかるから
製造や物流・販売など、一連の流れで発生する温室効果ガス排出量のことを「サプライチェーン排出量」と言います。サプライチェーン排出量の全体像(総排出量や排出源ごとの排出割合)は、CO2排出量を算出することでわかります。
自社が「何のエネルギーをどのくらい排出しているのか」といった、詳細な数値や情報を計算した上で把握しておくことが重要です。CO2排出量を算定すれば、自社と他社のCO2排出量が明確になり、自社が優先的に削減すべき対象を特定できます。またサプライヤーであるメーカーに対し、環境負荷低減への活動を要請することで、他社と連携してCO2削減を進められるでしょう。
LCA(ライフサイクルアセスメント)とScopeの違い
LCA(ライフサイクルアセスメント)とScope(スコープ)は、どちらも環境負荷を評価するための考え方ですが、いくつかの重要な違いがあります。
まず、評価対象が異なります。LCAは、製品やサービスのライフサイクル全体を評価対象とします。一方、Scopeは、企業や組織の事業活動全体を評価対象とします。
次に、評価範囲が異なります。LCAは、資源の消費量、環境への排出量、環境への影響など、幅広い項目を評価します。一方、Scopeは、温室効果ガスの排出量に焦点を当てて評価します。
また、算定方法も異なります。LCAでは、製品やサービスのライフサイクル全体における環境負荷を定量的に算定します。一方、Scopeでは、企業や組織の事業活動から排出される温室効果ガスを、Scope1、Scope2、Scope3の3つの範囲に分けて算定します。
- Scope1: 事業者が直接排出する温室効果ガス
- Scope2: 他社から供給された電気、熱、蒸気などの使用に伴い間接的に排出する温室効果ガス
- Scope3: Scope1、Scope2以外の間接排出(サプライチェーン全体での排出など)
| 項目 | LCA | Scope |
|---|---|---|
| 評価対象 | 製品やサービスのライフサイクル全体 | 企業や組織の事業活動全体 |
| 評価範囲 | 資源の消費量、環境への排出量、環境への影響など | 温室効果ガスの排出量 |
| 算定方法 | ライフサイクル全体における環境負荷を定量的に算定 | Scope1、Scope2、Scope3の3つの範囲に分けて算定 |
近年では、Scope3の算定にLCAの手法が活用されるケースも増えています。これは、サプライチェーン全体での環境負荷を把握し、排出量削減に向けた取り組みを効果的に進めるために有効な手段となります。
LCAとScopeの違いを理解し、それぞれの目的に合わせて適切に活用することが重要です。
CO2排出量の計算方法は「活動量×排出係数(排出原単位)」
基本的なCO2排出量の計算方法は「活動量×排出係数(排出原単位)」となります。ここでは、CO2排出量を算出する上で欠かせない「活動量」と「排出係数(排出原単位)」について解説していきます。
活動量とは
活動量とは、電気の使用量や貨物の輸送量といった「事業活動中にどれだけのCO2を排出したか」を表した数値を表します。活動量の調べ方は、前年度に使用したエネルギーの種類、電気やガスといったエネルギー使用量の集計が必要です。毎月のエネルギーの使用量は、電気料金の請求書で確認できます。請求書が発行されていない場合、ポストに投函される口座引落の通知書や電力会社のサイトでチェックすることも可能です。
どうしてもわからなければ、年間のエネルギー使用量を契約している電力会社に確認してみましょう。具体的な数値は、社内の各種データや業界平均データから調べて算出します。例えば建設業の場合、各工事で使用するエネルギー別の量などを把握するため、サンプリング調査を行います。業界によって、必要となるエネルギーの種類や数値は異なるため注意しましょう。
排出係数(排出原単位)とは
排出係数(排出原単位)は「どれだけのCO2が排出されるか」を表した数値です。燃料の種類や輸送手段などによって、排出係数は異なります。例えば電気を1kWh使用した際に排出されるCO2の量や、ガソリン1L当たりに排出されるCO2の量などが該当します。
排出係数には「基礎排出係数」と「調整後排出係数」があります。「基礎排出係数」は、電力会社から供給した電気発電の場合、排出したCO2排出量を販売した電力量で割った値です。一方「調整後排出係数」は、再生可能エネルギーの利用や排出量削減を目的として出される数値となります。「基礎排出係数」に、電力会社による修正が加えられます。
基本的には環境省が公表するデータから「基礎排出係数」や「調整後排出係数」が確認できるでしょう。また、排出係数を直接計算する方法や取引先から算定結果の提供を受ける方法もあります。
ライフサイクルアセスメント(LCA)の実施方法
LCA(ライフサイクルアセスメント)は、以下の4つの段階を経て実施されます。それぞれの段階で、具体的な手順や手法が定められています。
1. 目的及び調査範囲の設定
LCAを実施する最初の段階では、まず目的を明確に定義します。目的は、製品の環境負荷を低減するためなのか、環境政策の策定に役立てるためなのか、企業の環境活動の一環として実施するのかなど、様々です。
目的が明確になったら、次に調査範囲を設定します。調査範囲とは、LCAで評価する製品やサービスのライフサイクルの範囲のことです。原材料の調達から廃棄・リサイクルまでの全過程を対象とするのか、特定の段階に絞るのかなどを決定します。
例えば、ある企業が、新たに開発するスマートフォンの環境負荷を低減するためにLCAを実施する場合、目的は「スマートフォンの環境負荷低減」となり、調査範囲は「原材料調達から廃棄・リサイクルまで」となります。
2. インベントリ分析
インベントリ分析では、調査範囲で設定したライフサイクル全体における投入と排出を定量的に把握します。
- 投入: 製品やサービスのライフサイクルにおいて、投入される資源(原材料、エネルギー、水など)を調査し、その量を定量化します。
- 排出: 製品やサービスのライフサイクルにおいて、排出される物質(大気汚染物質、水質汚染物質、廃棄物など)を調査し、その量を定量化します。
例えば、スマートフォンのLCAでは、製造に必要な電力量、部品に含まれる金属の量、使用時に消費する電力量、廃棄時に発生する廃棄物の量などを調査します。
3. 影響評価
影響評価では、インベントリ分析で得られたデータに基づいて、環境への影響を評価します。具体的には、以下の項目について評価を行います。
- 地球温暖化: 温室効果ガスの排出による地球温暖化への影響
- 酸性雨: 大気汚染物質の排出による酸性雨への影響
- 水質汚濁: 水質汚染物質の排出による水質汚濁への影響
- 資源枯渇: 資源の消費による資源枯渇への影響
- オゾン層破壊: オゾン層破壊物質の排出によるオゾン層破壊への影響
- 人体への影響: 有害物質の排出による人体への影響
- 生態系への影響: 生態系への影響
影響評価では、それぞれの影響について、科学的な知見に基づいて定量的に評価を行います。
4. 結果の分析
結果の分析では、インベントリ分析と影響評価の結果を総合的に分析し、製品やサービスのライフサイクル全体における環境負荷を評価します。
具体的には、以下の項目について分析を行います。
- 環境負荷の大きい段階の特定: ライフサイクルのどの段階で環境負荷が大きいかを特定します。
- 環境負荷低減のための改善策の検討: 環境負荷を低減するためには、どのような改善策が有効かを検討します。
- 環境負荷低減効果の検証: 改善策を実施した場合、どの程度の環境負荷低減効果が見込めるかを検証します。
結果の分析は、LCAの最終段階であり、LCAの目的を達成するために非常に重要な段階です。
CO2の排出量を計算して自社のエネルギー使用量を把握しよう
CO2排出量の基本的な計算式は「活動量×排出係数(排出原単位)」です。正確なCO2排出量を把握する場合は自社と他社を区別し、製造や物流といった活動で排出されるCO2を分類して算出する必要があります。
数値を計算する場合、データの収集や算定に、時間や手間がかかるでしょう。そこで、弊社が提供する、CO2排出量計算(簡易シミュレーション)を活用してみてください。ガス、灯油、ガソリンなどの請求書や領収書をご準備いただき、自社の電気やガスの使用量についてチェックしてみましょう。
請求書・支払明細、あらゆる帳票に対応!