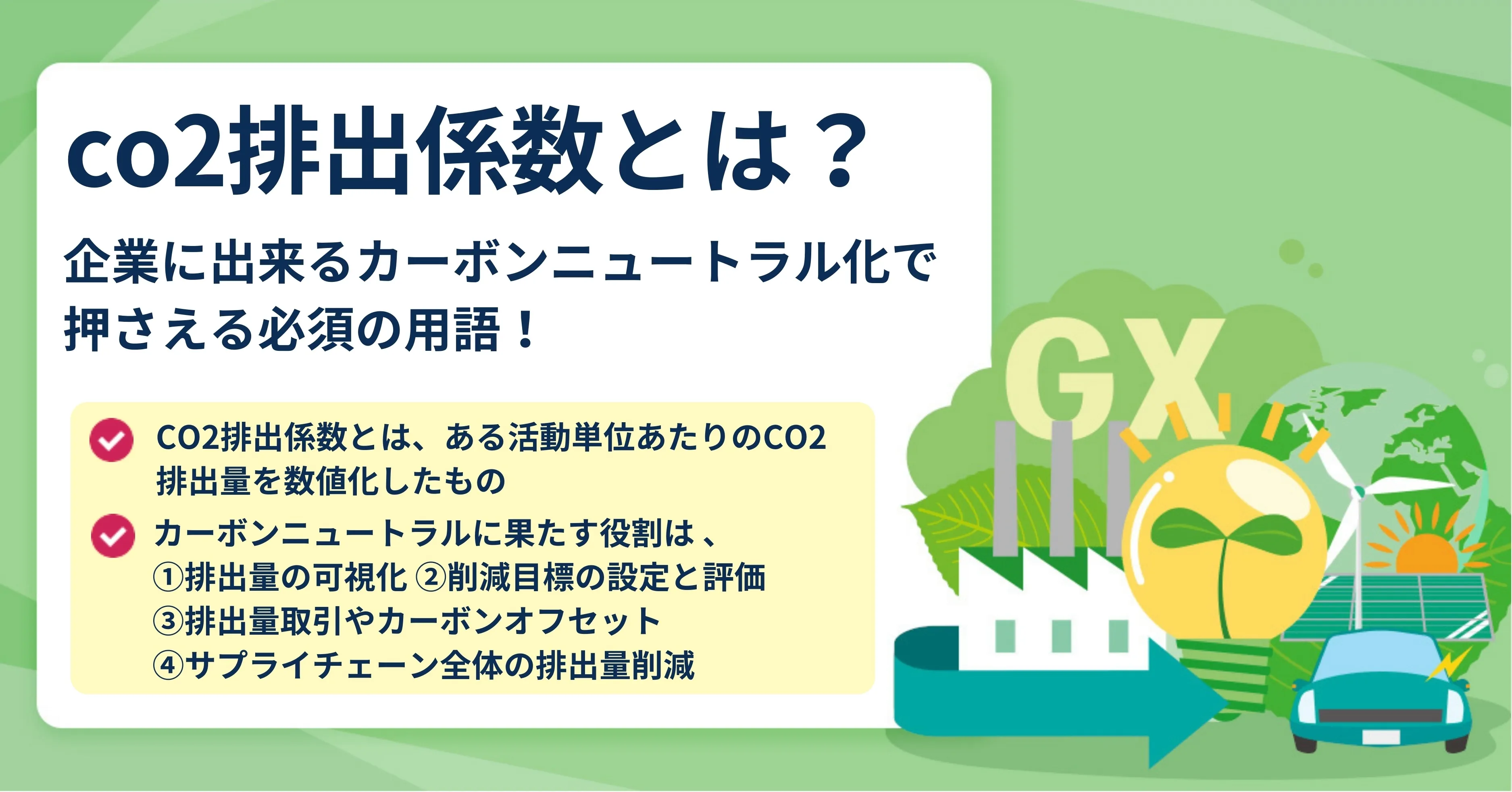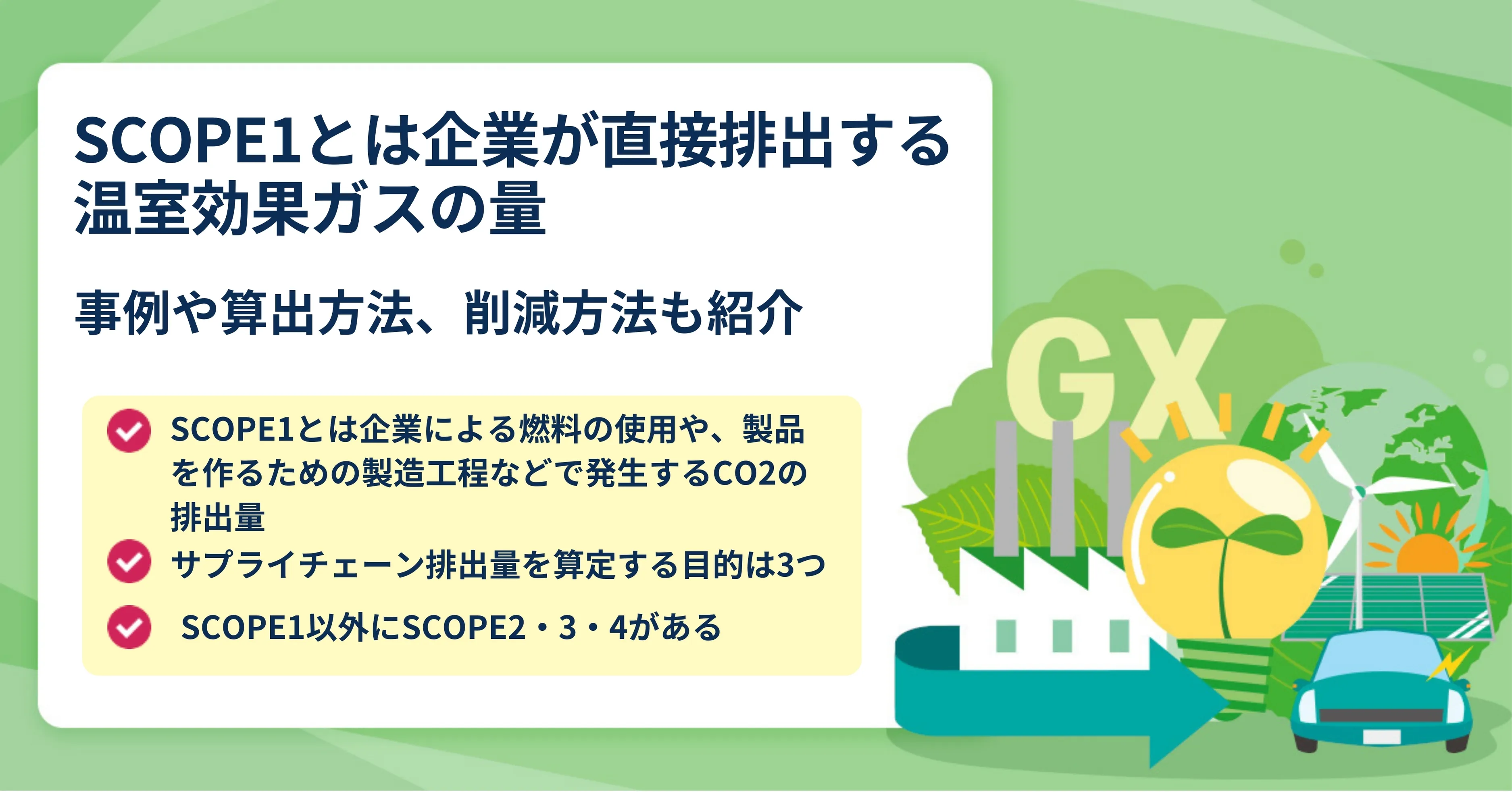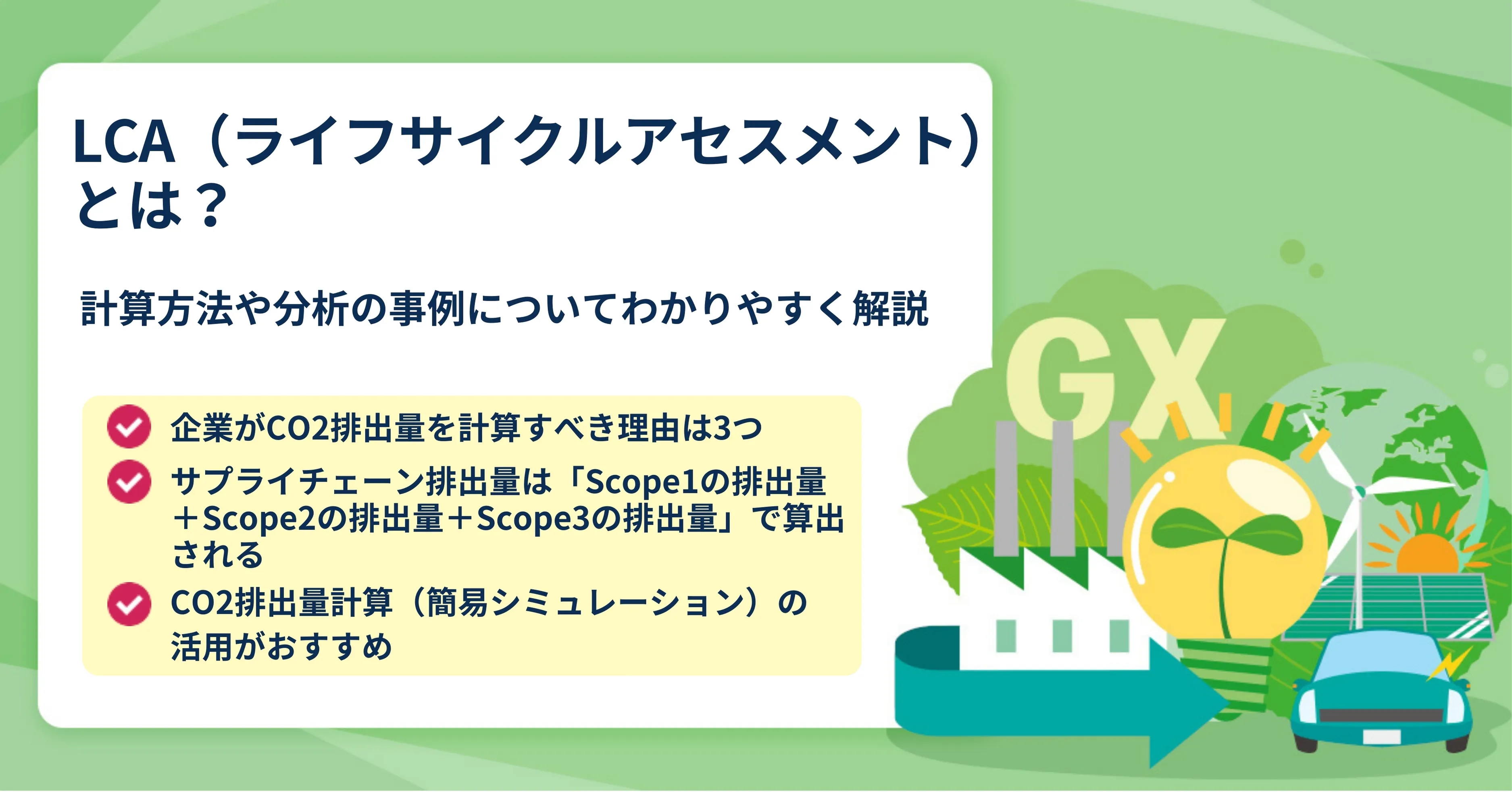CO2排出係数とは?計算方法や係数の一覧を紹介。
更新日:2025.09.08
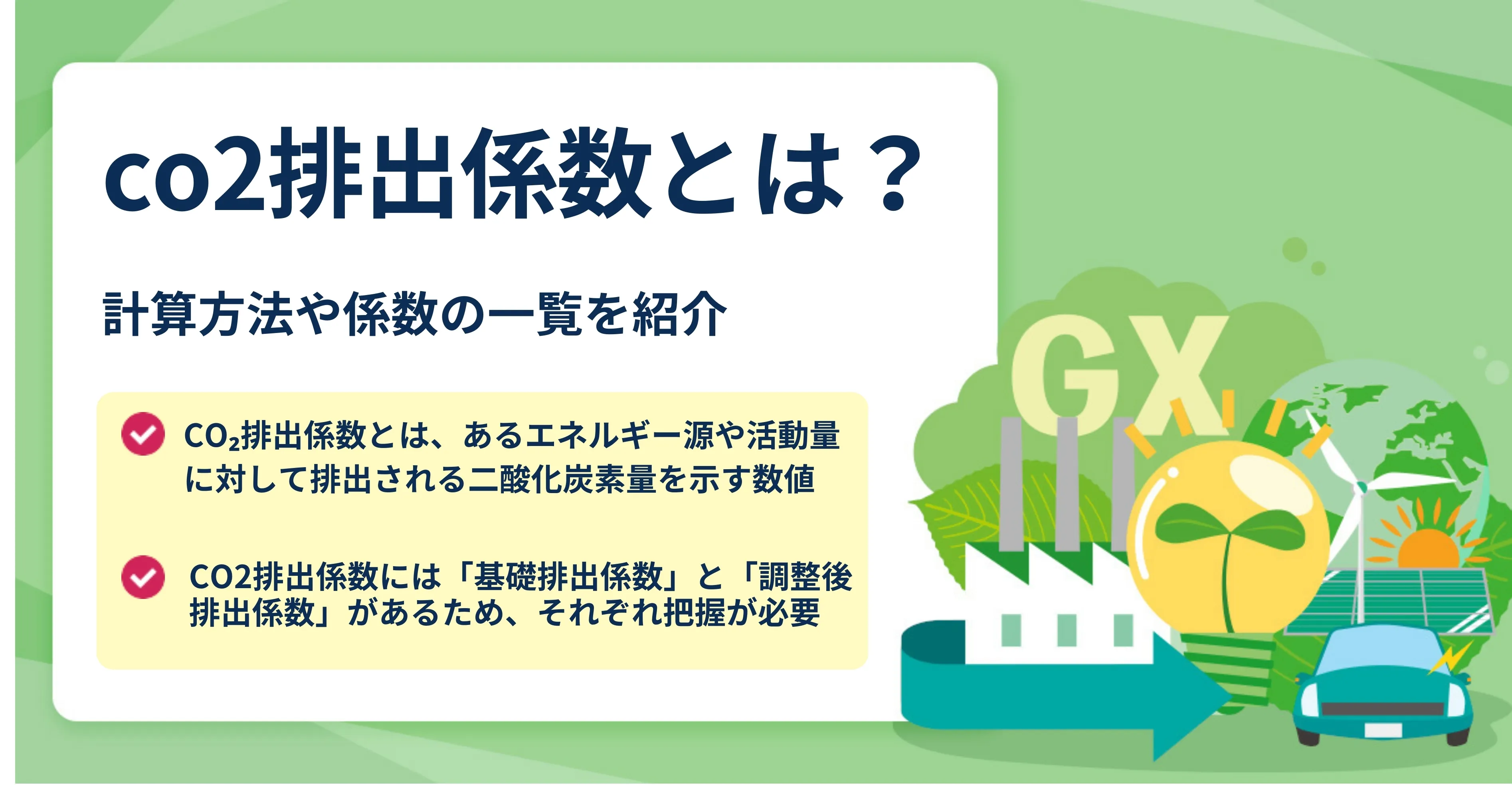
ー 目次 ー
昨今の政府の『温室効果ガス削減目標』の表明やメディアで数多く取り上げられている『カーボンニュートラル』という言葉により『二酸化炭素(CO2)の排出量』を減らす動きが注目されています。
その関係で『CO2排出係数』という言葉を知っていても、一体何のことなのか、まで知っている人は少ないのではないでしょうか?
この記事でCO2排出係数を知り、毎月届いている請求書からCO2排出量を算定しCO2排出量の削減の準備をしましょう!
本記事で分かること
- CO2排出係数とは何か
- CO2排出量を減らす理由
- CO2排出量を減らすポイント
また、CO2排出の計算は以下のツールから可能ですのでぜひ試してみてください。
CO2排出係数とは?
聞きなれない言葉かもしれませんが、これは『電気量1kWhあたりのCO2排出量を示す数値』のことで、単位は『t-CO2/kWh』です。
地球温暖化対策の一環で温対法という法律があります。
この温対法により各電気事業者は温室効果ガスの排出量を国に報告する義務があります。
その際に用いているのが『CO2排出係数』になります。
CO2排出係数は発電手法などにより、電気事業者ごとに異なります。
ちなみに環境省は、各電気事業者のCO2排出係数を公表していますので、環境省のホームページより確認することが出来ます。(年一回更新)
※CO2排出係数は請求書には記載されていません。
CO2排出係数の計算方法
CO2排出係数とは、あるエネルギー源や活動量に対して排出される二酸化炭素量を示す数値です。
一般的な計算式は次の通りです。
- CO₂排出量 (kg)=活動量×排出係数
排出係数の一覧としては以下のとおりです。
- 電力使用量(kWh)
- 燃料使用量(リットル、㎥ など)
- 移動距離(km)
- 製品製造量(kg, t)
対象となるエネルギーやサービスの使用量や活動量を指します。
- エネルギー源ごとに定められた、1単位あたりのCO₂排出量です。
- 例えば、電力なら「1kWhあたり何kgのCO₂を排出するか」、ガソリンなら「1Lあたり何kgのCO₂を排出するか」が決まっています。
- 排出係数は、政府(環境省・経産省など)が公表している値を使うのが一般的です。
例えば、
- 活動量:電力使用量が 10,000 kWh
- 排出係数:0.000466 t-CO₂/kWh(※令和5年度環境省公表値・調整後排出係数の例)
の場合、
- 10,000kWh×0.000466t-CO₂/kWh=4.66t-CO₂
つまり、この電力量の使用で4.66トンのCO₂が排出されたことになります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 計算式 | 活動量 × 排出係数 |
| 活動量例 | 電力量、燃料使用量、移動距離など |
| 排出係数例 | 電力、ガソリン、都市ガスなどに応じて異なる |
| 参照元 | 環境省「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度」など |
基礎排出係数と調整後排出係数とは?
CO2排出係数には以下のように2種類あります。
●基礎排出係数とは
電気事業者が発電するために排出したCO2の量を推し量る指標。
以前は実排出係数と呼んでいた。
●調整後排出係数とは
基礎排出係数にJ-クレジット制度分を反映した指標。
J-クレジットとは、国が認めたクレジット制度であり、温室効果ガスの排出削減量や吸収量を『クレジット』として売買可能な制度です。
そのクレジットの売買行為を『カーボンオフセット』と呼びます。
例)
- 排出された温室効果ガスに見合った量の削減活動に寄付や投資をする。
削減活動に間接的に関わることが可能になり、関わることで排出量を埋め合わせるという考え方になります。
自分で出したCO2排出量を知る
私たちが使った電気によるCO2排出量を計算しようと思ったら、以下のような計算式になります。
『CO2排出量=電力使用量×(契約している電力会社の)CO2排出係数』
※¹電力使用量は毎月届く請求書に記載されています。
※²CO2排出係数は電気事業者よって異なるので環境省のHPをご覧ください。
前項でCO2排出係数には2種類あると説明しました。
『基礎排出係数』と『調整後排出係数』どちらをあてはめればいいのでしょうか?
基礎排出係数と調整後排出係数はどちらを使えばいい?
結論としては、国への報告資料にはそれぞれで算出し報告する必要があります。
しかし、私たちが日ごろ便利に豊かに生活できている反面、排出してしまっている温室効果ガスの排出量という観点で言えば、調整後排出係数をあてはめるべきだと思います。
これは上記にも書いたとおり『調整後排出係数』は温室効果ガスを減らそうとする活動が加味されている係数になっているからです。
今は料金見合いで自由に電力会社を選択することが出来る時代です。
しかし、私たちは自身の家庭や働いている企業で使っている電気について、正しい知識を持ち"CO2排出量を減らす"という観点を忘れてはいけません。
<確認してみて下さい>
請求書から毎月の電力使用量を確認し、環境省のホームページから契約している電気事業者の基礎排出係数と調整後排出係数を知って、CO2排出量を算定しましょう。
▼今すぐに使っている電気量からCO2排出量を調べる。
シミュレーションページへ